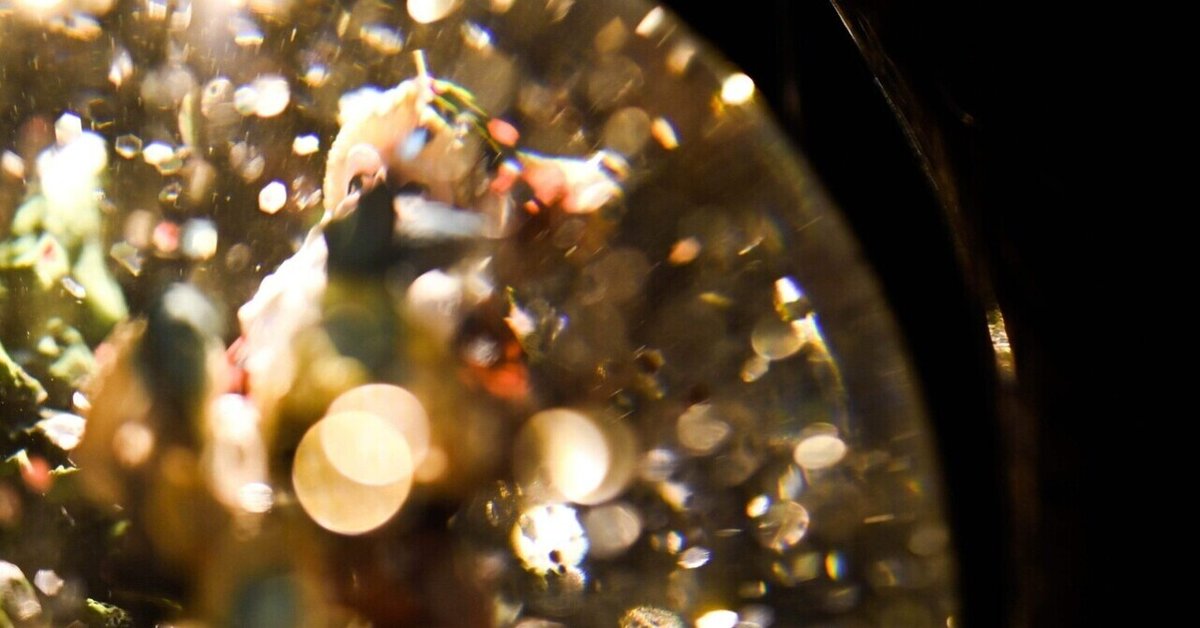
召されなかった天使【4】
自問自答の日々が続いていた。
ある日、眠剤を飲んでも眠れなかった。
AM07:25
近くのコンビニへ行こうとルームウェアの上からパーカーを羽織り、財布とスマホを持って家をでた。
昼の人間達が忙しなく駅へと吸い込まれていく。
まるで働くためだけに生きているように。
小学生達が石を蹴りながらケラケラ笑っている。
これから起こりうるであろう様々な困難も知らずに
その時スマホが震えた。画面を確認すると高木からの連絡だった。
「やっぱりミアとは付き合いきれない」
私は意味が分からなかった。思考が一瞬にして停止した。ただ涙は出てこなかった。
頭の中は高木のことよりも、いつから自然な涙が、自然な笑顔ができなくなったのだろうと思い返していた。
「分かった」
そう一言返信すると、コンビニの喫煙所で煙草を一本吸った。
コンビニに入り、いつもの野菜ジュース、寝酒として度数の高い酒を次から次にカゴにいれていった。
きっと高木は私が食事の後に吐いているのを気付き始めていたのだろう。
ただもう過ぎた男のことなどどうでもいい。スマホのデータフォルダから元カノの画像も消した。
それからひと月、私は売り上げ関係なく、店でも家でも酒を飲みまくった。ただ二日酔いや以前から明らかに減っている体重31・2キロでの労働、手足の痺れはともかく手の震えにより、当日欠勤が多くなっていった。
いつしか主食は店での酒、吐く為の水以外は口に出来なくなっていた。
鎖骨、肩の骨、手首の細さ、両脚の枝のような細さに加え、過度な脚のマッサージによるDVのような痣。恍惚としながらもどこかで、自分の築き上げてきた分身はコレなのかと思い、また同時に望んでいた身体はコレなんだ、と自身に思い込ませた。
酒をどれだけ呑んでも、眠剤を飲んでも寝付けない日々が多くなっていった。
かかりつけのメンタルクリニックの先生には、これ以上の眠剤は処方できないと言われた。そして、これ以上痩せると貴方死にますよ、と。
医者に言われてしまったらもうお仕舞いだ。
いや、私はどこかで死への憧れがあったのかもしれない、この仕事を始めたときから、或いはもっと幼き頃から。もっというと母の子宮に根付いたときから・・・
人間は産まれた直後から”死”へと向かっているのだ、その中で世の中に蔓延る世間体という名の罵倒、誰が決めたか知らない“普通という概念”の押し付けに苛まれながら、死に着々と向かっている。
まだ漆黒の暗闇の中、朝刊を運ぶバイクのエンジン音。その一時間後には、近所の老人が住む家だろうか、雨戸を開ける音がする。月が太陽の恩恵を受けなくなり、代わりに太陽がこれでもかと偉そうに顔を出す。
ふと、いつか子供の頃に父と母にねだって遊園地に行ったことを思い出した。
その時に駄々をこね、スノードームを買ってもらった。あの時のスノードームは今もベッドサイドに飾ってある。
私はスノードームの中にいる、あの天使。
ただその天使は外側の人間によってクルリと回転させてもらわなければ、煌めきの中にいられない。
数秒後には私の周りが煌めきでいっぱいになるかもしれない。いや、もしかしたらもう永遠に、私の足元にある煌めきには触れられないのかもしれない。
足元にある小さなカケラに気付きつつも、自分では身動きが取れないのである。
ミアはまた暗く黒い部屋に一人体育座りをするような感覚に陥った。
そこは床も分からずもしかしたら、1ミリでも身動きを取ったらどこかにブラックホールのような穴があり、永遠に戻ってこれないかもしれない、一人震えながら爪を噛んでいた。煌びやかな爪先のラインストーンはとれていた。
・・・今日は行かなきゃ、出勤しなきゃ・・・
シャワーを浴び、髪を乾かそうと鏡に向かった瞬間、見知らぬ女が映っていた。
あなた誰・・・
そこに映っていたのは、髪の毛は所々むしり取られたように薄く、頬はこけ、目は窪み、歯は度重なる嘔吐での虫歯による黒ずみ、首はまるで老婆のように皺だらけ、ハリのあった胸は垂れ下がり鎖骨の下からは肋骨が浮かび上がっていた。
それを見た直後、なにも食べていない筈の胃がひっくり返るような気持ち悪さがこみ上げて、洗面台に勢いよく吐いた。が、出てくるものは胃液しかない。
行けない、このままじゃ人の目が、世間の目が怖くてどこにも行けない、
あの華奢で可愛かった私は何処へいったのだろう。皆からチヤホヤされ、売り上げもよく、街を歩けば男達の熱い視線を横目に颯爽と歩いていく自信満々な自分・・・全てが自己愛、自信過剰に満ちていたことに気がついた。
気づけば飲み忘れて捨てられずにいた薬、新しく処方された4週間分の抗うつ剤、眠剤を、ミアは一人プチップチップチッと軽快なリズムでベッドの上に出していった。
並べられた無数のそれは、色とりどりでアメリカのタブレットのようだ。そして、誰かがピルケースから出してくれるのを待っていた風にも思えた。
終わりにしたかった、何もかも手放したい気持ちしかなかった、自分を空洞にしたかった。
それを片手いっぱいに、一粒も落とさないよう慎重に持ってリビングに向かう。
キッチンでは夕飯、と言ってもミアは食べないので、夫婦二人分の食事が準備されている最中だった。
私はコップいっぱいに水道水を注いだ。
表面張力で今にも溢れ出しそうな水、私とどこか似ている。
テーブルに座り一旦持ちきれなく掌からこぼれ落ちそうなその薬を置く。
母が横目で私を見やって怪訝そうな顔をした後、私は勢いよく薬たちを口に含んだ、水で流し込もうと思った瞬間、父と母が私に飛びつき、
吐きなさいっ・・・
なに飲んだの・・・
早く口から・・・出して・・・
ミアはその、終わりへと近づける無数の薬たちを噛み砕き、唾液で飲み込んだ。
意識が遠のく
救急車のサイレンが途切れ途切れ聞こえる
誰かが私に触れている、嫌だ、触るな、おまえ達に分かってたまるか、ここまで痩せてきた私の努力を、誰からも本気で愛されず世間と戦ってきた私を・・・分かってたまるかよ・・・
そう思いながら力いっぱい救急隊員の腕を振りほどく、しかしもう身体はいうことをきかない。鼓膜がまるでタワービルを勢いよく上がったときのピンと張るそれに似て、上手く音が聞き取れない、その救急隊員を睨んでやろうと思ったが、もう目の焦点が合わず視界が曇っていく。
あぁ良かった、これで良かったんだ、ようやく解放されるんだ、偽物も本物もない自分へと。
どこかで聞いたことがあるような曲が聞こえる、オルゴールのような居心地のいい曲だ・・・私を導いてくれている・・・
「コレが・・残留物で・・・」
「親族・・・の・・・方は・・・」
夢を見ていた。
ミアの背中には羽が生え、身体は空気のように軽い。妖精のように飛んだり跳ねたり、足は地に着かないように。
いや、着こうとしても着けないのであった。
ふと気がつくと周りがうっすら明るい、目は開けていないが、ここが私の導かれた場所・・・
そう頭の中で捉えたが上手く手が動かない。重い目をゆっくりと開けた瞬間、
ミアの視界には殺伐とした病院の白い天井、腕は拘束され、今度は生きる地獄が待ち構えていた。
完
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
