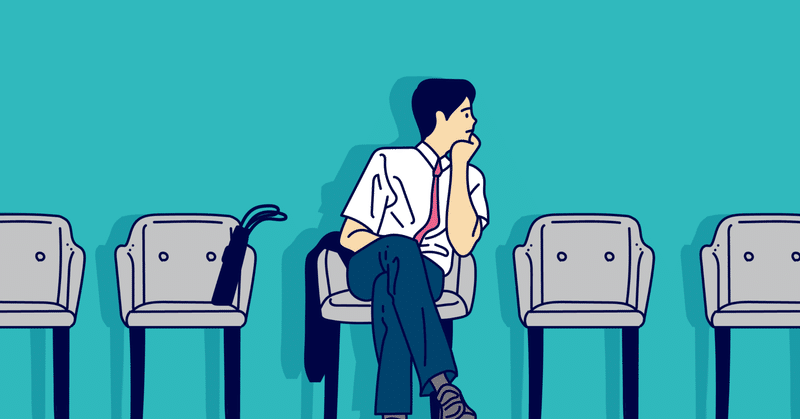
【ショートストーリー】 空白 〜 ブランク 〜
そのブランクは、まるでエアポケットのように突然に私のもとに訪れた。
ちょっとした谷間に入り込んだ仕事のスキマを縫い、その日は午前中の休暇をとることにしていた。
毎夜、ささなければならない何種類もの目薬のひとつが、もうひと月ほど前から切れたままになっていた。
暗闇は足を忍ばせながらではあるが、しかし確実にやってくる。それがやってくるのを、無駄な抵抗と知りつつも少しずつでも先延ばしにしていかなければならないのだ。それ以外に私たちに取れる手はないのだから。
薬を体に中に入れるということは、多かれ少なかれ結局はそういうことなのだ。
そして、私はシャッターの下りた眼科の前でたちすくむ。シャッターには臨時休業とパソコンで作成された長方形の紙が貼られていた。
夏至に近い太陽が、昨日から持ち越した温度とともに私の頭上へ不躾に降り注いでいた。
左肩に掛けていたリュックを、私は背中に背負いなおした。背中が汗に濡れているのを感じた。
「なんや、臨時休業やってフクダさん」
ふと見ると私のすぐそばに、高齢で背の小さな女性がふたり日傘を差しながら立っていた。
しゃあないからちょっとうちによってお茶でもしていかへん? と彼女は言った。
そうやなぁ、時間あるしいこか。もうひとりが言った。
そういやあんたんとこの旦那、どうなったん、介護とか。
先週からヘルパーさん来るようになってだいぶ楽になったわ。
そらよかったわ。
そやけどそうでもないんよ。昨日なんか新しいヘルパーさん来たんやけど、何が気に食わ んのか怒鳴って帰してしもたんよ。何であんな偉そうにすんねやろなぁ。もう、かなん人やわ。
そんな人と長年連れ添って、あんたもえらいわ。
ふたりは笑いながら去っていった。白と薄い桃色の日傘がふたつ並んで、歩みに合わせて揺れながら少しずつ小さくなっていった。
時刻はまだ9時過ぎだった。
私の前に突如として空白があらわれ、何もする事がない、真っ白なブランクの壁が立ちはだかる。
眼科を背にしながら、右へ曲がれば職場がある。私は左へと足を踏み出した。なんだか、何もしたくなかった。ただただ時間をつぶすしかなかった。しかし、出社までの4時間は途方もなく長い時間のように思われた。
細い路地を歩きながら私は再び駅に向かった。路地の角にはお地蔵さんの小さなほこらのようなものがあった。これまで何度も通った道であるのに、そこにお地蔵さんがいることに気づかなかった。地蔵の前の線香からは細くて白い煙が立ちのぼっていた。
背後から私を追い抜いた若い女性が、お地蔵の前ではたと立ち止まり、数秒間手を合わせて、また急ぎ足で去っていった。
地蔵はとても優しくてかわいい顔をしていた。
歩いていると、額から汗が流れ落ちてくる。そういえば長いこと髪を切っていなかった。 私は散髪屋に行くのもいいかも、と思いながら、しかしこの近くのどこに散髪屋があるのかも、長い期間この町で働いているにも関わらずあまりよく知らなかったのだ。
その上、実のところ本気で散髪屋に行きたいとも考えていなかったのかもしれなかった。
今日はすべてが何者かに支配されているような、自分で選択しているけれど、もっと深いところでは実は何も選択していないようにも思われるのだった。
私はどうやってこの空白で何もない時間を埋めていけばいいのだろうか?
私は何もあてのないまま駅から再び電車に乗った。この郊外の小さな町から、再びセンター駅のある都会へ向かった。
電車の中はクーラーがきいていてとても涼しかった。毎日の足りない睡眠が負債となって貯まっているはずなのに、どうしてなのかまるで眠くなかった。
そのことにかすかに腹立ちを覚えながら、私はスマホを取り出し、ネットショッピングでもしようかと思ったが、途中でやめた。かといって、本も読む気分にもなれなかった。
車両の隅には数人の若者がたむろするように陣取りながらーー学校はどうしたのだろうーーベラベラと身振り手振りを添えて喋っている。良くも悪しくも、途方も無いエネルギーだ。それを聴くとはなしにではあるが自然に私の耳に、ある種暴力的にぶち込まれてくる。私はとてつもない疲労を覚えた。
そして私は、普段からコミュニケーションに疲れ、辟易していることにおもむろに気付かされるのだ。それは会話だけではなく、態度のコミュニケーションについても同様なのだ。
人は思いや不平を、言葉だけでは事足りず、態度や表情においても雄弁に語るのだ。しかもそれは時に曖昧であるため、そのメッセージを受け取る側にも知らず知らずのうちに大きな圧力を強いるのだ。
無意識のうちに、そういうものから常に開放を求めていた。
私は、背もたれに深くもたれかかり、頸をたれ、眠くもない目をギュッと無理矢理につむった。鋼鉄の車輪と線路がぶつかる、規則正しいリズムに意識を集中するようにした。規則正しい音と不規則な揺れに身を任せながら、いくつかの思考が現れては消え、消えては現れた。そうしていつのまにか私は眠っていた。
センター駅につくと私はふらつきながら電車から出た。大きな洞窟を思わせるような広々とした空間に高い屋根。一羽の鳩が屋根の下をくるくると飛び回っているのが見えた。
朝のラッシュ時間にはここは人で埋まっているのだ。一体どこからそんなに集まってくるのだろうと不思議に思うくらい、多くの人間がこの駅に集まってくるのだ。もう何年も何十年も。そしてこの先もずっと繰り返し繰り返し、この馬鹿げた芝居は続くことになるのだろう。何世代にも渡って。
幸いにしてこの時間帯は比較的乗客は少なくなっていた。鉄が焼けたような独特の匂いが漂ってくる。駅のエスカレーターを下り、私は歩いた。どこへも行くあてがない。私の足は仕方なく駅の下にある大きな書店、紀伊国屋に向かった。書店の前には多くの人たちが待ち合わせをしていた。かつては私もここで待ち合わせをしたものだった。妻と初めて待ち合わせをしたのもここだった。あのとき、私は早めに到着し、階段の上から彼女が来るのを今か今かと見下ろしていたんだったなぁ。だけれど彼女はなかなかこなかった。なのであのときも私はやるかたなくて、紀伊国屋に入ってしばらく時間を潰したのだった・・・。
私は書店に入り、目的もなく歩き回った。本屋には、あらゆる知識と想像と思想が詰め込まれている。小さな宇宙のようなものだ。
私は手当たりしだいに本を手に取り、パラパラとめくっては再び棚に戻していく。
朝井リョウと辻村深月が平積みに大きなスペースを取っていた。そして川上未映子があり村上春樹の新作も並んでいた。
文庫の棚へ行くと、おお、上野千鶴子や内田樹の本もある。
ああ、ここの良心は失われていないようだな、まだ。と私は勝手に思い、勝手に感動したりした。
ひと通りあるき回ったあと、結局私はーーこれまで特別読んだことはなかったけれどーー朝井リョウの本を一冊購入したのだった。
外へ出ると、日差しが強かった。ビジネスパーソンや外国人の観光客が歩道橋を行き来している。ビル群を眺めながら歩道橋を渡り、いくつかのベンチのある広場にたどり着いた。日差しが強いため、日陰になったところを探したけれど、日陰のベンチはすでに誰かに座られていたため、私は仕方なく日の当たるベンチに腰掛けた。考えてみれば私の人生は、仕方なく、にあふれている。
ベンチには多くの西洋人の観光客が座りながら、何かを食べたり喋ったりしていた。彼らは何が楽しくてこのような世界の端っこの、偏見に満ちたこの国に来ているのだろうか。私は思った。何を求めてやってきているのだろうか。
私はリュックから、ロールパンを取り出し、かじった。パサパサの食感で、口の中の水分が一気に失われてしまうようなパンだったけれど、これしか持っていないのだから仕方がなかった。私は時間をかけて、強い日差しをまともに浴びながら、そのパサパサのパンを食べた。その光景がなんだか面白くもないコントのような気がして、自嘲的な笑みが漏れた。
笑ってみるとしかし、どこか自分に肯定感が生まれたような気がして、それが不思議でもあったのだ。
もうそろそろ戻らないといけない時間だった。
私は駅に向かって再び歩き出した。駅の柱の陰で、ひとりの男性が陸上競技のクラウチングスタートのような姿勢でかがんでいた。中腰になり、まるで彫像のような格好で静止していた。ハンチング帽をかぶり、その仕草はどこか獲物に向かう猟犬のようでもあった。
何かのパフォーマンスか、と近くに行って見てみると、彼はただかがみながら解けた靴紐を結び直しているだけだった。
彼のそばを何人もの人が過ぎ去っていく。彼は立ち上がると、まるで失った時間を取り戻すかのように雑踏の中へと早足に歩き去って行った。
私はもう一度電車に乗り込み、職場へと向かう。職場に戻れば、大量の書類が机の上に積まれていることだろう。でも仕方がないことだ。それが私の仕事であり、誰かがやらなければならないことなのだから。
電車の中にはまばらに乗客が座っている。多くの人が静かにスマホの画面を見つめている。電車の走る音が変わった。ひときわ音が大きくなった。車両が鉄橋に差し掛かったようだ。大きな川の上にかかった橋だ。窓からは川の水面が見え、川べりで釣りをする人たちが見えた。運動する人たちもいる。
私は居住まいをただした。そしてリュックから真新しい文庫本を取り出した。
読んでいただいて、とてもうれしいです!
