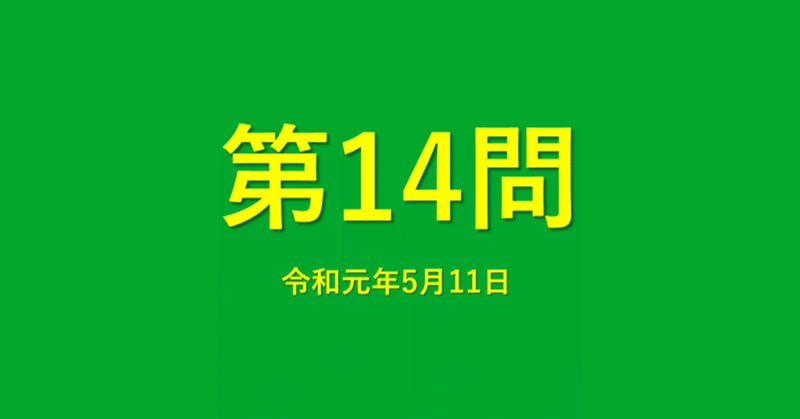
14.やりたいことがみつけられない・・・その時に
はじめに
そうです!!このお題、グッときました・・・。
最近、自分のやりたいこと、それを見つけたいと思う人が増えてますね。
昔から「自己実現」や「自分探し」はありましたが、今の社会はホントに先行き不安ですから、結局「自分自身」しか頼れないと感じる人たちが多いのでしょう。
そして盛んに「自己責任」を問われる中で、自分に「自信」が持てずにいることは、それなりに「痛い」ことかもしれません。
ですから、自分の生活と社会への参加という公私を貫く、首尾一貫した「自分軸」を保つことが大切になります。
そして、こんな時代だからこそ、やりたいことが「自信」につながり、「自信」がやりたいことにつながっていく自分への「信頼」という課題もあるのでしょう。
この「自分軸」については、第18問の「自信をつけるには」でお話しする予定です。
姿勢としては、自分を知り「自信」をつけるために、「やりたいこと」あるいは「できること」を探していく、そして探しているうちに「自分軸」が出来上がる・・・やっぱり探さないといけないのでしょうか・・・。
ここで、一つの問いかけをしますが、本当に「やりたいこと」は「探す」姿勢なのでしょうか。
少し前置きが長くなりましたが、とにかく「やりたいこと」を見出す法則はあるのか。ご一緒に検証して参りましょう。
「やりたいことは思い出す」
僕は、これからは「やりたいことを思い出す」という表現を使うといいと思います。
「やりたいことは思い出す」というのは、まず根本的な自分自身のモノゴトに対する姿勢です。そもそも「探す」という表現は、手元にないものを「探していく」とか「外に見出す」印象が強くなります。
だから、本当の「自分探し」にするには「思い出す」という言葉を当てたいのです。
「自分探し」「やりたいこと」を「探す」となると、自分は「わからない」、「知らない」が前提になりやすく、「自分の感情を無視する」とまではいいませんが、他にあるとして自分へ焦点が向きにくい印象があります。
「やりたいこと」は、自分の「好きなこと」が圧倒的に多いと思いますし、「得意なこと」も同様で、物心ついた時から「知らず」と持っている性格そのものです。
でも「自分」はそれを「知っている」から「そうしたい」「そうするのが好き」だから「できちゃう」わけです。
それを、すでに「自分は知っている」そして「思い出す」と感じることが大切です。それが自分を「信じる」という第一歩です。
やりたいことはまず「探さない」。自分は「思い出す」と感じてください。
すべては「どう感じるか」
自分がそう感じない限りは、そうならない。これは、鉄則です。
世の中の本質というと大げさですが、すべては「どう感じるか」に関わっています。そして何に「関心」があるか。それは、ホントに好きなことの中に、答えがあると思います。
今回ここで、僕自身の現在の仕事と好きなことの関連をご紹介することにしました。そうすることで、皆さんの「やりたいこと」に向かう手掛かりになるのでは、と考えたからです。
ホントに好きなこと
僕は、幼少期、小学校1年から高校生まで模型作りが大好きでした。
そのなかでも鉄道模型が大好きで、細部のディテール表現や自分で作りだすというクラフトマンシップがありました。完全なるオタクです(笑)。
中学1年にして、一枚の真鍮板から設計図をもとに自作しました。製図も技術の先生が舌を巻くほど描き方が上手でした・・・(単なる自慢のようですが、これは僕の「得意なこと」ですね)
とにかくこういうのを一般的には「器用」というのでしょうか。
鉄道模型に焦点をあてると、何よりレールの上を台車が「滑らかに走る」感覚がたまらなく好きだったのです。
これが本質的な「好み」だと感じたのはずーと後のことですが・・・。
もう一つ、大学時代はバンドにハマってました。実は「ドラマー」なのですが、はじめからリズムが得意じゃなかったのです。バンド仲間のベースの奴の方がずっと上手かった。
しかし、猛練習しました。何のために? 本当は「やりたいこと」って「好きなこと」や「得意なこと」なのに、どうして僕はそこに「こだわった」のでしょう。
これも、本質的には「好きなこと」に関係していたのですが、それは、「のり」でした。どうしたら、「のり」や「グルーブ感」を出すことが出来るのか?
同じリズムをひたすら心地よく叩き出す。
こればかりをひたすら追求して、細かな技、たとえは「パラディドル」とか、演奏に関係ない「スティック回し」とかには見向きもせずに、ひたすら「のり」を追求していたのです。
「滑らかなのり」「グルーブ感」
夢中なときには、その感覚には気付かなかったのが、ある時これが本質的な「好み」なんだと分かりました。
この本質的な「好み」を、さらに社会や大勢の人に役立つように展開させることが、新しい仕事や「やりたいこと」に繋がっていきます。
つまり「滑るような感覚」は、「バリアフリー感覚」や「疎通性の良さ」、「物事の理解を障壁なく伝えられるような工夫」、さらに「壁を無くしていくような感覚」や「流れを良くし障害を根本的に減らすような志向性」に展開できるのです。
僕の本質的な「好み」すなわち「関心」や「興味」は、このように応用し展開出来ると気付いたのです。
実際の仕事としての立ち位置
医者としての僕の立ち位置は、心療内科であったり、リハビリテーション医であったり、産業医であったりしますが、いずれも、様々な障害を取り除き、心身両面において巡りを良くし、体には促通を、心には共感や共鳴という共通理解をもたらすことが、僕の「好み」であり「関心」や「興味」だったわけです。
このことに気付いたときは目から鱗でした。このように自らの「関心」「興味」をそのままに、「好きなこと」を仕事にできるようにするためには、その「好き」の本質的な部分に自らが気付いていくことが大切なのです。
実際に、今でも鉄道模型を作りたいと思うこともあります。それは良いとは思うのですが、このことに気付き、鉄道模型を「諦めなければ・・・」と考えなくて済むようになりました。
今では本質的な「好み」の「関心」「興味」を追求したことで、根本的な「好き」を変えることなく、より多くの人々に役立つ「仕事」に生かしていく術を学んだわけです。
ですから「関心」や「興味」の本質を追求すれば「好きなこと」「やりたいこと」を「仕事」にする「新しい仕事観」が生まれるのです。
習慣化すること、そして更なる展望へ
ですから、心の内面にある自分自身が持つ「関心」を観察する習慣が必要です。
人生を賭けた究極の表現が、「やりたいこと」を仕事にする「新しい仕事観」の本質です。それが「生きがい」に他なりません。
一方向的な考えから視野を広げ、新たなるビジネスを展開しようという意識。ただ広がるだけではなく、そこには秩序観が大切です。
そして、更なる展望を予想します。これから起きるワクワクするような、カラフルで美しく、軽安(きょうあん)で、軽やかな巡りを意識することができる未来への展望です。
それでは、次に具体的な方法論についてご紹介しましょう。
具体的な方法論
様々なアイデアを活かすような趣向で自分の情熱を傾けられる分野とは一体なにか。
さあ、ここで、分野とか職種とか、仕事を探すような価値観になりやすいのですが、ここで、皆さんには敢然と踏みとどまってほしいのです。
その理由はすぐにお教えしますが、先に次の公式を見ていただきましょう。
好きなこと[情熱]× 得意なこと[才能]=やりたいこと

好きなこと(情熱)…その行為自体に価値を感じる・没頭する・熱中する・夢中になる・自分の絶対的な感覚・・・職種
得意なこと(才能)…苦なくできる・人より上手くできる・スイスイできる・自然とできる・他人との比較で気付く・・・仕事
やりたいこと…好きなことを得意なやり方で実現すること
簡単ですね。これで「やりたいことを」本当に見つけられたら、それはホントにラッキーでしょう。結果から見れば確かにこうなると思います。
この中で確認したいことは「好きなこと[情熱]」がWhat(何を)ではなく、「情熱」は、how feel(どう感じるか?)を問うことが大切なのではないかと思います。
そして根源的な疑問詞why(なぜ?)とwhen(いつから?)というのも以外と大切です。なぜなら、「好きなこと」の嗜好性は、時間が経つと変わることもあるからです。
「いつから」としても、物心ついてから・・・とか、曖昧かもしれません。しかし、その「スキ」(※カタカナの「スキ」は自分が感じていない状態の「好き感」)がいったいwhen(いつから)→why(なぜ)という流れを思い出すことは大切です。
そして最終的に「スキ」の意識化がなされ「好き」を→how feel(どう感じたか)になるのです。
「好み」を「形容」する
今回検証する、やりたいことの公式の課題は、職業的な「何か」に注目するのではなく、選択の幅を広くするために、まず「感情」に取り入りたいのです。
「スキ」なことは、何かに「関心」や「興味」があるのです。
さらに、「スキ」な感覚はそもそも感情で成り立つので、その感情そのものを表現するのに必要な「コトバ」として「形容詞」が挙げられます。
形容詞は、「美しい」とか「綺麗」もありますが、もう少し感触を示す「さらさらした」「流れるような」など「形の容を為す」表現、つまり中身に価値を与えるような表現を見出していくと自分の好みが分かってきます。
このことを念頭に置くと、単なる職業などの「型」にはまることがなく、実際に自分が、どのような「形・容」で「ありたい」のか、つまり「形」のみならず、その「容姿」、中味の「姿勢」が見えてきます。
よく大人が子供に「大きくなったら何になりたいの?」と聞くことがあります。その中で、必ずと言っていいほど、「職種」が出てきます。
運転手さん、デザイナー、料理人、サッカー選手、医者、弁護士、とか・・・でも最近では、やたら横文字のコンサル系職種も多いので、職種でも構いませんが、とにかく固定観念のような枠組みを一度外しましょう。
この「在り方」が、限定した思考にハマる最初の呪文です。
そもそも、情熱=職種 ではない
ですよね。
未だに「何になる?」「何をする?」「どうやる?」という方向性で「やりたいこと」を見いだそうとします。
そうではなく、「好きなこと」なのですから、ただただその感覚を味わうようにすれば良いのです。
好みを支える情熱には、3つくらいの形容ができるはずです。これは、結構抽象的な課題なので、とっつきにくいのですが、皆さんには是非、踏み止まっていただいて、肯定的(困難がありながらも須(すべか)らく執り行うこと)に解釈していくとよいでしょう。
はじめに職種を考えないでください。
職種は生み出す
原初は「感情」を、「情熱」を、そして「好み」を、形容すること。これを自分の嗜好性とも言います。
そして、それがどんな仕事を生み出せるのかを考えていくことです。そうすると自分の嗜好性に合う
「仕事」を「選ぶ」から
「仕事」を「創る」へ
シフトできます。
自分自身のロイヤリティーを遺憾なく発揮するために、自分の「好み」をしっかりと味わうことに努めてください。
この順序であれば、職種を選ぶ必要がありません。そうすることで職種を見出せるのです。そして、さらに新たな職を生み出すこともできるのです。
最後に「得意なこと」
「やりたいこと」は、得意なことを見つけるように勧めている人もいます。仕事としての職種で選ぶ場合も、その方が優位性があることは一理あるでしょう。
しかし先ほどの僕の例のように「リズム音痴」なのに「ドラム」にこだわることで、さらに「スキ」な感覚を抉(えぐ)り出すこともできます。
そこには、自分自身の「理想」と「現実」のギャップがあるから「スキ」な感覚がさらに良く見えてくるのでしょう。
得意なことについては、過去に人に褒められたことや、自分があまり努力しない状態でもスイスイとできてしまうようなことなど、これも自覚するのは結構難しいとおもいますが、これらは、できてしまうことなので、先ほどの「好きなこと」の感覚と合わせていくことで「やりたいこと」につながります。
とにかく、「やりたいことがみつけられない・・・その時に」の順序は、
基本姿勢=「やりたいことは思い出す」
形容化=「好き」な感覚の容姿や姿勢を言語化する
焦点化=「好き」な感覚や感情をあぶりだす嗜好性を追求する
汎化=「嗜好性」を幅広く「一般化」してみる
実用化=最終的な職種の選定や組み合わせを考えていく、
しっくりこなければ創造する。
このような流れです。はじめの「スキ」な感覚にこだわるのは、それが感情の流れの原初であり、「スキ」なことのなかに「関心」や「興味」を持つ首尾一貫した「感覚」があるからです。それは、本人自身しかわかりません。
それが、与えられたギフトです。
それを是非、皆さんにも「思い出して」いただきたいと思います。
ギャップが仕事になるとピータードラッカーは言っています。
そのギャップを埋める役割は、人それぞれに与えられていて、本人にしか分からないことです。だからこそ、そこに価値があるのです。
本日も最後までお読みいただき
誠にありがとうございました。
ここのコメントを目にしてくれてるってことは最後まで読んで頂いたってことですよね、きっと。 とっても嬉しいし ありがたいことです!マガジン内のコンテンツに興味のある方はフォローもよろしくお願いします。
