
ロジャーズが"NO"としたアプローチ
まえがき
パーソンセンタード・アプローチ(旧:来談者中心療法)は、専門用語も少なく、病理で人を捉えないこともあって、その馴染みやすさから、世界的に有名なアプローチとなりました。しかし、その馴染みやすさによって、多くの誤解を受けたアプローチでもあります。
そういう筆者自身も、多くの誤解をしていました。大学でカウンセリングを学び、キャリアコンサルタント養成講座でも来談者中心療法について触れてきましたが、いざ支援現場にでると、うまく行かないことだらけで、「共感的理解とは、具体的に何をすることを指すのだろうか」や「これをしていて、クライアントにどんなメリットがあるのだろうか」など、さまざまな疑問に直面しました。
数年にわたって、心理士の先生方から手ほどきを受けつつ、仕事のあとにカール・ロジャーズの書籍や論文を頼りにし、支援の振り返りを通して、一つ一つ自分なりの理解に落としてきました。すると、「共感的理解の意味」や「無条件の肯定的配慮を行う理由」など、以前とは全く異なる意義を見い出だすに至り、今では支援のなかで、どのようなプロセスを経ていけばいいのかという方向性が見えてきたところです。
今回「パーソンセンタード・アプローチ」に関する記事を、数回にわたって簡潔に解説するにあたり、大変不遜ではありますが、上述の自身の理解にのっとりつつ、参考文献を引用しながら、細心の注意を払って概説してまいります。読者の皆さまに、最後までお付き合いいただけましたら、幸いです。
1.「心理カウンセリング」はアドバイスや権威性を批判して生まれた

ロジャーズは、はじめて自身のカウンセリング・アプローチを紹介するにあたり、事前に、それまで横行していたカウンセリングのあり方について、複数の批判をしています。
まずは、なにを"NO"と示しているのかを知ることで、パーソンセンタード・アプローチの輪郭を捉えていきます。
2.助言と指導をする介入を批判

わかりやすいものだと「助言の使用」があります(1)。
カウンセラーが、こういうことが達成された方がいいという目標を定めて、クライアントがその目標に向かって前進していくよう働きかける助言・指導のことを指します。
ロジャーズは、具体例として、ラジオの身の上相談の専門家を挙げています。込み入った問題に数分間耳を傾けただけで、何をすべきか間髪入れずに相手に助言するスタイルを、実際のカウンセリング・セッションでも行っているケースが当然のようにありました。この時に紹介した記録には「私があなただったら、このようにする」や「それはうまくいくはずない」「このように考えてみてはいかがでしょう」という発言が、頻繁になされていました。
3.専門的な解説を批判

次に、「説明や知的解釈」も批判しています(1)。それは、クライアントのうまくいかない行動パターンを変えようとして、専門的な知識にもとづく解釈をし、その行動の原因を本人に説明することによって、クライアントの態度や感情が変容する、というものです。
ロジャーズはこれを短絡的であると批難し、「カウンセラーは最上のことを知っている」という考え方になっていることを指摘しました。
ちなみに、現代の精神医療の世界でも、「治療する側-される側」という力関係が発生してしまうあり方は、建設的ではなく、また、問題の原因を本人のせいにしてしまう考え方は、道理にあっていないため、それらのあり方を是正しようとする「障害の社会モデル」への取り組みが広がっています(2)。
4.励ましや勇気づけを批判

意外に思われる方も多いのですが「励ましや勇気づけ」も、控えた方がいいとしています。
「励ましや勇気づけ」は、クライアントをより良い方向へと向かうよう動機づけを高める狙いがあります。それでも、これを受けたクライアントは、抱えている問題を意識化することを拒んでしまったり、その問題についての感情を抑圧してしまう場合があります。
現代の心の専門家でも、この関わり方をされることがあり、クライアントはその瞬間から言い出しづらくなってしまうというケースはよく耳にします。
5.受容されたと感じる受け答えを目指す
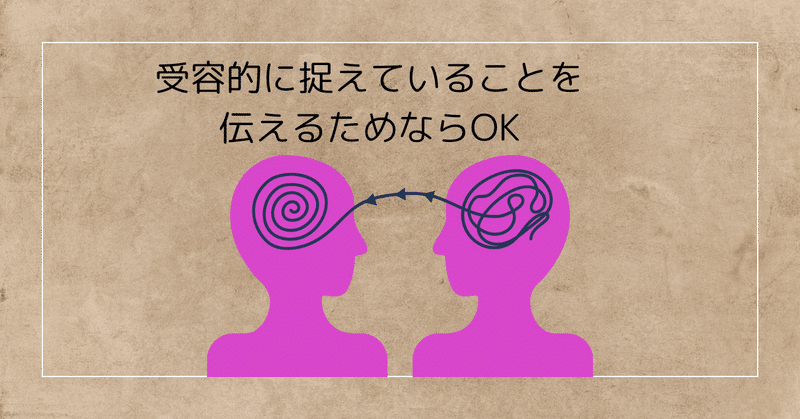
ここまでロジャーズの批判を概観しましたが、念のため書き添えておくと、後にロジャーズは「説明や知的解釈」や「励ましや勇気づけ」に価値はないとしつつも、クライアントに対する尊重と温かい思いやりを表現する方法として使用する場合にのみ価値があるとしました(3)。
たとえば、解決構築アプローチ(解決志向ブリーフセラピー)などの他の理論でも、コンプリメントという労いや励まし・賞賛などをする方法がありますが(4)、それも関係性のなかで、クライアントを尊重した温かな思いやりを意味する「無条件の肯定的配慮」を伝える手段になっているのであれば、クライアントは「理解してもらえた」という有効性を体験します。
同様のことが、「助言の使用」や「説明や知的解釈」にもいえます。
つまり、ロジャーズが批判によって、言いたかったことは、目の前のクライアントを大切にしてほしい、という尊重の姿勢だったといえます。
【引用文献】
(1)Rogers,C.R.,1942,Counseling and Psychotherapy.Houghton Miffl in.末武康弘・保坂 亨・諸富祥彦(共訳),2005,カウンセリングと心理療法,ロジャーズ主要著作集第 1 巻,岩崎学術出版社,p.24-31.
(2)永井順子,2017,精神障害の生活モデルとインペアメント―精神障害の社会モデルを展望して―,北星学園大学社会福祉学部北星論集第54号.
(3)Rogers, C. R. 1957,The Necessary and Sufficient Conditions of Therapeutic Personality Change. Journal of Consulting Psychology. In Kirschenbaum, H. & Henderson, V. L. eds., 1989 The Carl Rogers Reader. Houghton Mifflin(伊東博訳,2001,セラピーによるパーソナリティ変化の必要にして十分な条件,伊東博・村山正治監, ロジャーズ選集(上):カウンセラーなら一度は読んでおきたい厳選33論文,誠信書房,p.283)
(4)王家芸,山本眞利子,出雲文子,2022,場面想定法を用いた相談内容とコンプリメントの違いが問題解決に及ぼす影響,Kurume University Psychological Research,No.21,pp.13-22.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
