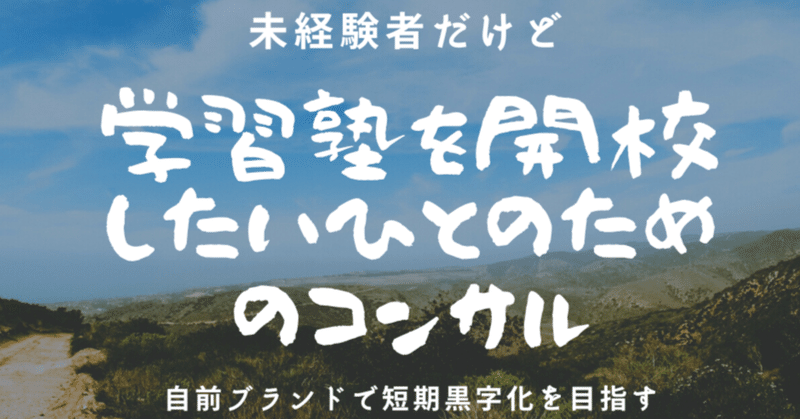
未経験の僕が仕事を辞めて学習塾を開校する話。その6―どんな塾をつくるのか/学習塾開業コンサルタント
どんな塾にするのか
スタートするときの目的のひとつに,子どもたちの居場所をつくりたいという想いがあったので,サブスク型サービスにすることは最初から決めていました。
いつ来てもいいし,いつ帰ってもいい,いつまで居ても良いし,何したっていい。
そんなかで,勉強したくなったらすればいいし,宿題だけでも終えていったらいい。先生とお話して,本を読んで,友だちに挨拶して帰って行ってもいい。
で,そうするためには,時間割をつくることができませんし,無学年制にしないといけないし,マンツーマンとか1対2とかそういう個別指導はできないことになります。
学習塾の形態
学習塾には一般に
集団塾
個別指導
自立学習
の3つの形があります。
最近では,オンライン型や広義の塾という意味で家庭教師のような形態も出てきています。
どれが一番良いということではなくて,一長一短があるわけです。
その特徴をしっかりと理解したうえで,自分が望むスタイルを決めていく必要があるのですが,僕の場合はこれはあっさり決まりました。いや決まったはずだったんです。
先に述べたとおり,目的に照らすと個別指導はできないし,集団で授業をするようなことができないので,自立型一択ですから。
ところがでもやっぱりそうは簡単にはいきませんでした。
ネックになったのは夏休みや冬休み。
長期休暇こそ,お父さんお母さんは子どもたちがダラリと一日を過ごすことにちょっと否定的で,できれば学校に行っているのと同じぐらい勉強して欲しいと思っているし,できれば誰か面倒見てくれるひとがいたら良いなーと思っているのです。
いいですか。
夏季講習や冬季講習の仕組みというのは,学習塾にとってはコレは本当にものすごい稼ぎを産む仕組みです。
この概念をどうとらえるか。
僕は実を言うと,通塾生に対して,夏季講習と称してプラスで授業料をもらうことに否定的です。
なんでかというと,商業主義全開過ぎて引くぐらいお金かかるからです。
(でも,本気でやるとどうしてもお金はかかるんだけれど…)
夏季講習については一般に,塾生と保護者に対しては,それまでの成果や学習状況などをネタにして面談を行い,生徒ごとに必要なカリキュラムを提案する形でオススメするのです。
この仕組みだと,成績でいうと一番真ん中のボリュームゾーンにいる子たちと成績が悪い子たちは長期休暇中に”弱点補強”とか,”次学期の予習”とか,ぜひ受講してください!と言えるポイントがたくさんありますから,これをまともに受けて課金していくとものすごいえげつない金額の提案書ができます。
夏季講習だけで30万円とか
予備校行けばそれぐらいかかるとか
でもやらないわけにはいかないし(と思わせて囲い込む)とか
最初は「全のせ」の見積もりだして,いくつか減らしていって折り合いつけるのは交渉の常套手段じゃん,とか
いろいろ思うことがあります。
したがって,僕はこういう競争を避けるために夏休みも通常の授業料で「朝から晩まで居ても良いよ!」を貫くというシステムをとりたいと思っていました。
ちなみにサブスク型をやろうと思うと,本当に毎日来る子たちがたくさんいて,逆算的に授業料を決めなくてはならず,一見すると他塾さんよりも高額な授業料に見えてしまいます。
しかし長期休暇も金額据え置きにすればそのあたりも相殺できて,ちょうどいいのですが,でもそうするとどうなるかというと
夏休み一ヶ月だけ入塾するひとと,通常時から来てくれているひとの区別ができなくってなんだかなーという気持ちになります。
でもまぁ
最終的には,このことには目をつぶって,サブスク型で始めちゃいました。
念のため
それでもやっぱり夏休みは,学習状況が芳しくなく,遅れ気味の子どもたちを「ひとりで学習できる」レベルまで引き上げてあげたいと本気で考えている塾長や塾講師のひとからみればすごく重要です。
学校の授業が停まっている間に,一気に引っ張り上げるチャンスなのは間違いないのです。
だからこそ
かかるコストと成果の案配を世の塾長さんたちは毎年一生懸命考えるわけですからね。
話を戻しましょう。
塾の形態をここで一度洗っておきましょう。
集団
集団塾は,先生ひとりに対して生徒10人とか20人とか。いわゆる学校の授業のようなスタイルです。
生徒はひとりひとり能力も学習進度も異なるので,全員にとって同等に効果的な授業はできません。
一度にたくさんの生徒を教えられてコストを下げられる反面,ボリュームゾーンをターゲットにしながら授業はすすめられてしまって,置いていかれる子と,簡単過ぎてつまんないと思う子にとっては学習効果は低いです。これは構造上の問題なので,先生の責任ではありません。学校の授業も然りです。
個別指導
個別指導という言葉は,なんだかいろいろな意味に使われてしまっているので注意しましょう。
先生ひとり,生徒ひとり,という本当の意味の個別指導は,いわば家庭教師の学習塾バージョンです。生徒ひとりである以上,完全オーダーメイドの授業になります。生徒の個性に合わせた学習ができますね。
ひとりで勉強できない子たちはちょうどよいかもしれません。
一方でコストが圧倒的に高くなります。
そして,もうひとつの弊害は,教えられている間だけできるようになるという現象です。教えてチャンとか,言われないとやれないことにも繋がります。手取り足取りの指導はどうしても依存に繋がりやすいということです。
また
一対一での指導ではなく,個別に内容を変えて生徒ひとりひとりに対応したカリキュラムで学習指導しますよ,という意味で個別指導と謳う学習塾さんも少なくありませんので,このあたりは注意して欲しいとこですね。
先生一人,生徒4人ぐらいまでは少人数制とか言ったりします。
この場合も,個別指導ですね。
実際は1対1でも1対2でも,成果はあまり変わらないというデータもあるそうです。生徒がひとりで演習問題を解いている時間やマルつけをしている時間などを勘案すれば先生と生徒が関わっている時間は,実質的にはあまり差はないようです。
自立型
コンピュータ教材使って,生徒が各々自分の速度とタイミングで学習をすすめていくものです。わからないところは先生のフォローが入ります。
教材の善し悪しによるところは大きいですが,現代人にフィットしますし,これだと時間割から離れることができます。学年も無視できますし,自由な空間を作りやすいと思います。また,コンピュータが教えてくれるので講師の人数を減らすことができます。
塾長ひとりで運営することも難しくないでしょう。
あとはあれですね。
コミュニケーションが減らないような工夫は必要です。
学習塾って勉強するところのようで,子どもたちにとってはそれだけではないので,雰囲気とか通いたいと思う気持ちとか,そういうのが案外大事です。
そんな感じで今や学習塾の形態は本当にイロイロです。
細かいアレンジを加えてしまえばもうホント自由で多様です。
高校生向け学習塾ともなるともうなんだろ。
これはもうかつての予備校とはまったく異なるというか。
(これはまたいつか詳しく書こう。)
長くなったので次回へ続く。
>>その7
ゆるい学習塾のコンサルマガジン
まとめました。
サポートいただけると燃えます。サポートしすぎると燃え尽きてしまうので,ほどほどにしてください。
