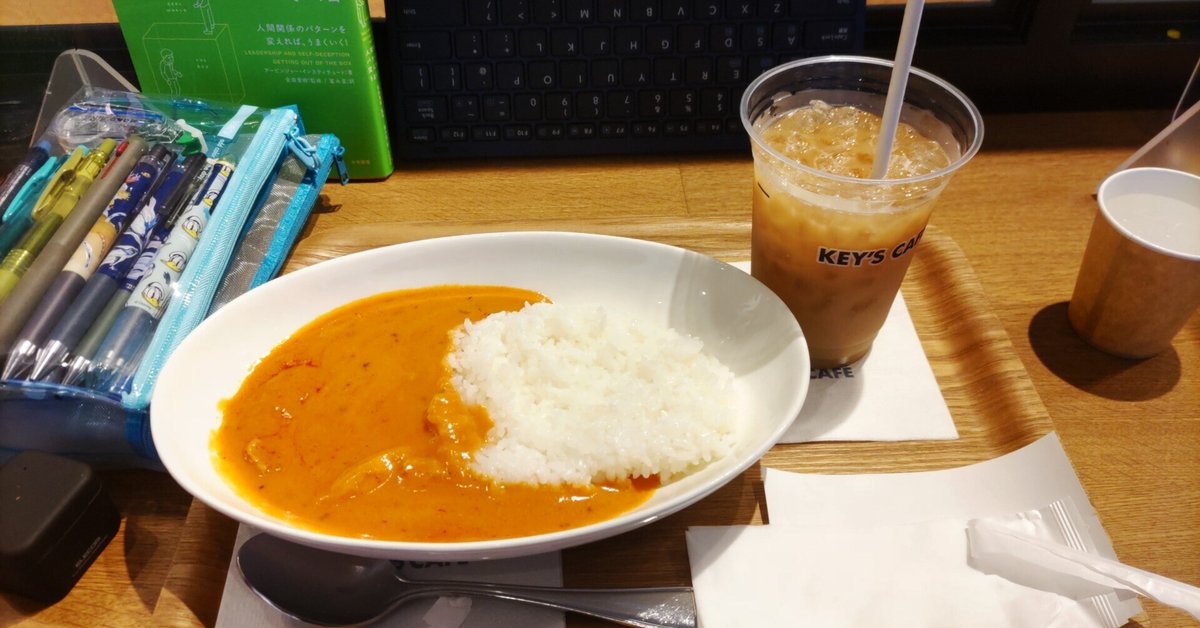
あと半月
あと半月で8月が終わりますね。気候的には夏の終わりは相当先になりそうですが、暦の上ではもう秋なんですよね。信じられない。
個人的には、袖無しの服を着ている女性がいなくなれば夏は終わったと毎年認識しています。ちなみにそのときは当然がっかりします(理由は聞かないでください)。
そういえば
夏休みの宿題でもっとも重いものといえば、読書感想文ではないでしょうか。読書感想文は他の宿題と違い、取りかかる前の準備にかなりの時間と労力を要する課題です。
私も子どものころは読書が嫌いで、読書感想文を最後まで残していました。正直なところ、読書嫌いな子どもを大量生産する要因のひとつが読書感想文だと思っていますがね……。
個人的に読書嫌いの子どもにおすすめする読書感想文の書き方
いろいろな人がいろいろなことを言っていますが、多くの場合は「人による」が基本です。
小説よりも説明文・論説文を選ぶ
前書きと目次でどんな本なのか(よく言うあらすじ)を書く
目次の中から興味を持った項目を1つ選んで重点的に読み、そこの要点と感想を書く
自分のことに置き換えてみる
関連する項目があれば、補足説明を入れるつもりで読んでみて、使えるところはしっかり入れる
読んだうえで今自分に何ができるのか、将来何がしたいかを書いておく(本によっては「~してみるといい」的な指南があるのでそれを参考にして書いてみる)
1.小説よりも説明文・論説文を選ぶ
小説は場面展開が目次に現れないことが多く、その分あらすじを正確に書く必要があります。その結果時間をかけて本を読んでいく必要があるため、読書感想文が嫌いな子どもには向きません。
そもそも読書嫌いな子どもは小説のように、想像力を働かせながら読む文章はすぐに飽きてしまううえに、字面を追うだけでいっぱいいっぱいで、感想文どころではなくなってしまいます。
2.前書きと目次でどんな本なのかを書く&3.目次の中から興味を持った項目を1つ選んで重点的に読み、そこの要点と感想を書く&5.関連する項目があれば、補足説明を入れるつもりで読んでみて、使えるところはしっかり入れる
説明文・論説文でできている本の前書きには主に筆者がどのような背景から、どういった意図で、どんなことを文章にしたのかが書いてあります。そしてその内容を細分化したのが目次となっています。
その中から興味を持ったところだけ本文を読めば、抵抗なく読み進めることができるはずです。また、感想を持つゆとりもできます。はじめは単純に「面白い」「驚いた」でも、ゆとりがある分その根拠を深掘りすることができます。そうなると、「なぜ」「どうして」という疑問が発生し、それを知るために他の項目を読み進めることをするようになってきます。
ゆとりを持てるように読んでいくことが大事です。
4.自分のことに置き換えてみる
といっても、これは絶対に必要なことではありません。というのも、自分が実際にその場にいないことについて書かれているため、読書嫌いな子どもに求めても想像ができず、ほとんどの子がやる気をなくしてしまいます。
自分がもしその場にいたら、と想像できる子にはそのとき思ったことを率直に書かせればいいです。また、その想像ができない子にはデータを取り出させてどう思うかを書かせましょう。数字や図形は視覚で認識できるものなので、その読み取りだけできればいいのです。
6.読んだうえで今自分に何ができるのか、将来何がしたいかを書いておく
自分の興味をベースに、今すぐにできること、今からやってみたいこと、将来やってみたいことのうち1つを書かせましょう。そのときにその理由も書かせましょう。
作文を書き慣れていない子どもは埋めることだけを考えて全部書こうとしてしまいます。1つに絞れば、理由やきっかけを考えるゆとりができます。
そもそも
読書嫌いな子どもが多い理由と作文を書くのが苦手な子どもが多い理由を考える必要があるのではないかと思います。
読書嫌いな子どもが多い理由を考えてみた
一概には言えませんが、幼少期の読書習慣の定着のためのステップとして、絵本の読み聞かせ→絵本を自ら読む→絵と字の割合を少しずつ絵<字とする→字の大きさを少しずつ小さくして、字の量を多くする、といったものがあると考えられます。
その中でいうと、絵本の読み聞かせの次の段階の「絵本を読む」のところにあるのではないかと思われます。結局、親子ともに普段家にいないため、家で絵本を読む習慣がつかないことが大きいでしょう。さらに、親が本を読むところを子どもに見せない限り、子どもが本を読もうとは思いません。
ただこれは超複合的な要因が絡み合っているため、解決には時間がかかります。
そして、動画コンテンツの普及と電子書籍の普及。大人であれば文字として認識できますが、子どもは画像として認識し、文字情報よりも早く読み取れる視覚情報を優先して拾いに行くようになります。
こういったところが読書嫌いの子どもが多い理由でしょう。
作文が苦手な子どもが多い理由も考えてみた
これも読書習慣が定着しておらず、いい文章に触れていないからというのがひとつ。さらに学校の先生(特に小学校)に文章の書き方を教えられる人が少ないからというのもあるでしょう。
さいごに
読書嫌いな子どもにはどんな本がいいのか、文章を上手く書くにはどうすればいいのかについて書いておきます。
読書嫌いな子どもにはどんな本がいいのか
ズバリ社会科や理科に関する本です。歴史、地理、政治、経済、生物、物理、化学、地学。この中に必ずひとつは興味を持てるジャンルがあるはずです。どのジャンルに興味があるのかわからないという子どもも多いでしょう。そういった意味では図書館に通うことを習慣付けるのも大事です。
文章を上手く書くにはどうすればいいのか
言葉の意味と使い方を知ることです。それにもってこいなのは「辞書を読む」ことです。辞書を読みこむことによって、言葉の使い方を例文から知ることができるからです。
そして、一文を作る練習を繰り返すこと。それによって言葉の意味と使い方を深く定着させることが可能です。
だいぶ長くなりましたが、悩みの解決の一助になれば幸いです。
それでは
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
