
「子どもの学習意欲が高まらない」という悩みを抱える保護者の皆様へ
新中学3年生をもつ保護者のみなさん!高校受験(都内)に向けた進路相談は私にお任せください!
はじめに
多くの受験生や保護者が迷う高校受験の進路選択には、正しい情報や適切なアドバイスが必要です。
しかし、公立中学校の先生は、進路指導を3年に一度しか行いません。つまり、中学3年の担任全員が進路指導に詳しいわけではないのです。
私は教師経験38年間で25回以上中学3年生を担当してきました。退職直前11年間では8回も中学3年生の進路指導を担当してきました。
私は都内の高校受験の進路相談に詳しくて、受験生の希望や能力、現在の学習状況を考慮して最適な進路を提案します。高校受験での進路相談は非常に重要な決断です。私と一緒に進路について話し合い、良い結果を得るための道筋を作りましょう。
さらに、個人の塾で受験のための三者面談代行も行っています。塾を経営している方々からの連絡をお待ちしています。(4月から)
自己紹介
① 都内の公立中学校(東村山・世田谷・町田・大田・府中・新宿・品川)で、38年も理科の教師として勤めました。また、世田谷・町田・大田・府中・新宿・品川の学校では進路指導の主任を務めました。
② 2024年3月には品川区の中学校を退職します。
③ 2024年4月からは都内の公立中学校で時間講師として働きながら、受験のコンサルティングの仕事を始める予定です。
④ 私は気象予報士の資格も持っています。
⑤ 趣味としては」、「ソロ活」「読書」「ひとり飲み会」「ひとり旅」などです。
⑥ さらに、私はYouTuber「しらスタ(ボイストレナー)」の父親でもあります。(ちょっとだけ息子の知名度を利用させてもらってます笑)
息子の挑戦する気持ちに大いに触れ、自らのビジネスの道を選ぶことを決意しました!
たくさんの保護者が、子どもが部活やゲームなど好きなことにはやる気があるのに、勉強へのやる気が出ないという悩みを抱えているでしょう。
その理由を、親子関係(人間関係)に焦点を当てて、解決方法をひとつご提案いたします。
参考にした書籍は「思春期のトリセツ/黒川伊保子著」です。
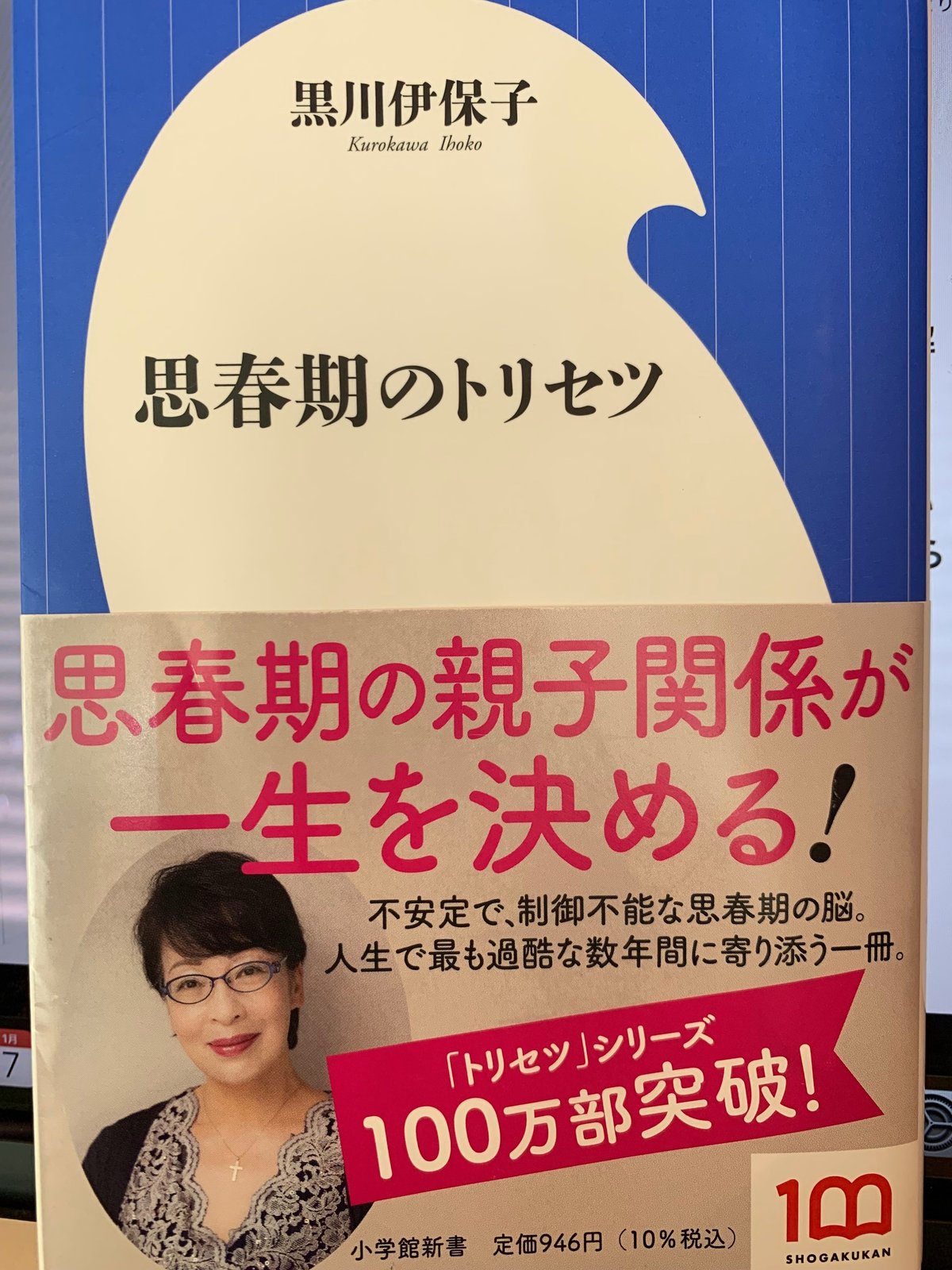
思春期は「親と子が、互いを敬愛し合える親友になる」ために用意された、子育ての最終イベント!
中学生の脳はポンコツ装置
一言で述べるなら、思春期は、子ども脳から、おとな脳への移行期である。
12歳までは子ども脳、15歳からはおとな脳。13〜15歳の間の3年間は、脳の移行期に当たる。ハードウェアとソフトウェアのバージョンが合わない、いわばポンコツ装置なのである。一生で一番、そう、新生児の脳より、ずっと不安定で制御不能なのだ。
〜中略〜
愛する子どものために、果敢に立ち上がり、賢く立ち回ろうじゃありませんか。
今回は、子どもの学習意欲を高めるために、絶対やってはいけないことをひとつ提案します。
思春期の子どもには「主語なしNO」を言ってはいけない!「主語なしNO」は子供の未来を奪う!
日本語は「主語なしNO」は相手を全否定している!
「無理」「ダメに決まってるでしょ」「何言ってんの」「バカなこと言ってないで、宿題しなさい」・・そんなセリフに覚えがないだろうか。主語をつけない全否定である。
〜中略〜
主語がないから、相手の脳の中では、暗黙の主語がつく。「世間」あるいは「ふつう」である。
相手には、「ふつう、無理でしょ」「ふつう、ダメだよね」というふうに聞こえる。つまり、世間を笠に来て、上から目線で、全否定しているように聞こえるのである。
このセリフを言った人が、一秒もこっちの気持ちになって親身に考えてくれてなんかいないのもわかってしまう。
また、いきなりの「ダメ」には、別の主語が付されることがある。「おまえは」である。そう、「おまえはダメなやつだな」と聞こえるわけ。
言ったほうは、「これ(この度のやり方)」がダメだと言っただけかもしれないが、相手の脳が「おまえは」を補完してしまうのである。
これは、生命の与奪権を握られている脳に、自然に怒る補完だ。ひねくれているわけじゃない、生存本能に基づく反射的な反応である。
「主語なしNO」は子供の未来を奪う!
頭ごなしの否定から、共感受けてからの主語つき否定に!
子どもの選択を「気持ちはわかる」と受け止めたうえで、「もっと別のアイデアもある」と否定する。
子どもの選択を、「そりゃ、ダメだろう。無理に決まってる」と阻止する親は、娘にとって目の上のたんこぶになってしまう。思春期に何度かそれをしてしまったら、「人生の選択に、いちいち口を出してくる、厄介な敵」として位置づけられる。
〜中略〜
一方、子どもの選択を「気持ちはわかる」と受け止めたうえで、「もっと別のアイデアもある」と言ってくれる親は、人生の師(メンター)になる。子ども自身の人生をより良いものにするために、共に心を痛め、最善策を考えてくれる支援者に位置づけられる。やがて親を失ったのちも、何かあれば、親の愛を思い出せる。
人生の早い時期に、親がくれる「きみの気持ちはわかるよ」付きの否定は、子どもたちの脳に「たとえ否定されることになっても、思いを表現する価値がある」ことを根付かせることになるのです。
子どもたちの学びの欲求を引き出すためには、心身ともに健やかな親子の絆を深めることが肝要なのです。
教師と生徒の人間関係も同じです。「主語なしN0」は言ってはいけない!
理科室では、私のところに昼休みや放課後にたくさんの生徒が集まってきます。受験に関する悩みや友人との関係など、一方的に話して帰っていくのです。特にアドバイスを求めるわけではなく、ただ共感してもらいたいのです。生徒たちは理科室を「第二保健室」と呼んでいます。
4月の受験アドバイスでは、学ぶことへの熱意を掻き立てるための親子の絆を深めるヒントもお教えします。ぜひ、お悩みを相談してみてください。
お知らせ!
2024年3月31日までは、公務員の立場なので、活動はできません。しかし、毎週金曜日の夜には、自由が丘の「酒場シナトラ」さんで読書をしながら日本酒を楽しんでいます。もし見かけたら声をかけてください。進路相談にもできるだけ対応したいと思います。

