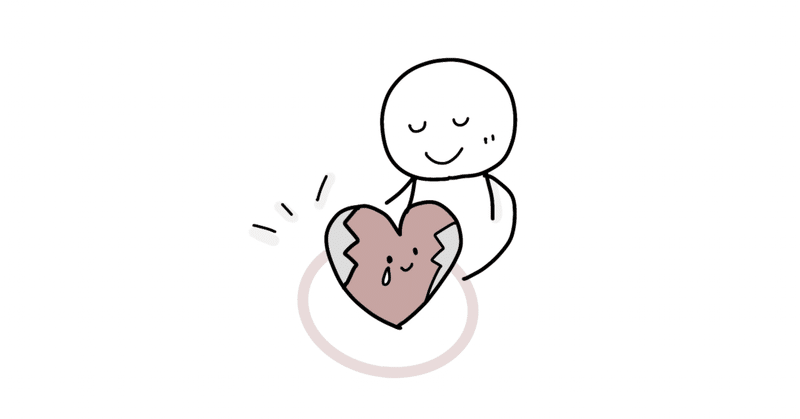
共感するって難しい
こんにちは、精神科医のはぐりんです。
共感する、共感できている、と良く言ったりしますが、実際に患者さんの診察をしていると、共感することって難しいな、と思う場面が多々あります。
今回は私(ロスジェネ世代♂精神科医師)が思う共感することが難しいと感じる患者さん達を挙げていきたいと思います。
一番難しいと感じているのが、御高齢の方、精神科医として診察している立場上申し上げにくいのですが、断トツと言っていいほど難しいと思っています。
想像してみてほしいのですが、例えば外来にきて戦争の話、あるいは宗教の話、昔と今とでは価値観も全然違うし、人生の年季も違います。患者さんの中には若い先生に話しても分かってもらえないだろう、と思いながら話している方もいます。今の高齢者世代、特に男性はプライドが高い方も多く、若い医師だと治療関係を築くのが中々難しいような方も多いです(こんな若造に言われたくない)。
他にも老年期うつ病という病名がありますが、御高齢の方のうつ病の場合、加齢に伴うライフイベント、例えば配偶者の死であったり、自身の健康問題、退職後の社会的な孤立感、などが契機となってうつ病を発症します。こういった事も年齢が離れていると実感的にわかりづらい部分ではありますよね。
次に共感が難しいと感じるのが女性。とある患者さんから言われて印象的だった言葉があるのですが、その方は抗不安薬(安定剤)をたくさん服用されていて、こちらから薬を減らそうと提案した際に言われたのが、「薬減らしたくないです。だって先生、男だからわからないでしょ」。「はい、ごもっともです」と心の中で返しました(笑)。
女性は月経によるメンタルバランスや、不安障害にもなりやすく(男女比1:2)、普段からかなり意識している部分ではありますが、それでも完全には共感というか、男ではわからない部分はどうしてもあると思っています。
他にもトラウマを抱えた方、統合失調症の方にしてもそうだし、発達障害の方も当事者にしかわからない苦悩があると思います。精神科医も人間ですし色々な先生がいるので、中々自身の経験に当てはめて追体験し共感するというのは難しいケースが多々あります。
上の例の逆の場合もあって、高齢の先生からしたら今の若い子たちの生活を想像するのは難しいでしょう(tiktokやマインクラフトを知らなかったり)。逆に子供がいる精神科医であればそういった部分は共感というか想像しやすいでしょうし、子育て世代の奥さんの苦悩なども共感しやすいでしょう。
酸いも甘いも知り尽くした、仙人のような万能な先生はいないので、あまり普段診てくれている先生がどういった先生なのかとか細かいことは気にせず、共感は完全じゃなくとも寄り添ってくれるような先生、実際に受診してみて先生や病院の雰囲気・フィーリングが直感的に合うかどうか、が一番だと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
