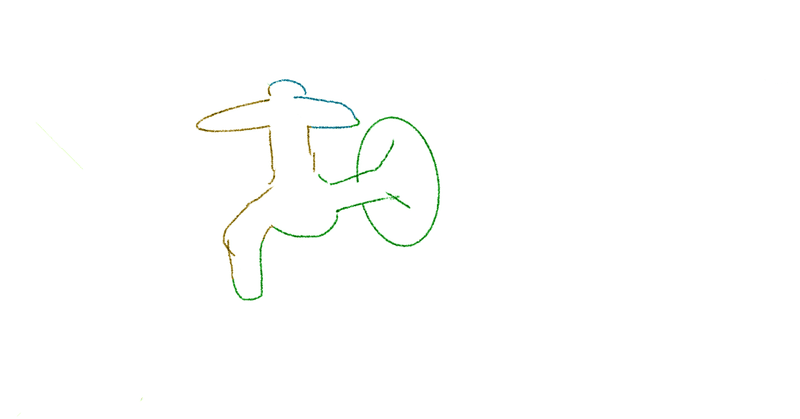
邪口
以前からずっと、写真から着想をえて、小説を書くことをやってみようと思っていたのですが、以下の企画を見つけ、書いてみました。
今回は以下の記事の写真から着想しました。
(※記事に完全な写真(切れていない)が載っているので、そちらをみていただけると物語とうまくリンクします)
「邪口(じゃぐち)」
「中級クラスの案件だけど。森田君、本当に一人で大丈夫?」
「ええ、問題ありません」
できるだけ堂々と、しっかりとした口調で答えたが、果たしてそれが彼女に伝わっているのか? 僕は『ミモザ』さんの目からそれを探ろうと試みたが、やはり無駄だった。そこはいつものようにしっかりと閉じられている。
「じゃあやってもらおうかしらね」
「は〜い」
少しめんどくさそうに返事をする僕に、「おまえ、何つくってるんだよ」と僕自身が文句を言ってきたのだが、僕はそれを無視した。
地点『pnst-04382』は、夜ほとんど人通りがない。だからその『邪口』が利用されるのは、もっぱら深夜である。商品の購入者は指定日時にその邪口へやってきて、あらかじめ指示されたリズムでその邪口てっぺんのバルブを叩く。そうやって鍵を解除した後、邪口をひねると、そこから希望の商品が出てくるという仕組だ。
邪口は全国におよそ15個ほど存在すると考えられている。そのうち、場所が分かっているものは、今回発見されたものを含めて3つ。1つは苦闘の末、何年か前に我々によって解体された。しかしもう1つの方は、かなり鉄壁に守られており、なかなか手が出せない。ただ、今回見つかった邪口に関しては、ガードと呼べるものはほぼ存在しない。おそらく邪口は訳あってほとんど利用されておらず、近く閉鎖されるのではと考えられている。その邪口が最後に使われたのはおよそ一年前で、その時に取引されたのは『特殊な音』であるという。
「その音は人にある種の変化を起こさせるんだ」
『堀田』さんは言った。
「音なんて、いつでも人に何かしらの変化を起こさせてますがね」と僕は言った。
「まあ、少なくともそれが誰にでも聞こえる音で、人への影響も良識の範囲内なら問題はないのだよ。ただ、その時取引された音は、鳴っていても人はそれを認識できず、そのくせ勝手に人を編集してしまう音なんだ」
*
邪口の近く、周囲を警戒しながらおよそ一時間待機した後、僕は素早く邪口の前にやってきた。軍手をはめて、試しに邪口を少しひねってみる。当然、邪口はびくともしない。さて、僕は息を整え、『ルーナップス』という呼吸を始める。分析は集中力が全てである。『ルーナップス』を始めて1分。フロー状態に入ると、すぐに目に全意識を集中し、邪口をスキャンする。
あたまに邪口の情報が一気に流れ込んでくる。僕はその情報の川の中から必要なものを選び出す。それらを統合し、その方法を組み立てていく。つまり、どうやればこの邪口を解体できるのか。
*
「邪口の下にある、2つのネジを外せば、確実に解体できます。ただ、それにはそれぞれのネジに合う特殊なドライバーが必要です」
ミーティングで僕はそう発言した。
「ドライバーをつくるのにどのくらいかかりそう?」
ミモザさんが技工士チームの『新田』さんにたずねる。
「まあ、1週間と言いたいところですが、そうなると手遅れになる可能性が高いので、3日でなんとかしましょう」
「よろしくお願いします」と僕は頭を下げた。
3日後、新田さんから木箱を手渡された。
木箱を開けてハッとする。そこにある2本の完璧なモジュール。美しく、同時にまがまがしい。
「ありがとうございます!」 僕は興奮して少し叫んだ。
「雨の日はもちろん、ドライバーの能力は落ちる。今日やるか、もしくは明日にするか。まあ、お前次第だ」
そう言い残し、新田さんは去っていた。
確かに今日は雨降りで、僕自身の能力も半減するのは避けられなそうだった。ずいぶん迷って、僕はベストが尽くせる明日を選んだ。
*
ネジにしっかりと合うドライバーに感動を覚える。『ルーナップス』の呼吸をしながらゆっくりとドライバーを回していく。ドライバーがネジを分解するその瞬間をとらえるため、全意識を集中する。
3/4ひねりしたところで、僕は違和感に気付く。何かがおかしい……分解が起こらない。いや……むしろドライバーに対してネジは全く反応していない。このネジは無機質で、停止している。僕は目に意識を集中し、改めて邪口をスキャンする。
果たして邪口は、この間僕がスキャンしたものとは別ものになっていた。
*
「しかたないわね」ミモザさんは言った。
僕は唇をかんだ。解体後、邪口をさらに詳細に調べることが我々の一番の目的だったのだ。
「すみません」
謝りつつ、悔しさでいっぱいになる。ミモザさんの心配が的中したのだ。
「あの邪口から、人の判断を狂わす音が出ていたことがわかった」
ミーティング後、一人で悶々としていた僕のところに堀田さんがやってきてそう言った。
「邪口はまだいっぱいある。邪口の危険がわかったと言うことで、次に期待してるよ」そう言って堀田さんは僕の肩を叩いた。
いつも読んで下さってありがとうございます。 小説を書き続ける励みになります。 サポートし応援していただけたら嬉しいです。
