
ウクライナからの避難民をケア 広島出身の医学生が接した「争うことの悲しさ」
ウクライナ国境の町、ハンガリー・ザホニーで、広島市西区出身の医学生が、ロシア軍の侵攻から逃れて来た人たちの医療支援に取り組んでいます。ハンガリー在住の椿原弘將さん、26歳。ボランティアとして活動しながら、SNSでの情報発信も続けています。遠く離れた日本でも「ウクライナの人々が置かれた状況に、関心を持ち続けてほしい」と呼び掛けています。(湯浅梨奈)
3月27日に実施した椿原さんとのU35インスタライブはこちら⇩⇩⇩
国境の町ザホニー「みんな不安を抱えていた」
ウクライナとハンガリーの国境の町ザホニー。男性は戦うためウクライナ国内に残っているため、避難してくる人の多くは、女性と子ども。「泣きながら座り込んでいる人もいる。みんな不安を抱えていて、顔は青白いです」と椿原さんは胸を痛める。他人の子どもを預かって逃げている女性や、独りで避難している中学生など10代の子どもも少なくない。

医師をサポートするボランティア
ハンガリー南部セゲド市にある国立セゲド大医学部4年の椿原さんは、赤十字国際委員会(ICRC)が募ったボランティアに、大学の4連休を利用して参加した。医師1人と学生2人でチームを編成。椿原さんはザホニーの高校で午後8時から翌午前8時まで、避難してきた人たちの体温や血圧を測定して、問診票を記入する。体調が悪そうな人がいないか確かめながら、声を掛けて医務室まで寄り添う。医師をサポートする役割だ。


医学生仲間5人とタクシーに乗り合い、6時間かけてたどり着いたザホニー。地元の高校は、避難する人たちの一時滞在施設として使われていた。ザホニー駅には、ウクライナから10時間以上かけて移動してきた子ども連れの女性たちで混み合う。首都ブダペスト行き列車の発着駅で、多くはここから更に、ドイツやイタリアなどに避難するという。椿原さんはこの2カ所で、体調不良の人をケアしている。
SNSで避難民の実情を発信
避難民の実情を国内外に広く知ってもらおうと、椿原さんは許可を得て、避難施設などで動画も撮影。インスタグラムのライブ配信機能やツイッターなどSNSを駆使して英語と日本語で発信している。
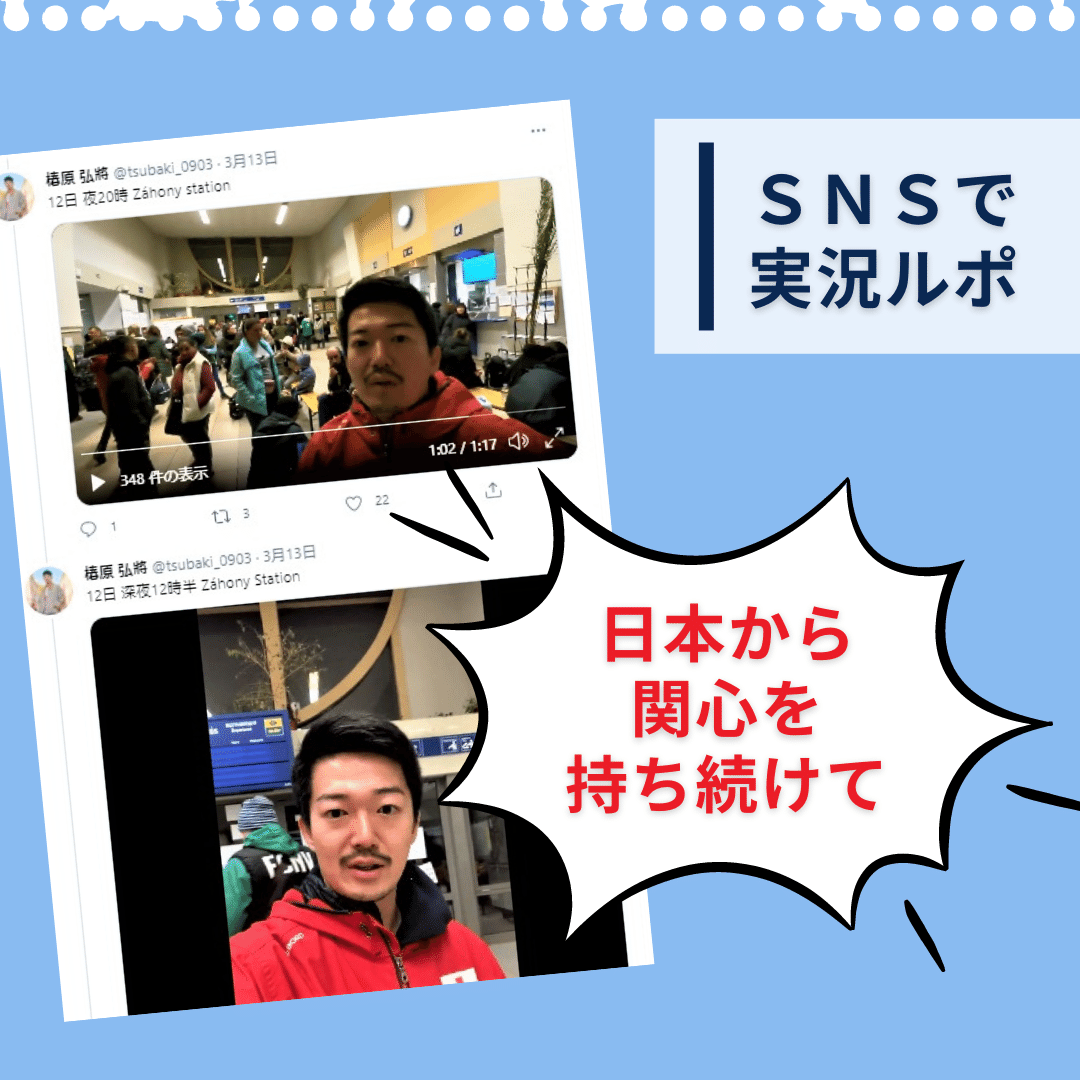
「時刻は夜の8時です。このあと午前1時ごろになると、4時の始発に乗られる方々がたくさんいらっしゃるので、駅はごった返していきます」「さきほど、駅の待合室には500人ほどがいました」‥。動画には、高校の教室にベッドが並ぶ様子や、大きな荷物と赤ちゃんを抱える母親たちの姿が映っている。

祖父は被爆者 平和に関心を持ち続けてきた
ボランティアに参加したのは、赤十字国際委員会(ICRC)から大学に呼び掛けのメールが入ったのがきっかけだった。ハンガリーを中心に欧州を飛び回り、巨大な魚を釣ってはインスタグラムに写真をアップしている椿原さん。4連休はギリシャに釣りに行く予定だったが「行くしかない」とすぐ予定を変更した。
祖父(77)は被爆者で広島市西区に生まれ育ち、平和に関心を持ち続けてきた。広島学院中・高時代には、原爆資料館が開く「中・高校生ピースクラブ」に参加。核保有国を含む世界の首脳に折り鶴を届けるなど平和活動に力を注いできた。そんな経験から「人の役に立ちたい」と、国際的に活動する医師を志し、高校卒業後、ハンガリーに渡った。
ウクライナからの避難民をケアする活動で接した現実は衝撃的だった。「自分の生まれ育った国を離れて、知らない国に避難せざるを得ない方々を目の当たりにしています。正直、自分の心の整理が着いていません」と椿原さん。「同じ人間同士が争うのは、本当に悲しい」
日本でできることは
日本でできることを尋ねると「今一番必要なのは、人道支援のための資金です」と言う。物資は、飛行機がロシア上空を飛べないため現地に届かない。「町の薬局は閉まり、輸送経路も遮断。持病を抱えて毎日薬が必要な人もいます。避難施設では子ども用の薬が特に少ないです。避難するにもお金が必要」と話す。
そんな現実をネットを通じて古里に伝えながら訴えている。「何より、ウクライナでの現状を一時的なものと考えず、心に留め続けてほしい。それが継続的支援の土台になります」
