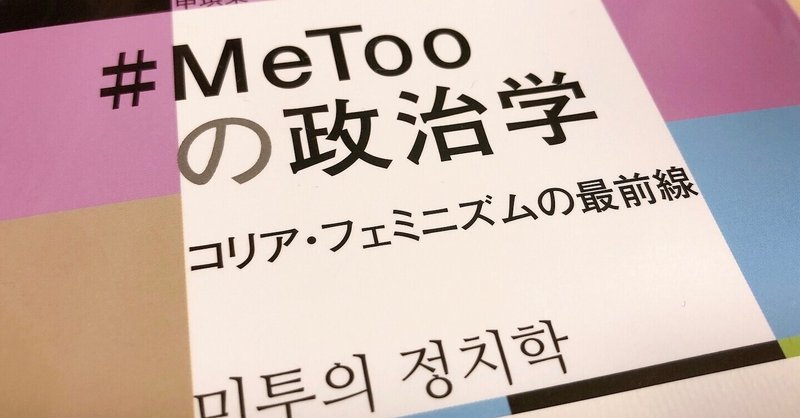
現状は「革命」的改善の余地があまりある/『#Metooの政治学 コリア・フェミニズムの最前線』 (鄭 喜鎭 ・編、金李 イスル ・訳/大月書店)
#Metooという文字列は、昨今世界中あらゆる地域で深刻な意味を持つようになった。本書の副題は「コリア・フェミニズムの最前線」とあるが、そこで展開される権力の不均衡と被害者への抑圧は、米国とも日本とも驚くほど近似している。
2017年末のハリウッドを起点として始まった性暴力・セクハラの被害者たちの告発と支援者たちとの連帯は、わずか数カ月後、韓国でも大きなムーブメントとなった。直接のきっかけになったのは2018年1月29日にソ・ジヒョン検事が韓国の放送局JTBCの看板ニュースに出演して、8年前の上司から受けたセクハラとそれを訴えた後のキャリアの不利益に対して証言したことである。その後次々と韓国社会のあらゆる分野で権威を持つ男性たちに対する性暴力の告発が続いた。特に、韓国社会に衝撃を与えたとされているのが、2018年3月、「忠清南道のEXO」と呼ばれるほどカリスマ的な人気を誇っていた韓国中西部・忠清南道の知事であるアン・ヒジョン氏の秘書による性暴力被害の告発である。(裁判の経過や様子は本書36頁以下に詳しい。)その後も2020年春に釜山市長、同年夏にソウル市長が女性部下や職員から訴えられ、政治的「進歩派」のリベラル左派の政治家に対する告発が続いた。告発後の深刻な二次加害や過剰に被害者の「落ち度」を問う「被害者裁判」の構造は、本書に帯文を寄せたジャーナリストの伊藤詩織さんの事件を彷彿とさせる。
本書では、一連の出来事について「問題は暴力が発生したことではなく、暴力が制度の一部になっていることだ。」と指摘されている(14頁)。性暴力の告発後、被害者は「拒否する権利」があるのに、なぜその権利を行使しなかったのか、と厳しく問われることになる。しかし、女性には男性には求められない「貞操を守る義務」が課される一方、男性には「相手の拒否を受け入れる義務」は課されてこなかった。それどころか、「教育」という名目で夫から妻への家庭内暴力は容認されてきたし、男性が女性に「夜伽を求める」ことは当然の権利とされてきたのである(本書113頁以下参照)。このように男性の女性への暴力が組み込まれてきた既存の制度は、現代にいたっても警察と司法に潜む根深いジェンダーバイアスというかたちで維持されている。
だからこそ、#Metoo運動は既存の制度の「外側」から始めなければならなかった。既存の制度の枠組みの中では、あらゆるスティグマによって被害回復・被害弁償の道のりが阻まれる。被害者は非難の対象となり、報復を受け、人生を破壊される。裁判でも被害者は無理解に基づく「落ち度」や「違和感」を追及され、主張が受け入れられることは極めて稀である。結果として、ほとんどの加害者は自分の地位を維持したまま、ホモ・ソーシャルな男性連帯の庇護の下、以前と変わらない生活を続ける。そこで、#Metooによって複数の被害者が集団的に証言することで、被害者の言葉に信憑性をもたせ、連帯を示すという運動がSNSを中心に展開されることとなった。運動を「大衆化」することによって、既存の権力集中の構造に風穴を開けようという試みである。
#Metooという運動はこのような運動であるからして、「革命」的な、“イリーガル”な側面を持つことは否めない。多くの事例で、被害者は加害者から「名誉毀損」の反訴を起こされることがその証左であろう。本書のまえがきにおいても、本書の刊行が進行中の裁判に与える負の影響について懸念せざるをえなかったことが言及されている。暴力が制度の一部として組み込まれている現状では、既存の司法や行政の枠組みで被害者を守り、被害者の訴えを社会に届けることは難しい。#Metooが必要とされる背景には既存の制度の致命的な欠陥がある。
だからこそ、#Metooは国を問わず激しい議論を呼び起こしてきた。「相手の拒否を受け入れる義務」を課されることになる男性はもちろん、女性にとっても、自分とも知り合いになる可能性があり、好きになる可能性がある男性が性的に暴力的であるという事実を直視し、日常的に自らが潜在的な危機に晒されていることを認めて生きていくのは楽ではない。世界は公正ではなく、あまりに残酷で、「革命」的改善の余地があってあまりあるという現状から目を逸らさずに、場所を超え立場を超え連帯していくために、本書は手放すことのできないお守りとなるだろう。
※図書新聞2022年2月12日より転載
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
