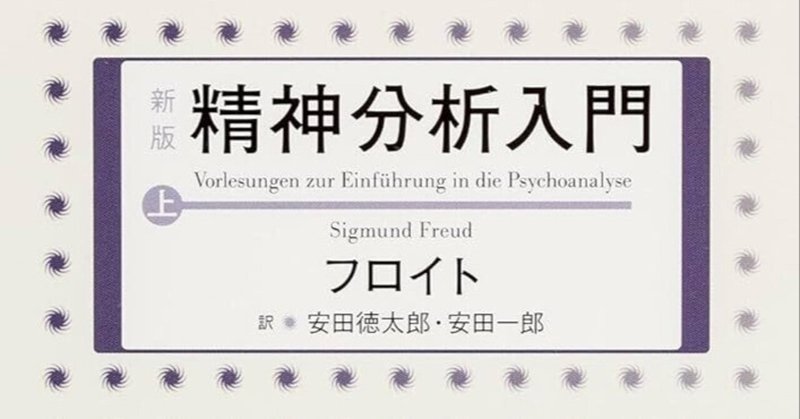
フロイト「精神分析入門 上巻」(1916年-1917年)
古典なだけあって面白いが、逆に疑問もわく。
当時と現代では当然時代が変化しているので、どの程度現代にも有効なのだろうか。
夢の解釈の話でかなりの分量をさいているが、あくまでもタイトル通り「精神分析」がテーマなので、「夢占いのハウツー」ではない。
といったあたりは留意点としたほうがよいだろう。
おもしろいと思ったのは、
・人が言い間違えたり、忘れたりするのは、深層心理でそれをガードしている。
・自由連想のくだり。人は自由連想で1番興味のあるものを連想する。しかしながら、自由連想というものはそれほど自由ではないらしい。
・夢を解釈する際に、夢に出てきた対象(アイテムとか)の名前や言葉にも意味がある。そこにも連想のヒントが隠されている。
・子どもの夢は前日の出来事のあらわれ。
・おとなの夢の一部は子どもの夢と機能がかぶっている。おとなの夢は歪んでいるので、それを直す必要がある。
といったあたり。
「フロイトは夢に出てくるものをなんでも性的な意味で解釈する」という話はよく聞くが、本書を読んでいるとたしかにそんな感じだ。フロイト自身は、「これはもう決まっていることだから」といった言い回しをする。
夢を解釈する際に、たとえば階段を上る行為は性的な意味がある、といった意味づけをしたのは誰なのか。そして、それを裏づけるためにどのような調査研究を行って、どのような結果が得られたのか、といったことが知りたい。
たとえばハイデガー「存在と時間」では、アリストテレスまでさかのぼって哲学の常識とされている命題に反論するといったことをしている。それをふまえると、フロイトの学説にもかっことした裏づけがあるのだと思うが、それについては今のところ説明されていない。
下巻がどのような展開をするのか楽しみだ。
サポートいただくと、よりよいクリエイティブにつながります!
