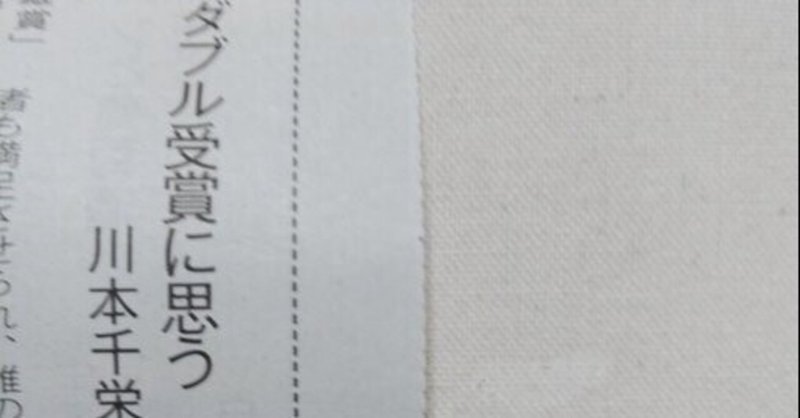
〔公開記事〕「ダブル受賞に思う」

今年、「塚本邦雄賞」「現代短歌社賞」「現代歌人集会賞」の三つの賞がダブル受賞であった。また、二〇一一年から二〇年の十年間に、四回のダブル受賞を出して来た「角川短歌賞」は該当作なし。
ダブル受賞と該当作なし、これらは相反することのように見えるが根は同じだ。選考委員が一つの作品を選べないのだ。
なぜ選べないのか。
一つには価値観の多様化があるだろう。しかし、それぞれの選評や選考座談会を読むと、価値観の多様化が原因で一作に絞れないというのとは少し違う印象を持った。それよりも選考委員の意識の問題の方が大きく影響しているのではないか。
「塚本邦雄賞」選評で北村薫は「二作授賞とすることにより、現代短歌の広がりを示せる」、穂村弘は「表現のゾーンそのものの拡大へ向かう試みがもっとあってもいい」と語る。このダブル受賞の根にあるのは二つの方向性を並列で認める態度だ。選べないというより選ばない。異なる作風の両方を受賞させれば、どちらの価値観の読者も満足させられ、誰の不満も買わないということか。賞の目指す所が曖昧だ。
「現代短歌社賞」選考座談会で気になったのは、とにかく自分の推す作品を受賞させたい、という選考委員の発言だ。阿木津英が、自身の推す伝統的な作品とダブル受賞であれば、将来性を重視した受賞作を出してもいいと発言した。他の委員は、阿木津の推す作品を認められず、しかし阿木津を説得もできず、各自の推す作品をダブル受賞に、と延々討議している。
「角川短歌賞」選考座談会では、この作品を選んだら自分達選考委員がどう問われるかを気にする発言が目立った。何を言われようとこれを推す、という気概は無かった。
ダブル受賞は気前のいいことでも多様性を認めることでもない。それは短歌という文芸の未来に深く関わることを避ける態度だ。今後どんな短歌が主流になるか分からないから保険をかけるのではなく、選考委員自身が今後あるべき短歌を決する覚悟で、全価値観を賭け、一作品に絞るべきではないだろうか。
現代短歌新聞 2022.1. 公開記事
