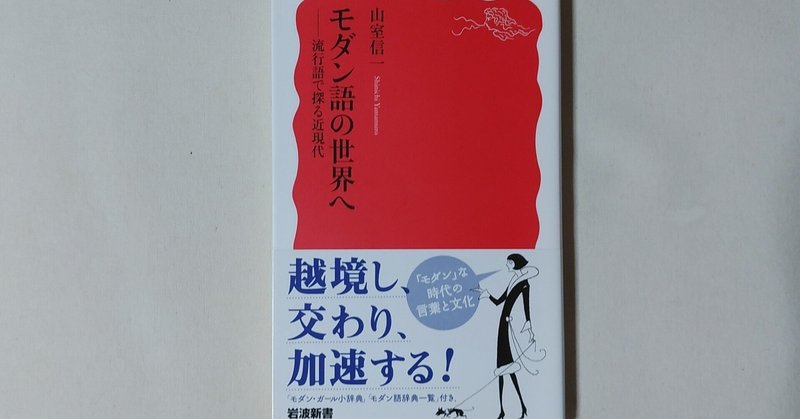
山室信一『モダン語の世界へ』─流行語で探る近現代(岩波新書)
1910~30年代に使われた新しい言語、モダン語を通して、日本の近現代を探る。単なる言葉の隆盛・流行をたどるのではなく、日本史・世界史の近現代とは何かを問うた骨太の本。近代と現代の複層構造にもたびたび考察が及ぶ。新書の手軽さは無く、むしろ学術論文と一般書の中間ぐらいの手応えだった。
〈第二次世界大戦後の日本では今風や当世流などを示すためにモダンを使うことは、少なくなった。それに代わって、同時代の流行や新しいことをさして「ナウ(now)い」「ナウな」などが流行語となったのは、1972年のことだった。(…)これらの流行語も既に死語となっている。同様に2010年に「ユーキャン新語・流行語大賞」でトップ10に入っていた(…)「~なう」も今や死語となりつつある。〉いつ、どの語が流行っていたのか、その特定は個人の記憶の中では曖昧だ。
〈1918年の米騒動後に成立した原敬内閣(…)の下ではまた政府の施策を周知徹底させるために、文語文に代わって理解しやすい口語体の公用文が初めて用いられた。〉これは大衆社会化への対応であるとともに国家総動員体制を作っていくためでもあったそうだ。
〈1921年に臨時国語調査会が設けられ(…)「常用漢字表」「仮名遣改正案」「字体整理案」「漢語整理案」などを決定した。1923年に発表された「常用漢字表」では(…)漢字1962字を選び、(…)2010年からは「改定常用漢字表」2136字が用いられている。〉しかし「漢語整理案」には実効性がなかったとする。
〈何よりも重要なことは単なる髪型や服装として軽視されている表象の中にこそ思想や個性が潜んでおり、それが社会を変動させていくという事実であった。〉毛断=ショートカット、裳短=短い裾丈、について。どちらも「モダン」の当て字。
〈自由民権運動の中で演説を歌にした「演歌」が生まれ、後に演歌師が歌う「はやり唄」に「流行歌」という漢字が当てられた。これを1927年にJOAK(現在NHK)が「歌謡曲」と名づけてから広まっていった。〉歌謡曲もこの時代に出来た語なのか。同ページには童謡の言葉の成り立ちも。
〈モダン語辞典で「てよだわ言葉=女学生間の言葉を冷笑する言葉。「よくってよ」「いやだわ」などをもじったもの。女学校・女学生がまだ物珍しかった過去の或る時期には、女学生の放縦ならんとする言葉が、ずいぶん下卑て聞こえた」(「新しい言葉の字引」)と説明されるものだった。〉これらは上品ぶった、気取った言葉と現在では理解されているものだろう。当時は下卑ていたのだ。
〈「新民謡」とは(…)北原白秋や野口雨情らが(…)起こした創作運動によって生まれたものだった。〉もちろん、当時はカッコ良かったはずだ。〈(1933年以降)経済不況下で、盆踊り歌に誰もが我を忘れて踊り狂う姿は、幕末の「ええじゃないか」の狂騒状況を想起させるとして警戒する声も出るほどであった。〉アツ過ぎる。そんなことになっていたのか盆踊り…。後年のディスコやクラブだね、全年齢層の…。
その他、同じ1924年に『文芸時代』と『文芸戦線』という二つの雑誌が創刊され、前者はモダニズム文学を、後者はプロレタリア文学のマルクス主義的理論づけをおこなったとする。文学を歴史的に考察する上で欠かせない一冊だと感じた。
岩波新書 2021.4. 1040円+税
