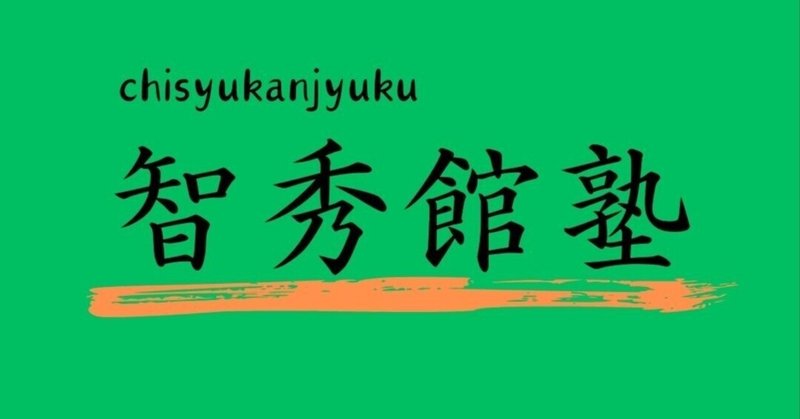
雑誌探訪 「kotoba 2024年春号」②
kotoba 2024年春号(2024)集英社
「kotoba 2024年春号」は「エッセイを読む愉しみ」という特集でした。その中で、古典の随筆を題材にしている記事が何点かありましたので、紹介します。
林望「随筆、この独特の世界」(P89~)
この記事では、作家であり国文学者である林望(はやし のぞむ)が、江戸時代の随筆を中心に紹介しています。
まずは三大随筆と言われる「枕草子(まくらのそうし)」「方丈記(ほうじょうき)」「徒然草(つれづれぐさ)」をあげています。
最初に、枕草子を、同時代の作品である「紫式部日記(むらさきしきぶにっき)」を引き合いに出しながら紹介しています。枕草子の物語的な魅力にも注目しています。
そして、方丈記をはさみ、徒然草の話題に至ります。徒然草が江戸時代に再発見された背景に、当時の時代の空気があるといいます。数々の徒然草の注釈書(徒然草の解説をした本)が生まれたことをあげ、それらが編まれるようになった背景に、当時の「隠者賛仰(いんじゃさんぎょう)」の空気があったというのです。
その後、そのような枕草子や徒然草の影響を受けたであろう作品について、近世(江戸時代)の文学をいくつか紹介しています。以下、一覧です。
井原西鶴(いはら さいかく)『西鶴諸国(さいかくしょこく)ばなし』
根岸鎮衛(ねぎし やすもり)『耳嚢(みみぶくろ)』
司馬江漢(しば こうかん)『春波楼筆記(しゅうばろうひっき)』
柳沢淇園(やなぎさわ きえん)『ひとりね』
松平定信(まつだいら さだのぶ)『花月草紙(かげつそうし)』
敬順(けいじゅん)『十方庵遊歴雑記(じっぽうあんゆうれきざっき)』
徳富蘆花(とくとみ ろか)『自然と人生』
薄田泣菫(すすきだ りゅうきん)『茶話(ちゃばなし)』
古典随筆の世界がそれぞれ影響しあい、同時にそれぞれのユニークなおもしろさがあることが伺えます。
様々な随筆を知るきっかけとしても、興味深い記事になっていると思いました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
