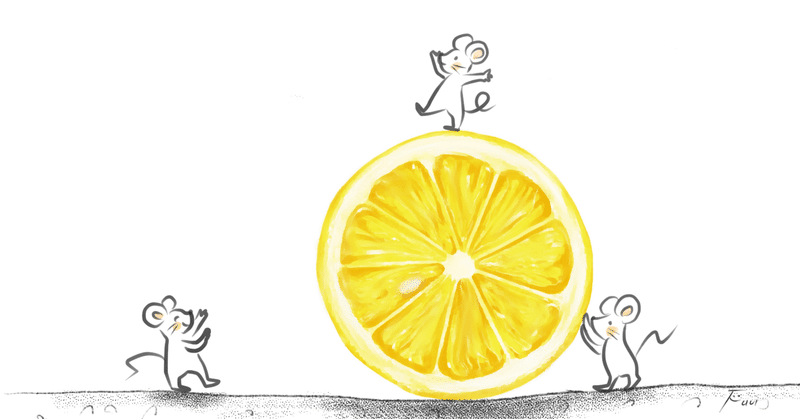
僕の未来予想図⑦
新人の朝は早い。僕の朝は職場の床掃除から始まった。6時起床、6時半自転車で出勤、7時に朝の掃除開始。就職後から毎日続けている、僕の朝の業務だ。一通り掃除を済ませると、お湯を沸かして、台所の湯飲みを片付ける。先輩たちは時々深夜まで仕事をしていて、各自の机に置きっぱなしのお茶を片付けるのも僕の朝の業務の一つだ。急いで朝の業務を済ませると、僕は机に置いた冊子に目を通した。先輩が来るまでに判例の問題点と解決策を考えておかないと議論にすらならない。新人の僕にはまだ慣れない環境だが、望んで選んだ道に進めたことの喜びの方が大きかった。
思い出して事務所の入り口を見ると、今朝の新聞が無造作に置かれていた。
新聞は所長のデスクに向きをそろえて置いておく、これも僕の業務の一つだ。何気なく新聞の見出し欄が目に入った。
「首相、不退転の決意で再度の法案審議へ」
あの時僕が
工場で話したのは、当時の首相が演説していたのは、この法案だった。超高齢化社会を前に政府は、慢性病の悪化に伴う安楽死の容認と、過剰な延命処置の抑制として医療報酬の改定を目指していた。一度は国民とマスコミの猛反対の前に否決され、その後の総選挙でも敗北し首相は退陣に追い込まれた。それでも今回再度登板し、新しい内閣の目玉としてこの法案を国会に提出したようだ。強者と弱者、それは時と立場により容易に入れ替わるものだが、弱者でしか存在できない人もいる、そんな議論はいつになったらできるのだろう。
あれから随分と月日が経った。警察には誘拐事件の共犯だと脅されたが、父だったヒトが同業者だったせいか、僕だけすぐに釈放された。
「このことは誰にも言うな、いいな。」
帰り際、僕らを殴りつけた男が脅すように僕を睨みつけてきた。
「わかりました。僕は僕のやり方でアンタ達を裁きます。待っていて下さい。」
そう言って僕は警官に背を向けて、古びた警察署を後にした。母親だったヒトのお姉さんが、僕を引き取ってくれた。聞けば母だったヒトは数年前に亡くなっていたらしかった。父だった人の仕打ちがひどくて、うつ病を悪化させての行為だったとお姉さんから聞かされた。
「貴方も大変だったでしょう。ゴメンなさいね、あんなことがあったのに何もしないで。妹とも全然連絡がつかなくて、私、何も知らなかったの。」
お姉さんの言葉には優しさと申し訳なさがこもっていた。そしてお姉さんは気を遣って、僕の名字を母方の姓に変えてくれた。
「昔のことなんて忘れて、自分の夢に向かって進むべき道を進んでね。」
そう言ってお姉さんは僕を励ましてくれた。後から聞いたのだが、お姉さんも元旦那だった人からDV被害を受けていたそうだ。だから今でも男の人が怖い、そう言ってお姉さんは時々僕に隠れるようにひとりで泣いていた。
それから僕はお姉さんの部屋でお世話になることになった。お姉さんは数年前に離婚し、今は事務職で働きながら何とか生計を立てていた。僕はお姉さんにお願いし、当座の学費の面倒をお願いした。週に何度か肉体労働のバイトをし、大学検定の準備のため朝から晩まで図書館にこもって受験勉強に励んだ。そして翌年の春、僕は有名ではないが地元の大学の法学部に合格した。奨学金をもらい、バイトと人権団体のNPO活動にも参加した。問題意識がより明確になり、僕は自分の進むべき道がよりはっきりとした。
大学をほぼ首席に近い成績で卒業し、何とか司法試験にも合格できた。現役での合格は20年ぶりの快挙だと、教授以下ゼミのみんなが僕を祝福してくれた。3年次からお世話になっていた法律事務所の先輩方が法学の道の現在地点を教えてくれて、試験対策にも付き合ってくれた。さすがに一度で合格するとは思わなかったよ、3年上の先輩は驚いたような笑顔で僕の合格を喜んでくれた。そして司法修習を終え、僕は晴れてこの法律事務所での勤務を開始した。弁護士になって社会の弱い人たちを支えたい、そのためには力が必要だ。工場でひどく殴られた時、右目の下にあざができたのだが、時間が経っても薄くそのあざは残っていたが、僕にはそれが過去を忘れない、決意を忘れないための証だと思って生きていくんだと心に決めていた。
大学に受かってからも、僕は時々あの工場を訪れていた。ヤンさんもアル君も強制送還されてしまい、工場は一時閉鎖の危機にあった。でもカネさんの尽力で何とか操業を続けて生き残ったようだ。僕が訪れるたび、カネさんは申し訳なさそうな顔でボクに謝った。カネさんの髪には、少しだけ白髪が混じっていた。
「修クン、ゴメンな。キミまで殴られてしもうて。」
こんなコトが何度か続いたので、いい加減何とかしようと思い、ある時僕はとっておきのお土産を持参することにした。
「そんなコトより、今日はカネさん囲んで飲みましょか?」
そう言って僕がカバンに詰め込んだ缶酎ハイを取り出すと、カネさんは嬉しそうに笑った。
「コレ、期限切れてないですよ。ホラ、見てください。」
僕が酎ハイの背中に書かれた賞味期限をカネさんに見せると、カネさんは参った、というような顔をして空を見上げると、缶のフタを開けて一気に飲みだした。僕もつられて空を見上げるように酎ハイを一気に喉に流し込んだ。炭酸の刺激が喉にしみ込んでいく。今までで一番おいしい味がした。
これからは、カネさんみたいに僕が面倒見れるように頑張りますから。いつかカネさんにそう言える日が来ると、そう信じて生きていこう。僕はそう思っていた。
(イラスト ふうちゃんさん)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
