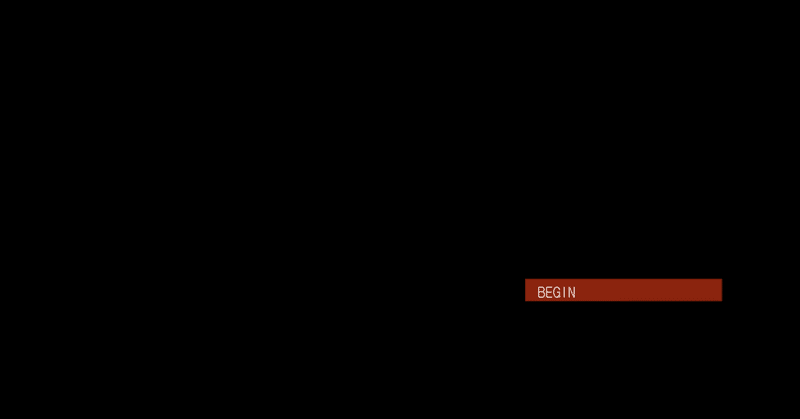
30 代半ばで ASD の孤独を受け容れた話
ASD を知るのは難しい

自閉症ときいて何を思い浮かべるだろうか。
空気の読めなさ?
奇妙なルーティン?
殻に籠もったいやな感じ?
発達障害の当事者が昔から身近にいた僕にとっては「他人の気持ちがわからない苦しみ」で、だからこそ、ひとの気持ちがわからないことがわからない僕には無縁の障害だとおもっていた。
自閉スペクトラム症 Autism Spectrum Disorder、通称 ASD とは、アメリカ精神医学会が「精神障害と統計マニュアル」の最新版 DSM-V で分類した神経発達症群のひとつだ。ひとりの当事者にさまざまな症状(あるいは特徴)がことなる濃淡であらわれること、また、いわゆる定型発達者と呼ばれるひとにもその特徴がでることに「スペクトラム(連続体)」のゆえんがある。
DSM-V では ASD の診断基準が以下のふたつにまとめられている。
・社会的コミュニケーションおよび相互関係における持続的障害
・限定された反復する様式の行動、興味、活動
いずれも抽象的で、非当事者的で、僕の自己認識にはかすりもしなかった。
ひとを笑わせることが得意だし(ユーモアは対人関係での強力な武器だ)ルーティンを守っているつもりもないし(たんに着るもの飲むもの食べるものへのこだわりが強いだけ)コミュニケーションに支障を感じたことは大人になってからはないはずだ(だよね?)。
もっとも、『自閉スペクトラム症の女の子が出会う世界』の著者サラ・ヘンドリックスは、43 歳で ASD の診断を受けるまでに ASD 研究で修士号を取得し、関連書籍を 5 冊も執筆し、数千人の ASD 者に訓練を施してきたという。理論実践ともにエキスパートの人物でも自分自身が ASD 者であることを検討するのには長い時間を要したそうだ。
ASD のグラデーションはそれぐらい彩り深く、他者や帰属集団への擬態の必要からときに自分自身にさえその特性を覆い隠してしまう。
ひょっとしたら、あなた自身も、あなたの愛する隣人も、発達障害のあざやかな彩りの「あわい」でひと知れず苦しんでいるのかもしれない。
奇人変人まみれのわが人生

ASD を疑いはじめたのはある ASD 者との会話がきっかけだった。
もともと僕の身のまわりにはメンタルヘルスに問題を抱えたひとが多く、たとえば父親が ASD 者で、母親はそれによるカサンドラ症候群で長年鬱病に苦しんでいた。また、兄も兄で、学生時代に大量の風邪薬をウィスキーで流し込んで寝ゲロで死にかけるというなかなかユニークな(?)自殺未遂を経験している。遺伝的なことをいえば、父方の家系には統合失調症で長年入院生活を強いられている叔父もいるらしい。
知人友人にも多い。
中学生の頃に少しだけ付き合った女性は若くして結婚したあと大量の睡眠薬の写真を mixi にあげて「不慮の事故死」を遂げた。僕が東京にいた頃に仲がよかった音楽家は、統合失調症、自殺未遂、強制入院、そして脱走をひととおり体験していた。その後の彼(あるいは彼女)は恋人に捨てられたのち消息がつかめない。どこかで生きていればと祈るばかりだが、正直諦めてもいる。
生死に関わらないまでも、学生時代にはなにか心が動揺するとパニックになって奇行に走る女性が身近にいた。しかも結構な頻度で。今でも覚えているのは女子トイレのペーパーをすべて廊下にもちだして紙を撒き散らしながら大声で喚いていたことだ。
今でも心から笑えるが、小説創作のリアリティ追求のために実家の風呂場で糞便を顔に塗りたくって「兄貴がまた変なことしてる〜!」と母親にチクられた後輩もいた。メンタルヘルスとはずれるが、彼との思い出は学生時代でゆいいつ暗い影のないものとして残っている。
ほかにも、僕がいまも心から賢いと慕っている友人は「他人の気持ちがわからない」と口癖のように嘆いていたし、僕が批評の師のひとりとして尊敬する日本語教師は考えごとへの過集中から歩きながら壁にぶつかって頭を怪我するというマンガのようなことを平気でやっていた。某有名パン屋でお世話になったオーナーシェフはおもちゃ箱同然の脳みそを衝動性や過活動とともにいつももて余していた。
なにより、芸術鑑賞の才能と呪いを僕にあたえた師匠については以前書いたとおり。
ヤドキン氏はよく激昂し、毒を撒き、嘲り、自身に都合の良いように記憶を改竄しては周囲に吹聴する悪癖があった。傍目にはその改竄が自覚的にはみえなかったのでなおのこと質が悪い。その餌食になったのは彼が期待し、眼を掛け、親しくなり、失望していった若いひとたちだ。ヤドキン氏はつまり、孤独の業火に焼かれた人格破綻者だった。
僕の人生は愛すべき奇人変人病人狂人たちに恵まれた。
自分自身はというと “自殺未遂の未遂” をしたぐらいで、今でも「死に損ねた」「狂いきれなかった」という此岸にとどまり続けた感覚が強い。
メンタルヘルスのサラブレッドを自称してきたものの、僕はあくまで彼ら彼女らの狂いを知り、受け容れ、尊重し、サポートする側の人間で、けっして逆ではなかった。だれがなんといおうと僕の自己認識は「常識に従わない選択をとるだけの常識人」だ。
そう、今年の 4 月までは。
見過ごされがちな心の苦しみ

あのひとたちはエンタメになるけど私たちはちがう。心の苦しみはひとを楽しませない。
脳の機能や配線のユニークさは奇行として表にでやすい。
いまや配信&実況の大戦国時代。演技であれ、天然であれ、大多数のひとがおもいつかない奇妙奇天烈な言動を大真面目にかつ高頻度にとれることはエンタメとして大きな武器になる(いまや世界トップクラスの女性 twitch 配信者に成長した赤身かるびはその典型だ)メンタル系の「障害」も時と場所と見せかた次第ではひとを楽しませる魅力に化ける、かもしれない。
だが、心の苦しみはどうだろう?
ASD 当事者として率直に話されたその言葉は僕の胸をしたたかに撃った。ゲーム批評系 Discord 鯖でのひと幕だ。
僕の人生はたしかに愉快な奇人変人に彩られていた。彼ら彼女らの奇行が傍目にもわかりやすいからこそ僕はその内面を想像し、寄り添い、不必要な偏見をもたずにおたがい気安く付き合えた。でも、脳の特性が表にでにくいひとはどうだろう?ひと付き合いの対処法を懸命に学んだがゆえにその苦しみが見過されてしまっていたかもしれない。
たとえばその画面越しの相手の苦しみをどれくらい想像できていただろうか?
そうして、僕は ASD の心の苦しみを知るために壊れかけの本棚の奥からいくつか本を抜きだす。
そのひとを今よりもっと理解したかったのもあるし、父親をはじめ、僕の人生ですれちがったひとたちの内面に眼を向けたかったのもある。
もともと、僕の哲学的関心には「他者を他者としていかに尊重するか」という切実な問いが出発点にあった。学生時代にはじめて付き合った恋人がいまでいう生理前症候群 PMS がかなり重く、月の半分は神話世界の荒ぶる神のような一触即発な状態で、それを、慢性的な離人症をともなう精神不安を抱えていた僕がどのように受け容れて適切に振る舞うべきかわからなかったのだ。
それも、スマートフォンがなく、日常的なグーグル検索もあたりまえでなかった頃の話。今でこそ当時の状況をある程度整理できているが、自分のメンタルヘルスの問題も彼女の女性ホルモンのこともおたがいよくわからなかった。実際、低用量ピルを使いはじめてから憑き物が落ちたように気分の波が安定し、性欲も減退し、そしてすぐ別れることになる。
余談だが、その恋人にはかなり手痛い振られかたをした。
結論からいうと東京のアングラシーンで音楽活動をする “生死鴉” という男性に奪われたのだが、その活動がなかなかユニークで、「生」あるいは「死」と書いた半紙をライブ中に踊りながらばら撒いていたらしい。で、彼には私が必要、私がそばにいないとダメになると別れを告げられたのが大学 3 年生の頃。今でもクソ笑える。
……という話を凍結前のアカウントでいち度だけツイートした日のことだ。
僕の 28 歳の誕生日で、運転免許の学科試験締切最終日をいち夜漬けで合格したあまりに出来すぎた日の帰り道。徹夜明けの疲れと安堵感で気が大きくなっていたのだろう、例の生死鴉と天秤に掛けられて捨てられた話を渾身のネタとしてツイートした。すると、ときたまイイネを交換する間柄のフォロワーからすぐにリプライが飛んできた。
でもお前わたしのこと好きじゃなかったよね?
このときの恐怖を越える映画を僕はいまだ知らないでいる。
「今何を考えているかわからない」

今となっては彼女の真意はわかりようもないが、実は僕にはごく近しい間柄のひとしか知りえない「欠陥」がある。
それが、今何を考えているかわからない、だ。
アイコンタクト、表情、口調、身ぶりといった非言語的手がかりの表現と読み取りに困難を抱えることは、ASD の明白な特徴であると考えられている。定型的な発達段階にある子どもたちにとって、これは相互的なスキルであることに留意しなくてはいけない。他人を「読む」能力だけでなく、他人が自分を「読む」ことができるように、適切な非言語的手がかりを示す能力でもあるのだ。
うん?
他人が自分を「読む」ことができるように??
ASD の本を読みはじめて眼から鱗が落ちたのがこの一節だ。他人の気持ちを「読む」ことはかなり得意だと自認し、だからこそ(いくらかの傾向はあるにせよ)自分は ASD ではないとしたコミュニケーション上の決定的根拠。どうもそれは相互的である必要があったらしい。
生死鴉の前にあえなく膝を屈した僕はその数ヶ月後に別の女性と付き合いはじめる。
僕の記憶がたしかならその交際は 2 年前後におよんだが、そのあいだにジッと顔を視られながら「今何を考えているの?無??」ときかれた回数はおそらく 500 はくだらない。もちろん彼女は「普通」ではなかった。けれども、暴虐な母親との生活に心を蝕まれた彼女に安全な居場所を作ってあげられなかったのも事実だ。
大学院卒業後、僕は当時付き合っていた女性と約 8 年間ともに京都で暮らした。正確には家を出ることを決め、別れ話をし、引っ越しの準備をしながらいまこの文章を書いている。そのひとからもやはり「今何を考えているの?」と繰り返しきかれ、こちらの表情を真剣に読みとろうとするまなざしを毎日感じていた。結局、彼女にたいしても愛情と安全で心を満たすことができなかった。
ひょっとしたら、生死鴉を選んだ彼女にもおなじ悩みを与えていたのだろうか?
それはわからない。
でも、最後に家族全員で食事した晩(あるいは大人になってはじめての家族会食)に父親から「今までおまえが何を考えているかわからなくてずっと不安だった」と泣きながら抱きしめられたことをよく覚えている。それは、ひょっとしたら、父親が ASD だからわからなかったのではなく、僕がそうだから読みとらせてあげられなかったのかもしれない。
なぜ「今何を考えているかわからない」かはたぶん常に何かに気を奪われているからだ。
それはたとえば、家事であり、仕事であり、文章であり、趣味であり、twitter であり、考え事であり、眼前の出来事であり……とにかく全部だ。僕はたぶん、一緒にいる「ひと」ではなくつねに「何か」にふかい没入状態にあり、ちかくの人間の気持ちまで意識できないことが多い。というかそれがほとんど。しかも、その沈潜を破られること、すなわち、いきなり話しかけられて無理やり意識を引き剥がされることにはかなりの苦痛と不快感がともなう。
そのため、僕がだれかと一緒に暮らすにはなにか医療的訓練か、ASD 的ライフハックか、それとも僕の「欠陥」を受け容れたうえで折り合えるパートナーかが必要なのだろう。
実のところ僕自身はそうした自分の没入癖を「異常」とは考えてこなかった。
むしろ、かつての恋人にせよ、父親にせよ、同棲相手にせよ、なぜにそうも他人の感情を「異常」なまでに気に掛けるかわからず、それは僕のことを「無愛想」「冷たい」「恐い」「いつも怒っている」「挨拶できない」「偉そう」「すましている」などと評してきた職場の同僚らにもいえる。
要するにひとがなぜ僕を放っておけないのか、感情的なねっちょりした付き合いを職場でも求めてくるのか、その大多数の「異常」を受け容れられずに僕は長いこと孤独に苦しんできた。
ひとの気持ちを「声」で理解する

いつも「何か」に気を奪われていること。
それゆえに一緒にいる「ひと」の気持ちを意識できず、今何を考えているかわからないという印象を与え、無理やり意識を剥がされようものならおもわず不快感が漏れだしてより一層関係を悪化させてしまう……僕の対人関係上の苦しみは突き詰めればこの悪循環に集約される。だから、おなじ家でながく生活するひとほどこの「欠陥」に苦しみ、おなじ職場で作業するひとほど悪印象をもちやすい。オンラインでしか繋がらないひとは僕の「欠陥」と孤独を知らずにいられる。
不思議なことに、僕自身が他人の気持ちを読めないことで苦しんだ記憶はない、少なくとも大人になってからはそうだ。
一般的にひとは相手の表情、とくに眼からその気持ちを読むらしい(そして、眼をあわせることでなにか情緒的な繋がりを育むらしい)。
ASD 当事者として長年啓蒙活動を続けているテンプル・グランディンは、高機能自閉症のひとと正常に発達しているひとの脳はアイコンタクトにおいて正反対の反応をするという機能的 MRI による研究を紹介している。
……自閉症の人は、相手が目を合わせようとしないときにふつうの人が感じるものを、相手が目を合わせたときに感じるのだ。逆もしかりで、相手と目を合わせたときにふつうの人が感じるものを、相手が目を合わせないときに感じる。まわりの空気を読もうとしても、ふつうの人が出す好意の合図を嫌悪の合図と解釈するかもしれない。
僕の体感では、他人の眼を観ることには刺すような「うるささ」の不快感を覚える。相手の表情から気持ちを読みとることにはたぶん支障はないが、それ以上になにか、情報過多の「圧倒される」感じを受けるため、表情をどうしても読みたいときは(あまりないが)顔をチラリと確認程度に盗み見て済ませがちだ。もっとも、特別な間柄のひと、つまり、恋に落ちたひととすらアイコンタクトを避けたがるかはわからない。
では、普段、相手の顔を見ずにどうやって気持ちを読むかというと、ひとえに声の調子と言葉遣いの変化への解釈だ。
声の具合からそのひとのパーソナリティーを推測し、その調子や弾み、ふるえ、タイミング、語彙選択の変化からそのひとの心の動きを察知し、その場の文脈や人格上の分析などから心の動きにより適切な「解釈」を与える……「緊張している」「苛立っている」「遠慮している」「我慢している」「嘘を付いている」「寂しがっている」「夢中になっている」などだ。正直、結構な集中力が要求されるため眼を観ることはノイズでしかないし、当然ながら疲れやすいので長時間におよぶ対面の会話は相手によるができるだけ避けている。抽象的な議論を好むのもたんに「ひと」に興味が向きにくいだけでなく、相手の心情を読みとる努力があまり必要ないのもあるかもしれない。
客観的にいってこれはユニークな心の読みとりかただろう。
他人の声の質を芸術鑑賞のごとく微細に聴きとり、文章表現として語彙選択の違和に気付き、その心の動きそのものを感じとること、そして、いまの場の状況や相手の人格的な分析から心の動きの背景を抽象的に組み立ててその動きに適切な解釈を与えること。これらはすべて批評家としての僕に得意なことで、だから、自分ができないことにできることを無理やり転用しかつ組み合わせて奇形的に解決した感触がある。卵が先か、鶏が先かではあるものの、僕なりの対人コミュニケーション上の「擬態」の技法がこれなのだろう(ひょっとしたら、だから、作品批評が得意なのかもしれない)。
ASD の本を 4、5 冊読んでおもうのは、ASD はある種の脳機能上の逸脱であり異端であって、ASD だからこうといった決まりきったパターンがあまりないらしいことだ。
とりわけ、自分の「症状」を帰属集団内で抑制することに強い圧力が働きがちな女性や、他人の情緒的な行動を学習して「擬態」を覚えた大人ほど第三者的な区別がむずかしくなる。
とはいえ、実験心理学者の井出正和は、ASD 者を対象にした質問調査で 9 割以上のひとが感覚過敏や鈍麻といった感覚上の問題を抱えているという興味深い報告を紹介している(もちろんそれも、個々人のなかでさまざまな側面をともなった「逸脱」であり、決まりきったかたちがないことには変わりないようだ)。
ひょっとしたら僕の他人の感情の「聴きとり」も、批評的訓練の副産物というよりは聴覚過敏のなせるわざなのかもしれない。
感覚世界の特異さと苦しみ

感覚世界の特異さは、ASD の診断基準として DSM-V に付け足されたものの、世間ではあまり知られていない傾向かもしれない。
感覚刺激に対する過敏さまたは鈍感さ、または環境の感覚的側面に対する並外れた興味
先述の井出正和によれば、感覚過敏の背景として ASD 者の刺激にたいする検出閾の低さと慣れにくさがある。つまり、ASD 者は定型発達者と比べてより小さな刺激にも知覚が生じ、繰り返しの刺激にも順応しにくいという(定型発達者はむしろ刺激に慣れるのだ)。余談だが、芸術鑑賞と作品制作において刺激に慣れにくいことはある種の才能として機能すると僕は考える。
さらに、井手の研究によると、感覚過敏には空間的要因だけでなくどれくらい細かく刺激の変化を感じとれるかという時間的要因もあるそうだ。
その結果、時間分解能の高さ(どの程度短い時間差で刺激の順序を正確に答えられるか)と感覚プロファイルの感覚過敏、感覚回避のスコアとの間に負の相関がみられました。この関係性は、ASDの方だけでみられ、定型発達の方ではみられませんでした。つまり、高い時間分解能をもつASD者は、日常生活においてより強い感覚過敏を経験していることが明らかになりました
実をいうと、自分の感覚世界の特異さをこの本を読むまで反省的にとらえてこなかった。
子どもの頃から濡れた足に砂が纏いつくのが気持ち悪いから海には行きたくなかったとか、真冬の家族旅行で服のなかに雪をしつこく入れられて「痛かった」とか、大人になったいまでも他人には心地よい熱さのものがさわれない(僕は「猫肌」と呼んでいる)とかはあくまで我慢の問題で、発達障害と関係する可能性には今のいままで思い至らなかった。
ひょっとしたら、部屋の照明の白さが視覚に刺さって昼夜問わず橙色にしていた頃、同居人から「眼がおかしくなりそうだ」と禁止されたときにもしも感覚過敏という言葉を知っていたなら、たんに黙って我慢するのとはちがう選択肢をとれていたかもしれない。
あるいは、自尊感情がゴリゴリ削られていった高校球児の頃に知っていたら。
硬式野球の経験者しか知らないことだが真冬の野球はとにかく痛い。
いちばん最悪なのはバッティング練習で、時速 130km の硬球が金属バットの芯以外に当たろうものならまた握って振ることすらままならなかった。手許に当たった瞬間バットを落としてしまったこともある。もちろん、みんなそれなりに痛かったはずだが、僕はとにかく耐えられず、手が痛みで痺れたあとはわざと空振りして誤魔化すようになった。
当然、チームメイトはそんな仲間を快くおもうはずはなく「はやく慣れろ」「気合が足りないだけ」という言葉から僕はいまだに「強い刺激を我慢できない意志の弱い男」という自己認識に囚われている。
激辛好きの美術家の師匠の呪いもあるだろう。
感覚過敏と鈍麻の問題は、個々人のさまざまな「こだわり」としてより軽微な場合もより甚大な場合もありえる。僕はまだ特殊な状況のみの苦しみで済んでいるが、日常生活に支障をきたす「症状」として顕在化しているひともいるはずだ。あなたの身近にいる奇妙な習慣をもつひともその裏には感覚上の苦しみがあるかもしれない。
一見すると「頭のおかしい」行動や習慣のもとにはそのひとの生きる感覚世界の特異さとそれによる心の苦しみが拡がっている。
僕らにできるのはせめて隣人の「おかしさ」の裏にある苦しみに想いを馳せていたわることぐらいだ。
ASD を認めるのは難しい

発達障害の可能性を認めることは正直にいうととても苦しい自己認識の修正だった。
「他者を他者としていかに尊重するか」という哲学的な問いの裏には「なぜ僕は他者を侵害せざるをえないか」という根本的な加害性への自覚が張り付いており(思い出してほしい。当時の恋人はひと月の半分はとても機嫌が悪く、かといってそっとしておけるほど僕は大人じゃなかった)、あれからずっと、対人関係上の悩みはその問題をていねいに切り分けて理解することだけが精神不安への対処法だった。
そのため、他人の「異常」として、あるいはたんに受け容れざるをえないものとして呑みこんできた他人の特性すらも、自分の「異常」の反映でしかなかった(かもしれない)ことにはいまでも動揺を抑えきれない。
もしも自分がまともな「普通」の人間だったら?
もしもこの苦しみがひとに理解されないとしたら?
もしもこの特性に折り合いを付けられなかったら?
「他者を他者としていかに尊重するか」は愛の技法の問題であり、僕の失敗続きのこれからの人生でいままでとはちがう答えを模索するしかないのだろう。たとえその正否にこの身が朽ちるまで焼かれ続けるのだとしても。
僕がこの自傷的な文章を書いたのは、ASD 当事者の心の苦しみを想像することをとおして自分自身の苦しみもまたひとに理解されずにずっと押し殺されてきたことに気付いたからだ。
もともと、自分の感情や記憶と向き合うのが得意ではなかった。
今、怒っているのか、かなしいのか、寂しいのか、苛立っているのか、辛いのか、妬いているのか、苦しいのか、悔しいのか、諦めているのか……その不快な感情を理解しようとすると急にあたまがもやがかる。当然、それらを言葉にして伝えることはおろかぶつけることもできず、居心地の悪い感情とはつねに論理的思考でねじふせるものでしかなかった。
だからたぶん、本当は、僕に気持ちを好きにぶつけられる恋人たちが羨ましかったのだろう。
僕はひとよりも共感能力が高く、精神不安があり、言葉にたいして繊細でかつ厳密な感性がある。だからこそ、自分の言葉で傷付けておたがいの関係を破綻させる未来が容易に想像でき、どんなときでも相手にとっていちばんいうべき適切な言葉を振り絞る癖が付いてしまった。もちろん、嘘をいったり騙したりするわけではないが、自分の本心であるナイーヴな暗い感情はいつも理性に切り捨てられて心の底に澱となって溜まっていた。
結局、自分自身がだれよりも安心感を得られていなかったこと、恋人たちに本心を見せられていなかったこと、そうであるがゆえにいつも見捨てられることに怯え、恋愛関係に緩慢な死をもたらし続けてきたこと、今の今までずっと孤独で寂しかったこと。
そして、本当はずっと、この心の苦しみをだれかに理解されたかったこと。
それらすべてを唐突に悟ったとき、論理的思考でぐちゃぐちゃに潰してきた古い感情が胸の奥からあふれだすのをどうしても抑え切れなかった。こんなにも暗く幼い感情が汚泥としてへばり着いていたことが信じられなかった。
だからこの文章もまた、見ず知らずのひとの暗い苦しみにわずかな光を差せるといい。ここでなら、あなたはひとりじゃないのだから。
ほんとうに。
ここから先は
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
