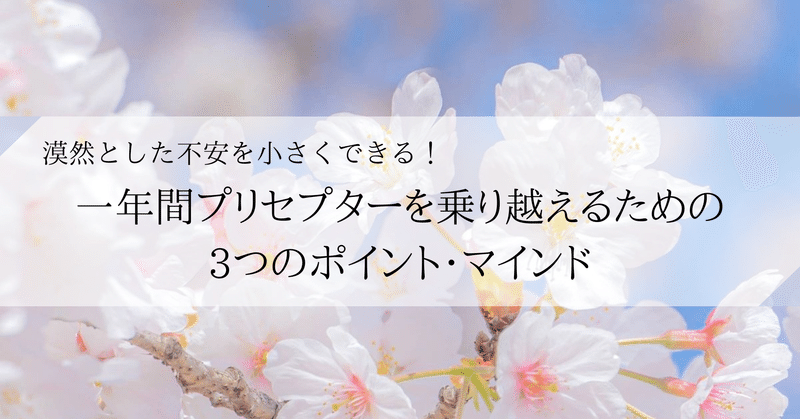
2023年版|プリセプターをやる方へ伝えたい3つのこと
2023年度が始まりました!新しい一年の幕開けです。
4月になると、あらたに新人看護師さんがやってきますね。
3〜4年目くらいの若手看護師さんの中には「あなた、次プリセプターね」なんて声をかけられてしまい、ついに来たか…と肩を落としている人もいるでしょう。
わたしも6年目でありながら今年度プリセプターを務めました。
はじめは荷が重いな〜と思っていましたが、結果的には色々と新人教育について考えることができて学びの多い一年になりました。
今回はわたしの経験をふまえて、次期プリセプターのみなさんに「もっておくといい心構え」や「困ったときの対応」を3つのポイントに分けてお伝えします。
この記事を読んで少しでも入職までに心の準備を整えてみてくださいね。
ポイント①新人にとっての【安全基地】になる
全部やろうとしなくて大丈夫
自分はプリセプター…!と思うばかりに強いプレッシャーを感じてしまう必要はないのです。
プリセプターのあなたは、新人看護師(プリセプティ)のパートナーであるというだけであって、プリセプティが思うように成長してくれなかったとしてもあなたの責任が問われることはありません。
新人看護師は病棟や部署全体で育てていくものです。
看護技術や仕事の進め方など、人それぞれ得意分野がありますよね。
いろんな人から指導を受けることによって成長することができるので、あなたが全部教えなきゃ!と頑張りすぎなくて大丈夫ですよ。
新人さんの成長が思わしくない時には先輩看護師や師長に相談してみましょう。
相談することで楽になりますし、先輩たちからも相談した点について新人さんをフォローしてもらえるかもしれません。
信頼関係を築き、相談役としてふさわしい人になる
当然のことですが、初対面の人を信用・信頼する人はほとんどいません。
何度も会い対話をする中で人柄を知ったり、いいことをしてもらうことで良い印象を持って信頼することができますね。
プリセプターとプリセプティの関係も同じことが言えます。
いくら職場で決められた関係とはいえ、はじめから刑事ドラマのバディのように通じ合うことはできません。
あなたから新人さんへコンタクトをとり、関係性をイチから作り上げる必要が出てきます。
具体的な行動としては以下のようなものが挙げられます。
会ったら挨拶をする(おはよう、お疲れ様、気をつけて帰ってね、等)
ねぎらう(大変だったね、ゆっくり休んでね、等)
承認する(○○が出来て素晴らしい!、手伝ってくれて助かったよ、等)
よく話す(技術の習得状況を確認したり、落ち込んだ・嫌な気持ちになったエピソードを聞いたりする)
頭文字を取ったら、「あ」「ね」「し」「よ」=姉しよ(笑)
でも、まさに妹や弟ができたようにお世話してあげて欲しいのです。
こうした行動を繰り返し行うことによって、新人さんにとってあなたは「安全な人」という認定がされることでしょう。
最近、よく相談してくれるようになったな〜
以前よりも少し距離感近く愚痴言ってくれたりするようになったな〜
そんな気づきは「安全な人」認定のサインです!
ポイント②親しくなりすぎない
ある程度さっぱりとした関係性を維持する
前の章で「あねしよ」で信頼関係を築き「安全な人」認定をされよう、という話をしましたが、お友達のような仲良しな関係にならないよう注意が必要です。
緊張せずに話が出来るような間柄になることは好ましいことです。
しかしそれ以上に仲良くなってしまうことでこんな弊害が生じる可能性があります。
あなたが、プリセプティへ指導しなければならない場面で指摘しにくさを感じてしまう
プリセプティが、あなたと業務にあたる場面で甘えやすくなり必要以上に楽をしてしまう
あくまで職場で頼れるお姉さん・お兄さんポジションを維持しましょう。
わざわざプライベートでご飯に頑張って行ったりも必要ないかなと個人的には感じます。
誰かを悪者にするようなフォローの仕方はしない
新人看護師はあなた以外の先輩看護師から指導をうけることもあります。
時には先輩の指導内容や言い方、普段の関わり方に不満をもち、あなたに訴えてくることがあるかもしれません。
「こないだ〇〇さんにこんなことを言われて。嫌味ったらしくて嫌でした」
「言われた通りにしたのに、後から文句を言われたんです」
こんな時、先輩を悪者にして一緒に文句を言って終わり、にならないようにしましょう。
実際にどんな会話・やり取りがあったのか具体的な1エピソードとしてはっきりさせ、先輩が何を意図していたのかを明らかにすることが重要です。
なにせ、思いやりのある指導や関わりができる人ばかりではないのが実情。
実はとても大切で、新人さんの成長に繋がることだったかもしれないのに、伝え方が良くないと総じて指導相手には届かないものです。
だから「本当はこういうことを伝えたかったんじゃないかな」と代弁した上で「でもそんな風に言われて腑に落ちないのは当然だよね」とフォローしてあげましょう。
新人看護師と先輩たちの関係性をプリセプターがわざわざ悪化させることにメリットはありませんからね。
新人さんもあなたというフィルターを通して指導された内容を改めて見ることで、腑に落ちることもあるかもしれません。
もちろん、どう考えても理不尽・いじめである場合には、しっかり気持ちのフォローをした上で師長に伝えるなどの対応も検討すべきでしょう。
ポイント③他のプリセプターと常に情報共有する
新人全員をプリセプター全員でお世話するイメージを持つ
規模の大きさにはよりますが、部署には新人看護師が二人以上配属されることが多いと思います。
そうするとプリセプターも新人の人数と同数いるはずです。
ポイント①でもお伝えしたとおり、新人指導はあなただけでするのではなく部署全体でするものです。
あなたの他にもプリセプターがいるのであれば、ぜひ密に情報共有や相談をしあう意識を持ってみましょう。
ご存知の通り、看護師は変則勤務で
早番、遅番、夜勤(2交代)、準夜勤・深夜勤(3交代)など24時間のうち様々な時間帯で働いています。
そのため、はじめはプリセプティと勤務が合っていても次第にすれ違いの日々になりやすいです。
そうするとプリセプティの働く様子を把握しにくく、相談に乗ったり指導することが難しく感じるかもしれません。
また、自分の担当でないプリセプティと急にペアで働く状況で「えっこの子の状況全然把握してない!」となったらきちんとフォローできるか不安が大きいですよね。
(プリセプターというだけで新人とペアにされることが多い印象です)
こんな時、
「○○さんの技術進捗こんな感じ!もしこんな処置の患者さんいたらつかせてほしい〜」
「なかなか報告のタイミングが掴めないみたいで、時間決めて報告してもらった方がいいかもしれない。」
といったふうに情報共有できていれば、自分のプリセプティ以外の新人さんも不安が少なくサポートできるでしょう。
わたしもプリセプター仲間にどんどん相談・報告し、時には愚痴をこぼして乗り越えました。
年間を通して、プリセプターとプリセプティのチーム戦だと思って頑張ってみてください!
スタッフにも見える形で情報共有する
プリセプター同士で情報共有しておくことも大切ですが、それはあくまで(わたしが考える)最低限の取り組みです。
新人看護師の成長には全てのスタッフの協力が必要不可欠になります。
忙しい毎日の中でスタッフが新人さんをサポートしやすいように環境を作っておくと協力を得やすくなります。
例えば、こんなことはできそうですか?
技術の習得状況を表でまとめ(病院で用意してある場合はそれを用いて)、フォローにつく先輩看護師にどんなサポートが必要か伝えられるようにプリセプティと打ち合わせておく
スタッフの誰もがみれる場所に優先的に受け持たせたい処置やケアの一覧を掲載しておき、割り振りを考える時に考慮してもらう
はじめにフォーマットを作っておいたり、スタッフにあらかじめお願いの声掛けをして回っておけば、あとは案外楽に軌道に乗り自然とやってもらえるようになります。
スタッフが自然と見てくれる環境が叶えば、あなたが新人看護師のすべてを見なければならないという強いプレッシャーも少し和らぐかもしれませんね。
必ず成長する
いかがでしたか?
人を教え育てるというのは、どんなに知識と経験を積んでも難しく感じるものです。
わたし自身、一丁前にこんなふうに書いていますが、たくさん反省したくさん向き合って今があります。
看護師は職業柄、良くないこと、異常、間違いに気づくスキルが高いと言われています。
そのため、新人さんの出来ていないことについ目がいってしまい、こんなことも出来てない…とがっかりしてしまいやすい。
でも、これだけは心に留めておいてほしいです。
どれだけ新人さんがドジで覚えが悪いとしても、1年で全く成長しないなんてことはあり得ません。
絶対に、必ず成長します。
そしてそれはあなたや周りのスタッフの頑張りに他なりません。
あなた自身も必ず成長します。
どうせ1年間プリセプターをやらなければならないなら、「これでもっと成長できちゃうな〜わたし」とプラスに捉えてしまいましょう!
頑張りすぎないでくださいね。
肩の力を抜いて、新年度もイキイキやっていきましょう。
プリセプティとの関わりでこんなこと困った…という時には、コメントやTwitterのDMでご相談いただければ対応いたしますので、もしもの時は活用してくださいね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
