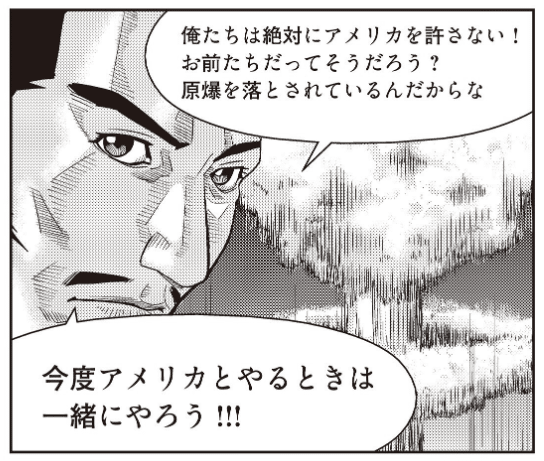日本の「戦後」は、何が欠落していたのか
「永続敗戦」、タイトルには疑問がいっぱいですが、本書の主張には賛同するところ大です。特に、近頃、テレビのコメンテーターを務める人々の歴史認識には閉口してしまいますが、本書はそれを再確認させてくれます。自虐史観や戦後レジームからの脱却などを軽々に口にするのはまさにその典型です。彼らは往々にして「対米従属」。しかもそれは卑屈なまでにアメリカの「犬」であり、とりあえず、中国や韓国・北朝鮮に向かって吠えていれば、独立国の気概を示せる。そういう感じすらします。外国の悪口を言うのが、一番お気楽な人気獲得手段なのです。その日本は、いざ、北朝鮮がミサイルを打ってくれば、アメリカの背中に隠れて、ワンワン吠える。韓国が日本の悪口を言えば、綱が伸びきるところまで出ていって、飛びかかるフリをする。そして中国については、彼らがくれる餌をほおばりつつも、後ろ足で砂を蹴り上げるパフォーマンスを続ける。
※冒頭画像は、永続敗戦論のマンガ版で登場するひとコマです。こちらもお薦め(下記に「W」リンク)。
「価値の外交」は中身がない
要は、「価値観外交」なる看板はすぐにでも下ろすべきです。アメリカと同盟し、アメリカの敵視する国と対峙することだけが目的のような方針です。ソ連がいなくなった世界で、あらたな敵を作り出すアメリカ。その理由は末尾にも書きましたが、正義を唱えながら、一定程度の「緊張」関係がほしいからです。敵がいれば、国内がまとまります。敵がいるから、同盟国もアメリカを頼ります。そして何より、敵のおかげでみずからが潤うのです。たとえば、本書から引用しますが、筆者はヨーロッパで運転手を務めていたムスリム系の青年に出会います。彼はこう言い放ちました。「絶対に許せない。すべてはアメリカだ(中略)奴らこそ世界中で人殺しをやっている」。彼が憤るのは、アメリカによって目の敵にされ、イスラム脅威論が世界中に広められてしまったからです。冷静に考えれば、中東(たとえば、アフガニスタン。毎日新聞にマンガ解説;下記参照)を舞台に、ソ連との派手な代理戦争を展開した張本人はアメリカです。皮肉にも、彼らの育てた反政府組織が、今日のテロ勢力となって、初の、アメリカ本土攻撃を許してしまいました。あの「9.11同時多発テロ」ですね。
また、目を隣国に移すと、選挙式民主主義を定着させているイランを孤立させ、王政のサウジアラビアに多額の支援をしているのもアメリカです。イラク戦争を起こした時には、ニセの情報まで捏造して世論操作を行いました。これが、アメリカの本来の姿です。日本の戦後も同様ですが、常にアメリカの都合に振り回されてきました。
日本人に不都合な「尖閣問題」
たとえば、「対米従属」のいわゆる保守派が、尖閣諸島の領土問題を声高に主張しています。ところが戦後の日本の領土は、ポツダム宣言によって、本州等の主要四島並びに、「連合国の決定する諸小島に局限」されると定められていました。具体的には、日清戦争以降に獲得した領土はすべて失うことを意味します。連合国とは、米英・中華民国・ソ連です。その中国と戦争していた最中(1895年1月14日)、日本は尖閣諸島をみずからの領土に組み入れました。それ以前は、「琉球処分」の中で、日本が一方的に沖縄(琉球)を併合しています。琉球の朝貢していた中国(当時の清国)は当然これに反対したままでした。つまり、日清戦争以前に、尖閣諸島が日本国家の固有の領土だった証拠はないのです。それゆえに、日本政府が引き合いに出した証拠はサンフランシスコ講和条約です。ところが、これまた厄介なのは、そのサンフランシスコ講和会議に、中国が排除されていたことです。当事者がいないところで第三者が勝手に決めたわけですから、台湾(中華民国)も含めた中国が納得していないのは当然のことです。
そんな尖閣問題で、かつての日中両国の政治家たちの知恵を出した結果が「棚上げ」でした。戦後の中国は、日本以上に大変でした。内戦を乗り越えた途端、朝鮮戦争が起こり、さらに毛沢東の大失政も加わります。悪な高き文化大革命の頃にはすでに国がボロボロの状態でした。そんな中、日中国交正常化交渉が始まり、中国建国以来のNo.2だった周恩来氏のようやく絞り出した言葉が「尖閣」(実際には、中国の呼び名である「釣魚島」)でした。それ以前は、はっきり言って尖閣どころではなかったのです。しかし、周氏の言葉はこう続きます。「日本は実効支配をこのまま続けても構わない」、と。ただし、現状以上に踏み込んでこないことを条件にするものだったそうです。
これを玉虫色と批判する幼稚な輩も多いのですが、見解を異にする国同士が平和を保つために「棚上げ」してきたのは非常に優れた大人の知恵です。しかし残念ながら、政権交代が行われたしまった後の民主党政権は、稚拙な世論に押され、幼稚な対応をしてしまい、今日の不用意な対立を招きました。多少同情するのは、当時の石原慎太郎都知事が、都の予算を勝手に使って、尖閣諸島購入をブチ上げたことに始まります。同氏は無責任なタカ派的主張で人気を得てきた政治家ですが、彼のパフォーマンスにハマったのが民主党です。その石原氏ですが、同じ尖閣にある久場島と大正島については口を閉ざしています。実はこの二島、日本人の立入が禁止されたままです。なぜなら、米軍の占領下にあるからです。対米従属の理屈は、あの「NOと言える」はずだった石原氏にとっても同じだったのです。
日本人に不都合な「北方四島問題」
北方領土にも触れておきましょう。日本がポツダム宣言を受託した後(1945年8月14日)、ソ連は軍事行動を続けて、南樺太や千島列島はもちろん、色丹・歯舞までも占領しました。しかし、サンフランシスコ講和会議ではそのソ連が条約調印しなかったこともあり、当時の実効支配がそのまま継続してしまいました。ところで近年、北方四島のうち、二島(先行)返還論が一時メディアを賑わせました。当の日本人はあまり理解していませんが、国後島と択捉島という大きな面積の二島は、千島列島に属すると言われています。他方、色丹・歯舞諸島は北海道の一部とされています。日本が調印したサンフランシスコ講和条約に基づくと、千島列島はすべて放棄し、残りの二島を日本に残したことになります。しかもその内容は、日ソ共同宣言に反映されました。つまり、本気の交渉をしている頃は、二島返還論が本筋だったのです。
日本からみれば「返還」だが、4島を自国領とするロシアは「引き渡し」。「主権」を認めるよう求めるのでなく「帰属の問題」。北方領土交渉をめぐる表現の背景を探ります。https://t.co/gPLLfg4eVm pic.twitter.com/YA4yBfDPIb
— 日本経済新聞 電子版 (@nikkei) November 17, 2018
ところが、これに待ったをかけたのがアメリカ国務長官のダレスです。彼は恫喝的に日本に指示し、二島返還に基づく日ソ平和条約締結は見送られました。恫喝は、決して日本のためではありません。ソ連が先に領土返還に応じた場合、今度は沖縄(当時はまだ米国の占領下)に目が向けられます。それを恐れたのです。日ソ共同宣言までは、日本の国連加盟のため(シベリア抑留者の帰国事業の交渉もあったため)にやむを得ないが、平和条約締結は時期尚早と示唆されました。こうして四島どころか、二島の返還もなくなりました。ご存知の通り、四島では現地のロシア化が進んでいます。では、なぜ日本政府は、いまだ四島に固執しているのか。実は、ほぼ何の根拠もないのです。もし、根拠があるとするなら、四島ではなく、千島列島すべてです。なぜなら、日本が千島列島を手に入れたのは、日清戦争の前の1875年です。ロシアとの樺太・千島交換条約によって平和的に日本領土へと編入されました。ところが、アメリカ主導のサンフランシスコ講和条約で、その放棄を迫られました。北方領土問題はソ連のせいではなく、アメリカの命令や恫喝が招いたものだったのです。
「従米」と「親米」を区別できない識者たち
ここまでの記述で、あたかもアメリカ憎しのような論調を繰り返しましたが、別に上掲書の筆者や僕が、反米を強調したいわけではありません。アメリカはみずからの国益にしたがって外交をやっているという当たり前の事実を述べたのです。アメリカが掲げる「価値観」などはいつも二枚舌です。それを真に受ける日本の評論家風情は、「対米従属」ポチなみの主張に成り下がっています。もっとも、この「従米保守=親米ポチ」なる表現は小林よしのり氏の独断場です。下記にも彼の書籍へのリンク(ゴーマニズム宣言)を示しておきます。
アメリカの占領下にあった日本。その後も軍隊が駐留し、事実上の間接支配が続いています。その上で、親米政権が継続するように様々な圧力や誘惑がなされてきたのも戦後日本の実情でした。しかし、アメリカのやったことが善なのか、悪なのかを論じても意味のないことです。日本では右派・左派両方とも、「東京裁判」「平和憲法」「天皇制」をゴチャゴチャと批評していますが、その大半が道徳的な意義を出ないものです。保守派が親米なのは、アメリカが天皇家存続を日本統治に利用したからです。革新派が反米だったのは冷戦に対するコマとして日本が利用されかけたからです。幸い、日本は冷戦の最前線ではありませんでした。アメリカの絶対的な影響下に置かれていたので、早くから、選挙式民主主義が許されました。逆に、韓国や台湾のような最前線では、軍事政権の統治がアメリカによって認められてきました。なぜなら、選挙は時として、反米政権を誕生させてしまうからです。日本は、アメリカの不安を極力高めないカタチで、「軽武装・経済成長路線」を打ち出し、冷戦の果実だけを手にする大成果を収めました。東京タワーが建設され(1958年)、東海道新幹線が開業し(1964年)、悲願だった東京オリンピックも実現しました。オイルショックに至る前の1968年には、瞬く間に、世界第二位の経済大国へとのし上がりました。だからこそ、日本には親米こそ正しいという認識が定着し、日本人には「従米」という現実が受け入れられなくなっていました。

「従米」での成功体験
80年代以降も、中曽根・小泉・安倍政権と、三代ともに強力な「従米」路線を採りました。米国の首脳とは個人的にも親密な関係を演出し、アメリカの要請をそのまま受け入れました。アメリカの敵は、日本にとっても敵。そうした「従米」に、多くの人は何の疑問も抱かなくなったようです。勇ましく嫌中を語るコメンテーターは、いわば洗脳を進めるアメリカの片棒を担いだようなものです。従米でもいいでしょう。親米は日本の既定路線です。しかし、問題は、その路線の背後で、先の大戦の敗北を認められず、「終戦」で済ませようとしている心理構造が横たわっていることです。なぜあれだけの被害を出してしまったのか、その総括をせずして、日本の平和は守れません。同じ失敗を、別の歩みで繰り返してしまう恐れがあります。「従米」者に限って、靖国神社参拝を政治ショーにしたがります。反省のない靖国神社の状態を放置したまま、敢えてそれを政治利用する。非常に姑息です。
繰り返しますが、日本が経験したのは、終戦ではなく、敗戦です。日本の生命線を守るためと言いながら、海外派兵し、結果的に未曾有の死者を出した。そして、日本経済ばかりか社会の成り立ちそのものを崩壊に至らしめた政治家たちには間違いなく戦争責任があります。ここのケジメ抜きに、日本は大戦の反省をしたことになりません。そんな昔のことは関係ないと言わんばかりに、この国は、アメリカに盲目的に従っています。そんな状態が続けば、いつしかまた、戦争に巻き込まれる、そんな危惧を上掲書の筆者は抱いています。
反戦平和の第一歩は、「従米」をやめること
最後に、僕の考えも述べておきます。アメリカがトランプ政権になってからはっきりしてきましたが、そのロジックは無茶苦茶です。オバマ政権の時には、少なくとも言葉のメッセージだけは見事なものでした。「アメリカン・ファースト」の現実をごまかすだけの装飾性を備えていたのです。しかし、トランプはある意味正直で、品のない政権です。そのえげつなさがはっきり示されています。日本は、彼らから多少の距離を置いた方が賢明です。なぜなら、対立の最前線が中国になった場合、日本は間違いなく巻き込まれてしまうからです。絶対に忘れてはならないことですが、アメリカの軍事産業は相当の規模があります。戦争あるいは戦争の準備で生計を立てています。平和を演出しながらも、対立を煽り、同盟国との商売を維持するのが最大の狙いです。アメリカの事実上の属国のようになっている日本が、完全に逆らうことはできないとしても、戦争だけには関わらない。そんな強い胆力を持ちたいものです。日本の言論界には残念ながら、中国を敵視する嫌中論者、北方領土問題を本気で解決する気のない「四島返還絶対」論者、北朝鮮との交渉に興味がないのに拉致被害者救出を訴えるだけのエセ強硬論者、そして従米参戦を許容する思考停止状態の面々が存在します。どれだけこれらの人々に煽られても、日本は最後の一線を越えてはいけないと思います。日本の周辺国で、日本に攻めてくる国はありません。彼らから平和ボケと揶揄されるはずですが、そのような事態は日本の振る舞い一つで十分避けられます。必要以上に怯える必要はありません。今日の人類の進歩は(少なくとも経済発展する地域において)、戦争・戦勝で得られる利益がないことを学んだことです。窮鼠猫を噛むと言いますが、その状態にわざわざ相手を追い込まない限り、戦争リスクは極めて低いのです。さんざん怯えた挙げ句、鬼畜米英を掲げて戦争を始めてしまった昔の日本の敗戦を、しっかり反省しましょう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?