GIDの立場で毛糸子さんの自治体発行「多様な性・LGBT対応 職員向けハンドブック」調査報告を読む。防災担当部署に女性職員がいない自治体が6割等避難所運営の生得的生物学的女性軽視の問題やアウティング禁止条例廃止した方が良いと思う件について
GIDの立場で毛糸子さんの自治体発行「多様な性・LGBT対応 職員向けハンドブック」調査報告を読む。防災担当部署に女性職員がいない自治体が6割等避難所運営の生得的生物学的女性軽視の問題やアウティング禁止条例廃止した方が良いと思う件について
トイレが性自認ペースという問題で生得的生物学的女性の身の安全が守られてないという報告。
性同一性障害が医師の診断と性別適合手術が必要な障害であり疾患であることが無視されて性自認ベースであることは問題だと思います。
性自認や、性表現……たとえばスカートを穿くことで、男性に生理が来るということなのか?
「性自認にかかわらず”生物学的性別に応じて”生理用品を配布する」ならわかるが。女性が男性扱いを求めたりズボンを穿いたところで、生理は来るのだから。
避難所での生理用品不足、入手困難は深刻な問題である。
運営が男性だと
・必要数を理解していない(1日に1個で足りる、2日くらいで終わると思っている、など)
・不要だと思っている(「こんなときに生理するな」など……)
・必要だとうったえても怒鳴られる
・もらいに行くのに抵抗がある
などの問題が起きている。
「性自認に応じた生理用品」というマニュアルに疑問を持たない自治体担当者が居ることからしても、生理を理解したつもりのバカ権力男性が牛耳っているのが透けて見える。
そんな環境で更に、限られた備蓄ややっと届いた生理用品を、
女性扱いしてほしい男性と分け合え……ということなのだろうか?
なぜ?
まさか、当該人物だけが生理用品を配られていなかったら、「女性ではないことをバラすアウティング」になりうるから……ということなのだろうか。
そのために女性の必須の衛生用品を分け与えると???
たとえば、男性器整形手術をして腸液等が垂れ流しになるのでパッドをあてる必要がある、といったことは考えられるかもしれないが、それだと
「性自認に応じて」には当たらない。
また、これは「痔の男性にもパッドが必要」と同じジャンルであり、決して「女性の月経のための生理用品」と同じではない。
必要なら、きちんと、別途、男性の中での必要な衛生用品としてカウントすべきだ。
「心の性別」思想のすべてに言えるが、本当になにか問題があるならばこそ独立した属性としてカウントし、真っ向から対峙すべきなのに
「男のままでは問題があるから、女ということにして女に受入れさせる」で解決したフリをするのは自他をさらなる問題に晒すだけだ。
真っ向からの対峙によって、「非常時に衛生を保てないほどの手術を、健康な臓器を摘出してまで行うこと」の是非、などそもそもの原点も見えてくる。
まあ、それが不都合だということなんだろうね。
(同じように「性自認に応じた髭剃り」もおかしいが……
不足すれば感染症を引き起こし命の危険もある生理用品は特に切迫した問題である)
★ホルモン投与問題
そのほか、「ホルモン投与できず心身に重大な不調をきたす」に配慮を求めている自治体が
7件/37
刑務所でも取りざたされるが、こういった観点からもさきほどの「パッド問題」のように
「本人が望んでいるので、心身の維持にかかわるホルモンを分泌する、健康な臓器を摘出する」是非から問われるべき段階だと思う。
他の疾患だとありえない処置なのだから。
本人が望めば、健康な腎臓を摘出して、人工透析が必要な状態をわざわざ作り出すだろうか?
このような手術によって
女性に必要な薬も生理用品のように分け合わなければならない危険性が出てくる。
また、災害時に限ったことではなく、薬の供給不足は社会情勢や製薬会社の不祥事などによっていつでも起こりうるし、ここ数年がまさにその渦中であることも念頭に置かれたい。
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/iryo/7210402
次回こそ、アウティングの項!
15
毛糸子
2023年5月19日 12:27
同性から、好きだと告白されて体をベタベタ触られたり行く先々に着いてきてストーカーされたり、
といったことは「人種や出身地の告白」では起きない。
女子トイレや女子更衣室を共有していた人物から「実は私、男なんだよね、これからも共存してね❤」とカミングアウトされた女性が、自他の女性の尊厳を守りたい場合はどうすれば?
誰にも影響を与えない個人で完結する情報と違って、他者との「関係性」「そのうえでの要求」にも関わり得るのが性的指向や性自認である。
なんらかの「関係の構築(構築への要求)」がなされ得る。
そうした情報を告白される側は「告白されないこと」を選ぶ権利はない。
そうして受けた告白には、
自分と相手、周囲と相手の関係性におけるなんらかの要求など、
自他の尊厳安全にかかわる問題が含まれてくる。
そんな場合でも己の内にのみ秘めねばならない。
これは、「他の尊厳安全を劣位に置き、恣意を振るう特権を与える」という理不尽な勾配あるルールだ。
たとえば「オレ、子供が性的に好きで好きで、ひそかに興奮してるし家でもオカズにしてるんだ。もちろん、園児に手を出したりはしないよ?でも、○○先生にはどうしても聞いてほしくて……」
と同僚の保育士が相談してきても、誰にも言ってはならない。
というのに近いかもしれない(たとえが悪い💢とまた怒られそうだが、近いと言うか、LGBT「Q、P」とかだとそれも入ってくる可能性が普通にあるよね)。
「へーそうなんだ」で終わらせられない重大な問題も含むものを
一律で「アウティング禁止!」としてしまうとそれこそ
生命の危機に追い詰められる「告白の受け手」が出ると思う。
★男性への影響
とかくLGBT差別禁止問題では、被害に合うのは女性と子供だけだろ、と思われがちだが、
アウティングに関してはさきほどの大学の事例でもわかるとおり、男性だってかなり影響を受ける。
16
毛糸子
2023年5月20日 17:30
同性愛ストーカー事例を無視した一橋アウティング裁判の事例を悪用したアウティング事例になってると思われますね。
一橋アウティング裁判は同性愛ストーカー事件なのだから、犯罪被害者の立場から相談できるようにアウティングしても問題ないとされる方が良いと
いう内容やアウティング禁止は性的マイノリティにとっても不利益になりうるのでアウティング禁止条例廃止すべきとのツイッターの内容が良かった件について過去記事に私が書いた内容があるので。
「アウティング禁止条例」に対して、私は「どちらかと言えば反対」の立場。以下、理由を書いていく。https://t.co/5n7PgNvng6
— Jiyu (@jiyu33) June 8, 2020
(1) アウティングのみを禁じる理由がない
— Jiyu (@jiyu33) June 8, 2020
アウティングに限らず、「他人の秘密を暴露する」という行為は、今回の条例がなくても「プライバシーの権利の侵害」ということで民事上の不法行為となり、損害賠償請求は可能。アウティング禁止条例があってもなくても、民事上の責任を問うことはできる。
裁判所もプライバシーの侵害による損害賠償を認めるだろう。従ってアウティングだけをわざわざ禁止する理由がない。もし「アウティングはプライバシー侵害の中でも特に重く扱うべき」「アウティングは民事責任だけでなく刑事責任も問うべき」という意見もあるだろう。しかしその場合、
— Jiyu (@jiyu33) June 8, 2020
「あらゆるプライバシーの中で、なぜアウティングだけ特別視する必要があるのか」を説明できるのだろうか。レイプにあった事実や、親が犯罪者である事実、障害者である事実など、性的少数者である事実と同じかそれ以上に重要なプライバシーはいくらでも存在する。
— Jiyu (@jiyu33) June 8, 2020
(2) アウティング禁止が性的少数者の権利擁護に常につながるとは限らない
— Jiyu (@jiyu33) June 8, 2020
元参議院議員の松浦大悟氏は、こう述べている。 https://t.co/PcpXWu0glw
>❷例えば、ゲイバーは歴史的にアジールとしての機能を果たしてきた。ゲイバーのママに相談する当事者も多い。だが会話を踏み外すと罪に問われ罰金を払わなければならないとなると今後は「相談お断り」と言われるだろう。諸問題を慎重に考えた条例とは思えない。
— Jiyu (@jiyu33) June 8, 2020
アジールとは「聖域」という意味。他の人には自分が性的少数者であることを告白できないが、ゲイバーのママになら何でも話せる。マジョリティでもそういう場所はあるだろう(「この店のマスターになら何でも相談できる」という場所に相当する)。
— Jiyu (@jiyu33) June 8, 2020
しかし、もし弁護士や医者のような秘密保持義務がアウティング禁止条例により設定されるのであれば、「相談お断り」となり、性的少数者は相談できる場所を失う。「性的少数者が匿名で相談できる仕組みを同時に作る」等の政策を同時にしなければ、当該条例は性的少数者の権利を奪う側面も出てくる。
— Jiyu (@jiyu33) June 8, 2020
(3) 性的少数者がこの条例を悪用して、他人の権利を侵害することがある
— Jiyu (@jiyu33) June 8, 2020
アウティング禁止条例のきっかけとなったのは、一橋大学アウティング事件( https://t.co/RkAj7ZaeXi )。
しかし、この事件には「転落死をしたゲイの学生がしつこくつきまとっていた」という情報もある。https://t.co/mFCMLv2Mf6
— Jiyu (@jiyu33) June 8, 2020
この情報の真偽は不明だが、男女の痴情のもつれに置き換えると「あり得ないとは言い切れない」。以下に例をあげる。
>男性Aが、好きになった同級生の女性Bに告白したが、「いい友達でいたい」と振られてしまった。男性Aは「わかった」とは言ったものの、諦めきれずにアプローチを続け、女性Bは不快感をつのらせていく。
— Jiyu (@jiyu33) June 8, 2020
>ついに女性Bが耐えられなくなり、他の人に相談をしていく中で、男性Aの行為が発覚し、共通の知人皆に顰蹙を買ってしまう。女性Bにも振られ、大きな恥をかいた男性Aは、次第に学校にもいけなくなり、心を病んで自殺をしてしまう。
— Jiyu (@jiyu33) June 8, 2020
どうだろうか。「そんなこと、絶対にない」と言えるだろうか。ここから少し想像力を働かせれば、条例の悪用という事例も見えてくる。そう、「このことを他人にバラしたらお前を訴えてやるからな」という脅しが成立してしまう。
— Jiyu (@jiyu33) June 8, 2020
性的少数者は聖人ではない。普通の人、優しい人、性格に問題がある人、どうしようもないクズ、いろんな人がいる。自らの立場を利用し、また斜に構えて他罰的になる当事者もいます。例えば以下のように。
— Jiyu (@jiyu33) June 8, 2020
https://t.co/LGrjBPxnEQ
私は、この条例が多くの当事者の立場に沿ったものとは思えず、活動家的な当事者の意向や、「LGBTを守らなければ」という素朴な考えにのみ基づいていると考える。様々な当事者の意見を集め、より込み入った議論が必要。
— Jiyu (@jiyu33) June 8, 2020
私は精神障害者だが、「精神障害者であることをバラすやつに罰則を与えよう」なんて言われたら「こいつ何もわかってない」と思うし。マイノリティがしたいことはそういうことじゃない。そういうことを従っているのは、一部の過激な活動家や、それに近いマインドを持っている人だけ。
— Jiyu (@jiyu33) June 8, 2020
マジョリティ側の人権にも配慮すべき。
— Jiyu (@jiyu33) June 8, 2020
障害者権利条約にある「合理的配慮」というのは、そのような「マジョリティとマイノリティの人権の調整」という考えも含んだ発想。この考えをLGBTの権利活動でも広めていくべき。マイノリティだからといって、どんな主張や行為も許されるわけではない。
— Jiyu (@jiyu33) June 8, 2020
Jiyu
@jiyu33
「アウティング禁止条例」に対して、私は「どちらかと言えば反対」の立場。以下、理由を書いていく。
https://news.yahoo.co.jp/articles/dc27392e7892d8e1eeed748aa79837a00f9348da
午後10:57 · 2020年6月8日
2
件の引用
1
件のいいね
Jiyu
@jiyu33
·
2020年6月8日
(1) アウティングのみを禁じる理由がない
アウティングに限らず、「他人の秘密を暴露する」という行為は、今回の条例がなくても「プライバシーの権利の侵害」ということで民事上の不法行為となり、損害賠償請求は可能。アウティング禁止条例があってもなくても、民事上の責任を問うことはできる。
Jiyu
@jiyu33
·
2020年6月8日
裁判所もプライバシーの侵害による損害賠償を認めるだろう。従ってアウティングだけをわざわざ禁止する理由がない。もし「アウティングはプライバシー侵害の中でも特に重く扱うべき」「アウティングは民事責任だけでなく刑事責任も問うべき」という意見もあるだろう。しかしその場合、
Jiyu
@jiyu33
·
2020年6月8日
「あらゆるプライバシーの中で、なぜアウティングだけ特別視する必要があるのか」を説明できるのだろうか。レイプにあった事実や、親が犯罪者である事実、障害者である事実など、性的少数者である事実と同じかそれ以上に重要なプライバシーはいくらでも存在する。
Jiyu
@jiyu33
·
2020年6月8日
(2) アウティング禁止が性的少数者の権利擁護に常につながるとは限らない
元参議院議員の松浦大悟氏は、こう述べている。
引用ツイート
松浦大悟(日本維新の会 秋田1区支部長)
@GOGOdai5
·
2020年6月3日
❷例えば、ゲイバーは歴史的にアジールとしての機能を果たしてきた。ゲイバーのママに相談する当事者も多い。だが会話を踏み外すと罪に問われ罰金を払わなければならないとなると今後は「相談お断り」と言われるだろう。諸問題を慎重に考えた条例とは思えない。
このスレッドを表示
Jiyu
@jiyu33
·
2020年6月8日
>❷例えば、ゲイバーは歴史的にアジールとしての機能を果たしてきた。ゲイバーのママに相談する当事者も多い。だが会話を踏み外すと罪に問われ罰金を払わなければならないとなると今後は「相談お断り」と言われるだろう。諸問題を慎重に考えた条例とは思えない。
Jiyu
@jiyu33
·
2020年6月8日
アジールとは「聖域」という意味。他の人には自分が性的少数者であることを告白できないが、ゲイバーのママになら何でも話せる。マジョリティでもそういう場所はあるだろう(「この店のマスターになら何でも相談できる」という場所に相当する)。
Jiyu
@jiyu33
·
2020年6月8日
しかし、もし弁護士や医者のような秘密保持義務がアウティング禁止条例により設定されるのであれば、「相談お断り」となり、性的少数者は相談できる場所を失う。「性的少数者が匿名で相談できる仕組みを同時に作る」等の政策を同時にしなければ、当該条例は性的少数者の権利を奪う側面も出てくる。
1.一部性的マイノリティであることを他者判断しにくいケースと特権化する懸念
本素案の名前には「同性」とは付いていませんが、制度創設の目的により性的マイノリティを対象とした制度だと理解しています。
素案の定義上「性的マイノリティ」とは、「性的指向が必ずしも異性のみではない者」「性自認が出生時に判定された性と一致しない者」となっています。「性自認が出生時に判定された性と一致しない者」とは「自認」で申請できるものと理解しますが、その場合、異性をパートナーに持つ者はどう対応されるのでしょうか?(FTMだけど男性とのカップル、もしくはMTFだけど女性とのカップル)
性同一性障害の診断を持たない場合、本人の「自認」以外はまったく他者から判別が付かない場合もあります。
また、ジェンダーフルイドのように性自認が男性だったり、女性だったりする人は性的マイノリティ当事者となるはずですが、その場合についてもどう対応されるのでしょうか?宇多田ヒカルのようなノンバイナリーを自認する者と男性とのカップルについても同様に疑問です。
パートナー関係にあることを宣誓しているとしても、それは事実婚の男女でもそのような条件に当てはまる者はいるでしょう。しかし、これらのケースではその人が性的少数者であることを他者が判断することができません。
都が提供する都民向けサービス事業について、「受理証明書」の保有者が活用できるよう検討するとも書いてあります。上記のようなカップルが申請できるのであれば、事実婚の男女から見ればマイノリティ特権にあたる制度になってしまいます。
2.性自認が他者から判別できないものである面からの懸念
「性自認が出生時に判定された性と一致しない」ことを他者が判断することはできないため、届出の際にその「性自認」を要件確認の対象にした場合、それは自己申告をそのまま受け取るのみとなるでしょう。
逆にもし、届出で申告している「性自認」について受け付ける側が正当か否かを評価をして届出を受理しないようなことがあれば、制度の要件に対して性自認を他者の視点で判断したとして大きな問題になると考えられます。
であれば、性的マイノリティの定義に「性自認が出生時に判定された性と一致しない」の項目が存在する意味は有って無いようなものです。性的マイノリティに限らず、全ての男女を対象にするべきです。
3.なりすまし発生の懸念と不満が生まれる懸念
素案の通りに性的マイノリティに限った場合、2で指摘したように性自認を他者が判定することはできないため、事実婚の男女でも生得的性別と異なる性別を「自認」するだけで届け出ることはできることになります。
仮にですが、そのようにして「なりすまして」利用しようと考えるカップルが出てきた場合、その「なりすまし」が何かトラブルを起こすと性的マイノリティの印象悪化に繋がる可能性があります。もしくは意図しない言動で性的マイノリティとはこういう人たちで、こういうことに悩んでいる、そういう面で周囲の人たちへ誤解を与える可能性もあります。
また、異性愛のパートナー関係にある人たちの中で、そのような抜け道があると知られれば不公平感から不満が生まれてしまいます。
4.LGBTQ人口が増える懸念と不平等感が生まれる懸念
1や2で示したようにノンバイナリーやジェンダーフルイドのような性自認の男女カップルが対象となれば、一般の男女カップルから見れば不平等感は否めません。不公平と感じる人が増えれば、性的マイノリティへの風当たりが強くなる可能性が高まります。
また、ノンバイナリーやジェンダーフルイドなどの性自認は、なりすましという意図が無くても、社会の空気によって増加する可能性があります。2021年10月26日のNewsweekでは「アメリカの若者の30%以上が「自分はLGBTQ」と認識していることが判明」という記事が出ています。
自認で届出が受理されるような制度を設ければ、名乗った者勝ちになります。そのような制度では、都でもLGBTQが増えていく可能性は十分あるのではないでしょうか?
このような名乗った者勝ちのような仕組みでは、性的マイノリティを自称する人たちへの反発が増えるだけでなく、本来の当事者より当事者が増えることで本当に悩む性的マイノリティの望む支援と制度が乖離したり、人々が思う当事者像と当事者の実態が乖離する懸念があります。
3にしろ、4にしろ善意やふつうの感覚を頼った制度は危険です。戸籍上の性別で同性同士に限るか、性的マイノリティ以外の全ての男女を対象にした制度とすべきだと考えます。
5.本制度で発行する受理証明書での懸念
受理証明書や、あれば関連で発行する証明書などもですが、「性自認」を「性別」と取れるような欄を作らないようことを強く望みます。
仮に、そのようなこと証明書を都が発行した場合、都が「性自認」を「性別」として認めたことになってしまいます。
「性別」は社会の根幹を作る基礎的な要素です。男性と女性はその身体的な違いにより明らかな力差、立場の強弱があります。一方で「性自認」は主観的な概念です。他者が判断することはできません。
この制度により発行する受理証明書等の文書には、戸籍上の性別、もしくは、性別欄は無しにされるようお願い申し上げます。
以上になります。何卒十分なご検討をお願い申し上げます。
性別不合当事者の会
8
性別不合当事者の会
2022年3月21日 12:27
ご存知のように、性同一性障害特例法は2003年成立 2004年執行だったのですが、この当時はようやく性同一性障害という言葉の概念が出来上がり、所謂TSな人しか居なかった時代だと言えます。
なので、TSな山本蘭氏が数千万円も自腹を切り、当時の自民党を説得し、性同一性障害(TS)の為に作った物が性同一性障害特例法だと言えます。
その後、時は流れ20年あまり、インターネットは普及し、性のあり方は多様化し、TGな人(Xジェンダー・ノンバイナリー)などが生まれ、そこに異性装者や、オートガイネフィリアの人をも巻き込み、世界の活動家の力により、トランスジェンダリズムが形成され、今の国連・アメリカ精神医学会のDSM-5やWHOのICD-11の様な考え方、が広まってきたのだと思うのです。
しかし、我が国日本では、TSの為の性同一性障害の、診断方法・法整備(特例法)しかない為、我が国のTG達はある意味その概念に乗っかった形となっているのだと思われます。
そこに歪みがあるから無理がありTGの人達は苦しんで要るのです。
当然ながらTGとTSは大きく考えが違うため、今やTG当事者やTG活動家などにとって、GID学会のガイドラインや、特例法は、世界の時代の追い風にも乗り、邪魔な物、時代遅れの産物、人権を踏みにじる物、去勢を強制する非人道的な物とまで言われているのだと感じます。
TSな性同一性障害者からしてみれば、今の診断方法と特例法は厳守したい所ではありますし、GDではなくGIDであり、病理(疾患)だと考えていますし、DSM-4・ICD-10に戻してほしいと説に願います。
TSは自分自身の事に関しては男性・女性のどちらか一方でしかないステレオタイプで考える。(他人の自認を否定する物ではない)と考える人が大半だと考えます。
少し話はそれますが、TSの課題としては、GID学会の提唱する、ホルモン判定会議→ホルモン開始→1年後→性別判定会議→SRSと言う流れは、急激なホルモンバランスを崩さないようにする為の必要な期間と考えるのは、医者として患者を思う至極当然だと思いますが、厚生労働省の言う所の、ホルモンン治療をしていた場合、混合診療とみなし、SRSは保険適用外とする箇所は見直して行かないと行けないと考えます。
ココはTS当事者の活動家やGID学会の先生に頑張って頂くしか有りません。
動画の奈良大学の教授が言うように、患者の負担率が高すぎるとも言えますが、これは今回の話とは別問題なので、今は置いて置きますし、TSとって再度元に戻せない性適合手術必須が、おかしいというのは理解し難い概念であります。
●一提案なのですが、そもそもTSとTGを一緒に考えるから無理があるのではないでしょうか?
TGはTSの枠組みで生きようとするから苦しいのであって、今のままでは、TSが作り上げてきたルールや制度を変えようとするのは至極当然かと思いますし、それに対しTSは今のままでほぼ良いと考えるため、TGの特に活動家の言う事はおかしい。となるのではないでしょうか?
●結論として、一番の良い改善方法はTSは
・今の性同一性障害の診断方法はそのままに
・ホルモン治療の保険適用とそれに伴うSRSの保険適用を実現させて金銭的負担を軽くする
・そして既存の特例法を元に、戸籍変更する
で良いのです。
殆どが山本蘭氏が作り上げた時点でほぼ完成しているのです。
17
性別不合当事者の会
2022年9月26日 00:51
性同一性障害者の立場からNOセルフID女性の人権を安全を求める会様の
医師の性同一性障害者との診断書提出が必須、性同一性障害者は性別関係なしトイレであるみんなのトイレを使うように義務付けた方が良い、性同一性障害者とアウティングで周知して良いとのNOセルフID女性の人権を安全を求める会様の対応、性同一性障害は病気であり疾患であり障害であるという事実からとても有り難く感じました。NOセルフID女性の人権を安全を求める会様にはGID患者に感謝される筋合いない生得的生物学的女性の身の安全を守ろうしただけだって返されそうだけどね。
ノートルダム清心女子大学 学長 シスター津田葵様
ノートルダム清心女子大学 多様な学生受入れ委員会委員長 本保恭子様
女子大である貴学が2023年度からトランスジェンダー学生を受け入れるというニュースに接してたいへん驚きました。これは一大学の方針転換にとどまらない大きな問題だと考えます。そのため、女性の人権と安全を求める立場から、いくつかの看過できない問題を指摘するとともに、強い抗議の意思を表明いたします。
1.他者から確認することができない「自認」によって入学の可否が決められ、しかも入学後は自認が不問とされること
『山陽新聞』の6月16日付の報道(https://www.sanyonews.jp/article/1273504)によると、「診断書の提出は求めない」とあります。つまり、医師のまったく介入しない、純粋な自己判断による性別認識での出願・入学が可能です。これは根本的に客観性を欠き、女子大学としてのあり方を根本的に損なうものです。そもそも女子大学ができたのは、女性がその生物学的性別ゆえに高等教育から排除されてきた歴史があるからです。けっして性自認が女性だから教育の場から排除されてきたのではありません。女性であるがゆえに学ぶことを許されなかった女性たちに高等教育の機会を与えるためにこそ、女子大学が設立され、存続してきたのです。貴学の新しい方針は、このような女子大学の歴史と理念を真っ向から否定するものです。
一方、貴学ウェブサイト内の「多様な学生(トランスジェンダー女性)受入れガイドライン」(https://www.ndsu.ac.jp/life/support/pdf/transgender.pdf)(以下、ガイドライン)には、「男性が自認を偽って入学するいわゆる『なりすまし』が発覚した場合、学則に基づき退学とします」とあります。しかし、医師の判断によらない主観的な自認にもとづくかぎり、なりすましなのかそうでないのか判断材料は存在しませんし、そもそも、貴学の「多様な学生受け入れ委員会」を含む他者から確認できるものではありません。確認することができないものを根拠に入学や退学を決定するならば、そこに必然的に恣意性が生じますし、それは教育機関としてあるまじきことです。しかし、実際に「なりすまし」であったとしても、ガイドラインには「入学後に、性自認や戸籍がどのように変わっても、そのことを理由に退学になることはありません」とあるのですから、それが適用されれば、問題は何もなかったことになるでしょう。それもまた教育機関としてたいへん不誠実なありかただと言わざるをえません。
2.「トランスジェンダー女性は『多様な女性のうちの一人』です」というメッセージは、現実においては女性の人権を侵害するものであること
前述したガイドライン、および貴学学長のメッセージにおいて「トランスジェンダー女性は『多様な女性のうちの一人』です」とされています。しかし、「トランスジェンダー女性」であることの根拠は本人の主観と自称しかなく、それをもって「多様な女性のうちの一人」と断定するのは、女性の権利と安全を脅かすものです。
女性はその身体性が男性とは異なることで、男性に比べて低く見られ、性暴力の対象となり、搾取されてきました。つまり、体格や筋肉・骨格などが男性に比べて相対的に脆弱であること、月経があること、妊娠する可能性のある身体であること、などです。だからこそ、女性を男性による侵害の可能性から保護し、その権利を守るために、女性専用のトイレや浴室、更衣室、女子スポーツなどが存在するのです。しかし、ただ性自認だけで決まる「トランスジェンダー女性」を「多様な女性のうちの一人」とみなすことは、このような男女間の身体差を否定することと同じです。それを押し付けるならば、女性の人権と安全を根本的に侵害することになります。実際、自認に基づく性別変更を安易に認めている国々において以下のような問題が起こっています。
・ 女子スポーツに身体的男性、とくに男性器を保有したままの人たちが女性を名乗って参加し、優勝し、賞金、栄誉、奨学金を得ています(アメリカの大学水泳選手権で優勝したリア・トーマスなど)。
・ 米国などで、性犯罪者を含む男性身体者が女性を名乗るようになった結果、女子刑務所に収監されるようになり、その中で性暴力事件を起こしています。妊娠させられた女性もいます(イギリス、カナダ、カリフォルニアなど)。
・ スパ施設などの女性用エリアに男性器を露出させ半勃起させている人物が入ってくることが可能になっており、施設側は法律の規定によりその人物を追い出すことができません(カリフォルニアのWi Spa事件など)。
以上の事例は極端なものに思われるかもしれませんが、いずれも自認優先の性別変更がなければ起こりえなかった問題です。
3.女子トイレの使用の可否および『みんなのトイレ』の問題性
貴学のガイドラインでは、「多くのトイレは女子トイレ/男子トイレにわかれていますが、男女の区別なく使用できる『みんなのトイレ』を……2か所に設置しています。どなたでも自由に利用でき更衣室としても使用できます」とありますが、「トランスジェンダー女性」にこのトイレを使うことを義務づけるものになっていません。ということは、貴学の女子学生には、男性器を具えたトランスジェンダー学生とトイレや更衣室をいっしょにしたくないという選択権は何ら与えられていないことになります。女性にとって男性から自分の無防備な姿を見られるだけでも生涯にわたる心の傷を残す可能性があります。トランスジェンダー学生には最大限の配慮をしながら、どうして女子学生たちの選択権や意向はないがしろにされるのでしょうか? あなた方は「女子大学」を名乗っているというのに!
他方で、トランスジェンダーの学生にこの「みんなのトイレ」を使うよう促すとすれば、おのずとそのトイレのみを使う学生がトランスジェンダーであることを外部に示してしまうことになり、したがって、「それ自体がトランス差別でありアウティングである」との非難が起こりえます。もしトランス権利運動家からトランスジェンダーの学生に女子トイレを使わせないのは差別だと非難されたら、それに反論できるでしょうか。
4.「アウティングしてはならない」という心理的負担を学生たちに負わせること
性自認は客観的なものではありません。入学審査はパスしたとしても、日々ともに過ごす女子学生たちの間で、「女性」として受け入れることに抵抗が生じる可能性は十分にあります。そうしたときにも、ガイドラインに従うならば、アウティングは「絶対にしてはいけない」ものとして「ハラスメントとして対処」されるものであるため、疑問に思ってもその感情を学生同士で話し合うことができません。 十代後半から二十代初めは、見聞を広めそれらについて考えをめぐらせ、その後の人生の基盤となる考えや価値観を形成する大切な時期です。その際に重要なことは、真実の追求が妨げられることなく、欺瞞なく、所与のものを疑ったり検討したりする場や雰囲気を持つことであり、大学とはそのような空間であるべきです。しかし、「トランス女性は女性である」と掲げられている大学の中では、自分の感覚や考えがそれに沿わないと入学後に気づいても、逃げ場がありません。それは思想信条の自由が十全に保障されないということであり、青年期の心の発達に対してもマイナスの影響が生じかねません。これもまた、教育機関としてあるまじきことです。
貴学は来年の2023年度からトランスジェンダー学生の受け入れを開始するとの方針を公表しています。他の女子大学では、在学生の抵抗感を考慮して、在学生が卒業してからのトランスジェンダー学生の入学を決めた女子大学もあります。しかし、貴学はそのような配慮すらせず、2022年5月にガイドラインを発表し、6月1日に学長メッセージで全学生に伝えました。安心で安全な女子大学に入ったつもりなのに、何の相談も受けることなく、いきなり来年度から、男性器を有した学生といっしょに大学生活を送らなければならなくなった女子学生の気持ちを考えたことがあるでしょうか?
貴学の教育理念の一つは、「時のしるしをよみとりながらも、時代の流れにおしながされることなく、人々が真に求めるものにまなざしを向け、人びとに奉仕する大学である」となっています。しかし、貴学の新しい方針のもととなるトランスジェンダリズム(性自認至上主義)は、「人びとに奉仕する」思想ではありません。それは女性を迫害し、女性の人権を抑圧する思想と運動です。どうか、人権擁護や多様性という美名に「おしながされることなく」、実際に世界中で何が起きているのかをよく調べ、貴学の方針をどうか再検討してください。貴学の女子学生たちの人権と尊厳を守ってください。
2022年6月25日
No!セルフID 女性の人権と安全を求める会
共同代表 石上卯乃 桜田悠希
日本の動き
トランスジェンダー, 女子大, 性自認
性同一性障害者が必要とする性別適合手術。
特例法の手術要件が生得的生物学的女性の身の安全を守る役割も果たしている事実は何度でも言いたい件。
12月7日、新聞各社は、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(以下、特例法)の手術要件が違憲であるかどうかの判断が、最高裁判所の小法廷から大法廷に回付されることになったと報じました。
https://mainichi.jp/articles/20221207/k00/00m/040/170000c
https://www.yomiuri.co.jp/national/20221207-OYT1T50184/
https://www.asahi.com/articles/ASQD76CVMQD7UTIL017.html
もし特例法の「手術要件」が憲法違反と判断されれば、深刻な問題が生じます。新聞報道では十分に語られていなかったこれらの点について、当会は女性の立場から声明を出し、広く社会に訴えるとともに、最高裁判事のみなさまに国民の声として届けることにいたしました。
1.違憲判決が出れば、同法を本来の主旨に沿わない法律へと作り替えることになる
2003年に特例法が成立した際の参議院本会議での提案においては、「生物学的な性と性の自己意識が一致しない疾患」と説明されていました。また、「おおよそ男性三万人に一人、女性十万人に一人の割合で存在するとも言われております」と、稀な疾患であることも強調されていました。
あくまでも特別な疾患の人たちが特別な条件に合致してこそ、法的な性別変更は認められる、という法律でした。性器や生殖腺が生物学的な性別のままであることが耐えがたいという疾患であり、なおかつ、それに対処するために性別適合手術を受け、裁判所において法的性別の変更が認められた人のみが、この法律の対象者でした。
同法第2条の性同一性障害者の定義には、「自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者」とあります。この意思を性別適合手術というかたちで示してこそ、一般社会はこれらの人たちの法的な性別取り扱いの変更を受け入れてきました。つまり、性別適合手術を受けることを望まない人や、手術を受けられないことに折り合いをつけていける人は、そもそも同法の対象者ではありません。手術要件などを違憲として削除すれば、同法はもともとの主旨から大きく踏み外したものになります。
2.性別の定義を変えることになり、女性を脅威にさらす
生まれ持った性器・生殖腺はそのままに、法的社会的な性別の取り扱いだけ変更を受けたいというのであれば、それは性別の定義そのものを変えることになります。
性別とは身体の型のことです。臓器、筋肉量、骨格、性ホルモンの分泌、妊孕性、妊娠させる機能、それらによって分けられる身体の型によって、一方を女性、一方を男性と呼びます。性別は2つしかなく、性分化疾患の方も男性か女性かのどちらかです。性別とは「生物学的性別」のことを指し、現在の日本の法律も制度も社会的ルールもそれに則って作られており、特例法自体も、性別とは生物学的性別であることを踏まえたものになっています。
特例法の手術要件が大法廷で違憲とされれば、それにもとづいて法律の変更が求められ、特例法から手術要件がなくなります。これは性別の定義を、身体の型の違いから、もっぱら性自認、つまり一個人が自分自身の性別をどう認識するのかという、主観的なものに委ねることになります。そうなれば、「ペニスのある女性」が法的に可能になり、女性の身体が無防備になる場所でも、そうした人々が利用することが可能になります。本来そこを使う権利があった女性たちが、「ここにペニスのある人間がいるべきではない」と言ったとしても、法律の力によって完全に無効化されることになります。
実際に、手術要件なしに性自認をもって法的性別を変えることが可能になっている諸外国においては、すでにさまざまな事件が起きています。たとえば、スパの女性用エリアに勃起したペニスを持つ人が入っていても、その人を追い出すことが法的にはできなくなりました。女性のみが使えるプールを利用していたイスラム教徒の女性は、そのプールにペニスを持つ人が女性だと名乗って入るようになり、利用を避けざるをえなくなりました。このような例はたくさんあります。
現代の日本社会において、性別でエリアを分けているのは、主に性的に侵害されやすい女性と少女の安全と人権を守るためです。このルールが無効化されたなら、たとえ何らかの加害行為がなくても、人として当然の羞恥心を傷つけられ、尊厳が損なわれますし、場合によってはより直接的な被害を受けやすくなるでしょう。人口の半分を占める女性たちの人権と安全が深刻な脅威にさらされることになるのです。
3.手術要件の撤廃は日本国憲法の第13条と第14条に反する
記事によると、最高裁大法廷では、特例法の手術要件が憲法第13条に照らして違憲ではないかを審査するとのことです。憲法13条は、公共の福祉に反しないかぎり個人の自由権、幸福追求権を保障するものですが、特例法の手術要件を撤廃して、ペニスのある法的女性が発生するなら、その人たちが女性専用スペースに入ることで女性の側に生じる甚大な被害は、十分に公共の福祉に反するものです。また、すでに述べたように、国の法律も制度も社会的ルールもすべて生物学的性別を前提にして構築されており、性別の基本を性自認にもとづかせることは、このような社会的秩序を根底から毀損することになるでしょう。
また、法の下の平等を定めた憲法第14条にも照らして審査するとのことですが、手術要件が撤廃されれば、女性が平等に社会に参加するために不可欠な女性の安全と人権が脅かされることになるわけですから、これは性別による差別を禁じたこの14条に真っ向から反することになります。
特例法の手術要件は、女性の安全と人権を守るために絶対に必要なものです。性別の境界は、なし崩しにされてはなりません。私たちは、手術要件の撤廃に断固反対し、国民のみなさまにこの問題の重大さを広く訴えるとともに、女性と少女の人権と安全を守ってくださるよう、切に最高裁の判事のみなさまに呼びかけるものです。
2022年12月19日
No!セルフID 女性の人権と安全を求める会
共同代表 石上卯乃、桜田悠希
【参考】
日本国憲法
第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする
第14条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
② 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
③ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
2019年(平成31年)1月23日、最高裁判所は性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(以下性同一性障害特例法)が定める性別の取扱いを変更するための「生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること」と「その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること」という条文(以下手術要件と呼びます)が、憲法13条などに違反するとして、戸籍上は女性である岡山県在住の臼井崇来人(たかきーと)さんが手術を行わないで男性への性別の取扱いの変更を求めた家事審判で、「現時点では憲法に違反しない」との初判断を示し、性別の取扱いの変更を認めない決定を出しました。
これは裁判官4人全員一致の意見ですが、うち2人は手術なしでも性別変更を認める国が増えている状況を踏まえて「憲法13条に違反する疑いが生じている」との補足意見を示したとのことです。
私たちは最高裁判所判断を妥当である考え、支持します。
以下、性同一性障害特例法の手術要件について、当会の考えを表明いたします。
1.性別適合手術は、強制断種手術ではない
性同一性障害特例法に手術要件があることを「断種要件」と呼んだり、旧優性保護法下において、遺伝性疾患や知的障害、精神障害の方の一部が国によって強制不妊手術を受けたことに関連づけて、国による不妊手術の強要であるとか強制断種であるかのように報道されたり主張する人が存在します。
しかし、性別適合手術や手術要件は、強制不妊手術でも強制断種でもありません。
まず、国による強制不妊手術は、本人の同意無く行われたものです。しかし、性同一性障害における性別適合手術は、本人の強い希望によってのみ行われ、しかも全額自費です。
性同一性障害の当事者の多くは、手術を受けたいために懸命にお金を貯めて、精神科や婦人科や泌尿器科に(場合によっては何年も)通って診断書をもらい、更に手術まで何年も待たされたり時には海外に行ったりしてまで受けます。
元々性別適合手術は、手術を嫌がる医師を懇願の末になんとか説得して、ようやく始まったという歴史的経緯もあります。このように強制性は存在しません。
確かに一部の当事者に「手術は受けたくなかったが特例法によって戸籍の性別の取扱いを変更するためには受けざるを得なかった。これは一種の強制である」と主張する人もいるようです。しかしながら、これはおかしな話と言わざるを得ません。
そもそも性別適合手術は、身体に対して強い違和感があり、それを解消するために行われます。精神科医が患者を診察して、本人が強く希望し、性別に対する違和感からくる苦痛・苦悩を取り除くためには手術をするしかないと判断して初めて行われるものです。しかもその診断が間違いでないように2人以上の精神科医が診ることになっていますし、更には専門家による判定会議も行われます。
当然、戸籍変更したいからというような個人の利得のために行うものではありませんし、それを理由として手術を希望しても、本来精神科医の診断は得られないし判定会議も通りません。
もし、本当は手術をしたくなかったけれど、戸籍の変更のために仕方なくやったという人がいるなら、その人は精神科医も判定会議のメンバーも騙したということに他なりません。
また性同一性障害特例法は「性別の取扱いの変更を行うには、手術をしなさい。」と定めているわけではありません。
この法律は、手術を行い、男性として、あるいは女性として生きている人の戸籍上の性別を、そのままだとあまりに不便だろうから現状に合わせて変更しましょうというものです。
つまり、「特例法の要件を満たすために手術をする」のではなく「手術をした人の性別を追認する」ための法律なのであり、順序が逆なのです。
2.性同一性障害の当事者の中でも意見が分かれている
そもそも、この手術要件の撤廃を性同一性障害の当事者が全員望んでいるのかというと、そうではありません。特に当会に所属している当事者の方には、手術要件の撤廃に反対の立場を取る人も多く存在します。
性同一性障害の当事者のうち、特に身体に対する強い違和感がある中核群と呼ばれる人たちは、手術を必要としています。従って中核群の当事者にとっては、手術要件があったとしてもそれ自体は大きな障壁とはなりません。
3.権利を侵害されることになる側(特に女性)への配慮が必要
手術を必要としないとなると、男性器を持った女性、女性器をもった男性が存在することになります。
世の中にはトイレ、更衣室、浴場、病室、矯正施設など男女別の施設がいくつもありますが、これらの施設が男女別になっていることには意味があります。特に、性的被害を受ける可能性が高い女性にとっては「安心・安全な環境を提供する」という意味合いがあります。
しかし、手術を必要とせずに戸籍の性別変更ができるとなると、男性器をもった人、しかも場合によっては女性を妊娠させる能力を持った人がこうした女性専用の施設に入場してくることになります。
世の中に女装した人の痴漢行為や盗撮などの性犯罪が多く存在する昨今、これで本当に女性の安心・安全な環境を提供することができるのでしょうか。
実際、手術要件の存在しないイギリスやカナダでは、女性用刑務所に収監された未手術の受刑者による強姦事件も発生しています。
もちろん、そうした罪を犯す人が悪いのであって、それによって無関係の人にまで累が及ぶのはおかしいという考えもあるでしょう。
しかし、罪を犯す人が悪いだけという論法であれば「女性専用車両」というものは必要ないわけです。痴漢は、それを行った人だけが悪いのであって、他の男性は無関係です。しかし女性専用車両が必要となった背景には、そうでないと女性の安心・安全な空間を確保できないと判断されたからです。
女性は、多くの人が小さいときから性的関心を受けたり怖い思いをしたりしています。触ったり盗撮したりという明らかな犯罪まではいかなくても、じろじろ見られたり、迫られたりしたこともあるでしょう。
それを考えれば、これはやはり男女別施設によって安心・安全な環境を提供されるという権利を侵害していると考えられます。となれば、当事者側の権利の主張だけで物事を通すことはできません。
それでは、入れ墨のように施設によって未手術の人を排除するということは可能なのでしょうか。
これも難しいでしょう。特例法では、第4条第1項に「法律に別段の定めがある場合を除き、その性別につき他の性別に変わったものとみなす」と定められています。従って性器の有無だけで法的に性別が変わった者を排除することに合理性は見いだしにくく「差別」にあたることになります。数年前に静岡で性別の取扱いを変更した人がゴルフ場への入会を拒否された事件では、差別にあたるとしてゴルフ場側が敗訴しました。
それでは「法律で別段の定めを作れば良い」という話になるでしょうか。例えば「未手術の人は特定の施設の利用を制限できる」とか。これもどうでしょう。これではある意味「あなたは完全な女性(または男性)ではない」と言われているようなものです。二等性別のように扱われることで当事者は傷つくことになります。
4.戸籍変更後に、変更前の性の生殖機能で子どもができる可能性
妊娠したFTMの人は生殖器をそのまま持っている訳ですから、当然男性に性別変更した人が出産したり女性に性別変更した人が妊娠させたりすることがありえます。つまり男性が母、女性が父ということがありうるということです。
実際、海外の事例で男性に性別変更した人が出産したという事例があり、ニュースにもなっています。
別に男性が母になってもいいのではないかという議論は確かにあるでしょう。が、こうなってくると男とは何か、女とは何かという定義というか哲学や宗教の扱う範囲になってしまいます。現状の法律や行政の体制はもちろんそれを前提としておらず、いろいろな制度で手直しが必要になってくるでしょう。
更に「家族観」も問題です。世の中には、保守系の方を主とする家族観に厳しい人が大きな勢力として存在しています。夫婦の選択的別姓が実現しないのも、代理母出産が実現しないのも極端に言えばこの人たちが反対しているからと言われています。特例法の「現に子がいないこと」要件の削除が実現しないのも「子どもの人権に配慮して」というよりはこうした人たちの家族観に反するというのが大きな要因と言えます。
そうした家族観からすれば、男性が母、女性が父となる要素は受け入れ難いと考えられます。私たちの存在は、そうした「家族観」を壊すものではあってはなりません。
5.要件の再検討が必要
現行の特例法から手術要件が無くなると、20歳(成人年齢が変更になれば18歳)以上、婚姻していないこと、現に未成年の子がいないこと、性同一性障害の診断を受けていることの4つが要件として残ることになります、果たしてこれでいいのかを考えなければなりません。
世界にはアルゼンチンのように、医師の診断書も必要なく申請だけで性別変更ができる国もありますが、日本もそこまで行くのでしょうか。
私たちは不十分と考えます。これだとホルモン療法も全くやっていない、身体の状態は完全に男性のまま、女性のままという人も対象になるからです。性同一性障害であるという確定診断は、身体の治療を始まる前に出ます。項目3に書いたように、権利を侵害されることになる側への配慮が必要ということを考えると、さすがに身体の状態が出生時の性別のままというのは厳しいと言わざるを得ませんし、社会適応できているとは言えません。髭もじゃの人を女性として扱うことに抵抗感があるのは当然でしょう。
とはいえ「性自認の性別で他者から見て違和感がないこと」のような基準は、客観性が無いため設けることは困難です。イギリスでは Gender Recognition Act 2004(性別承認法)において Been living permanently in their preferred gender role for at least 2 years(少なくとも2年間は望みの性別で日常生活を送ること)というように、性自認に従った性別での実生活体験重視の発想をしています。しかし、これもどうやって、誰が検証するのかという問題がでてきます。
基本的に法律は裁判官に判断を丸投げするような形ではなく、明確に判断できる基準を設けなければなりません。そのためには客観的な誰でもが評価できるような判断材料が必要となります。
それでは精神科医が判断するということではどうでしょうか?いや、これだと精神科医が完全に門番になってしまい、現在のガイドラインで唄われている当事者にサポ-ティブに接するということと反しますし、精神科医に人生の大問題を決める権限があるのかというのも疑問です。というわけで、手術を外すのであれば代わりにどのような基準を設けるのかについて、今後検討が必要でしょう。
6.性別の再変更の可能性の検討が必要
手術要件を撤廃すると、変更へのハードルはが大きく下がることになります。逆に言えば安易に性別変更を行う人が出てくるということです。現行の特例法では再変更は全く考慮されていませんが、手術要件を撤廃するとなると考えておかなければならなくなります。
もちろん自由に変更できて良いでは無いかという考えもあるでしょう。が、性別というものを、その時々の都合でそんなに変えて良いものなのか、私たちは疑問に思います。
7. 結論として
結論的に、現時点で手術要件を外すということについては議論が不足しており時期尚早と考えます。
少なくとも、当事者のニーズがどれくらいあるのか、実際に外した場合影響を受ける(特に女性)側の受け入れは可能なのかなどの調査が必要でしょう。また、上記項目5で書いたような要件をどうするのかという検討も必要です。
GID学会や日本精神神経学会には、まずはこうしたアカデミックなエビデンスを揃えていただくよう要望いたします。また、今後の性別変更の要件についても試案を提示すべきでしょう。
さらに、手術要件撤廃を訴えている人は、国に対してその要望を行う前に、世間に対して男性器がついていても女性、子どもが産めても男性なのだということについて、理解と支持をとりつけるべきでしょう。
以上より、私たちは「性同一性障害特例法からの現時点での性急な手術要件の撤廃には反対。撤廃するかどうかを含め、今後更なる意見収集や国民的議論が必要」と考えます。
これに基づき、今後国会議員や関係省庁にも議論をスタートするよう求めていきたいと思います。
私たちは、社会の一員です。当事者の主張がわがままになってはなりません。この問題は、みなさんで大いに議論をし、納得をした上で進めようではありませんか。
2019年2月 運営委員一同
手術要件の撤廃には、更なる議論が必要
2019年2月20日
拝啓、
年があけました。寒気の候、貴党におかれてはご健勝のこととお慶び申し上げます。
日頃からのご活動につき、深く敬服いたします。
私たちは、性別不合当事者としてその権利と女性の権利とが共存する社会を目指して昨年12月21日成立しました。
そして、LGBTの内の「T」性自認概念を導入して伸展させる法案には反対する旨、12月22日その趣意書をお送りさせていただきました。
「性自認」という曖昧かつ主観的な概念が導入され進められていることは、女性の権利法益を奪うものであり、反対する趣旨であります。
そして今回、これに関係して「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」の手術要件を撤廃することを求めないようにされたいなどとする要望書を、GID学会あてに「要望書」を提出しましたので、今後のご参考までにお送りします。
性別適合手術をせずして性別変更ができることは、性自認による性別変更ができることと、ほとんど同義です。
身分証明書の記載と身体的状況が一致しない状況は、私たちのアイデンティティも社会からの信頼も大きく失われると思います。
私たちにとって、手術要件は決して「過酷な条件」ではなく、それこそ「身を守る盾」だとさえ感じています。
この法律は、強い身体違和を持つ私たちに国内の手術を可能とし戸籍変更の道を開くためにできたものでした。
女性たちはより一層、真剣に女性専用スペースでの性被害について懸念しなければいけないことになり「性自認」という曖昧かつ主観的な概念により性別変更がされてしまうことと似てしまいます。
どうぞ、当会の趣意書(一部修正しました)と、今回のGID学会あての要望書とを参考にされて、貴党の政策・方針を定めて下さるようにお願いします。
また、LGBT法・理解増進法案を推進しようとする方々だけではなく、まさに当事者団体である当会ともとも今後、面談の機会を頂けますようお願い申し上げます。
時期柄、皆様のご自愛と、貴党の益々のご発展を祈願いたします。
敬 具
〒100-8910 千代田区永田町1-11-23
自由民主党 総裁 岸田文雄 殿
〒102-0093 千代田区平河町2-12-4 ふじビル3F
立憲民主党 泉 健太 代表 殿
〒 542-0082 大阪市中央区島之内1-17-16三栄長堀ビル
日本維新の会 代表 松井一郎 殿
〒 160-0012 新宿区南元町17
公明党 代表 山口那津男 殿
〒102-0093 千代田区平河町2-5-3 Nagatacho GRiD 4F
国民民主党 玉木雄一郎代表 殿
〒151-8586 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-26-7
日本共産党中央委員会 志位和夫委員長 殿
〒 102-0083 千代田区麹町 2-5-20 押田ビル4階
れいわ新選組党本部 山本太郎代表 殿
〒 104-0043 中央区湊3‐18‐17 マルキ榎本ビル5階
社会民主党党首 福島みずほ 殿
GID(性同一性障害)学会 御中
2022年1月14日
要 望 書
性 別 不 合 当 事 者 の 会
共同代表 河 村 み さ き
共同代表 御 堂 こ ず え
共同代表 森 永 弥 沙
共同代表 吉 崎 真 琴
tsatgism@tukiyo.net
1 私たちは性別不合当事者の会と申します。その名の通り、強い身体違和を持つ性別不合(性同一性障害)を抱える当事者の集まりとして2021年12月21日発足しました。その趣旨は同封の趣意書や、ホームページ(https://note.com/ts_a_tgism/)に代表らの紹介と手記などありますので、ご覧ください。
私たちの多くはいわゆるMtF ですが、FtM の会員もいます。
私たちは、貴学会所属の先生を含め医師らにお世話になっている立場ではありますが、ここにいわゆる「手術要件の撤廃」に反対することを中心に、下記のとおり強く要請します。
2 私たちが新しく団体を作ったのは、強い不安に駆られたからです。
海外では「セルフID」といったかたちで、「性自認」だけで社会的な性別を変えてしまうことができる国もあります。
一時的に「セルフID」は脚光を浴びたようでもありますが、しかし、今では女子トイレでの混乱など弊害も大きいと認識されているという報道を目にします。
また、去年の東京オリンピックでも、体格的に男性的な重量挙げ選手が女子選手として参加する、というのを目にもしました。
アメリカでは男性としての競技実績のある大学水泳選手が「女子選手」として参加し、これらに「スポーツとしてアンフェアではないか?」という疑問の声も上がっています。
「性自認」での性別変更扱いであれば、性別適合手術を受けてさえいない場合を含むのですから、当然だと考えます。
このような声が女性らから強く聞こえるにつれ、FtM、MtF の者として、女性の権利法益、公平性を害することには耐えられず、「性自認」概念を導入することに反対するため、私たちの会は成立しました。
3 ICD-11 が今年発効し、「性同一性障害」から「性別不合」への概念が変わってきました。
日本でもいわゆるLGBT 法の審議や理解増進法案の提出が話題となる中、2021 年5 月21 日、貴学会は 「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」の改正に向けた提言を出されました。
そこでは、<提言2>として「生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること」「その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること」(いわゆる、「手術要件」)の撤廃を求めます」としています。
しかし、私たちはこれに賛成ではなく、正反対であり、強い危惧の念を抱いています。
4 現在でさえ、GID の医療的サポートは十分であると感じている当事者は少ないです。
ホルモン療法への健康保険適用がないために、国内での性別再判定手術への保険適用も「混合診療」を理由としてなかなか適用されてない状況です。
ここで「脱医療化」を主張したりすれば、どういう根拠で健康保険が適用可能なのか、強い懸念が持たれるは当たり前です。
当事者が求めるのは、「脱医療化」ではなくて、
・「安全な医療」
・「安価な医療」
・「アクセスしやすい医療」
なのです。
5 さらに現状、「一日診断」を謳う一部クリニックも存在し、ガイドラインは形骸化している、と批判の声も上がります。
安全な医療・アクセスしやすい医療とは、「しっかりと標準化された医療」、ということでもあり、それが「ガイドライン」として形になりました。ところが、それが名目化しているという懸念を、ほかならぬ当事者が抱いているのです。
貴学会でも「認定医」制度がありますが、ホームページを見る限り日本中に33人しかいません。
地域的な偏りもありますし、実際にどのような役割を果たしているのか、当事者に見えているわけではありません。
「認定医」は特に性別再判定手術や戸籍変更に際しての診断書の要件であるわけでもありません。
いったい何のための「認定医」なのでしょうか。
それこそが大きな問題です。
これを活用して「医療を標準化し、信頼させる」ような手段はないのでしょうか。
診断の標準化とその信頼性は、私たち当事者の利害に直結します。
実際、手術を受け戸籍も変えたにも関わらず、「自分は性同一性障害ではなかった」と、手術と戸籍変更を後悔した方も何人もいます。
2017 年11 月30 日には家庭裁判所が誤診を認め、性別変更の取り消しを認めた例があると報道されています。
しかし戸籍変更は取り消せても、手術によるダメージは元には戻せません。これは性別の法的変更を求める当事者にとって、見逃せない懸念事項なのです。
後悔するのなら、止めてくれ、と誰もが思います。
診断が信頼できるものであることは、またさらに当事者の社会的な信用にも結び付きます。
「性同一性障害の診断を受けた人は、本気で移行先の性別に馴染もうと努力している人であり、それを医学が保障している」と周囲に信用されるのであれば、どれほどか性別移行の助けになることでしょうか。
口では「自分は女性」あるいは「自分は男性」とでも何とでも言えます。
しかし、ただの自称ではなくて、それを医療が明白にサポートすることを示すこと、そしてその診断に責任を持つことが、当事者が安心して性別移行を試みる条件であり、かつ社会に広く深く受け入れてもらえる条件だと言っても過言ではないでしょう。
6 日本でも年少の頃からの確認・働きかけの動きが始まっています。
すでに海外の事例として、安易に未成年者に性別移行の医学的介入をして悲劇を招来している事例が見つかります。
しかし、幼児の一時的な思い付き、あるいは思春期の女子が体の変化・ジェンダーロールの押し付け・男性からの性的視線への嫌悪などから、「性別移行」というアイデアに飛びついてしまっている可能性はないでしょうか。
そして、それを専門医ですらちゃんと判断しきれずに肯定してしまい、後に「脱トランス」して裁判になるなどのケースも見つかります。
若い頃の一時の気の迷いで人生を狂わされることのないように、「引き返せる道」をちゃんと提示しつつも、医療的介入の開始年齢の引き下げにはより慎重に、人権モデルではなく医学的エビデンスに基づいた決定がなされることを求めます。
7 このようにみてくると、「性同一性」、統一性・一貫性・持続性として語られ、事実上性別移行と性別再判定手術への適性とも理解されるような「性同一性」と、いわゆる「性自認」とは、本当に同じものなのか、という疑問が当然に湧いてきます。
どうも最近LGBT 運動に関して口に出される「性自認」とは、ただ「自分はそう思う」という主観的な意見に過ぎないようにも感じられます。
曖昧かつ主観的な概念であるというほかないのではありませんか。
そしてこの「性自認」を盾にとって女性専用スペースへの侵入を試みて問題になる例が、最近もあとを絶ちません。
中には性同一性障害の診断などまったく受けておらず、身体違和も全くな
いのではないかとみられる、痴漢行為の言い訳に使われているのではないか、と懸念される事件も起きています。
8 このような「性自認」に強く不安を感じるのは、女性だけではありません。
真剣に性別移行をしようとしている私たちMtF・FtM の当事者もまた強く不安を感じています。
私たちの信用が失われ、「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」に対する国民からの信頼が失われてしまうのです。
すでに女性らの一部からは、性適合手術を受け法的に「女性」になった人に
ついてまで信用できないという声が上がっているのです。
このようなことでは、女性たちが自らの安全を守るために、女性スペースで少しでも「男性?」と疑われる人を問い詰め、通報するというような事態を招くことになります。
これは私たちの求めることではありません。
たとえば手術済・戸籍変更済であっても、いわゆる「パス度」が低い当事者の場合、女性の警戒心が高まった状況は、針の筵のようなものでしょう。
もちろん、女性専用スペースの利用にあたっては、当事者の側の配慮と自己規制も求められるのは承知の上の話です。
しかし不心得者や偽装を許してしまえば、女性の当事者に対する眼が厳しくなるばかりです。
それでも、現行制度では、戸籍変更の要件として手術要件があります。
戸籍が女性ならば手術済ですから、女性スペースを利用できる筈です。
ですから、この現行の「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」が、私たちが性適合手術を受け、MtF が法的に「女性」になった
後には、権利として「女性だ」と言える根拠なのです。
9 しかし、手術要件を撤廃してしまえば、どうなりますか。
それは「性自認」で法的な性別変更ができるということと同義ではありませんか。
身分証明書の記載と身体的状況が一致しない、私たちのアイデンティティも社会からの信頼も、大きく失われると思います。
そして女性たちは、より一層、真剣に女性専用スペースでの性被害について懸念しなければいけないことになります。
このような事態は、私たち当事者にとって、マイナスでこそあれ、プラスになることではありません。
私たちにとっての手術要件は、決して「過酷な条件」ではなく、それこそ「身を守る盾」だとさえ感じています。
この法律は、もともと性別適合手術が日本でも適法であることを示して、強い身体違和を持つ私たちに国内の手術を可能とし、戸籍変更の道を開くためにできたものだったことを思い出してください。
「性自認」の概念には「性別違和があるが身体違和はない人」もいるとされますが、まったく理解できません。
身体違和がない人を、この法律を検討する際に、考慮する必要がどこにあるのでしょうか。
10 ですから貴学会からも対策や知恵を出していただきたいのです。
どうすれば、当事者が社会に信用されるのか、真剣に考えて頂きたいのです。
それは「人権モデル」やらの流行の言葉を使うことではありません。私たちの生存が懸っているのです。
具体的な要望としては、次のことをご検討願いたいと考えています。
(1) 手術要件の撤廃は本当に当事者の利益なのでしょうか?
不安に感じる当事者、それに女性たちがいることを考慮ください。
少なくともその得失について開かれた論議と社会の納得なしに、手術要件を撤廃するのには反対します。
(2) 脱医療化が進むべき道なのでしょうか?
脱医療化が健保適用のさまたげにならないと、保証ができるのでしょうか。あるいは健康保険に相当する別な施策について何か提言することあるのでしょうか?
簡単に「脱医療化」を主張することに、危惧を感じます。
「脱医療化」の前に、ホルモン治療への健保適用を実現して頂きたい。
(3) 診断の標準化と、信頼性の確保に向けて、具体的な施策を求めます。
「一日診断」のような診断の簡易化は決して許さないで下さい。
逆に「診断の厳格化」が当事者にとっての利益だと考えます。
診断に責任を持っていただきたい。
もし、当事者が誤診を主張して脱トランスする、あるいは診断を悪用した性犯罪を起こしたなどの事件があれば、相応の責任を診断した医師に求めるでもしないと、診断自体が社会に信用されなくなります。
(4) MtF、FtM のいずれについても、未成年者の性別移行はもちろん、医学的介入の開始年齢の引き下げについては、「人権モデル」ではなくて「医学的エビデンス」に基づいて議論がなされることを求めます。
(5) 「性自認」というような曖昧で主観的なアイデンティティではなくて、客観的な根拠による診断を求めます。
もちろん理論的な研究などまだまだこの問題には光の当たっていない領域が数多く残っています。
単に「社会的なニーズがあるから」ではなく、科学として真実の究明に取り組んでください。
11 以上の通り、貴学会におかれて、いわゆる「手術要件の撤廃」を求めることのないよう、そして上記の具体的な要望を改めて正面から検討されるよう、強く要望します。
以 上
42
性別不合当事者の会
2022年1月12日 22:27
性別変更にかかる性適合手術、いわゆるLGBT法について
次に災害時、性被害に遭いやすい生得的生物学的女性の声が日本の避難所において軽視されている現状について。

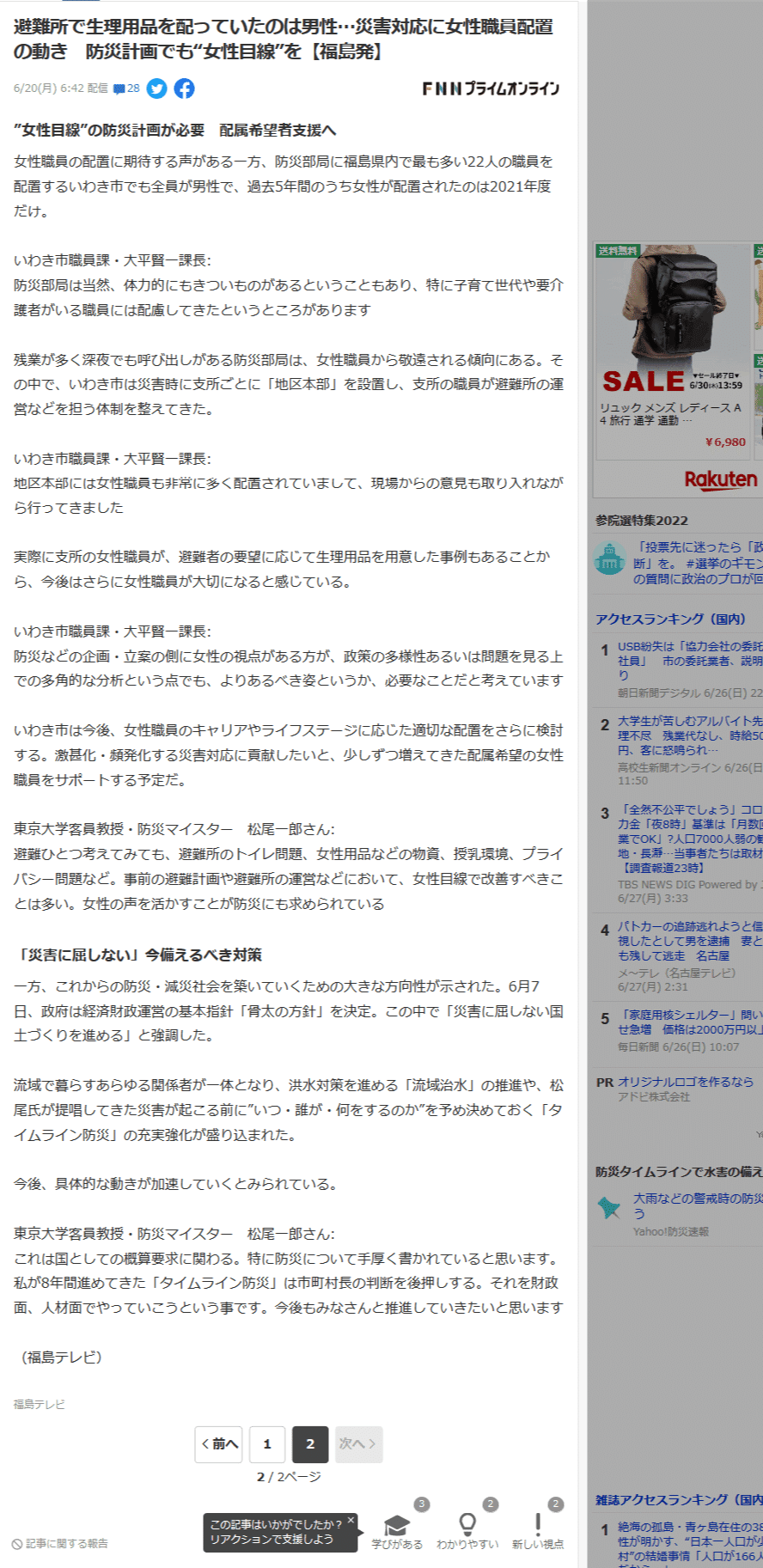
さっき「防災担当部署に女性職員がいない自治体が6割」というNHKニュースで防災担当の男性職員が生理用品を「1日1枚で足りるのかな」と言ってて、
— おたま@男子二児の母 (@otamashiratama) May 27, 2022
足りません!!!!!!!!
とTVの前で叫びそうになっちゃいました…
東日本大震災や熊本地震では、避難した女性たちから「生理用品をもらえなかった」とか「避難所に仕切りが無く、みんながいる場所で授乳することにストレスを感じた」とか、訴えがあったとのこと。
— おたま@男子二児の母 (@otamashiratama) May 27, 2022
防災担当部署に女性職員が1人もいない状況は怖いなと思います。
女性不足の理由として内閣府は「地震・大雨など緊急時の対応が多く、子育て中の女性など配置しづらい」と。
— おたま@男子二児の母 (@otamashiratama) May 27, 2022
子育て中の職員を配置しづらいのは本来「女性職員」に限った話ではないはずなのに、まだまだ子育ては女性のもの、というのが多くの自治体での現状なんだな…と思いました。
しかし800人の避難所で生理用品が72枚しかないなんて、私のような素人が見たって明らかに足りないとわかるんですが、こういうのって内閣府とかが各自治体に「避難者の人数あたり○枚の生理用品を備蓄する」みたいなガイドラインを作ってくれたりしないんですかね。「災害時の生理用品の配り方」とか。
— おたま@男子二児の母 (@otamashiratama) May 27, 2022
800人の避難者のうち400人が女性で、200人が生殖年齢だとして、30日中5日間は生理だとすると、生殖年齢女性数の6分の1は生理中なわけですよね。そしたら33人は生理用品が必要。1日に1人が最低4枚のナプキンを使うとして、1日あたり132枚必要。できれば夜用と昼用両方を常備。みたいな。適当ですけど。
— おたま@男子二児の母 (@otamashiratama) May 27, 2022
よく考えたら防災担当部署に女性が1人いたとしても、その女性があらゆる状況の女性を想定して準備するなんて無理ですよね。女性がいるのは望ましいけど、女性がいれば良いというわけではない。やっぱり国として「避難所には生理用品、オムツ、ミルク…それぞれ○○個を用意」とか決めておいてほしい。
— おたま@男子二児の母 (@otamashiratama) May 27, 2022
https://twitter.com/otamashiratama/status/1530185999938383872
拡散されてるようなので追記します。
— おたま@男子二児の母 (@otamashiratama) May 27, 2022
女性の皆さん、是非ともこの週末あたり、ご自分の防災リュックに生理用品が入っているか確認してみてください。
使用期限は3年が目安らしいのでご参考まで。 pic.twitter.com/uW4ryc6YjX
Tweetを補足しつつ、私が調べたこと&考えたことを書きました。
— おたま@男子二児の母 (@otamashiratama) May 28, 2022
避難所に生理用品が足りなかったらすごく困る/災害備蓄の生理用品の使用期限にもご注意を - おたまの日記 https://t.co/riSRjnxNun
おたま@男子二児の母
@otamashiratama
·
2022年5月27日
さっき「防災担当部署に女性職員がいない自治体が6割」というNHKニュースで防災担当の男性職員が生理用品を「1日1枚で足りるのかな」と言ってて、 足りません!!!!!!!! とTVの前で叫びそうになっちゃいました…
158
9,296
5万
おたま@男子二児の母
@otamashiratama
東日本大震災や熊本地震では、避難した女性たちから「生理用品をもらえなかった」とか「避難所に仕切りが無く、みんながいる場所で授乳することにストレスを感じた」とか、訴えがあったとのこと。 防災担当部署に女性職員が1人もいない状況は怖いなと思います。
午後8:25 · 2022年5月27日
1,239
件のリツイート
26
件の引用
5,614
件のいいね
17
ブックマーク
おたま@男子二児の母
@otamashiratama
·
2022年5月27日
女性不足の理由として内閣府は「地震・大雨など緊急時の対応が多く、子育て中の女性など配置しづらい」と。 子育て中の職員を配置しづらいのは本来「女性職員」に限った話ではないはずなのに、まだまだ子育ては女性のもの、というのが多くの自治体での現状なんだな…と思いました。
9
1,040
4,830
おたま@男子二児の母
@otamashiratama
·
2022年5月27日
しかし800人の避難所で生理用品が72枚しかないなんて、私のような素人が見たって明らかに足りないとわかるんですが、こういうのって内閣府とかが各自治体に「避難者の人数あたり○枚の生理用品を備蓄する」みたいなガイドラインを作ってくれたりしないんですかね。「災害時の生理用品の配り方」とか。
6
1,612
5,821
おたま@男子二児の母
@otamashiratama
·
2022年5月27日
800人の避難者のうち400人が女性で、200人が生殖年齢だとして、30日中5日間は生理だとすると、生殖年齢女性数の6分の1は生理中なわけですよね。そしたら33人は生理用品が必要。1日に1人が最低4枚のナプキンを使うとして、1日あたり132枚必要。できれば夜用と昼用両方を常備。みたいな。適当ですけど。
3
775
3,310
おたま@男子二児の母
@otamashiratama
·
2022年5月27日
よく考えたら防災担当部署に女性が1人いたとしても、その女性があらゆる状況の女性を想定して準備するなんて無理ですよね。女性がいるのは望ましいけど、女性がいれば良いというわけではない。やっぱり国として「避難所には生理用品、オムツ、ミルク…それぞれ○○個を用意」とか決めておいてほしい。
4
955
3,859
おたま@男子二児の母
@otamashiratama
·
2022年5月27日
拡散されてるようなので追記します。 女性の皆さん、是非ともこの週末あたり、ご自分の防災リュックに生理用品が入っているか確認してみてください。 使用期限は3年が目安らしいのでご参考まで。
6
1,101
2,590
おたま@男子二児の母
@otamashiratama
·
2022年5月28日
Tweetを補足しつつ、私が調べたこと&考えたことを書きました。 避難所に生理用品が足りなかったらすごく困る/災害備蓄の生理用品の使用期限にもご注意を - おたまの日記
自然災害は、誰しもに同様に降りかかるものではない
1991年、バングラデシュで発生したサイクロンでは、犠牲者の90%が女性と子どもだったと推定されています。
これは、サイクロンや洪水の早期警報の情報が公的な場所で男性から男性に伝えられ、家にいる女性には直接届かなかったから。
2004年、スリランカを襲った津波では、男性の多くは既に漁に出ていて難を逃れましたが、その妻たちが自宅で朝食の準備をしていて流されたと言われています(*1)。
自然災害は、誰しもに同様に降りかかるものだと思われているかもしれません。しかし、受ける被害の度合いはその内容は、その人のジェンダー、年齢、障害の有無によって違いが生じることが、このように数々の事例から指摘されているのです。
これらの問題は海外で──開発途上国でのみ起きていることなのでしょうか?
実は、日本でも同様の事象は起きています。災害復興の現場には多様な視点が盛り込まれるべきですが、とかく「シスジェンダー(生まれた時の性別と自認する性別が同じ)の男性」のニーズが自明のものとされ、吸い上げられていない声が数多く存在していました。
たとえば、東日本大震災の際に、避難所では、生理用品や女性用の下着などが届いても配布担当が男性で、取りに行きづらいなどの状況も。避難所や仮設住宅では女性に対しての性暴力が起き、夫・交際相手による暴力(DV)も増加していました(*2)。
災害をメディアの報道でしか見たことがないと、自分ごととして考えた時に「何か起きたら避難所に行けば大丈夫」などと漠然としたイメージになってしまいがちです。でも、じっさい現地で何が起きていたのか理解が深まると、「何が」「どう」問題なのか、より明確に見えてきます。
ゲストと一緒に未来の防災を考えます
東日本大震災の被災自治体を対象に行った調査では、復興に関わる委員の中で女性の割合は14.6%。熊本地震の時、県の対策本部では女性6%でした(*3)。
このような男女比の偏りは、日本の政治の世界における男女の非対称性の縮図でもあります(日本のジェンダーギャップ指数は121位(*4)、その中で著しく他国と引き離されているのが政治分野です)。
イラスト:アベナオミ
3月6日、ハフポストはこうした課題を投げかけるべく、JICA(独立行政法人国際協力機構)のスポンサードのもと、「女性の視点から考える防災」をテーマにLIVE番組を配信します。
3月8日は国際女性デー、そして、3月11日は今年、東日本大震災から10年を迎える節目。多様な視点を取り入れた未来の防災について考えるため、まずはジェンダーという切り口からこれまでの常識の刷新を試みます。
ゲストにお迎えするのは、藤原しおりさん、長野智子さん、田中由美子さん(城西国際大学教授・JICAジェンダー・アドバイザー)、高橋宗也さん(宮城県議会議員・元東松島市役所復興政策部長)の4名。
藤原さんは、2018年7月の西日本豪雨の際、岡山県のご実家が被災され、ご自身も個人で志願するボランティアに参加された経験があります。
藤原さんの等身大の目線、そして、国内外の災害の報道をされてきた長野さん、ジェンダーの専門家で国際協力に携わる田中さん、行政の立場から復興に尽力されている高橋さんの知見をお借りし、番組で未来の防災について議論をしていきます。
災害時、対策に当たる行政も被災しているという過酷すぎる状況の中では数々のジレンマもあります。そんな現状も踏まえながら、もしもの事態に備えて、今日から私たちの意識は、社会の仕組みはどう変わっていくべきなのでしょうか? 3月6日、視聴者の皆さんと考えたいと思います。
東日本大震災の時、女性はこんなことに困っていた……なかなか知られていないけれど、被災時から復興、そして防災に取り組む中で、現場からは数々の困難が報告されている。
2021年02月24日 18時5分 JST|更新 2021年03月05日 JST
http://risetogetherjp.org/wordpress/wp-content/uploads/2015/12/bouryokuchosa4.pdf
https://www.nagoya2.jrc.or.jp/content/uploads/2021/08/Sphere-Handbook-2018-Japanese.pdf
https://drive.google.com/file/d/1MTAgZ_3P51dIMPm_MiZ6EC51zq8wpozB/view?usp=share_link
https://www.bousai.go.jp/taisaku/hinanjo/pdf/1604hinanjo_guideline.pdf
https://www.gender.go.jp/policy/saigai/fukkou/pdf/fukkou-gideline.pdf
https://www.jica.go.jp/jica-ri/ja/publication/other/l75nbg0000096gzf-att/20170529_01_JP.pdf
https://www.gender.go.jp/policy/saigai/report2012FY/pdf/hearing_jirei08.pdf
https://www.gender.go.jp/policy/saigai/report2012FY/pdf/hearing_jirei01.pdf
https://www.gender.go.jp/policy/saigai/report2012FY/pdf/hearing_jirei02.pdf
https://www.gender.go.jp/policy/saigai/report2012FY/pdf/hearing_jirei04.pdf
