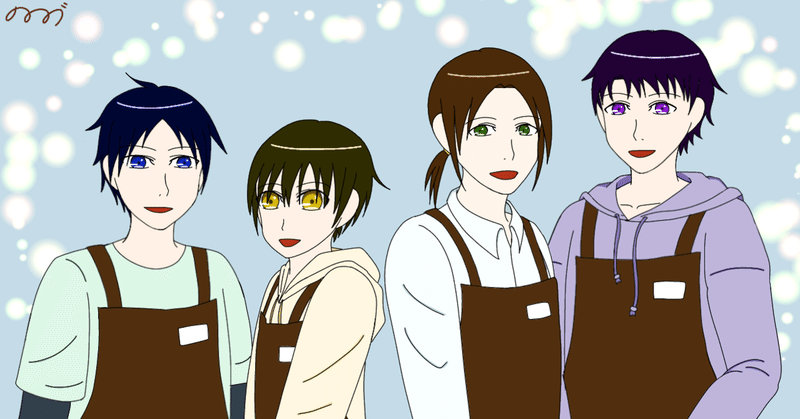
羽倉茶葉店×謎の紅茶屋 1
クロスオーバー「羽倉茶葉店」×「謎の紅茶屋とお話を」
・羽倉の場合
長身に長髪の男は目を丸くした。ほぼ同時に顔を上げた彼は言う。
「おや、お客様で――」
「おや? 何だか変な場所だね」
彼が何かを感じて口を閉じれば、男は困ったような顔をして笑う。
「こんなところに人がいるとは思わなかった」
そして男はテーブルの上に食器が並んでいるのを見ると、断りを入れずに椅子を引いて腰かけた。
「そこにあるのは紅茶だね?」
「ええ、そうですよ」
と、彼はティーポットの蓋を取ると、茶葉をティースプーンですくって二杯ほど入れた。
「俺、ミルクティーがいいんだけど」
「自らリクエストをする方は初めてですね」
くすりと笑って、彼はティーポットに湯を注いだ。
「その茶葉はアッサムかい? セイロンだったら飲まないよ」
「おやおや、ずいぶんとわがままな方のようで」
彼は男に視線をやると、率直にたずねた。
「戸惑わないところを見ても、あなたは普通の人間ではなさそうですね?」
「おや、気づいちゃったかい?」
男は端正な顔立ちでにこりと笑い、言った。
「そうだよ。実は俺、魔法使いなんだ」
「そうでしたか。では、他人から距離を置かれることもあるのでは?」
「まあね。でも、今は最高の環境で仕事をしているから、毎日が楽しいよ」
「悩みは無いのですか?」
「うーん、売り上げも前に比べて、上がって来たからなぁ。しいて言うなら、早く元の場所へ帰りたいかな」
にこっと笑う男を見て、彼は少し呆れたように息をついた。
「仕方ないですね。分かりました、すぐにお帰りください」
「ありがとう。でも、ミルクティーは飲みたいから、その後に帰るね」
「……本当にわがままな方ですね」
と、彼が困ったように返すが、男は動じることなく言った。
「だって俺、紅茶専門店のオーナーだもの」
・乙女の場合
「何ですか、ここ。悪夢ですか?」
男性にしては小柄で華奢な青年は、開口一番にそう言った。
彼は薄く微笑みを浮かべて返す。
「あなたが悪夢だと思うなら、きっとそうなのでしょう」
「は? じゃあ、現実ですか? あっ、もしかしてあなたは魔法使い!?」
と、青年が混乱した様子で叫び、周囲をきょろきょろと見回す。
彼はかまわずに言った。
「どうぞ、そこの席へおかけください」
「えっ! いや、でも、僕は元の世界に……そうだ、現実を思い出そう!」
「そんなことをしても無駄ですよ」
「大丈夫、現実を思い出せ。現実、現実――僕は魔法なんて信じない」
と、両手で頭を抱え、ぎゅっとまぶたを閉じて唱える青年。
彼は気にすることなく、紅茶を淹れ始めた。
すると、茶葉の香りで青年がはっと目を開けた。
「この匂い、紅茶……!? それは何のブレンドですか!?」
「さあ、存じません。私はただここにいて、客人へ紅茶を振る舞うだけの存在ですので」
彼の返答に困惑しつつも、青年はそっと席へ座った。
「甘い香りがするから、たぶんアッサムですよね。でも、ちょっとスモーキーかな。いや、フラワリーな気もする」
ぶつぶつとつぶやく青年へ彼は問う。
「紅茶にお詳しいようですね」
「あ、はい! 僕、こう見えて紅茶アドバイザーなんです」
と、青年は照れたように言い、彼はうなずいた。
「そうでしたか。ところで、あなたの話を聞かせていただきたいのですが」
「僕の話、ですか?」
「ええ。悩みや迷いなど、何でもかまいません。今話したいことをお聞かせください」
「えぇー……」
青年は困った様子で眉尻を下げる。
「そうですね、ここがどこであなたが何者なのか、僕は分からなくて困っています」
「その問いには答えられませんね。私に名前はなく、この場所にも名前がないんです」
「そんなわけないでしょう? あっ、答えたくないって言うなら、今すぐに羽倉さんへ連絡を――あれ?」
立ち上がった青年は、自分の体を衣服の上から触った。通信機器を探しているのだ。
「な、ない……さっきまで肩にかけていたはずの鞄もない」
と、青年が顔面蒼白になる。
彼はかまわずに言った。
「もうじき紅茶が出来上がります。どうぞ、リラックスして気持ちを落ち着けては?」
「う、はい……。というか、一つだけいいですか?」
「ええ、何ですか?」
青年は再び腰を下ろし、おずおずと彼を見ながら言った。
「その、茶葉のブレンドが気になるので、分析させてください」
彼は微妙に表情をゆがめたが、すぐに茶葉の入った缶を青年へ差し出した。
「どうぞ」
「ありがとうございます」
と、青年は少し緊張した様子で缶を受け取った。
「分析したところで、正解はどこにも存在しませんがね」
「そうですか? 自分が信じたものが正解では?」
「おや……」
多少なりとも驚く彼へ、青年はにこりと笑う。
「なので、僕は僕の信じたものを真実とします」
そして青年は蓋を開けると、鼻を近づけて香りをかぎ始めた。
彼はその様子をどこか呆然と見ていたが、ふっと息をついた。
「あなたに私は必要なさそうですね」
・森脇の場合
「はー……本当にこんなんばっか」
青年はがっくりと肩を落とし、ため息をついた。どうやら、早くも状況を理解した様子だ。
彼は紅茶の用意を進めながら言った。
「どうぞ、そこの席におかけください」
平均より少し背の高い青年は、じとりとした目で彼を見つめた。
「何なんすか、ここ」
「さあ、何でしょうね」
「あんたは? 何でこんなところに一人で、しかも紅茶なんて淹れてるんです?」
青年は冷静だった。
彼はちらりとそちらを見てから言う。
「私に名前はありません。私はただ、ここで客人に紅茶を振る舞うのが役目」
「紅茶の精霊か何かか?」
「あなたがそう思うのであれば」
「……ま、いいや」
と、青年はようやく目の前の椅子へ着席した。そして周辺を見回しながら言う。
「何だかここ、魔法空間とは違うものっぽいし、紅茶を飲まねぇと帰れなさそうだ」
「魔法、ですか。あなたはそうしたものを信じているのですか?」
と、彼はティーポットに蓋をした。
青年は顔を前へ向けてから答える。
「信じるも何も、あるんだよ。オレは生まれつき霊感が強いから、嫌でもそうしたものと関わらずにはいられなかった」
「なるほど。それでは、大変なご苦労をされたことでしょう」
と、彼が言えば、青年はため息をつく。
「そりゃあ、な。大人になってから、見えなくなったこともあったけど、結局また見えてるし。生きるとか死ぬとか、ずっと昔から考えさせられてるよ」
砂時計がさらさらと落ちていく。
「では、あなたは今、生きていらっしゃいますか?」
「は?」
「それとも、死んでいらっしゃいますか?」
彼は神妙な顔をして問いかけていた。
青年は少し悩んだ様子だが、すぐにへらりと笑った。
「両方だ」
風がざわりと吹き抜け、青年の足元を揺らす。
「オレは生きてるけど、死んでる。そもそも、誰かに認識されないと、生きてるって実感はわかない。死んでるは、その実感がなくなって、自分が別の何者かになったと感じること」
「独特な価値観ですね」
「まあな。高校二年の時、親友が自殺した時にオレらは死んだんだ。けど、生きてもいた。だからこうして、今も生きてる。でも、心の奥では死んでいて、どれだけつついても、ゆすっても、起き上がらない自分がいるんだ」
皮肉めいた笑みを浮かべた青年へ、彼は言った。
「もったいないですね。あなたはもっと、影響力を持つべき人間なのに」
「何言ってんだよ。オレはもう死んでるって言ったろ? 影響力なんていらないし、ごくごく普通の人生を送るだけで、精一杯なんだよ」
「将来の目標や、夢は持たないのですか?」
「ないない。オレは普通でいいんだって」
「生まれついた霊感を活かすことも、しないのですか?」
「しねぇよ。そりゃあ、もったいないかもしれないけどさ」
と、青年は視線をそらして頭上を見た。
「オレの周りには、すごい人たちがたくさんいるんだ。だからオレは……生きてる方のオレは、よけいなことをしないで、ただ周りの人たちを応援していたいんだ」
砂時計がすべて落ちると、彼はつぶやいた。
「本当にあなたは、死にながらにして生きているようですね」
視線を戻した青年がへらりと、力なく笑った。
・真木の場合
大学生風の若い青年は、呆然とその場に立ち尽くしていた。
彼はにこりと笑みを浮かべて言う。
「ようこそ、いらっしゃいませ。そちらの席へ、どうぞおかけください」
「え……えーと」
と、周囲をきょろきょろと見回す。
「戸惑われているようですね。無理もありません」
「そ、そうなんですか?」
と、聞き返す青年へ彼は言った。
「ええ。何故なら、私にもここが何なのか、分からないからです」
「マジですか。じゃあ、その、紅茶は?」
青年が注目したのは、彼の手元に置かれたティーセットだ。
「私の存在する理由です。私はただここにいて、やってきた客人へ紅茶を淹れるのが役目なんです」
「役目? うーんと、それなら、まあ……」
と、青年は椅子に腰を下ろすなり、ため息をついた。
「何かお悩みですか?」
「ええ。就職活動が、全っ然うまくいかないんです」
「そうですか。努力が足りないのでしょうか」
冷淡に言った彼を、青年はむっとしたようににらみつける。
「努力はしてます。足りないのはたぶん、度胸とか、根性とかです」
「ご自分で分かっているなら、それを克服すればいいのでは?」
「うぅ、それはそうなんですけど」
青年が再びため息をつき、彼は言う。
「根本的な問題は、他にありそうですね」
「……ですよね」
と、青年はうなだれる。
「自分、本当は暗くて地味な性格なんです。熱中するような趣味も無くて。でも、それだと恋人ができないし、ずっと一人になってしまう。それが嫌で、大きい声を出すようにして、今の明るいキャラを作ったんです」
正直に吐露された思いに対して彼は言う。
「偽るのは辛いだけですよ」
「分かってます。大学はそのせいで、全然楽しめてないですもん」
「世界は広いんですから、暗くて地味なあなたを好きになってくれる人もいるのでは?」
青年は口を閉じた。紅茶の甘い香りがゆらゆらと漂う。
「そのままのあなたを受け入れてくれる場所を探し、見つけ出すことができたなら、あなたは本当の幸福に出会えることでしょう」
静かに紅茶がティーカップへ注がれていく。
「さあ、どうぞお飲みください」
差し出されたそれを見て、青年は顔を上げた。
「この色、香り……ルフナかな」
小さくつぶやいてから、青年はそっとカップを手に取った。ふうふうと何回か息を吹きかけ、一口だけ飲みこむ。
「うわ、上品な味がする。ちょっとダージリンっぽいかも。こんなルフナ、飲んだのは初めてだ。いや、ブレンドかな?」
と、首をかしげる。
その様子を見て、彼は穏やかに言った。
「灯台下暗し、でしょうか」
「え? どういう意味ですか?」
と、たずねた青年へ、彼は首を左右へ振った。
「いえ、何でもありません。自身で気がつかねば、何にもなりませんからね」
・宵田の場合
「純血をこんなところに呼びこんで、いったいどういうつもりだ?」
金髪の男が目付きも悪く、そう言った。
彼は怖気づくことなく返す。
「分かりません。私は何もしていませんので」
「はあ? じゃあ、何だ。他のやつがオレをここへ来させたわけか?」
「いえ、そうとも言えませんね。そもそも、私はここが何なのか、私は何者なのか、ちっとも分からないのです」
彼の返答を聞いて、男は眉間にしわを寄せた。
「記憶喪失か? それとも、てめぇは人間じゃないのか?」
「さあ、それすらも私には分かりません」
ひょうひょうと答える彼から視線を外して、男はふうと息をつく。
「っつーことは、ここは別世界ってわけか。魔法空間じゃねぇのは確かだし、おそらく地球上には存在しない類のものだな」
「おやおや、ここへいらっしゃる方は皆、地球からいらした様子でしたが?」
「何らかのきっかけでつながって、その結果として人間がここへ来ちまうんだろう。で、お前はここに閉じこめられていると言える」
先ほどまでと違い、真面目な顔をした男へ彼は問う。
「私にはむしろ、開けているように見えますが?」
「ああ、そうか。じゃあ、ここは開放的な空間だ。で、その地球人たちはどこにやった?」
「帰られました」
「は? 帰れるのか?」
「はい。一定の時間が過ぎると、客人たちは姿を消すのです。時にはこちらの意思で、強制的に帰らせたこともありますが」
「お前、そんなことができるのか?」
「はい。ただし、この場所をはっきりと意識してしまった方には、効かないようなのです」
「は? ますます分からねぇんだが」
と、男は困惑した顔になる。
「とにもかくにも、お座りになられては?」
と、椅子を示されて、男は腰を下ろした。
「悪いな。それで話の続きだが、ここへ来る人間に共通点はあったか?」
「いえ、ありません。若い方からご高齢の方まで、性別も考え方も、育った環境までも、すべてがばらばらなのです」
「ということは、ランダムなのか。いや、そうだよな。普通、オレみたいなやつを呼びこもうなんて思わないはずだ。もっとも、この世界でオレの魔力が通じるかどうかは疑問だが」
と、思考を働かせたところで、男ははっとした。
「そうか。お前の魔力を解析すれば、この世界について分かるかもしれない」
がたっと席を立ち、男は彼へ歩み寄った。
「お前の心臓はどこだ?」
彼は男に体を向け、答えた。
「ありません」
「脳みそは?」
「ありません」
「心はどこだ? 記憶はどこにしまわれている?」
「おそらく、外です。私は客人に認識されることで、初めて存在を確立します」
「ホログラムか? 五分前仮説か?」
「似て非なるものです。客人がいない時、私はどこにも存在しない。客人が現れると、私も同時に現れます」
男は口を閉じると、おそるおそる右手を伸ばした。彼の頭部にかざしたが、驚いてすぐに手を引っこめる。
「何だ、これ……こんな状態、見たことがない」
「だから言ったでしょう?」
男はちっと舌打ちをした。
「くそ、気色悪ぃ。早く帰らせてくれ」
彼はどこか安心したようにふっと笑った。
「もうじき帰れますよ」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
