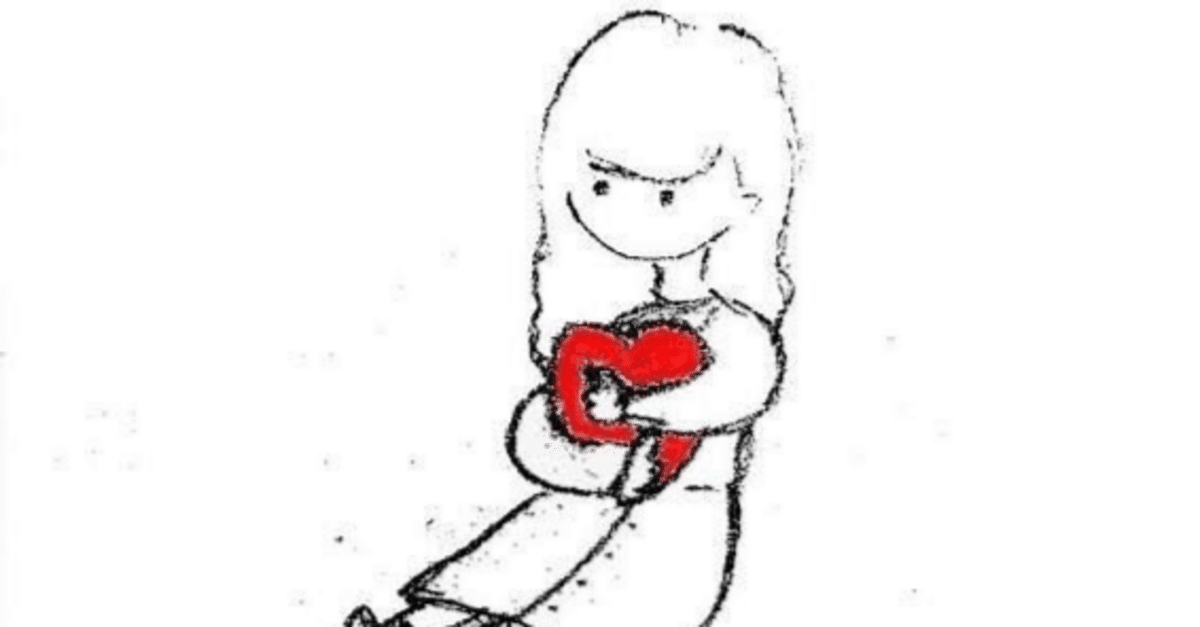
文披31題:Day19 トマト
ピンク色の髪に、赤い目。その見た目でからかわれるのはしょっちゅうで、隠すのに必死になっていた。
さらにしゃべり方もおっとり気味だったし、あげくに自分の魔法の気質が花とわかると、ますますからかわれた。何もかもが、嘲笑の対象だった。
だから隠したいと思って眼鏡をかけ、なるべくしゃべらないようにしたし、髪は一つにくくってこっそりと過ごしてきた。
ありがたいことに、得意の魔法は大した力ではないと思われたために長じるにつれ相手にされなくなり、髪だけが目立つ容姿であればそれはそれとして、最初だけ騒がれることのみ我慢すれば済んでいく。
すると派手な色合いの少女だがあまりにおとなしくて面白みがないと判断され、あとは放っておいてもらえるようになるという処世術を身につけた。
みんな、みんな私のことを見ないで。私のことなんて放っておいて。
憎むよりも、世界に愛想を尽かして生きていたが、自分の魔法は好きだった。花の魔法は、花に働きかければ自分の意思で自由にできる。
花の咲かせる植物に対して力は働く。花を咲かせる、枯らす、花びらを動かす。花に働きかけると花にも感情のようなものを感じ、それに働きかければ効果的だということがわかった。
使えるというほどではないにしろ、風の要素も相性が良かったのか、花びらを動かすという意味で花吹雪だけはできるようになった。華やかだと、セレモニーなどでは重宝された。
花の魔法使いは、見た目こそ派手な色合いを持つが引っ込み思案でおとなしくて毒にも薬にもならない。
そんな印象を植え付けて静かに学生時代を過ごし、目立たないよう行動するくせがついて生きてきた十数年。これからも同じように生きていくのだろうなと思っていた。
あの日、アカデミーのゼミ研究室のドアを開くまでは。
「魔法研究ゼミ、ですか」
「はい」
迷いのない回答に、総務課の担当者は眉を下げた。困っていると一目でわかる仕草に不安になる。
「もしかして、応募者多数で抽選、とかでしょうか……」
あまり人気のなさそうなゼミを選んだはずなのに、しくじったか。人気があるゼミで抽選となると、面倒だ。なにせ人気のゼミということは人が多いだろうし、抽選前も後も、誰かと接触する可能性が高まるからだ。
そうですと言われたら、申し込みを取り下げよう。そして、人気のなさそう、否、人の少なそうなゼミを教えてもらってそこに希望を出そう。
職員が言い淀む合間に脳をフル回転させて結論を出す。それならば行動は早いほうがいい。
「「あの」」
声が、重なった。職員がどうぞお先にと譲ってくれるが、先の質問への回答ということであれば聞いておきたい。
どうぞと譲りなおすと、たいへん言いにくそうに職員が口を開いた。
「あなたが希望を出したゼミは、数年、希望者がいないのです。なので、基本的にゼミ担当者と個別での応対となりますが……」
「ぜひお願いします!」
食い気味に、なんなら机に前のめりでゼミ希望の用紙を差し出して頭を下げる。職員は白黒しながら書類を受け取った。
「本当に、いいんですか? 後悔しますよ……?」
そんなことはない、むしろ大歓迎だ。前半の質問は縦に、後半の質問は横に何度も首を振って希望したゼミへの用紙を受け取ってもらえるように再度頭を下げる。
「お願いします。ぜひ、そのゼミで!」
「わ、わかりました。でしたら、このゼミに関してだけ、希望者は基本的にすべて受け入れるとのことですので、結果を待っていただく必要はありません」
え、と顔を上げると少々顔をひきつらせた職員が、差し出したゼミ希望の用紙に受付印とゼミ決定の印をスタンプしていた。用紙の下方に何かを書き込み、写しをとって返却してきた。
「はい、どうぞ。ゼミ決定、おめでとうございます。正式な通知等は後日になりますが、写しに記載の研究室に向かってかまいませんよ」
担当者にはこちらから一報いれておきますので、と手続きの終了を告げられて総務課から退出を促される。アカデミー生の様々な手続きに忙殺されている総務課だ。用事の終わった学生にいつまでも居座られては迷惑だろう。
出口まで呆然としながら歩き、最後に振り返ると、先ほど対応してくれた職員はすでに別の学生の対応に追われていた。だが、視線を感じ取ったのかこちらに気づいて手を振ってくれた。
『健闘を、祈ります』
親切な人だな、と思った。縮こまって生きている世界に、不意に現れる善良な人は、固くなった心を緩めてくれる気がする。
なにはともあれゼミ決定だ。しかも人が少ないどころかいない。先輩もいない。担当者と二人きり。
希望者数の少ないゼミは、たいがい担当する教授らが自分の研究で忙しくて相手にしてもらえないか、偏屈だったり付き合いにくいといったことが多い。
希望したゼミの担当者は、噂はなかった。だが、アカデミーで教鞭をとる教授ではないにしろ研究室を持っている著名な人物であるにも関わらず研究する対象と行動ゆえに忌避されているとの噂だった。
魔法研究家。魔法そのものを研究し、探求する者。行動は奇抜で奇怪、ときおり研究室から奇声が聞こえる。
そして、魔法が使えない。
魔法を学ぶアカデミーで、そんな人物に教えを乞うものはいないと思ったが、当たりだったようだ。もしかしたら逆に多い可能性も考えていたが杞憂だったようだ。
良かった。これで平穏な学生生活を送ることができる。
静かに、目立たず(変な人が担当するゼミ生としては有名になるかもしれないが一時のことだ)、このまま過ごしていきたい。
ささやかな願いを胸に、指示された研究室のドアを開くと、ぼふん、と謎の爆発音と共に灰色の煙に視界を覆われた。
「いかん! ドアを閉めたまえ!」
慌てた声につられるようにして部屋に飛び込み、内側からドアを閉める。
「よしよし、外気を遮断すればとりあえず大丈夫」
部屋の奥から響いた声にすみません、と返すと驚いたような声があがった。
「んん!? 誰か入ってきたのかね? この研究室に人が来るなんて珍しい」
好奇心に満ちた声と弾むような足取りで近づいてきたのは、白髪に金色の目をした男性だった。ただし、見目が麗しすぎる、と頭につく類の。
そんなきらきらしい容姿の男性が近づいてきて、こちらの存在に気付くとぴたりと足を止めた。一歩半ほどを挟んで対面に立った彼は、上から下、下から上と何度も目線が動いてこちらを見てくる。
「あの、ご連絡があったと思いますが」
「連絡?」
「はい。このたび魔法研究のゼミを希望した、」
名乗ろうとすると、とんでもない速度で近づいてきて両手を握られた。細くてひんやりした指が、がっちりつかんで上下に手を揺さぶる。
「なんと! ワシのゼミにとうとう希望者が! なんたる僥倖、なんたる日か! 今日は祝いだ!!!」
ものすごく喜ばれているのがわかったので、正直嬉しい。偏屈だと聞いていたので門前払いもありうるかと思っていただけに、少しほっとした。
しかし、この驚きようは、連絡が届いていないのだろうか。
「ふむ、魔法を研究したいとな。素晴らしい。その目! 真っ赤に熟れたトマトのようじゃないか! 素晴らしい。その目と髪から察するに、植物、いや花に関する魔法を得意としておるな。これはちょうどいい!」
「……わかるんですか?」
普通は、人の得意な魔法を見抜くことなどできない。髪の色や瞳の色に若干の要素を宿す場合もあるが、大きくカテゴライズを絞ることができるくらいで、ここまでぴたりと当てることはそうそうできない。
驚きとともに尋ねると、うむ! とふんぞり返って答えられた。
「ワシは魔法が使えんが、魔法が大好きでの。魔法を感じるのは得意になったんじゃ。おかげでこう、うっすらとではあるが魔法線が見えることもある!」
道具を使ってだがね、と机の上に置かれた不思議な眼鏡を手に取り自慢げな様子に、しばらく固まってしまった。
沈黙が続いたことに若干の気まずさを覚えた頃、まったく気にかけた様子もなくゼミ担当者―「先生と呼んでくれ」と言われたので先生―は、こっちに来いと早速指示をしてきた。
「このな、フラスコの中の苔に魔法を使ってくれんかの?」
示されたのはいくつか並べられたフラスコで、中にはそれぞれ小さな苔が埋め込まれていた。
「種は仕込んだし、湿度と温度は管理ばっちりなんじゃが、うまく芽を出してくれんくての」
ぽりぽりと頭をかきながら説明をしてくる先生は、困ってはいるが楽しそうでもある。このフラスコの中で花が咲けば、小さな花の森のようなものができそうだ。
そう伝えると、嬉しそうにうなずかれた。
「そう、そうなんじゃ! フラスコでホムンクルスなんてことも聞くが、そうではなくて、ワシはこの中に小さな『世界』を作ってみたいんじゃ」
「でも、それなら植物の魔法使いにお願いしたほうが」
「なんでじゃ。ここに適任がおるのに」
おずおずと上位とされる魔法の使い手を口にしてみると、先生はきょとんと返してきた。
「ワシはここに花を咲かせたいと思ったんじゃ。だから君が適任じゃ。そのピンクの髪に赤い目は、花に好かれている者が持つという色。良い縁があったものじゃ」
からからと笑ってフラスコを差し出して、抱えられるだけ抱えさせた先生は、「ようこそ、これからよろしく」と手を差し出した。
フラスコを抱えていたので握手は無理だったが、まっすぐに、なんの偏見もなく自分を受け入れて、必要としてくれる存在がまぶしくて、頭を下げた。
そうだ、私は受け入れてほしかったんだ。
変な色の目や髪じゃなくて、役に立たないような魔法じゃなくて、私という存在が何ができるか、それを知りたかったんだ。
それを示してくれた先生のそばで頑張ろう、この世界を少しくらいは好きになって愛してもいいかもしれない、と思えた出来事だった。
結局、アカデミーでの生活は終わらなかった。卒業した後も、就職活動においてはピンクの髪と赤い目で不利であることはわかっていたし、消去法で選んだ魔法研究ゼミが案外と自分の思考や嗜好にあっていた上に奥深くて、のめりこんだのだ。
結果としてゼミ生からそのまま助手となり、数年の時を経て晴れて研究員として所属することとなった。
「同輩よ」
先生は、いつの間にか自分のことを隣に並び立つ存在として「同輩」と呼ぶようになった。恐れ多くてこそばゆかったが、否定しても変えてはくれなかったのであきらめて受け入れている。
「はぁい、なんでしょうかぁ。今日ばかりは徹夜は勘弁したいところですがねぇ」
つい昨日、共同研究が終わったばかりだ。改めて確認は必要だが、論文にまとめる前に少し仮眠が欲しい。
それは先生も同様なのか、うん、とうなずいたあと、にっこり笑って朗報だ、と告げた。
「我が研究室に、新たな助手が来そうだ!」
両手を広げてくるくる回りだした先生を眺めて、良かったですねぇ、と笑った。
新しい助手、どれくらいもつかなぁ。
自分以外にこの研究室で持ちこたえた助手という人材は皆無だったし、新たなゼミ生もとんと見たことがない。先生は基本的に人が好きだからいつでも来客歓迎だが、相手方がそうではない。
まぁ、どうにでもなるでしょ。それにしても、私以外の人事関係の連絡は、ぜーんぶ先生のところにちゃんと入るの、不思議だなぁ。
へろへろと机に突っ伏しながら、赤い目でひとつまばたきして。
「せんせぇ、今日はトマトのたっぷり入ったパスタが食べたいですねぇ」
などと提案してみた。それはいいな! とテンションの高い返事を聞きながら、少しの仮眠をむさぼることに集中することにした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
