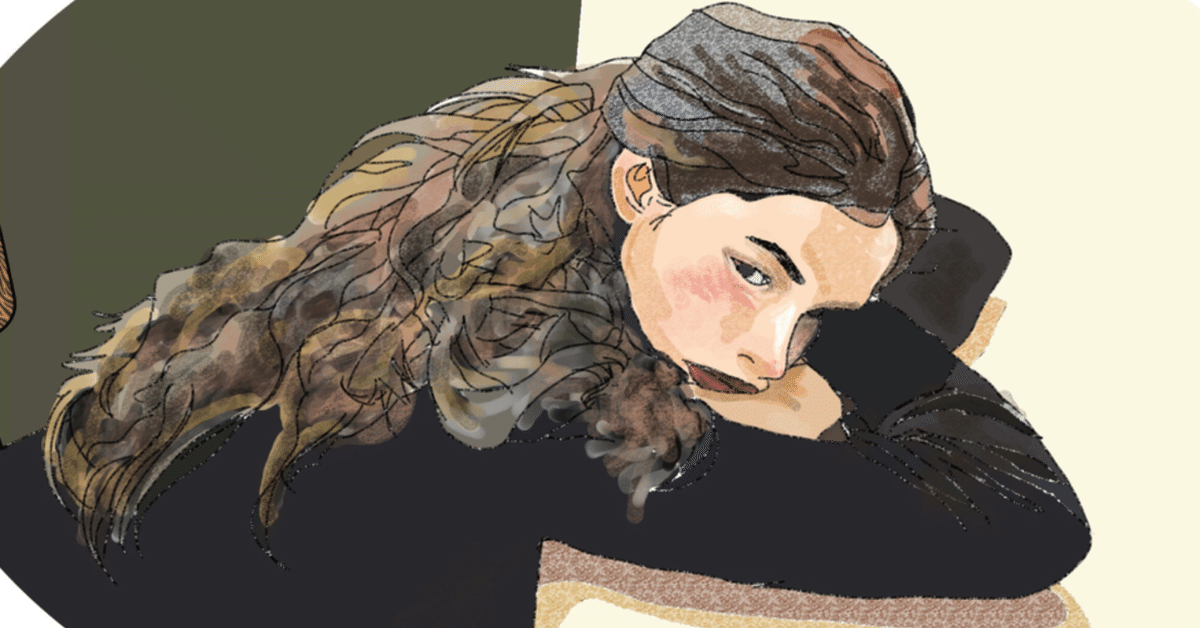
『奇跡の自転車』 ロン・マクラーティ
中年デブッチョの「ぼく」ことスミシー・アイド。
スミシーにはべサニーという美しい姉がいたが、ベサニーは精神を病み、長い間行方不明になっていた。
姉から「フック」という愛称で呼ばれていた少年時代のスミシーは、痩せて、川釣りと自転車を愛し、いつも走っていた。だが今の彼は、だらけた生活を送る巨漢の独身43歳だ。
ぼくは、誰にでも、どんなことにでも勝手に反応してはねかえってしまうビリヤードのボールだった。だから少年としてのぼくの人生が、はっきりした計画だとか、論理的な行動パターンといったものをかねそなえていなかったとしても、それが、ぼくという人間のこの世界におけるありかただった。そうやってぼくは、大きな全体の一部分でいられた。でも今は何も起きない。ぼくはもうビリヤード台の上にはいない。傷ついたり、べサニーのことがあったりしたからじゃない。テレビやプレッツェルのほうが快適だということを発見したからだ。テレビのスイッチを入れ、ラガーですっきりし、煙草でゆったりする。物事を考える必要なんて、あるわけがない。
そんなスミシーは、ある日突然、両親を事故で失ってしまう。
葬儀の後、スミシーは両親宛の郵便物の中から、姉の死亡通知書を発見する。さらに、ガレージで少年時代の愛車(自転車)を発見した彼は、無我夢中のまま自転車にまたがり、こぎはじめる。
出発点は東海岸ロード・アイランド州のイースト・プロビデンス。目的地は、姉の遺体が保管されているというカリフォルニア州ロサンジェルス。中年デブッチョの、アメリカ横断の旅が始まる。
スミシーは旅を続けながら折々に、昔あったこと、家族の過去の様々なシーンを思い出す。
スミシーの自転車の旅と家族の物語が、小説の2つの基軸になっていて、特にベサニーを巡る回想は読ませどころだ。
誰かをあまりに愛しすぎると、傷ついているときのその人の姿が忘れられなくなってしまう。
愛する家族が壊れていき、それを止める手段が分からないというのはどれほど苦しいことだろう。
畑の中で痛々しく正気を失っているベサニーを家族で保護して連れ帰る場面はあまりにも悲しく、心が締め付けられる。
その夜ぼくは早くにベッド入った。母さんがべサニーの部屋で姉のかたわらに座り、ロッキン・チェアをきしませているのが聞こえた。母さんは「イン・ダブリンズ・フェア・シティ」を歌っていた。できるかぎりゆっくりと歌っていた。きっと、べサニーの髪をなでながら、こんなに愛おしい娘が見知らぬ他人になってしまったように思えるのはなぜなのだろうと考えていたにちがいない。
しかし、そんな悲しさ苦しさを書いていながらも、この小説のトーンは明るい。
理由の一つには、スミシーの回想の内容があるだろう。
ベサニーが心を病むことになった原因などについて彼は語らない。そして、家族の苦しみについても、そればかりを語るわけではない。
むしろ語られるのは、苦しみを抱えつつも、家族同士慈しみ合って生きる自分達の姿である。
ウスターソースが大好きな母、野球が大好きな父、きれいでセンスの良い姉、優しい弟。
スミシーの記憶の中の家族の時間は、悲しかった時を除けば、いつでも楽しく愛情に満ちているのである。
(だからこそ、引用したような悲痛なシーンが胸をえぐるのであるが)
そして、もう一つ、この小説を明るいものにしているのは、主人公スミシーの人物像だ。
基本的に受け身で覇気のない彼は、しかし覇気がないのと同じくらい悪気というものもない。
一人で過ごす夜にはビールを飲みながら女性のおっぱいを夢想したり、犬がいたらいいなあと考えたりと、基本的に彼の思考は毒にも薬にもならない。
人と話せば、なんとなく相手に合わせた応答をしてしまい、何か勧められればなんとなく受け入れる。
店に目当てのクッキーがなく持ち金で買えるバナナを買ってみると、「もう何年も何年も、バナナなんて食べたことがなかった」と言いつつ、「食べやすくて、おなかにたまる」となんだか気に入り、以後バナナ、リンゴ、オレンジと、果物中心の食生活に移行する。
読書習慣ゼロにも関わらずなんとなく買った本を読み出せば、「あまりにおもしろくて、読みおえるのがもったいないくらい」と、すっかりはまってしまう。
流れに抵抗しない、きれいに言うならしなやかな性格なのだ。
そして思考も言動も柔らかく優しいので、読者はどんどん彼を好きになる。
そして、そんなスミシーに旅上でふりかかる災難の数々。それらの展開がコミカルで、不運でかわいそうなのに思わず笑ってしまう。
シリアスとファニーの絶妙な掛け合いが飽きさせない。
旅は続き、毎日の自転車漕ぎと果物中心の食生活で、スミシーの体は、以前のスリムな体型へと変わって行く。
そして、突発事故や紆余曲折はありつつも、様々な出会い、そして幼馴染のノーマとの電話でのつながりを通して、スミシーはゆっくりと、明るい未来への道を見つけていく。
そんな彼と共に旅をした読者の心も、いつしか静かな感動で満たされていることだろう。
あたし、あんたのこと、愛してるの、フック。世界中の何より愛してる。頭がおかしいときだって、あんたのことは大切に思ってるし、あんたにいいことが起きますようにって願ってる。あたしを捜してくれたときのこと、覚えてる?給水塔の下で見つけてくれたこと、あったでしょ?あたしを自転車に乗せてくれて、自分はならんで走ってたよね。あたし、だから、怖いの。あんたが走るのをやめちゃうんじゃないかって。やめてほしくないのよ。あんたにはランナーでいてほしいの。走ることを覚えててほしいの。
一度読まれることをおすすめしたい、素晴らしい作品である。
