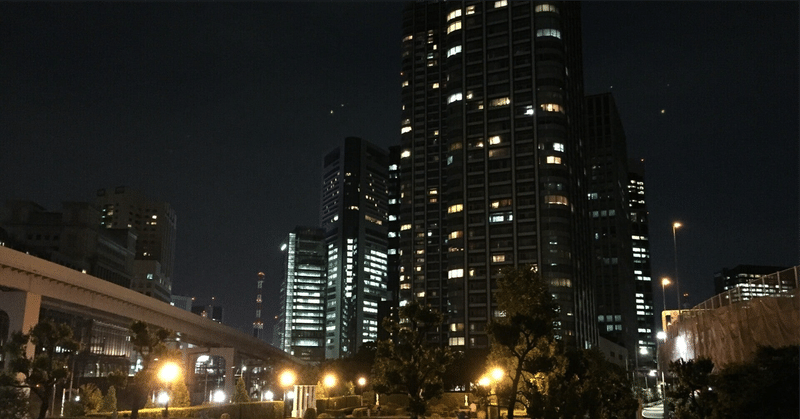
パスはどこに出すべきなのか
こんばんは。
最近は新しい学年の選手が続々と合流する時期になっています。
一人一人「何ができて何ができないのか」を確かめながら、3年後にはプロのピッチに立たせるために自分はどんな手伝いができるのか考える機会も自然と増えています。
将来を考える楽しみもありながら、大体は焦る事が多いです。意外と出来ない事が多く、大抵は基礎基本から徹底してやり直します。
まず、今回は題名にもあるように
パスを出す場所
を考えていきたいと思います。あらかじめ断っておきますが、僕の考えが必ず正しいという訳ではありませんし、僕自身も将来は違う事を言っている可能性があります。ただ、2024年3月時点では「これだろう」と思う事を書いていきます。
まず結論から言うと、
①味方 ②スペース
この2つに分けられると考えています。
最近、新入生のみで練習を行う際に必ず入れるメニューがあって、それは2vs1( 8m×8m の正方形)です。
この時に意識欲しい事はいくつかありますが、受け手と出し手に分けて見ていきます。
まず、出し手(ボール保持者)について。
1つ目はボールを失わない事。
これはほとんどの指導者の方が仰ると思いますが、「ボールを失う=攻撃から守備になる」ので、まず守備をしないためにボールを保持する事が求められます。
2つ目は相手に触られない事。
ボールを失わずにキープできたと仮定した時に、次に意識して欲しいことは相手に触られずにプレーをする事です。なぜなら、「触られる=押されて体のバランスが崩れてボールを失う可能性があるからです。僕はよく「間合い」と言う言葉を使います。守備の選手が全力で足を出しても届かない位置に立っていればタッチミスは減ります。また、触られなくても自分の間合いには入られない。例を挙げるとパーソナルスペースの確保に近いイメージだと思います。人と自分の距離が近すぎると何をされたわけではないのに、何か嫌な雰囲気を感じることはないでしょうか。それと同じで自分のパーソナルスペースは確保しながらプレーする事が必要です。奪われない距離が取れているのであれば、パスをしてもドリブルをしてもいいと伝えています。本当は寄せられる前にパスを選択して欲しいですが、自分1人でボールを守らないといけないシーンは出てくるので、今のところは特に伝える事はしていないです。
もし狭くて難しければ、選手の能力に応じて10m×10mでも問題ないと思います。
3つ目はパスコースを創る事。
相手に触られない(=スペースを確保しながらプレーする)事を意識した後は味方とのパスコースを生み出すことです。特に+1のポゼッションはいくら味方がうまく動いてもパスコースを消されてしまう可能性があります。なので、受け手はボールを少しズラしてパスをするなど、自分で何とかする力を持たなければなりません。仮にパスの移動中に相手がアプローチを強くした時は1stタッチで動かす、逆を取ることが必要になってきます。この3つ目は特にDFラインやFWが苦手としている事が多いので、積極的な声かけをするように僕も心がけています。
4つ目は判断を変える事。
1回パスコースを作ったが、相手DFが足を出してパスカットされそうな時はその行動(この練習ではパスをする事、試合の他の場面ではシュートを打つなど)をキャンセルしてもう一度新しいパスコースを生み出さないといけません。これを伝えるのが非常に難しい。
個人的に面白いなと思っている事は「最初の頑張っている時よりも、中盤〜最後にかけてのヘロヘロになって疲れている時にこのキャンセルの現象が起きやすい」傾向にある事です。
もちろん守備も疲れているので、ボールの移動中のアプローチで寄せきれない事もありますが、個人的な推測としては「ボール保持者の力が抜けている事」に1つ要因があると感じています。
メニューを開始して1-3セット目まではボール保持側も元気があり、それが返って動きの固さに繋がっている気がします。イメージとしては闘牛のように興奮している状況に近いです。「やってやろう!」と言う気持ちは存分に伝わりますが、その分力が入っているので、キャンセルできない事が散見されます。
実際に動画を撮影した時、僕のコーチングも「キャンセル持っとくよ」「相手を見て判断変えるよ」と言う趣旨の言葉が多かったです。
それが時間が経つにつれて「よく相手見て判断変えたね」「ナイスキャンセル」と言う趣旨の言葉が増えていました。
これが初めての練習であれば、時間が経つにつれて選手の頭に刷り込まれていると言えます。しかし、この傾向は毎回の練習で見受けられます。今までに10回以上は行っていますが、確実にメニュー終盤の方がキャンセルする回数が増えています。
その理由の2つ目に「楽をしたい」という心理もあるのかなと勝手に考えています。すぐにパスを出すと今度は「自分が受け手に回らないといけない=サポートの動きで7-10mほど動く」というアクションが入ります。
その一方、ボールを持っていればそれが1-2mで済みます。もちろんボールを守る事は必要になってきますが、相手と向かい合ってボールが静止している状況であれば相手が無闇に突っ込んでくるケースは少ないので体の向きやボールの置き所を調整するなど最低限の動きで済みます。
これに関しては自分の中でも結論が出ていないので、もう少し深く考える必要があると思います。「こうなんじゃないか」という物があれば教えていただけますと嬉しいです。
注意点
とりあえず受け手に関しては以上になります。最初にも言ったようにこれが普遍的な正解かは僕自身も分かりませんが、今現在はそうなのではないか、と考えています。
極論ですが、もしかしたら明日には言っている事が変わっているかもしれません。それは決して嘘をついたわけではなく、自分の中での解像度が上がり成長した証なのかなと思います。
まとまりのない文章を書いてしまった気がしますが僕にとっては非常に良い練習なので、1年後や3年後に見返した時に「最初の俺、文章書くのめちゃくちゃ下手やん!」と思えるくらい成長が見えるといいなと思います。
文量が多くなってしまったので、受け手の役割は後日改めてnoteにしようと思います。
それではまた後日!
p.s.来月にはリーグ戦が始まるので、チーム登録や会場確保などの事務作業に追われています。
それに加えて新入生の登録・通学する学校の予定把握も入ってきてダブルパンチです。
良い成長の機会だと思って前向きに頑張ります。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
