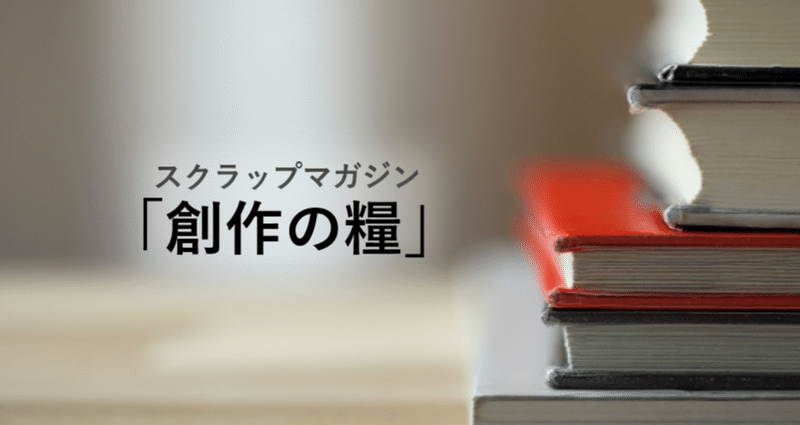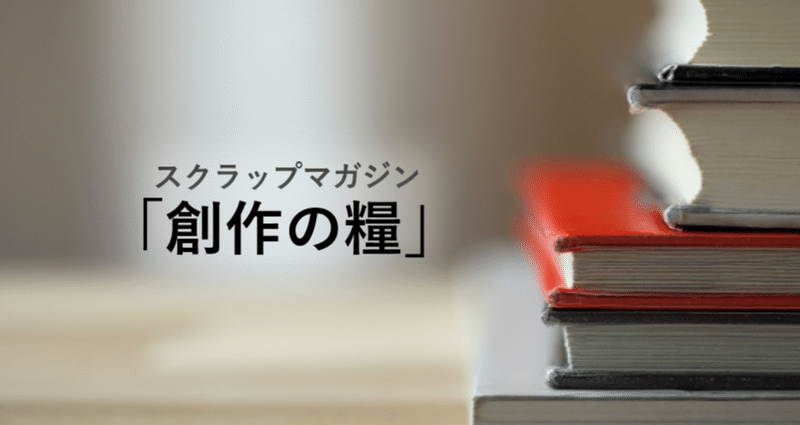金曜日の随筆:江戸時代の三俳人
また運命を動かしていく金曜日がやって来ました。2021年のWK26、水無月の肆です。本日は、俳句の歴史をさらっとなぞった後、江戸時代の三俳人について纏めます。
『俳句』になったのは明治時代『俳句』は、季語の含まれた五・七・五(十七語)の定型詩です。『俳』という字には、「こっけいなこと、おどけ。(小学館デジタル大辞泉)」という意味があり、俳句を読む人は『俳人』と呼ばれます。
『俳句』とは「俳諧の発句」の前後を取った略語で、明治時代に正岡子規(1867/10/14-1902/