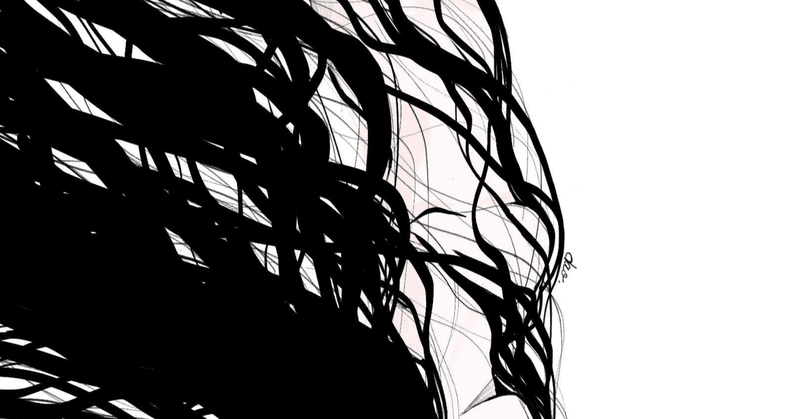
人魚のやってくる渚(SFショートショート)
あらすじ
オカルト雑誌の編集者は、人魚が出たという話を聞いて、その場所に行くが……。
「人魚の画像を手に入れたけど、見てみるか」
まるで小学生のガキみたいな笑顔を浮かべて、同僚の海野(うんの)がビジホに浮かぶホロ画像を俺に見せる。
ちなみに俺と海野が記者を勤める雑誌ってのは、そんな高尚な雑誌じゃない。
扱うネタは心霊写真に座敷童、宇宙人やUFО、ツチノコ、口裂け女、雪男に雪女……そんなあるのかないのかわからない、いかがわしい存在を外連味たっぷりに扱うオカルト雑誌だ。
どうせまたインチキだろうと思いながらホログラムを見た俺は、あまりの事に一瞬言葉を失った。人魚の顔は亡くなった夏美に似ていたのだ。生前は、俺の恋人だった女である。海野は彼女を知らないはずだから、いたずらとは思えない。
そもそもこいつは、仮に知っていたとしても、そんなたちの悪い真似をするような男じゃなかった。
「今度の特集はこれでいこう」
海野は何も知らないらしく、清流のように澄んだ笑顔で宣言した。
「『龍ヶ島(りゅうがしま)で発見された人魚を追え』ってタイトルはどうだ」
どうやら海野は、驚愕に満ちているであろう俺の表情に気づいてないらしい。いや、俺自身が思う程顔には出てないかもしれないが。
「その画像は龍ヶ島で撮影されたのか」
「画像の送り主はそう言ってる。CGじゃなければの話だけどな。ちなみに読者が送ってきた映像だ」
沖縄の近くに浮かぶこの島は、ダイビング中に夏美が事故死した場所だ。今も彼女の父が一人で住む。最初は冗談かと思っていたが、海野は龍ヶ島行きを編集長にかけあって、奴と俺は飛行機で取材に出かけた。
空から見おろす日本は、無残な光景をさらしている。外国の核攻撃を受けたためクレーターだらけになった地面は月面のようだった。日本の撃った核ミサイルも、西の大陸に注がれたので、そっちも似たような光景をさらしているのだが。
5年前勃発した7時間大戦の結果、地球上はどこもこんなだ。20世紀後半米ソの冷戦が終了すると、代わりに世界にふきあれたのがナショナリズムの嵐であった。こいつはまるで、手におえないウィルスのように世界中を覆いつくし、自分達と対立する国家を殲滅するしかないという機運が嵐のごとく地球上に吹き荒れる。
自分達と言語や宗教や肌の色が異なる者は悪であり、殺しても構わないという風潮が増大し、平和を口にする人々は弾圧された。それが21世紀前半の世界であった。21世紀後半になると日本も含め核を持たなかった国も争って保有するようになり、核戦争が勃発したのだ。
最初にどの国が核ミサイルを撃ったのか、今となってはわからない。世界中の都市が消滅し、跡には無残な廃墟が残っただけなのだ。かろうじて生き残った人類は地下都市を作り、放射能で汚染された地上から移住した。
今のように飛行機で東京の地下都市から沖縄に行けるようになったのも復興がかなり進んでからの話である。やがて飛行機は龍ヶ島空港に到着した。ここも日本だが、本土からも沖縄からも離れているので核攻撃を免れていた。
戦争を生きのびた金持ちが移住して、地代や物価が上昇している。防毒マスクや防護服を身につけなくても生活できる、地上では数少ない土地だ。俺と海野も久々に暑苦しい防護服を脱ぎすてて、飛行機から降りた。
俺はTシャツにジーンズというラフな格好。サナギから羽化したセミや蝶なら、きっとこんな気持ちだろうか。全身に、開放感が満ちていた。まるで靴に翼がついて、今にも飛んでけそうな気分である。
俺達はレンタカーを借り、自動運転で人魚が撮影されたという海岸に向かう。やがて視界に青く広がる美しい海が見えてきた。白い砂浜。心地よい潮風。灼熱の太陽、波の囁き……取材に来たというよりも、休暇に訪れた気分である。
放射能はこの島の近辺の海域も汚染したが、新たに開発された放射能除去装置のおかげでかなり無毒化されており、戦争前の綺麗な海を取り戻していた。そこでバッタリ、懐かしい顔に出あう。夏美の父の水川(みずかわ)だ。
「しばらくだな三島(みしま)君。相変わらず都市伝説なんか扱ってる雑誌の記者をやってるのか」
水川の物言いは、以前と同様ざっくばらんだ。もっとも俺を馬鹿にしてるわけではなく、むしろ親しみのこもった声だ。
「ええ、そうです。なんなら定期購読しますか。ナノメディアからダウンロードできますが」
俺の提案に、水川はほろ苦い笑みを浮かべた。彼は典型的な不可知論者で、幽霊は信じてないし、宗教にも無関心だ。
「今さら言ってもしかたないが、君には気の毒だった。娘はせっかく大戦を生きのびたのに、つまらん事故で死んじまって」
水川は、顔を曇らせた。夏美の美しい容貌は父親似で、親父の水川も、ヴァーチャル・シネマの俳優のようなイケメンだ。
「はじめまして、水川さん」
海野が横から割りこんだ。
「僕は三島の同僚で海野です」
「同じ職場の人だったか。これは失礼。君らの仕事を揶揄するような発言をして」
「お気になさらず。慣れてますんで」
海野は一笑に付した。
「実は僕達、この浜辺に人魚が出るという情報を入手して、取材に来ました。もしかしたら何かそんな噂をお聴きしてるかと思いまして」
「人魚なんて、いるわけないだろ」
突然顔を曇らせて、水川が断定した。
「それでは、これを観てください。ナノメディアで、人魚の画像を送ります」
海野は自らの脳に埋めこんだナノメディアから、水川の脳内のナノメディアに画像を送る操作を、腕時計型の端末でした。ナノメディアとは、今や人類のほとんどが、21世紀前半の人達がスマホを持ってたように脳に埋めた、微細なチップだ。
「こんなのCGに決まってる」
送られた画像を確認した水川は、吐き捨てた。
「博士、どことなく夏美さんに似てると思いませんか」
横から俺が質問した。
「バカ言っちゃいかんよ。全く似ても似つかぬ顔だ」
「博士って……水川さん、科学者ですか」
質問したのは海野である。
「海洋生物の研究をしてる」
ぶっきらぼうに博士が答えた。
「大戦で陸地のほとんどは汚染されたが、海の大半は免れた。都市の近海はともかく、遠洋はね。ロケット発射場も大戦で破壊され、宇宙への夢も頓挫した。人類のフロンティアは大海原にあると思う。海底都市を建設し、移住するのも一つの選択肢だと信じてる。生きのびた人類は地上や地下に住んでるが、放射能の影響から完全に免れないだろう。我々は母なる青い大海に、生存の場を求めるべきだ」
*
水川と別れた後、俺と海野は取材を始めた。情報なんて出ないと思ったが、意外にも複数の人達から証言を得た。目撃者の話によると、人魚は午前零時から午前二時の深夜に出没してるらしい。
SNSでも話題になってると、地元のサーファーに聞かされた。実際人魚の画像をアップしたSNSがあった。海野が入手した物程はっきり映っていなかったが。人魚を撮影するため、借りたホテルの一室から浜辺に向けて暗視カメラを設置した。
翌朝動画を確認すると、人魚らしい姿が録画されていた。それは深夜の暗い海から現れたのだ。砂浜に腹ばいになった上半身は明らかに女性で、長い髪を伸ばしており、胸には二つの乳房があった。
下半身の先端には、ひれのような物がついている。午前一時頃現れたそれは、午前二時前に、再び海に姿を消した。画像を一緒に確認した俺達は思わぬ展開に言葉を失う。
相棒はその顔をにかわで固めたように凍りつかせていたが、恐らく俺も似たような表情だろう。まさかこんな画像が撮れるとは、想定の範囲外だった。俺達の取材ってのは、大抵こうだ。
どこどこで幽霊が出たという読者からの脳波通信があれば、そこへ行く。当然ゴーストだの魑魅魍魎に遭遇するとかまずないので、CGで画像をでっちあげ、地元に伝わる怪談を紹介したりして、記事を作成する。それを信じるか信じないかは読者次第。
インチキっちゃインチキだけど、俺は読む者に夢を売ってるつもりであった。ヴァーチャル・シネマやマンガだってフィクションであれば嘘っぱちだが、みんな喜んで読んだり観たりするわけだろう。それと同じだ。
早速俺達は間近で人魚を撮るため、交代で寝ずの番をした。最初は俺だ。ホテルの一室で照明を消したまま望遠レンズと暗視装置つきのカメラを浜辺に向け、人魚が来るのを待ったのだ。
やがて深夜の零時を過ぎ、浜辺に人魚が這うようにして現れた。その顔は、やはり夏美そっくりだ。俺は考えるより先に部屋を飛びだした。手にした懐中電灯で、浜辺の人魚にライトを当てる。
よく見ると上半身は人だが、全身が鱗に覆われ、首の左右にエラがあった。両脚はあったが鱗に覆われ、つま先に大きな水かきがある。
「夏美……お前、夏美だろう」
俺は思わず叫んでいた。人魚の顔は凍土のようにこわばっている。返事はなかった。波音が、静かに時を刻んでいる。背後で砂を踏む足音がした。懐中電灯のライトを当てると、水川博士の姿が浮かんだ。その目には困惑がある。
「やっぱりあれは夏美でしょう」
俺は大声で疑問をぶつけた。人魚というより半魚人のような異形のものを、夏美だと認めたくない気持ちと、そんな姿でも俺の元へ戻ってほしいという思いとが、腹だか胸だか心だか脳だかの奥底でぶつかりあい、せめぎあっている。
全身が極度の興奮と緊張のために、炎のごとく燃えていた。とてもじゃないが、冷めそうにない。世界の終わりがやってくるまで続きそうな灼熱だ。
「あなたがやったんですか。夏美をこんなふうにしたのは」
俺はいつしか両目から熱い涙をほとばしらせ、疑問の声をぶつけていた。こんなガキみたく泣いたのは、ひさかたぶりだ。
「娘を改造したのは私だ」
胸の奥の、そのまた奥からふりしぼるように、ようやく博士が声をだした。
「どうしてこんな……」
「私は夏美を元通り蘇生したかったが、臓器の損傷が激しく現代の医療でも不可能だった。寝たきりで植物人間のように暮らすしかなかったが、両棲人類として復活させるのはぎりぎり可能だったのだ。地上の汚染が進んでるので、むしろよかったかもしれん。各国政府は国民に希望を持たせるため、地上の放射能除去が進んでるような話を喧伝してるが、実際は逆だ。この島も、近い将来放射能の影響で、放棄せねばならんのだ」
水川の言葉は重かった。天の蒼穹をその肩に乗せたアトラスのような表情だ。
「人類は、海に活路を見出すしかない。そのために、断腸の思いで夏美を改造した。君は今の娘に対し違和感を覚えるかもしれないが、あれこそ未来の人類の姿なのだ」
「こんな姿、見られたくなかった」
人魚の夏美が涙を流してつぶやいた。忘れもしない。まるで鈴が鳴るようなその声は、夏美のものだ。
「水川博士、僕も改造してください。夏美と同じように」
俺は思わず言葉を放った。驚愕に、博士が目を見開く。
「三島君、本心から言ってるのか。よく考えたまえ」
「本心です。博士は今の夏美の姿が、人類の未来の容姿だと話したじゃないですか。だったらぼくがほんの少しだけ、明日を先取りしたっていいでしょう」
放射能で汚染され、夏美もいない場所にこれ以上いたくない。俺と夏美は人魚のアダムとイブになるのだ。
「三島君、やめて。あなたまで、こんな姿にならなくていい」
俺は夏美に駆けよった。そして彼女を抱きしめた。鱗に覆われているとはいえ、紛れもなく、この女は夏美である。2度と、離したくはない。いつしか誰もが黙ってしまった。耳には浜辺で波の砕ける音が、聞こえてくるだけだ。そして、夏美の鼓動の音が。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
