
【開催報告】 自治体におけるヘルスケアDXとAPPA
2022年9月30日、GSCA Japan Summit Autumn が東京の虎ノ門で開催されました。自治体、政府、民間、有識者など130名を超えるメンバーが集った本サミットでは、最後に「自治体におけるヘルスケアDXとAPPA」としてヘルスケアの最前線にいるさまざまな立場の有識者が集い、ヘルスケアDXについて自由闊達な議論を交わしました。

ヘルスケアデータ活用に関する課題
冒頭、当センター・ヘルスケアデータ政策プロジェクト長である藤田から、ヘルスケアデータ活用に関する2つの大きな課題について説明がありました。
課題① 進行する少子高齢化への対応や市民の健康増進といった課題の
解決のために、どのようにヘルスケアデータを活用していくか。
ヘルスケアデータの活用では、患者一人ひとりが自身の健康・医療情報を確認できるPHR(Personal Health Record)や、病院間で診療情報等を確認しやすくするEHR(Electronic Health Record)の導入がまず考えられます。ただ実際はヘルスケアデータ活用に関する基本原則等が十分に定められていないために、日本国内だけでなく、国際的にみても、PHR・EHRの成功事例はあまり多くはありません。

こうした現状を踏まえ、私たちヘルスケア・データ政策プロジェクトでは自治体がヘルスケアデータを活用する際の基本原則やチェックリストをまとめたツールキットを公開しています。本セッションにおいても少し言及させていただきました。
課題② どのようにデータの二次利用を推進していくべきか。
データ活用では、基本的にデータ主体である個々人の同意を取りつけることが重要です。しかしながら、データ活用のたびに該当する個人に同意を取りつけることは実際に困難であったり、高齢者であれば本人の同意能力が低下していたりするなど、同意にまつわる問題が多く存在していることも事実です。
他方で、このような同意の問題を背景にして、研究目的やそのほか明示された公益目的のためであれば、必ずしも本人同意をとりつけなくても、データの二次利用を進めていくという潮流もあります。本セッションのタイトルにもあるAPPA(Authorized Public Purpose Access)は、データの二次利用に関するガバナンスモデルです。詳しくは、下の記事をご覧ください。
さて、ヘルスケア分野において、少子高齢化や市民の健康増進のためのヘルスケアデータ活用と、データの二次利用という2つの課題をクリアするためにはどうすればよいでしょうか。
以下の先進事例に注目です。セッションでは少子高齢化や市民の健康増進のためのヘルスケアデータ活用について長崎のEHRシステムである「あじさいネット」を、データの二次利用についてはデジタル田園健康特区にも選出された岡山県吉備中央町の取組みについてご紹介していただきました。
長崎「あじさいネット」の取組み
日本国内でも有数のEHRシステムである長崎県のあじさいネット。2004年から稼働しているEHRシステムで、現在では長崎県民15万5千人のカルテ情報等が登録されています。
あじさいネット理事・長崎大学病院准教授の松本先生は、通常の診療情報の取扱いに関して以下の問題を指摘しています。
・開業医が初診患者の情報に十分にアクセスできないこと
・とくに重症患者やがん患者等の情報が中核病院に集まってしまい、中核
病院以外の病院での診療が難航すること
⇒ カルテ情報が分散
上記の問題は、あじさいネットの成立によって解決に向かいます。まず初診の患者については、過去の診療等によってシステムに収められている情報(病名、手術結果、入院経過等)を、患者同意のうえで参照することで、診断の質が向上しました。患者の正常状態および経過への情報アクセスは無駄な診療を避けるなどのメリットもあったといいます。

あじさいネットは患者情報等を収めているだけでなく、多くの付属システムとも連動しています。患者数が膨大となる感染症や、高齢・離島在住のために気軽に病院に足を運べない患者への対応、仕事で忙しい若い世代の患者への対応としても、あじさいネットのもつネットワークが活用されています。
今後、あじさいネットはEHRシステムの基盤を利用してPHRを展開するほか、臓器移植や認知に関する情報など、よりパーソナルなデータに踏み込んでシステムを構築していくとの展望が共有されました。
デジタル田園健康特区、吉備中央町
デジタル田園健康特区に選ばれた吉備中央町では、データの二次利用も視野に入れたPHRシステムの構築に向けてプロジェクトを始動させています。少子高齢化および人口減少の進行は、既存システムや地域全体の存続性を賭けてその見直しを迫ります。吉備中央町デジタル田園健康特区のアーキテクトである岡山大学病院の牧助教は、できるだけ早く新たなシステムの構築をしておくことが肝要であると強調しました。

吉備中央町の取組みの第一歩として「ウィラバ:We Love Baby」があります。ウィラバは、紙とアプリを併用するハイブリッド母子健康手帳です。母子健康手帳をスマホで写真に撮って取り込むだけで簡単にデジタル化できるので、紙の電子手帳の良さを残しつつ、母子の健康情報がより扱いやすくなったと評価されています。
注目を集める吉備中央町ですが、牧助教は、システム拡大には地域住民や地域企業の協力が不可欠であることを指摘します。地域住民や地域企業からの信用があってこそPHRシステムが成立する、そしてタスクシフトによる行政職員の負担軽減や、PHRをはじめとするシステムのランニングコスト等も考慮すべきことも併せて共有されました。
ウィラバにより生み出されるPHRデータを基盤に、マイナポータルや他の様々な健康管理システムと連結していく展望もあり、今後とも注目されます。
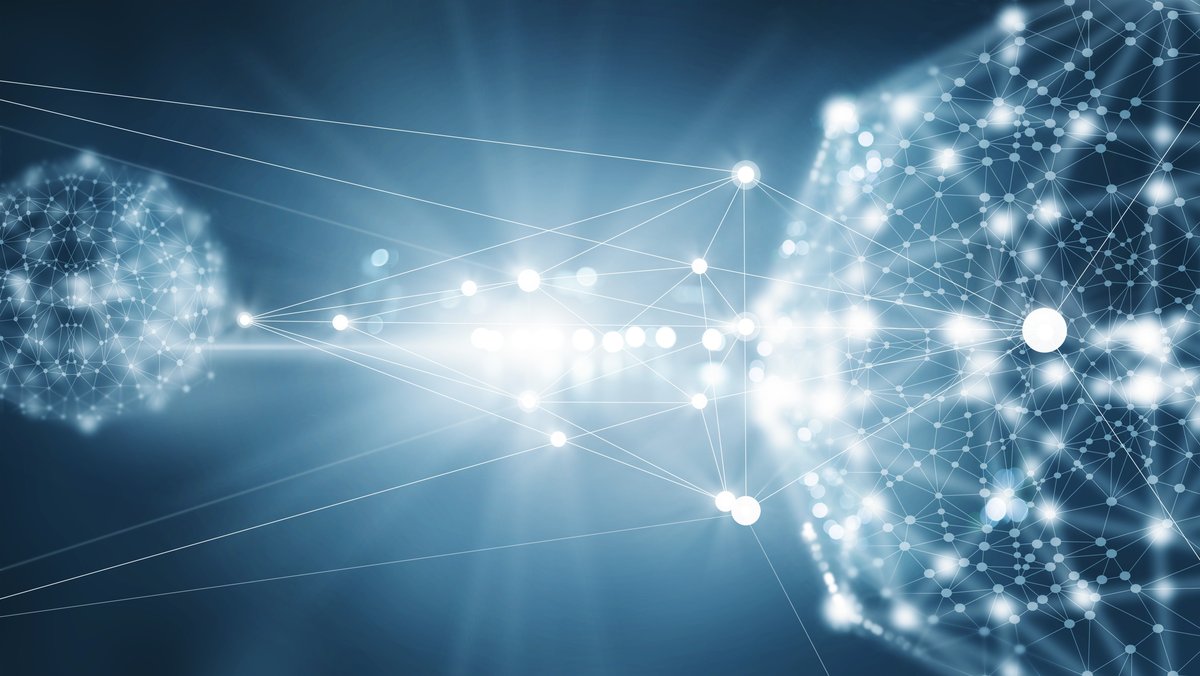
おわりに
本セッションのディスカッションでは、スピーカーおよび参加自治体の間で質疑応答がなされ、自由闊達な議論が交わされました。また海外事例ということで、アメリカ・シカゴ、フランス・ニース、ポルトガル・カスカイスにおけるPHRの取組みが紹介されました。先進的な取組みを参照することは、今後PHRシステム構築を進めるうえでよいメルクマールとなります。
本サミットでは、他にもデジタルマーケットプレイスの動向やスマートシティの実装、モビリティ政策についてもセッションが設けられています。本サミットの他のセッション概要については、以下の記事をご覧ください。
私たちヘルスケア・データ政策プロジェクトでは、自治体におけるヘルスケア領域のデジタルトランスフォーメーションを推進する取り組みに加えて、グローバルでのデジタルヘルスの推進に向けて様々な取り組みを行っています。きたる11月22日には、関連して5th Well Aging Society Summit Asia-Japan(WASS)内でのセッションも企画しております。ぜひそちらもご覧いただけましたら幸いです。
世界経済フォーラム第四次産業革命日本センター
佐々木誠矢(ヘルスケア・データ政策プロジェクト インターン)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
