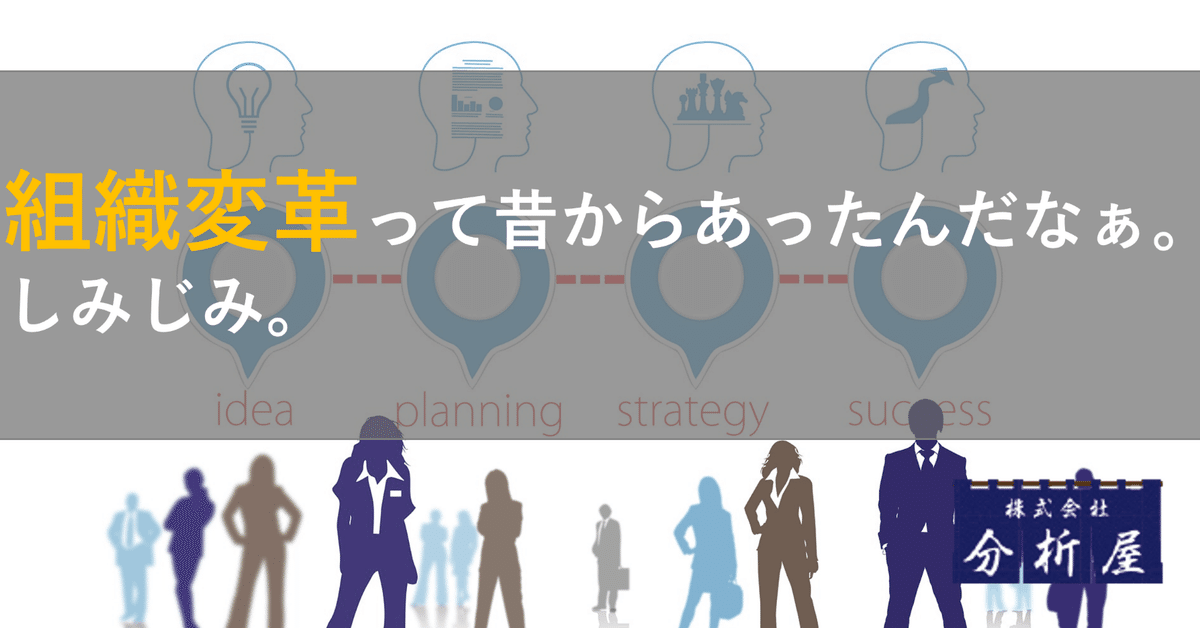
組織変革って昔からあったんだなぁ。しみじみ。
分析屋の下滝です。
DX(デジタルトランスフォーメーション、デジタル変革)の話を見ない日はないくらいですが、組織変革、あるいは、企業変革の話って古くからありそうなんですかね。
分析屋では、読書会を定期的にやっているのですが、読書会で発表しそびれた内容を紹介しようと思います。
紹介する本はジョン・コッターの『企業変革力』です。この本を知ったのは『DX実行戦略』で紹介されていたからです。ちなみに、コッターの新著の翻訳の『CHANGE 組織はなぜ変われないのか』が最近出ました。
『企業変革力』は、原著は1996年に出版で、26年前となります。日本では、1997年出版され、改題・一部改訳したものが2002年に発売されました。手元にあるのは2002年のものとなります。
Windows 95が発売されたのが1995年なのでその時期くらいの本ですね。インターネットもそんなに普及していなかったんじゃないでしょうか。テレホーダイは1995年開始のようです。当時はプログラミングの興味しかありませんでした。VC++、VBは、参考書もなく、何も作れませんでした。PerlとCGIを学んでいた時期です。
昔話はおいておいて、『DX実行戦略』では、組織変革を2軸で整理しています。一方の軸は、変化の程度を、もう一つの軸は、組織のもつれの程度(部門横断など)です。

右上以外は、コッターの『企業変革力』のような本でのアプローチで対応できるというものです。詳しい話は『DX実行戦略』を参照してください。
この記事では、昔話での「(大規模な)変革の取り組み」とは、何を指すのかを見てみます。
『企業変革力』では、次のような取り組みが、変革との取り組みとして紹介されています。
・リエンジニアリング
ビジネスプロセス・リエンジニアリング(BPR)は、1990年代初頭に提唱された経営戦略であり、組織内のワークフローとビジネスプロセスの分析と設計に焦点を当てたものである。BPRは、組織が顧客サービスを向上させ、運用コストを削減し、世界的な競争相手になるために、仕事のやり方を根本的に見直すことを目的としている。
・リストラクチャリング
リストラクチャリングとは、企業経営用語で、企業の収益性を高めるため、あるいは現在のニーズに合わせてより良い組織を作るために、企業の法的、所有的、運営的、その他の構造を再編成する行為のことである。
・品質向上プログラム
・企業合併・買収
・戦略転換
・文化変容
細かなことは、勉強不足なので分かりません。ただ、このような取り組みが企業変革・組織変革と呼ばれるそうです。
リエンジニアリングなんかは、『リエンジニアリング革命』も少し読みましたが(日本では1993年発売)、参考になると思いつつも、この分野はこれまで勉強してこなかったのもあって、今読む方がいいのか? 古い話なんじゃないのか?とも思っちゃいます。
さて、これらの変革の取り組みも、簡単ではなくやり方を間違うと失敗しちゃうよという話が、『企業変革力』の話です(たぶん)。
8つの過ちと8段階の変革プロセス
もう少しだけ『企業変革力』を紹介します。目次は次のようになっています。
第一部 変革に伴う課題とその解決
第1章 企業変革はなぜ失敗するのか
第2章 成功する変革とその原動力
第二部 八段階の変革プロセス
第3章 危機意識を生み出せ
第4章 変革を進めるための連帯
第5章 ビジョンと戦略を作る
第6章 ビジョンを周知徹底する
第7章 従業員の自発を促す
第8章 短期的な成果の重要性
第9章 成果を活かしてさらに変革を進める
第10章 新しい方法と企業文化
第三部 変革の持つ意味
第11章 これからの企業群
第12章 リーダーシップと継続的学習
1章は、「企業変革はなぜ失敗するのか」です。8つの過ちが紹介されています。2章はそれら過ちに対する対策と、リーダーシップに関してです。2部は、各対策の詳細になります。
変革の取り組みでの8つの過ちは、以下のようです。これは、今の企業でも当てはまるのではないでしょうか。
・従業員の現状満足を簡単に容認する
・十分なパワーを備えた変革推進のための連帯のチームを築くことを怠る
・ビジョンの重要性を過小評価する
・従業員にビジョンを十分に伝達しない
・新しいビジョンに立ちはだかる障害の発生を許してしまう
・短期的成果をあげることを怠る
・早急に勝利宣言をする
・変革を企業文化に定着させることを怠る
これらの過ちの結果、どうなってしまうのか。
・新しい戦略が効果的に展開されない
・企業買収によって期待されたシナジー(相乗効果)を生まない
・リエンジニアリングのプロジェクトに長い時間と多大のコストが掛かる
・ダウンサイジングによってもコスト削減が思うように進まない
・品質向上プログラムでも所期の目標が達成されない
こうも書かれています。
・新しい変革を遅らせる。
・不必要な抵抗を生む。
・従業員に長い間不満を抱かせる。
・必要な変革を完全に停止させてしまう結果をまねく。
8つの過ちは、そのまま、8つの段階のプロセスとして対応できるというのが『企業変革力』での話です。
1.従業員の現状満足を簡単に容認する
→ 危機意識を高める
2.十分なパワーを備えた変革推進のための連帯のチームを築くことを怠る
→ 変革推進のための連帯チームを築く
3.ビジョンの重要性を過小評価する
→ ビジョンと戦略を生み出す
4.従業員にビジョンを十分に伝達しない
→ 変革のためのビジョンを周知徹底する
5.新しいビジョンに立ちはだかる障害の発生を許してしまう
→ 従業員の自発を促す
6.短期的成果をあげることを怠る
→ 短期的成果を実現する
7.早急に勝利宣言をする
→ 成果を活かして、さらなる変革を推進する
8.変革を企業文化に定着させることを怠る
→ 新しい方法を企業文化に定着させる
ここでの注意点は、順序をスキップせず、キッチリ守ることのようです。また、各段階でキッチリ成果を築いてから次にすすむのが大切のようです。
過ちの1つ目だけ少し紹介します。
過ちその1「従業員の現状満足を簡単に容認する」
なんとなくの部分的要約です。
・十分な危機感を盛り上げないうちに、変革に突入してはならない。
・現状満足の状態から引きずり出すことは難しい。
・引きずり出されて業績低下になれば、防衛的になってやるきがなくなる。
・これまで、成功してきた経験、目に見える危機が少ない、容易に達成できる目標、企業の外部からのフィードバックのなさ、が満足をうんでいる。
・上司からの変革の話には抵抗する。
ではどうすればいいのか。危機意識を高める方法として9個紹介されています。いくつか紹介します。
・業績上で赤字を出す。マネジャーたちに競合企業に比較して自社の示す弱点を明示する、最終段階で間違いを是正するのではなく途中でその間違いをめいじする、といった手段を通じて危機状況を生み出す。
・ビジネスを通常通りに進めたのではとても達成不可能な売上、利益、生産性、顧客満足、生産期間の目標を設定する。
・人材に対し不満を抱く顧客、満足していない供給企業、怒りをあらわにしている株主に、もっとたびたび接触することを求める。
おわりに
けっこう大変なんじゃないでしょうか。DXとかいってる場合なんでしょうか。DXの方が難易度が高いようにも思えますし。
まず、会社での何らかの取り組みを、「変革」だと認識して取り組むことが少ないように思えます。実際、私も、認識していませんでした。どのレベルからが変革なんでしょうか。単に仕組みづくりとして捉えることが多いです。
ですので、個々の仕組みとしてはしっかり設計するのですが、このような変革の段階・順序があると考えて取り組むことはありませんでした。
試して、検証していきたいですね。難しそうですが、頑張っていきましょう。
株式会社分析屋について
ホームページはこちら。
noteでの会社紹介記事はこちら。
【データ分析で日本を豊かに】
分析屋はシステム分野・ライフサイエンス分野・マーケティング分野の知見を生かし、多種多様な分野の企業様のデータ分析のご支援をさせていただいております。 「あなたの問題解決をする」をモットーに、お客様の抱える課題にあわせた解析・分析手法を用いて、問題解決へのお手伝いをいたします!
【マーケティング】
マーケティング戦略上の目的に向けて、各種のデータ統合及び加工ならびにPDCAサイクル運用全般を支援や高度なデータ分析技術により複雑な課題解決に向けての分析サービスを提供いたします。
【システム】
アプリケーション開発やデータベース構築、WEBサイト構築、運用保守業務などお客様の問題やご要望に沿ってご支援いたします。
【ライフサイエンス】
機械学習や各種アルゴリズムなどの解析アルゴリズム開発サービスを提供いたします。過去には医療系のバイタルデータを扱った解析が主でしたが、今後はそれらで培った経験・技術を工業など他の分野の企業様の問題解決にも役立てていく方針です。
【SES】
SESサービスも行っております。
