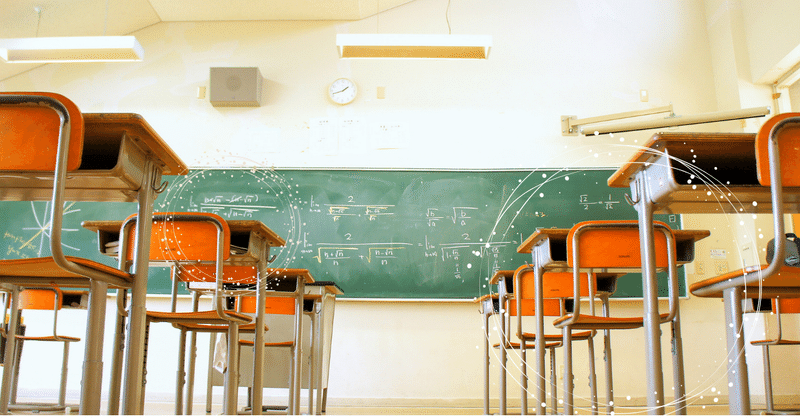
自称進学校在学が教える効率のいい授業の受け方
なぜ学校の授業はわかりにくいのか。
学校の授業を「わかりにくい」と感じる人は多いかもしれない。それは学校の先生は学校の授業をみんなのためにやっているからだ。学校の授業は基本的に下のひとに揃える。下のひとに揃えなければ、その人たちは授業においていかれ、学力が向上しない、最悪留年してしまう可能性がある。学校では一部のみが90%理解できる授業よりも、大多数が50%理解できる授業の方が好まれる。
したがって、その授業が自分にとって受けやすいものなのかどうかは、正直周囲によるのだ。
学校の授業
では、学校の授業をより身になるものにするにはどうすればいいのか。それは自分が授業に介入することだ。つまりいえば、気になることがあればその都度質問し、思いついたことがあれば、その場で提案する。こうすることでみんなのための授業は自分のための授業に変わる。授業に関係する質問は、自分だけでなく周囲のためにもなる。周囲が気づかなかったこと、気になっていたことを聞けば周囲にとっても利益になる。先生にとっても授業を盛り上げる材料にもなる。誰も損しない方法なのだ。
能動と受動
勉強は能動的であればあるほど定着が早い。例えば、自分でひとに説明してみることは能動的な行為だ。他の人に説明するには、そのものに関して詳しく理解していなければならない。そして、自分の中で曖昧にある知識、理解を言語化することで、更なる理解につながる。
りんごとは何かと聞かれて説明できない人間はいないだろう。しかし、それが勉強になったらどうだろうか。「なぜこの問題はこのようにして解くのか」「この公式はどのような場合に使うことができるのか」などといったことを聞かれた場合答えられない場合がほとんどであろう。それは単なる知識不足などではなく単に、言語化ができていないだけだ。べつにその答えを知る必要はなく、それについて考えさえすればそれで十分だ。
授業を受動的に受けることはただ聞いたことを吐き出すだけ、与えられたお小遣いだけでどうにかやりくりしようとするようなことだ。
生徒主導の授業
私のクラスで実際に能動的な学習をしたことがある。それは生徒が授業をすることだ。休み時間、授業中に先生ではなく生徒主導で勉強を周囲に教える。それによって,説明する能力や理解度、考え方など様々なものを得ることができる。
今まで感覚で解いていた問題も、感覚ではなく根拠を持って解けるようになる。
なにより、受動的な授業よりも自分みづから乗り込んでいく能動的な授業の方が圧倒的に楽しく、学になる。
能動的な質問
質問をする=能動的ということではない。というのも、質問の仕方によっては、全く意味のないものになってしまう。
質問をする時に意識して欲しいことがある。
・質問は具体的にする
・理解したらそれを相手に説明し、正しいかどうか確認してもらう
「この問題はなぜこのようにして解くのですか。〇〇ではダメなのですか。」
「ーーーーーーーだからだよ。」
「なるほど。つまり〇〇ということですね。」
といったように、そこで得た理解を実際に使ってみることが大事だ。理解が間違っていたとしてもそこで気づくことができる。自分の中の理解が本当に正しのか、それが周囲に伝わるのかは実際に言葉にしてみないとわからない。
たとえ質問が抽象的なものであったとしても、最終的にそれを理解し言葉にして確認してもらい、己のものにしてしまえばそれでいい。理解を自分の中で留めておくことは実にもったいないことだ。
まとめ
長々と書いたが、結局言いたいことは「自分から授業を受けに行くことが大事」ということだ。それさえ意識すれば授業の見方も、意識も、理解も変わっていくだろう。
学校の先生は基本的に勉強が好きだから、教えるのが好きだから教師をやっている場合がほとんどなので、質問するととても嬉しそうに解説してくれるので、安心して質問しましょう!
最後までご覧いただきありがとうございました。
note以外にもYouTubeにて勉強に関する動画を投稿していますので、興味のある方はぜひご覧ください。
https://youtube.com/channel/UCPDfgs6XwmAjcTlCabyF_hA
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
