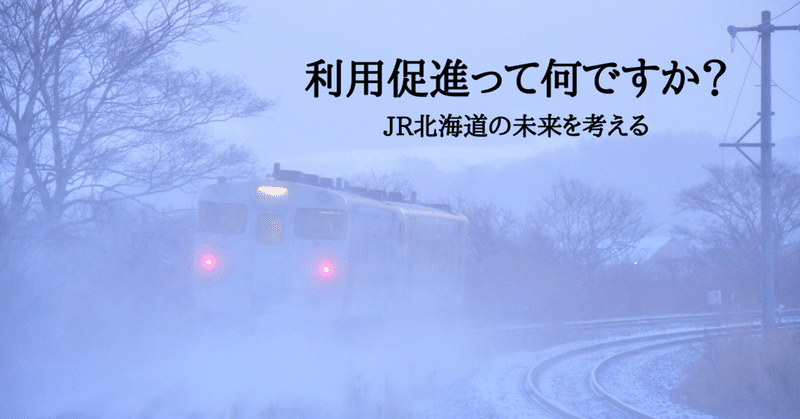
利用促進って何ですか? -JR北海道の未来を考える-
今年度末が期限となっていたJR北海道を支援する国の新しい支援策が見えてきました。JR北海道はこの2年間、年間200億円、計400億円の支援を受けてきましたが、来年度からは3年間で計1,300億円もの巨額の支援を受けることになったのです。年間当たり400億円以上、これまでの倍以上の支援を受けることになります。
1.国の支援内容
北海道新聞の記事によれば、国の支援内容には、青函トンネルの更新費用や資金調達における債務の利子分負担、さらには債務の株式化による資本増強が含まれます。特にJR北海道にとって大きな支出であった青函トンネルの整備費用を国が持ってくれるというのは大きいでしょうし、喫緊の課題であったJR北海道の債務負担の軽減は、同社の経営安定性を高める効果を生みそうです。
当然、今回これほど手厚い支援となったのはコロナの影響があるでしょう。JR北海道はこの1年、過去にないほどの旅客需要の激減に苦しみました。稼ぎ頭といってよかった新千歳空港から札幌へと乗客を運ぶ快速エアポートはこれまでの15分間隔から12分間隔に増発させたところで航空需要が蒸発、頼みの綱のインバウンド観光客も消え失せ、札幌から各地を結ぶ特急列車は軒並み減便を強いられました。そんな厳しい環境下、国として、可能な限りの支援策を今回盛り込んだものと思います。
2.北海道としての支援
ひとまず、JR北海道は、会社としての存続可能性は向こう3年は延命されたといってよいでしょう。
しかし、まだ解決していない問題があります。それは、JRが「単独では維持困難」としている通称8区間のことです。すなわち、宗谷本線名寄-稚内、石北本線全線、釧網本線全線、富良野線全線、根室本線の滝川-富良野と釧路-根室、室蘭本線の苫小牧-岩見沢、そして日高本線の苫小牧-鵡川間です。こちらの赤字総額は年間120億円で、国と地元自治体が同額を折半して支出することとしていますが、北海道庁や地元自治体はこれを拒否。2億円を赤字補填ではなく、あくまで「利用促進」として支出したのみです。国も北海道側と調整が合わないため、2億円を支出しているのみです。今回発表された支援スキームにこちらの増額は盛り込まれていません。
そして、今回の支援内容が明らかになった後、北海道の鈴木知事は以下のように述べています。北海道新聞の記事を引用します。
「コロナ禍で道財政も厳しく、多額の支援は困難。JRに対する国の実効ある支援が不可欠だ」。鈴木直道知事は12日のJRの路線維持問題を話し合う関係者会議で、21年度以降の道の支援について増額は難しいとの認識を示した。合わせて、拠出する支援金は鉄道の利用促進費であり、8区間の赤字補填(ほてん)はできないとの姿勢も重ねて強調した。
コロナの感染で大きな痛手を被っている地方自治体として、なかなか支援額の増額が難しいことはわからないでもありません。しかし、この発言は極めて残念でした。
国は今回、これまで倍以上という手厚い支援策を発表し、JR北海道に対する国の責務を表明しました。しかし北海道庁の考えは、この2年間で何ひとつ変わらなかったのだなと思わずにはいられません。
そして、こうも思います。「鈴木知事、利用促進って何ですか?」
3.利用促進って何ですか?
鈴木知事、いや、前任の高橋知事の時から、北海道庁からは「利用促進」という言葉がよく出てきます。言葉としては大変いい響きの言葉ですね。しかし、具体的な施策、成果は現れているのでしょうか。「利用促進」というからには、JR北海道の乗客が増えていなければおかしい話になります。今年はコロナ禍という極めて特殊な状況となりまして、いわゆる外からの観光客はあまり期待ができませんでしたので、その成果は極めて限定的であったとはいえるでしょう。しかし、何も「利用促進」は外から来る人向けのものだけではありません。鉄道沿線、地元の「利用促進」だって大きな意味があります。ところが、地元の利用が増えたという情報はなかなか入りません。
北海道庁が開設しているホームページに「北海道鉄道活性化協議会」というのがあります。
ところがここに出てくる活性化策の取り組みはきわめてわずかです。私が本稿を執筆している時点で「各地域の取組み内容」にはわずか3つしか掲載がありませんが、フォトコンテストの開催、流氷観光で訪れた客へのステッカー配布、レンタサイクルの支援だけです。ん? 利用促進ですか、これ。
「利用促進の取り組み例」には、例えば出張での公共交通機関利用、通勤での「ノーマイカーデー」の創設による公共交通機関利用などが謳われていますが、そもそも北海道庁や沿線自治体は率先してこれに取り組んでいるのでしょうか。そのようなニュースすら見ないのですが、さすがに自ら立ち上げた協議会で推奨している施策ですから、やってないわけないですよね?
なお、個人的によい取組みだなと思ったのは、今年の夏に北海道の「ぐるっと北海道・公共交通利用促進キャンペーン」の補助金によって創設された「6日間周遊パス」です。
大人気を博して、残念ながら発売から2ヶ月足らずで補助金上限に達して終了してしまいましたが、ちょうど夏休み期間ということもあって、かつコロナが比較的落ち着いていたということもあって利用は好調でした。これこそまさに「利用促進」です。JRを利用する人々に対する直接的な支援。JRの乗客増に貢献する事業です。ただしどの程度増収に貢献したかは、その効果はよくわかりません。
「利用促進」という言葉、実にいい響きです。しかし、北海道庁のホームページや各種報道を見ても、その具体的取組みが見えてくることが非常に少ないのが残念です。今回もまた「利用促進」の費用しか出さないと北海道庁は宣言したわけですが、それならばせめて、その具体的取組みや効果がより見えるような政策を打っていただきたいと思います。
4.JR北海道のこれから
鉄道が存在する意義は、人によっていろいろと変わりますが、鉄道が走っている理由は明らかです。人や貨物を運ぶこと、その移動に伴う対価を受領し経営していくのが鉄道会社です。
それでは、ここで運ぶ「人」とは誰のことでしょうか? 外から来た「観光客」ですか? それもそうでしょう。しかし、まず基本となるのは、内にいる「地元客」です。「地元客」に見離された鉄道会社はゆくゆくは立ち行くことができません。そういう意味では、JR北海道は札幌圏等の一部を除いて残念ながら「地元客」に見離されていると言っても過言ではない状況だと思います。
当然、これにはJR北海道側にも責任があるでしょう。幾度も起こしてきた運行トラブルもそうでしょうし、これまで地元と向き合ってこなかった会社の姿勢も問われるかもしれません。しかし、すべてJR北海道が悪いのでしょうか? 地元自治体は、北海道庁は、何も問題はなかったのでしょうか? JR北海道が、地元路線が廃止されるという意向が示されて反対の意思を示す自治体が多いわけですが、ではそれまで、地元を走る鉄道路線を大事にしてきましたか? 走っていて当たり前と思っていませんでしたか?
「誰かが乗る、だから残せ」ではないのです。「自分が乗りなさい」なのです。「自分は乗らない、金も出さない、だけど鉄道がなくなるのは反対」という論理はもはや通じない世の中になりました。国鉄の分割民営化とはそういうことです。独立独歩で運営し、当然、維持できなくなったら廃止もあり得る。
本来であればJRと地方自治体は協力し、JRは安全な運行はもちろん、利用しやすい時間に列車を走らせるなどの努力をし、地元自治体は利用促進へ向けて、例えば観光客が駅を降りた後に観光地へと向かうバス路線の整備やレンタサイクルの整備、地元客が鉄道を利用しやすいように、例えば公共施設を駅前に造るであるとか、パークアンドライドの推進であるとか、いくらでも知恵を絞ることはできたはずなのです。
しかし地方自治体はその知恵を絞らなかった。その知恵を絞ることができる人材を育てなかった。JR北海道の経営危機が表面化して、残念ながらJR北海道は人員が減り、余裕がなくなり、前向きな施策を考えるよりも、まずは列車運行の継続が第一になってしまった今「利用促進」について明確なビジョンを打ち出せる人材が、JRにも、地方自治体にもいないこと、これが最大の問題であるように思います。
今回、国はJRに対して手厚い支援を表明しました。国としては北海道新幹線札幌開業の2031年までは最低でも面倒を見るでしょう。今後も状況を観ながら2年や3年のスパンで支援策を決めていくことになると思います。
これは対症療法にすぎません。いろいろと識者が進言しているように、全国に無料の高速道路をどんどん建設する国の道路行政と違って「自立運営ありき」の国の鉄道行政に対する抜本的な意識改革も必要でしょう。本当に公共交通を守ろうとするなら「自立運営ありき」では成り立たない状況となっています。しかし、我々は知っています。国には、抜本的な意識転換は難しいということを。政権が代わっても、それが戻っても、官僚機構の権限が強い国に抜本的な政策転換を求めるのは厳しいものといえます。
そうなるとやはり対症療法をどこまで続けられるかの勝負となってきます。今回、国は対症療法に関しては、比較的強めの薬を出しました。あと、それに応えるのはJR北海道、いえ、そこも当然そうでしょうが、彼らには余裕がありません。私は北海道庁を始めとする地方自治体の意識だと思います。地元がJRを本当に必要としているのか、いらないなら「いらない」とはっきりと意思を示すべきでしょうし、「いる」ならいるで、ではどのように利用してもらうのか、真剣に考えを巡らせる必要があるでしょう。延命治療を続けるのか、やめるのか、今こそ地元自治体の意識の改革が必要だと思います。
コロナが落ち着いたら、GoToキャンペーンをやるか否かに関わらず、また北海道を訪れたいと思います。その時に、どうか、沿線に住む人々が、笑顔で列車を見送ってくれることを願っています。
(トップ写真は筆者撮影。室蘭本線・長和-有珠にて)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
