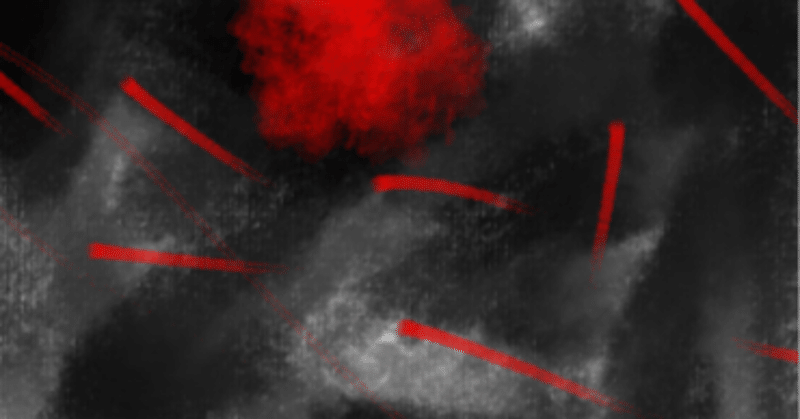
道化の手紙 <後悔Ⅰ>
俺の生きていたところは夢であり、美であり、愉しみであった。大凡この世の者の享受できる幸福の極地を俺は知っていたし、それが他人様の他愛もない手付きによって絞殺されるに至るまで、俺の心はすべてを黙して受け入れる貪婪なプリズムであった。
寒々しき音立てるプレハブの小屋、斜陽の黄金の差し込む時刻、
俺は俺の幸福が他人の手にかけられたのを、幼気な、それでいてまるで穏やかな目つきで眺めていた。
もはや何も望むまい。何を願うでもない。だからひとつだけ、あの幸福の、たとえ似姿だつて構やしない。あれともう一度だけ抱擁させてはくれまいか。もう接吻だつて望みはしない。その吐息に触れられぬでもよい。もう額をひつつけてくれなくたつていい。髪を撫でるでもない。
ただそれを、それだけを望んだ筈だった…
ギトギトした後悔を、俺は俺のうちに飼い続けてきた。
これはのべつ語るべくものではなし、それがこの俺をつくるための伝統とあらば、なおのことだと諦めている。
諦めていた筈だった!
ー伝統
この身をいつたいどれだけのそれが中心を占め、そのどれだけが俺に不法を働かせてきたろうか。
不法というのは冗談にもならぬ冗談だ。
この世の因果律というものの裡にとどまって、逃れられぬがこの人間という者の宿命とあらば、この世に不法というものはない。
俺は伝統という、或いは宿命という、そういうものを畏れている。
そう言っておけば足りる。
「昔を思い出すのは止したがマシだろう。」
それは十分承知なのだが、そうしておらねば満足には生きられぬという事も、俺には十分真実なのだ。
織り込まれた、或いは積み重なっただけの歴史の反物を、俺は俺自身を絞殺するために弄んでいる。
でなけりゃ後悔なぞなんだと一笑に付してしまうがよい。
現在の何にも結びつかぬどのような後悔も記憶も、そんなものはみな戯れに過ぎまい。弄ぶ手付きすら知らぬ白痴に過ぎまい。
あゝ、しかしこの澱みが、人生を弄ぶためだけにあるのだとすれば、
俺はどうにもやりきれない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
