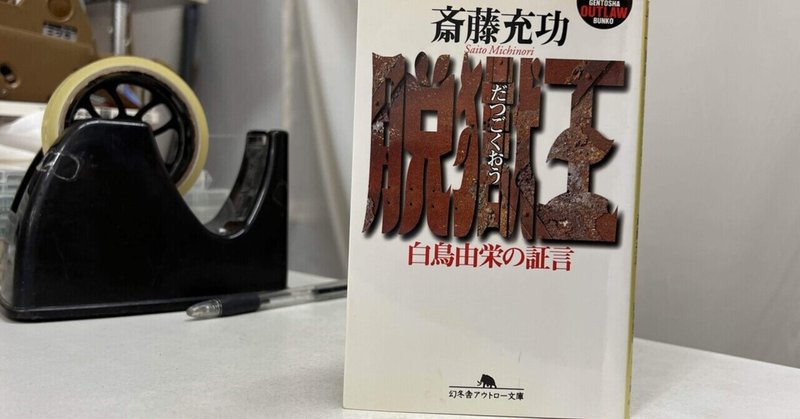
「脱獄王 白鳥由栄の証言」
天気がよい土曜日でした。売上はぼちぼちでしたが、本をお売りくださるお客さんが来てくださったので、古本屋としてはまずまずの一日でした。
そして今日は読書ブログを書いてみたいと思います。読んだ本は「脱獄王 白鳥由栄の証言」というタイトルで、1985年に祥伝社より出版された単行本を、幻冬舎が1999年に文庫化した著作です。
もうすでにお気づきになった方もいらっしゃるかと思いますが、この白鳥由栄(よしえ)という脱獄王は、ゴールデンカムイに登場した白石由竹(よしたけ)のモデルとなった実在の人物です。
実際に脱獄を4回も繰り返し『脱獄王』との異名を持っていたこと、肩関節を外すことができたこと、そして人情に厚いところなどは似ています。しかしその反面、本物の白石由栄と相違する部分もありました。手錠の鉄環をねじ切ってしまう程の怪力の持ち主だったこと、わりと小柄であったこと、そして明晰な頭脳(特に記憶力)の持ち主だったことなどです。
この本の冒頭で、著者が白石由栄に興味を持つきっかけとなった新聞記事が紹介されています。その文章に、店主も同じく興味を持ちました。少しだけ抜粋します。
脱獄の理由がすべて看守たちの冷酷な仕打ちに対する反抗であったといわれる彼の愚純なまでの人間増悪心と優しい言葉で接した巡査の前に静かに縛めについたという彼の二重人格性を…P16
この一文の中で愚鈍という表現を著者は使っていますが、その意味をググると「無知でまぬけなこと」という意味だそうです。昭和初期の日本の監獄に人権という認識が薄かったことは想像に難しくありません。拷問に近い取り調べもあったでしょう。
看守たちの非情ないじめに耐えかねた白鳥がそれを理由に脱走を企てた。しかし優しい巡査や看守の前では従順に罪を償った。ここに脱獄王という称号を得た反骨精神あふれる白鳥と、どこか子供っぽい白鳥の二面性を感じずにはいられません。
また、青森刑務所脱獄後の白石由栄の証言によると宮城刑務所と小菅刑務所は普通の囚人として扱ってくれたものの、秋田刑務所ではひどい扱いを受けたと証言しています。
入れられた部屋は普通の独房ではなくて”鎮静房”といって、昼間でもほとんど日が射さない部屋で、高い天井に薄暗い裸電球が一灯点き、明り窓は天窓が一つだけ。それに、三方の壁は銅板で張られ、扉は食器を出し入れする小窓もない作りになっていた。そんな部屋に手錠をかけられたまま放り込まれ、一冬過ごしたんだ。P49
そして、その惨状を訴えるために脱獄したのだと証言しています。
「俺が逃げたのは青森、秋田、網走、札幌と四回だが、別に私利私欲で脱獄したわけではないんだ。秋田のときは刑務所の酷い扱いと、役人の横暴な態度に腹を立てて、そのことをなんとか役所に直訴したいと思って、そこで、小菅時代に面倒を見てくれた主任さんに会えば俺の話を聞いてくれると考え、主任さんに会うために脱獄したんだ。P52
当時は映画さながらの集団脱獄という方法もあったようです。脱獄することが目的であれば、そういった方法で脱獄する手もあったでしょう。しかし、白石は逃げることが目的ではなく、正義を訴えるための脱獄だと考えていた。ここに賢さと愚かさが入り乱れ、善悪が混沌とした白石という人間の難しさを感じました。
さらに、2度の脱獄を経て収監された網走監獄では、極寒の中で手だけでなく足も拘束され、風呂に入ることもなく過ごしたと証言しています。命の危機を感じた白石は3度目の脱獄を決意しますが、その決行日は彼独自のセンスで決められます。
逃げる日は親切にしてくれた看守が休みの日を狙ってね、その看守さんに迷惑をかけちゃあ気の毒だと思ったからだよ。P84
このように合計4回の脱獄を成功させた白石由栄ですが、最後の府中刑務所では恩赦によって短くなった刑期を全うし社会復帰を果たしています。しかし、体力が衰え闘病生活に入ったところでこの本の著者が取材のために彼の元を訪問し、この本が世に出ることとなりました。
この著者のおかげで、ゴールデンカムイという人気漫画に魅力的な脇役が登場したことは間違いないと思われます。もしかしたら、日本の漫画文化を支えているのは、こういった過去の事件を取材しておおやけに発表しているのオンフィクションライターの功績もあるかもしれません。多くの人に支えられた出版文化、今後も残していきたいですね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
