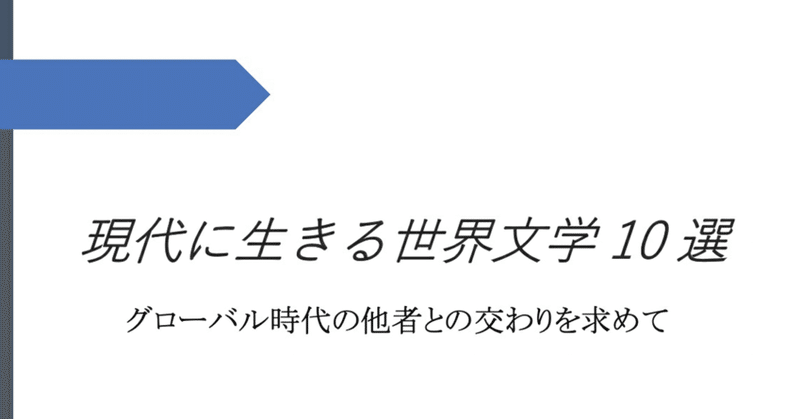
現代に生きる世界文学10選
現代に生きる世界文学10選
グローバル時代の他者との交わりを求めて
著者 津田清延
Kindle Unlimited
はじめに
インスタでフォローさせて頂いているきんぐさんこと、津田さんのKindle本を読んだ。
とても論理的な文章にも関わらず謙虚さとわかりやすさと丁寧さと共に、良書を読む大切さを再実感させられた。
現代における問題に挑むに当たっての叡智を、人間社会の「 不易」 な問題意識を古来より取り扱ってきた文学に求めてみようとする著者の試み
津田清延. 現代に生きる世界文学10選: グローバル時代の他者との交わりを求めて (Kindle の位置No.26-28). Kindle 版.
他者との関係性を通して自己を作り、多様性を大切にすべきことを名著から学び取ることの大切さが述べられている。
挙げられている10選はドストエフスキー、トルストイ、フローベール、スウィフト、カフカ、シェイクスピア、ロレンス、クンデラ、ヘッセらの名著である。
ドストエフスキー…カラマーゾフの兄弟/悪霊
トルストイ…復活
スウィフト…ガリヴァー旅行記
カフカ…審判
フローベール…ボヴァリー夫人
シェイクスピア…リア王
ロレンス...チャタレイ夫人の恋人
クンデラ…存在の耐えられない軽さ
ヘッセ…シッダールタ
感想
全体を通して感じたのは、非常に現代の他者とのつながりの希薄さ、特にコロナ禍で加速しかけていると思うのだが、自と他との分断に対して危機感を抱いているのがよく伝わってきた。とりわけ、ボヴァリー夫人(フローベール)と存在の耐えられない軽さ(クンデラ)で、著者の主張には共感を覚えた。
きんぐさんこと津田氏によるボヴァリー夫人評
太宰とボヴァリズム
また、つい最近、太宰治人間失格を再読後、「太宰治を二十代の我々世代が支持するというのは危機感を覚える」といった類いのことを僕はインスタのストーリーで書いていた。
理由は、行き過ぎた自己愛と虚弱性と、それによる他者を巻き込んでまでの破滅が根底に流れているからだ。自己中心の何者でもなく、すべてにおいて責任放棄し、破滅的な自分に酔いしれていつつも、何かしら他人のせいにしている、まさしく人間失格の主人公、葉蔵。
あたかも、人の弱さを露呈し弱い自分に寄り添ってくれているようである、などと共感する若い世代がいるのは、非常に虚弱な現代社会の姿を垣間見るようでもある。
葉蔵=ボヴァリズムの象徴に僕は見えてくる。
そして、ストーリーにそれを投稿したわけだが、その翌日、本書を開くと、ボヴァリー夫人が挙げられていた。
また、クンデラの存在の耐えられない軽さにおいても、他者との交わりをキーワードに他者との中での自由についてや多様性について触れられていた。
僕はとりわけ、ドストエフスキー「カラマーゾフの兄弟」フローベール「ボヴァリー夫人」クンデラ「存在の耐えられない軽さ」を推したい。
最近の自己啓発書を読むよりよほど多くのことを学べて、何度も再読に耐えられる古典を読むことの価値を本書を読んで再実感した。
おわりに〜サルトルを敬愛する僕
ここからは僕の個人的な思想のような話である。
前述でも述べたとおり、本書の他人との交わりを通して自分自身にフィードバックをかけて自己を磨くというのは、サルトルの他者の「眼差し」を通しての自分というものの存在を自由選択責任を負い選びとって作り上げてゆくこととも言える。
僕なりの考え
自己とは他者を通して自ら作り上げていくもの
僕はサルトルを敬愛している。
人間というのは、全てにおいて自由であり、そのある種の不安とも言えるような自由の中で自ら責任を持って、選択していくことで、己が作り上げられていく。社会に積極的に責任を持って、「主体性」を持って参加し、「他者を通して」自ら作りあげていくものである。
というのが僕のサルトルに対する解釈である。
「人間は、自分の置かれている状況がいかなるのもであるにせよ、そこで自己を存在させるところのものでもあるがゆえに、人間はこの状況を、その逆行率がいかにたえ難いものであっても、それをも含めて全面的に引き受けなければならない」
存在と無の中でサルトルは対自としているが、「人間」そのものであろうと考える。
「それゆえ、わが身を嘆くことを考えるなどは、心得違いも はなはだしい。というのは、外来の何ものも、われわれ が感じるところのもの、われわれが生きるところのもの、 もしくは、われわれがそれであるところのものを決定しはしなかったからである」
ー存在と無 J.P.サルトル
それゆえに、前述でも出した「人間失格」太宰治著のボヴァリズム甚だしい葉蔵のように、ナルシシズムに陥ってしまうのは見当違いであり、そこに同調や、自身に寄り添うと共感することは、ややもすると己の在り方に対して、他者を通してのフィードバックをかけることを放棄してしまった状況とも言えよう。
恥の多い人生でした、と言い切るのは逃げ口上でしかない。
著者の他者との交わりからのフィードバックによって、自己認識を深めていくという主張は、僕の好きな哲学者サルトルの思想「他者の眼差しを通して自己の存在をはじめて認識できる/自由の限界を取り戻す」
というものに通じるものがある。
主体としての他者が存在するという事実からわれわれは逃れることはできない。
主体としての他者の自由を認め、対他存在(他者から見た自分)としての自分自身を如何なる形であれ認めなくてはならない。
これは他者を通して自分自身を自身にフィードバックし、反省もしくは変革のきっかけとなる。
他者の自由を認め、己れの対他存在を引き受けることによって、
「私の自由は、いわばふたたび自己自身の限界を取り返す」
ー存在と無 J.P.サルトル
こうした他者の自由を承認し、自己の自由の制限を取り戻すというプロセスは多様性へも繋がる。
現代はどうであろうか?
主体性を持つこと、思想を持つこと、自分自身で良く考えパッションを持ち、希望を見いだしながら行動すること、
こうしたことをむしろさせないような教育がなされてきていないだろうか?
また、前述のように、多様性を認めるということは、他者の自由を認め、自己の自由の限界を取り戻すということだ。現代の特徴とも言える他人に無関心な超個人主義というのは、いかがなものかと思える。
一見、超個人主義であるような現代社会の日本。
画一的で無個性かつ他人に無関心なスカスカのベニヤ板だけでできた伽藍洞の箱である。
はみ出たものはリカバリー効かない。
しかも、もっと良く見ていくと、日本という国単位ではなく、人間の思想でもなく、得体の知れないGAFAらによって作られたアルゴリズムとマイニングによるトレンドが常識となり、それに簡単に迎合してしまうリスクのある人々。
やがては、常識どころかそれが倫理とさえなってしまいかねない。
虚弱な思想なき人々は一部のビッグデータを扱う企業の駒でしかなく、そうなっていることにすら無自覚である。
サルトル自身、存在と無の前後で希望を持つな、期待をするな、と言ってきた。
それは絶望を招くからだと。
しかし、晩年、彼はこう言い直す。
希望の中で死ぬ。
希望、生きる力、生き抜く力。
これらに関して現代では非常に希薄さを感じるときがある。
画一的ではない、個だけではなく、社会の中での人間として、主体性を持って「生きる力」としての「考え抜く力」と「責任行動」、「情熱」。
これこそが虚弱ではない力強い社会を作る我々の大切な基盤と、僕は考える。
いずれにせよ、己とは他者を通して己で作らねばならない。
「意識は、まったく空虚なものである。何しろ、世界はすべて、意識の外にあるのだから」
ー存在と無 J.P.サルトル
いただいたサポート費用は散文を書く活動費用(本の購入)やビール代にさせていただきます。
