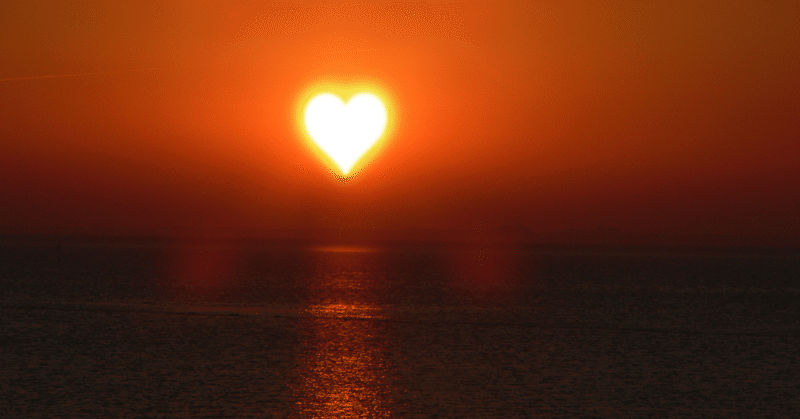
創作の源はあふれ出る感情
仕事を通して消費社会の在り方に徐々に疲弊、枯渇し、同時に我が子からのSOSサインに気づき始めた私は、(過去の記事→サイン) 自分の在り方を軌道修正しなければいけないと思っていた。
子どもの気持ちにしっかりと向き合おうと思い始めていた時、小3になった息子が友達に誘われて、小学校のグラウンドでやっているサッカーサークルに交じって遊ぶようになった。
彼が参加し始めてから1か月ほど経った時、サークルの代表の方から「入会しますか?」と電話があり見学に行った。
そのチームは地域のサークルとして約40年前に生まれ、歴史は古くてかつてはたくさんのメンバーがいたらしいけれど、その後のサッカー文化の広がりに伴い近隣に多くのクラブチームが創設される中、正直ちょっと廃れかけていた。保護者のお茶当番、練習見守り当番、休みの日に試合に連れていく車出し当番があり、入会するには親のサポートが必須だった。忙しい保護者は子どもの付き添いを敬遠するので、お茶当番や見守り当番のないクラブチームが今や人気のようだ。
今思えば、子どもがサッカーを始めようとする時、いろんなクラブチームを見に行って、その中から子どもにあったチームの方針だとか、保護者の都合も考えて入会するチームを選ぶのだろうけど、私はそれまでサッカーの世界というか、スポーツの世界とはかかわりのない世界で生きてきたから、正直何がいいのか全く分からなかった。
ただ息子が楽しそうにボールを追いかける様子を見て、それならばと、その場で廃れそうなそのサークルに入会を申し込んだ。
入会した時にはメンバーは10人。小学生のサッカーの試合は8人制なので(私はこれも知らなかった。)試合のできるほぼぎりぎりの人数だった。そして息子が小5になるときには、上級生の卒業で残されたメンバーは3人になってしまった。別のチームに入会することも考えたけれど、3人がそこに残ってサッカーをしたいというので、子どもたちと保護者サポートメンバーは、まずは8人制の試合ができるように仲間を集めることにした。それぞれに自分のできることで仲間を集めようとしてみた。その後、新メンバーはみるみるうちに増え、2年後の彼等が卒部をする時には42人になっていた。ここにたどり着くまでは様々なドラマがあり、そのことについては別の機会に書くとして、前置きが長くなったが、この経験が私に教えてくれたことを、ここに書きたいと思う。
私は仲間を集める情報発信のために、チームの活動を綴るブログを始めた。練習や試合、ほとんどの活動に付き添いをし、その様子をブログに綴った。そもそもサッカーのことを何も知らないので、専門的なことなんて何も書けなかったのだけど。
楽しそうにボールを追いかける様子
新しい仲間ができて嬉しい様子
うまくプレーできて嬉しい様子
思うようにプレーできなくて悲しい様子
試合に負けて悔しい様子
楽しい、嬉しい、悲しい、悔しい…。活動の中のいろんな感情を私もそばで一緒に味わった。一緒になって笑ったし、喜んだし、泣いた。
そんな時は、書きたいことがあふれ出して止まらない。家に戻ると、すぐにパソコンに向かって、すごい勢いで感情をブログに綴った。
パソコン操作やSNS発信に詳しいわけではなく、ましてやサッカーの専門的なことは分からない私が、2年間ブログを続けられた理由は、そこにあふれ出る感情があったからだと思う。
ちょうど仕事人として、創る、生み出すということができなくなっていた時だった。
創り出すことの源が、あふれ出る感情だということを、子どもたちは思いさせてくれた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
