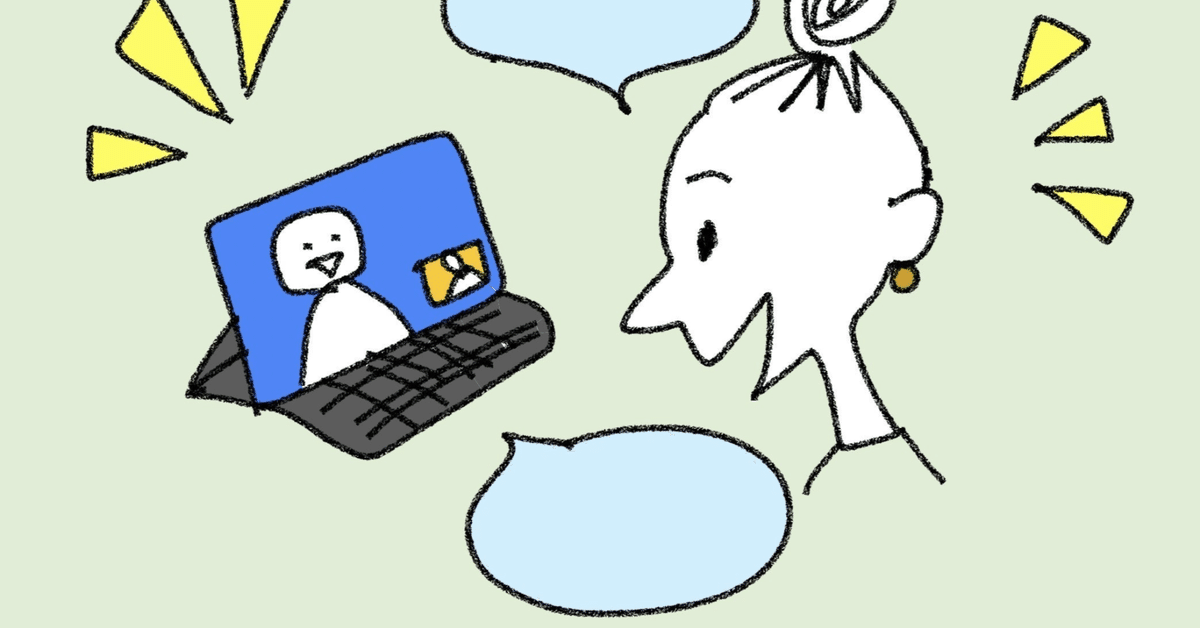
+1読書会 対象図書
もしもオンラインで+1読書会をするとしたら、一緒に読む本はどうしたらいいのだろう…と考えていた。相手に本を贈ってもらう?手に入らない本だったら?とか。
じゃあ、とりあえずは私の持っている本の中で、一緒に読みたいという人がいたら…というのが気楽でいいかも。しかも一人で読み通すのではなく、誰かと一緒に読みたいような本。
というわけで、自分の本棚から対象図書を少しずつ紹介していきたいと思います。
本日はこの2冊。
「ケアの本質」 ミルトン・メイヤロフ ゆみる出版
看護学校で教材として用いられることが多いようですね。おもに課題図書として指定され、読んでレポートを書くという。でも、これ、一冊読み通すのがけっこう骨なんですよね。ケアの現場を知っている人にはピンとくる箇所も学生さんには「何のこっちゃ⁉」な感じがあるし。
でも、すごく名著なんですよ。ケアの本質というだけあって、ケアとは何かということがいろいろな側面から語られていて、私もすごく影響を受けました。
一度、読書会で最後まで読み通したのですが、グループはもちろんのこと、1対1の読書会でも十分読み応えがありそうです。
「プシコナウティカ ーイタリア精神医療の人類学」 松嶋健 世界思想社
これまた骨太な一冊です。イタリアの精神医療改革を下敷きに、著者がフィールドワークを丹念に行った成果を一冊にまとめています。「ひとが病むとはどういうことか」、「社会の中で生きるという時、社会はどのようであるべきか」私も読み通してから、ずいぶん時間が経つのでちょっと記憶が薄れていますが、いま「 」で書いたようなことを思い巡らせながら読んだ記憶があります。また誰かと一緒に読んでみたい一冊です。
一緒に読んでみたい本って、「本が分厚くて読み通すのが大変」というものから「短いけど意味をつかむのが難しい」というもの、「いろいろな解釈ができるから他の意見も聞いてみたい」というもの、「誰かと読後に語り合いたい」というものまで、いろいろありますよね。
たぶんもうちょっとしたら+1読書会の無料モニターを募集すると思うので、ここで紹介された対象図書を使って、読書会に参加してみたいって人がいたら、記事の一番下にある【クリエイターへのお問合せ】からご連絡ください。オンライン(ZOOM)を使う予定です。
とりあえず、医療・福祉・教育・地域のケアの現場で、ケアをおこなっている職種(立場)の方を対象とします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
