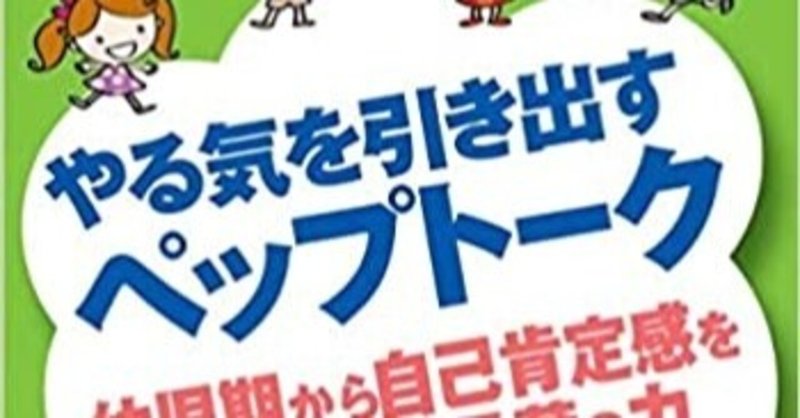
相手の言葉を受け入れる土台づくり
「やる気を引き出すペップトーク」を一気読みしました。イラストや図解が豊富で分かりやすい本です。やる気が出る言葉かけ「ペップトーク」のポイントを幼稚園・保育所での実践をもとに、実例をあげて解説が書かれています。
著者の倉部雄大氏は主に幼稚園・保育所で講演をされています。氏から、実践についてお話しを伺ったことがありますが、子どもたちへの思いと「熱量」・「愛情」の深さを実感しました。
同じく、乾倫子氏は小学校でペップトークの授業を実践されている方で、現在、ペップ・ティーチャー(ペップトーク授業をできる先生)の普及活動をされています。
教育に関わる方には、是非とも手に取っていただき、タイミングが合えば、著者の講演を聴いていただきたいです。
私自身もあちこちでペップトークの講演をさせていただいておりますが、この本のエキスを交えながら講演内容をリニューアルしているところです。
さて、この本の目次にある内容で、長らく教育に携わる者として、どうしても触れておきたいことがあります。
2 言葉を受け入れる土台
( 1 )素直さの原点
(ア)躾の三原則
(イ)立腰
素直さの原点について、次のように書かれています。
伸びる人の特徴を一つに絞れと言われたら、それは「素直さ」の他にはないと感じます。(中略)素直な人は、成長のスピードも速いように感じます。私は、この素直さの原点は幼児期にあると思っています。そして、その素直さを磨く術と言われているのが、国民教育の師父、森信三の考え「躾の三原則」と「立腰」です。
昨今、「躾」と称した言葉の暴力や体罰による虐待が問題になっています。「躾の三原則」は先人の知恵が凝縮された極めてシンプルなものです。
1 挨拶は自分から先にする
2 返事はハイとはっきりする
3 履き物を揃える
かつて、小学校低学年の担任をしていた頃、総幼研の幼稚園を訪問した際に学びました。シングルエイジとよばれる脳が発達する時期には、リズムとテンポのよいインプットが大切であることを知り、「躾の三原則」や詩の暗唱などを、毎朝、子どもたちと唱和しました。落ち着かない状態だったクラスが次第に安定していきました。
ペップトークの威力は絶大ではありますが、スキルだけを使っても、子どもの心には響きません。
まず、本気になって相手に伝える気概をもつことが大切です。根底に子どもへの深い愛情があるかどうかが問われます。
その上で、「素直さを磨く」感性が大切です。
なぜなら、子どもは純粋な存在だからです。
水が砂にしみ通るように、プラスもマイナスも模倣しながら成長していくのです。大人のよくないところもよくみています。適当なことを言っても鋭い直感で見破られます。
教育者として現場に立つなら、この三原則を唱え、自分自身が日々実践し、自らを磨く努力が必要です。
「陽転思考」を唱える和田裕美さんの著書には次のようあります。
「人の話を聞くとき、ちゃんと『聞いてます』というアピールを忘れないこと。前を向いてきちんと座ることです。椅子の背もたれによかかったり、足を組んだりして姿勢を崩してしまう人がいますが、いかにもいいかげんに聞いているという印象を与えてマイナスです。あいづちを打つこと。うなずくこと。相手の目をみること」(『世界No.2セールスウーマンの「売れる営業」に変わる本』p.77)
スタンスは営業も教育も同じです。
まず、自分自身の土台をつくりましょう。自戒の意味をこめて・・・
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
