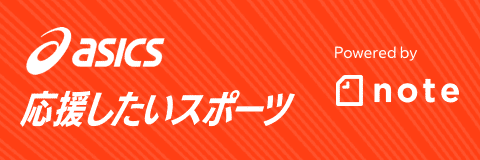僕があの夏に見た涙はどんな色だったか、もう思い出せない
1.
僕は、とても嫌な子供だったと思う。幼少より何となく人より勉強ができ、スポーツも出来た僕にとって、それほどガリ勉をしなくても神奈川県下有数の進学公立高校に入学できたことは、僥倖でもあり、不幸でもあった。自分が如何に「井の中の蛙」であったかを思い知ったからだ。自分より遥かに勉強していなくても、練習をしなくても、出来てしまう人のなんて多いことか。しかも、そういう人であっても、弛まぬ努力を惜しまない人のなんて多いことか。自分がもしかしたら「天才」なんじゃないかと自惚れて努力を惜しんでいた中学生の自分を、タイムマシンで戻っていって、グーでぶん殴ってやりたいと思った。
言うなれば僕の初めての小さな「挫折」だった訳だが、ただの凡人に過ぎなかった自分にがっかりしつつ、硬式テニス部に入部したのは、自分なりに覚悟を持っていた。中学の先輩から、硬式テニス部のハードさは前から聞いており、自分を鍛え直したいと思ったからだ。あるいは、今まで傲慢であった事を恥じ、自分を罰したかったのかも知れない。
確かに、硬式テニス部の練習はハードを極めた。夏であろうが冬であろうが、どの部活動よりも走った(陸上部よりもサッカー部よりも)。走っていて、胃の中のものをリバースするのは当たり前だった。筋トレもウェイトリフティング部よりもやっていた。ボールを打つのは、一日で30分もなかったと思う。オレたちは何部なんだ、と仲間内で笑っていた。
ご存じの方も多いと思うが、プロの硬式テニスの試合になると炎天下に3時間を越える事もままあり、その精神力と持久力、瞬発力は、人間の極限を求められる事になる。もちろん高校の部活程度であれば、そこまで求められることはないが、それでもトーナメント等になれば一日に複数試合することもある訳で、それなりのストイックさを追求する必要はあった。今の世の中にまだ本当の意味のストイックというものが残っているのかは分からないが。
当時の神奈川県硬式テニス事情も少し触れておこう。神奈川県という地域は、何の部活であれ強豪私立高校が幅を利かせており、全国から選りすぐられたスポーツエリート達がひしめき合っている。硬式テニスも多分に漏れず、全国で何連覇もしている私大付属の高校が存在していた。よって、我々公立高校在籍者がどれだけ頑張っても、県大会の上位は彼らで占められる事になる。我々の部活動において、「勝利」は得難いものだった。
それでも僕達は、毎日走り、胃の中身をリバースし、筋トレに励み、ボールを追いかけ続けていた。
2.
サイトウ先輩は、一学年上の女子硬式テニス部の部長だった。ショートボブと眼鏡がよく似合う、カリスマ的なものはないけれど、笑顔と人柄で皆を纏めるタイプの人だったと思う。サイトウ先輩を横浜駅の東口側にある代々木ゼミナールの自習室で初めて見かけたのは、僕が高校二年になった春だった。一瞬目が合い、僕は驚いてすぐに会釈した。サイトウ先輩はニッコリ笑って、すぐに参考書に目を戻した。何故か、胸がドキドキしていた。すぐに笑顔を返せなかった自分に少し腹がたった。
サイトウ先輩と話すようになったのは、その年の梅雨に入る少し前だった。代ゼミから横浜駅に歩いて帰る時に、声を掛けられたのである。
「...○○くん!」
「...あ、サ、サイトウ...先輩...」
「ねぇ、駅まで一緒に帰ろう。いい?」
「...はい」
わずか10分も掛からない駅までの帰路で僕達は少しずつ情報を交換し、少しずつ仲良くなっていった。ユカさん(そう呼べと言われた)は横浜市大の薬学部を目指していること、3人姉妹の長女であること。まあまあ裕福な家庭で育っていること(もちろんユカさんは自分からそんな事は言わない。僕が状況から推察した結果だ)。父親の事は話したがらないこと。早く家を出たいと思っていること。でも、妹達が心配で悩んでいること。
一日のほぼ全てを部活と勉強に費やしている僕の暗い灰色の高校生活にとって、ユカさんと話す10分は、ちょっとした差し色になっていた。
「...ねぇ○○くん。なんでテニス部なんかに入ったの?」
「え?どういう意味ですか?」
「え、だって。練習はハードだし、上下関係は厳しいし。大会で勝てるわけでもないし。私、○○くんみたいな人は、文化系の部活に入るものだと思ってた。」
「どういう意味ですか(笑)」
「はは、ごめん。怒った?たまに自習室で、難しそうな本読んでるし。」
「まさか。怒りませんよ。そうですね...自分に対する罰、みたいなものですかね...」
「罰?」
ユカさんは、考え込むような顔になる。
「罰です。...僕は小さい頃から、我儘に生きてきたと思うんです。世の中の末っ子がそうであるように。僕みたいな人は、基本的には好きなことしかしないし、それで大抵気がつくと周りの人に迷惑をかけていたりするんです。僕は、そういう自分が嫌いなんです。」
「ふむ...」
ユカさんは右手を顎に当て、30秒ほど黙った。
「間違っていたら言ってね?つまり○○くんは、自分の思い通りにならない世の中に出るために、訓練しているのね?世の中は、たぶん不条理に満ちている。そういう世界に負けないように、自分を追い込んで、嫌いな自分を変えようと思って、部活をやっている。」
僕はびっくりした。ユカさんの返答は、僕の想像を越えていたからだ。
「...たぶん、それ、あってます...」
「やった!!」
ユカさんは笑った。僕は眩しそうにその顔を見る。
「説明ヘタですみません。」
「ううん、大丈夫。なるほどね〜...そっかそっか」
僕達はいつものバスロータリーで別れた。
「○○くん、また明日ね。」
「はい、ユカさんお気をつけて。」
僕は、遠ざかっていく揺れるショートボブの髪、揺れる制服のスカートをいつまでも見ていた。
3.
僕がユカさんのことを好きだったのだと気がついたのは、それから10年ほど経ったある日の夕方だった。システムエンジニアの僕は、客先にプログラムを納品し、そのまま車で家に帰る途中、長い信号待ちをしていた。ふと横を見ると、高校生らしき男女が歩いていた。後ろ姿だったが二人共テニスラケットを抱えていた。女の子はショートボブの髪を揺らしていた。
その時、突然ユカさんの事を思い出した。
ユカさんの難しい問題を問いているときの真剣な表情や、友達と話しているときの笑顔やしぐさ、僕の顔を見上げる時の目。サーブを打つ時の、独特のステップ。
僕はそれらの全てを好きだったんだ。
その事に気がつき、呆然としていた。
後ろのバンがクラクションを鳴らした。僕は慌てて車を道の脇に止めた。ハザードを点灯させ、大きく深呼吸を繰り返した。心臓の音が聞こえる。冷たい汗が止まらない。
暫くして、車の窓をノックされた。そこにはまだ若い警察官がいた。僕は窓を開ける。
「どうしたの、顔色悪いよ。」
「...いや、すみません。すぐ出します。」
「本当に大丈夫?すごい汗だけど。救急車呼ぶ?」
「...大丈夫です。ちょっと、幽霊を見ちゃって。」
警察官は、ハハと笑った。
「無理しないでね。気をつけて。ここ駐車禁止だからね。」
「はい、ありがとうございました。」
僕は慎重に車を発進させた。ハンドルを握る手が震えている。ショートボブの子は、もう見えなかった。いや、本当に彼女がそこにいたのかも分からない。本当に幽霊だったのかも知れない。ユカさんだったのかも知れない。
久しぶりに、煙草を吸いたかった。
4.
ユカさんと話をするようになった年の夏休み、硬式テニスの地区大会が行われた。個人戦で出場する選手は何百人となるため、多くの会場に振り分けられる。大抵日にちも会場もバラバラになるため、各々で参加することになる。個人競技の良いところだ。生きるのも死ぬのも、一人。
僕は三ツ沢競技場に振り分けられ、2回戦を勝ち進んだが、3回戦で例の日本一大学附属高校の選手に当たり、順当にストレートで敗退していた。その日は女子の試合もやっていて、ユカさんも出場していた。事前に話していたので知ってはいたが、トーナメント表を見るとなんと4回戦まで勝ち進んでいた。
会場を探し回り、ようやくユカさんを見つけることが出来た。彼女はイヤホンで音楽を聴きながら、目を閉じて集中している。僕は声を掛けていいか躊躇したが、勇気を出して声を掛けた。
「...ユカさん。」
彼女は少しびっくりしながら顔を上げた。
「...!!!○○くん!」
「邪魔してごめんなさい。」
「ううん!大丈夫!...試合、残念だったね。」
「いいえ。あれが精一杯です。全く歯が立ちませんでした。」
ユカさんは少し笑ったが、すぐに不安そうな表情になった。
「...私、怖いの。次の試合の相手、知ってる?」
「...確か去年、全国でベスト4になった人ですよね。」
僕達は、暫く黙って見つめ合った。そして、どちらからともなく、プッと吹き出した。
「ハハハ...なんか笑っちゃうね。私なんかが敵うわけないのにね。」
「...大丈夫ですよ。分かります。」
ユカさんは不思議そうな顔をした。
「1ポイントも取れずに負けるかも知れない。今まで頑張ってきた事が何一つ通用しないかも知れない。でも大丈夫です。僕達は知っています。朝早くからコートの整備をしていたり、部活を辞めようとしていた人の相談に乗っていたり。同じ問題集を擦り切れるほど、5回も繰り返しやっていたり。たまに何にもない所で転んだり。」
じっと真っ直ぐに僕を見ていた。
「最後のは冗談ですけど、ユカさんが今までにどれだけ頑張ってきたか、知っています。どんなにカッコ悪く負けても、僕達は変わりません。僕達の女子硬式テニス部のカッコいい部長です。」
彼女は、唇をキュッと噛んだ。暫くして、彼女は勢いよく立ち上がった。
「よし!それじゃあ、負けてくるか!!後輩!先輩の負けっぷり、しかと見ておけ!」
「はい、先輩、いってらっしゃい。」
ユカさんの顔には、いつもの笑顔が浮かんでいた。
5.
僕達は着替えを終え、その後の試合を見るまでもなく、市営バスで横浜駅まで一緒に帰ることにした。バスが来るまで二人共、無言だった。バスが到着すると、ユカさんと二人がけの席に座った。
「ねぇ。私の高校最後の試合、どうだった?」
ユカさんがうつむいたまま聞く。
「...いきなりサービスブレイクしたので、ドキドキしました。」
「うん。」
「でも、それで相手のスイッチが入ってしまいましたね。」
「...うん。」
「左右に振られても、懸命に粘って。ユカさんのテニスらしいと思いました。」
「そういう事聞いてるんじゃないんだけど。」
僕はやれやれと思った。ユカさんには一生、頭が上がらないんだろうな。
「...とてもカッコよかったです。最後まで試合を投げずに、全力で走って。一所懸命で。相手の選手も本気を出してくれているように見えました。」
「...うん。...ありがと」
とても小さな声で彼女は答えた。
ユカさんの頭が、僕の肩に触れた。二の腕に、顔を押し付けてきた。心臓が爆発するかと思った。音が運転手にも聞こえているんじゃないだろうか。
「こっち向かないでね。」
「...はい。」
僕の二の腕が、制服のワイシャツが濡れていくのを感じた。彼女は声もなく泣いているようだった。横浜駅に着くまで、泣き続けた。何も言えない自分が情けなかった。もしかしたら、何も言わないのが正解だったのかも知れない。それでも、僕はユカさんを笑わせてあげたかった。いつもの、笑顔が見たかった。でも、僕は何も分かっていなかったんだと思う。
駅に着くと、僕達はいつものロータリーで別れた。
「今日はありがとうね。」
彼女の笑顔が眩しかった。目が真っ赤だった。
「...いえ。こちらこそ。」
訳の分からない返事をしてしまった。ユカさんも分かってくれたみたいで、クスッと笑った。
「じゃあ、また自習室でね。」
「はい。また。」
クルッと向こうを向いて、颯爽と歩いていく。ショートボブの髪が、制服のスカートが、揺れていた。
僕はその姿をいつまでも見ていた。彼女の涙で濡れたワイシャツを、逆の手で握りしめながら。
この記事が受賞したコンテスト
お気持ち程度いただければ、私がビアを飲めます。