
【「嗜む」のすすめ】デザインのいきづかいに焦がれ本を嗜む

私達が密かに大切にしているものたち。
確かにあるのに。
指差すことができない。
それらは、目に見えるものばかりではなくて。
それらを、ひとつずつ読み解き。
それらを、丁寧に表わしていく。
そうして出来た言葉の集積を嗜む。
・
・
・
■テキスト
「日本の美意識」(光文社新書)宮元健次(著)

[ 内容 ]
人間は「生」を得た瞬間から「死」という「滅び」に向かって生きている。
そうであるからこそ「生」を尊ぶという考え方が日本の美をつくってきた。
日本の美意識の基層をなし、自然に美を見いだした「優美」。
演技を七分にとどめ、完全に演じ切らないことを説いた世阿弥の「幽玄」。
慢心する秀吉を戒め、侘びることを説いた利休の「侘び」。
旅の途中で寂びつくして命つきることを願った芭蕉の「さび」。
西欧文化の影響が背景にある「きれい」。
そして、二一世紀に世界を席巻する「かわいい」とは-。
日本の美の潮流を俯瞰し、心のふるさとに耳をすます。
[ 目次 ]
序章 旅と他界
第1章 優美
第2章 幽玄
第3章 侘び・さび
第4章 きれい
終章 美意識の近代
[ 問題提起 ]
従前より、日本的なるものに関心が強かった。
偏狭なナショナリズムに陥ることなく、我が祖国、日本の魅力を海外に発信しようとするとき、伝統文化に見いだされる「日本的な美」は、世界に誇れるもののひとつだと、私は思っている。
もっと、この日本的な美を大切にし、そのかけがえのないオリジナリティを自覚し、守り育てていくことが必要だ。
著者の宮元健次さんは、ここでいくつかのキーワードをもとに、日本の伝統文化に表れている「美」の潮流を、俯瞰しようとしている。
「優美」「幽玄」「侘び(わび)」「さび」「きれい」・・・と続く美意識は、一連のものであり、それぞれ独立した概念ではないことがわかる。
時代とともに、日本人のなかに、これらの美意識が育まれ、発展してきたのだと言える。
人間は、この世に「生」を得た瞬間から、「死」に向かう。
だからこそ、「生」を尊ぶという考え方が、日本人の美意識の基底にあるという。
平安末期、この世の無常を嘆き、23歳で出家した西行は、全国各地を遍歴しながら和歌を詠み、旅の途中で世を去った。
その西行を慕って、江戸期には、松尾芭蕉が、旅と草庵での生活に明け暮れる。
「旅に病んで 夢は枯野をかけめぐる」と詠んで、芭蕉は、西行と同様に、旅の途中で客死した。
そして、昭和期に入ってもうひとり、旅に出て草庵に暮らし、旅先で死んだ人がいる。
ドイツの建築家、ブルーノ・タウトである。
芭蕉の『おくのほそ道』松尾芭蕉(著)/ドナルド・キーン(訳)(講談社学術文庫)はタウトの愛読書のひとつであったという。
「英文収録 おくのほそ道」(講談社学術文庫)松尾芭蕉(著)ドナルド・キーン(訳)

[ 結論 ]
第二次大戦前のドイツで、親ソ派としてナチスに睨まれたタウトは、職と地位を奪われて、日本に亡命する。
京都の「桂離宮」に日本的美を見出し絶賛した彼は、約3年半の日本滞在中、高崎市郊外の草庵「洗心亭」に住み、やがて、トルコのイスタンブールに職を得て移住し、そこで死去した。
【関連記事】
【読書メモ】「月と日本建築 桂離宮から月を観る」宮元健次(著)(光文社新書)
https://note.com/bax36410/n/n614b9800783d
彼ら三人の人生に共通して見出されるのは、旅の途中で、命尽きることを、理想の死ととらえていることだ。
そこには、「未完の美」という意識がある。
鎌倉期に『徒然草』(ちくま文庫)を著した兼好法師は「もののあはれ」という概念を示した。
「徒然草」(ちくま学芸文庫)島内裕子(校訂・訳)

「解説 徒然草」(ちくま学芸文庫)橋本武(著)永井文明(イラスト)

【参考記事】
彼が言わんとした仏教の死生観にもとづく無常観は、時間的に限りある美を、いとおしく思う心である。
人の一生は有限であり、そのさなかに出会う「美」もまた、一瞬のものである。
また、能楽の大成者、世阿弥は、「せぬ能」あるいは「せぬひま」ということを、強調している。
完全に演じきってしまうのでなく、身体の動作を七分に控えることによって、そこに、「心」を表現できるというのである。
世阿弥は、これを「無心」でやれと説く。
あえて演じないことによって、そこに漂う情感のことを、「余情」あるいは「余韻」という。
能がめざしているものは、まさに「未完の美」である。
生ある限り、無心で道を究めようとする(旅を続ける)。
そして、その完成形をあえて求めず、そこに表現される「心」を求めよ。
ということなのだろうか。
日本画における「余白」も、この「余情」と同じことだと筆者はいう。
あえて描かないことによって、画面に「心」を表現するということか。
「未完の美」というものを、何となく理解できた気がする。
21世紀に入り、日本のサブカルチャーが、海外で高く評価されていた。
「クール・ジャパン」あるいは「かわいい」が、現代日本発の新たな美意識として、世界中で受け入れられている。
「クール・ジャパン」の「クール」とは、「かっこいい」という意味であり、国内では、「おたく文化」として蔑まされてきた感のあるキャラクターやアニメが、もはや、日本のメインカルチャーを凌ぐほど、高い人気を集めているのは、皆さんも、ご存じのことと思う。
アメリカでも、「kawaii」は、英語の単語となり、「格好いい」という意味合いで、普通に使用されているようだ。
村上隆さんやポケモンやキティによって日本の美意識が輸出され、世界を席巻していったのだが、それにしても、どこか、いびつで、不格好なキャラがウケているのは何故だろう。
「かわいい」という美意識もまた、「未完の美」であるといえる。
宮元氏によれば、この言葉は、本来、未熟なために助けを必要とするか弱いもの、小さくていまにも壊れてしまいそうなもの、純粋無垢ですぐに汚れてしまいそうなものを「守ってあげたい」と感じる愛着を指している。
「未完の美」は、言い換えれば、「滅びの美学」でもある。
「かわいい」もまた、日本の伝統的な潮流の延長線上に位置する美意識であって、「もののあはれ」に通ずる、はかなく、か弱きものを、いとおしいと思う気持ちを表す。
これが、世界で共感を呼んでいるのだ。
[ コメント ]
昔も今も、日本のこの禅的な心持ち(無常観)が、特に、欧米人には、エキゾチックに映っているのかもしれない。
「クール・ジャパン」や「かわいい」の正体は、案外そんなところにありそうだ。
宮崎駿さんのアニメ映画「崖の上のポニョ」は、このあたりを狙ったものに違いない。
■31夜310冊目
2024年4月18日から、適宜、1夜10冊の本を選別して、その本達に肖り、倣うことで、知文(考えや事柄を他に知らせるための書面)を実践するための参考図書として、紹介させて頂きますね(^^)
みなさんにとっても、それぞれが恋い焦がれ、貪り、血肉とした夜があると思います。
どんな夜を持ち込んで、その中から、どんな夜を選んだのか。
そして、私達は、何に、肖り、倣おうととしているのか。
その様な稽古の稽古たる所以となり得る本に出会うことは、とても面白い夜を体験させてくれると、そう考えています。
さてと、今日は、どれを読もうかなんて。
武道や茶道の稽古のように装いを整えて。
振る舞いを変え。
居ずまいから見直して。
好きなことに没入する「読書の稽古」。
稽古の字義は、古に稽えること。
古典に還れという意味ではなくて、「古」そのものに学び、そのプロセスを習熟することを指す。
西平直著「世阿弥の稽古哲学」
自分と向き合う時間に浸る「ヒタ活」(^^)
さて、今宵のお稽古で、嗜む本のお品書きは・・・
【「嗜む」のすすめ】デザインのいきづかいに焦がれ本を嗜む
父の時代・私の時代
堀内誠一

細谷巖のデザインロード69
細谷巖

銀座界隈ドキドキの日々
和田誠
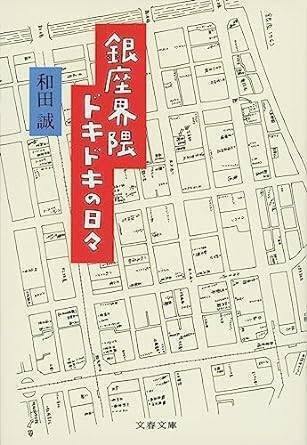
私 デザイン
石岡瑛子

松永真
松永真

陰影論:デザインの背後について
戸田ツトム

ポスターを盗んでください
原研哉

高岡重蔵 活版習作集
高岡重蔵

田中一光の文字とデザイン
田中一光

恩地孝四郎 装本の業

