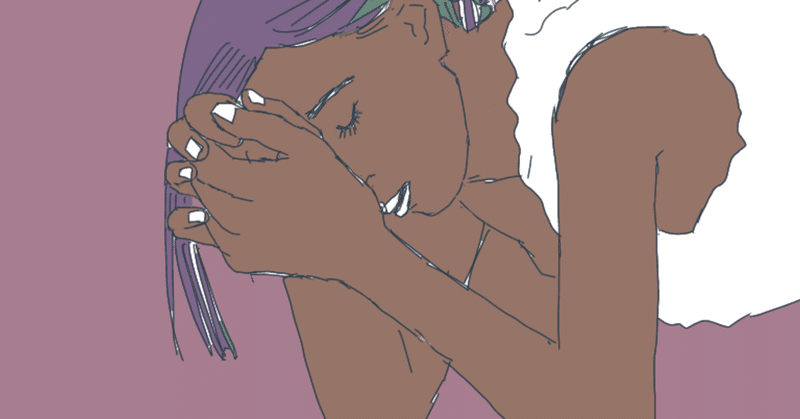
不平等なタレント
韓国のミュージシャン、イ・ランのエッセイを読んでいて、「タレント」と言う言葉の由来を知った。なんでも、今では音楽や芸術の才能だったり、芸能人やテレビタレントを指すようになった「タレント」の語源は、新約聖書に出てくる重さや貨幣の単位であるらしい。
『マタイによる福音書』ではこのタレントで三人の下人の能力を試験する内容が出てくる。主人は旅に出る前に下人たちの能力に応じてそれぞれ金5タレントと2タレントと1タレントを分け与える。しばらくして帰ってきた主人は下人たちが受け取ったタレントをどう使ったかを評価する。初めからたくさんのタレントをもらった下人はそれを二倍に増やしていたが、1タレントを受けとった下人はそれを地面に埋めて置き、そのまま返して大目玉をくらった。(『話し足りなかった日』イ・ラン)
昨日、天国についてのnoteを書いたので、ちょうど聖書が手元にあった。
あらためて読んでみると、ひどい話だ。少ししかもらっていない下人は別に1タレントを横領したりなくしたわけではなく、きっちり返しているにも関わらず、主人には「怠けものの悪いしもべだ」と罵られ、罰を受ける。
そうしてタレントを取り上げられ、その分はタレントを最もたくさん増やした下人に与えられるのだ。
だれでも持っている人は更に与えられて豊かになるが、持っていない人は持っているものまでも取り上げられる。(マタイ 25:14)
そもそもわずかしか与えなかったのは主人だと言うのに、ちょっと横暴すぎないだろうか。
一方では、こういう見方もある。当時の金額としては、たとえ1タレントであったとしても、下人の数十年分の給料に匹敵する大金だった。主人はそれを能力の低い下人にも与え、彼なりに増やす努力をすることを期待していたのだ。
ここで試されているのは主人への信頼、つまり神への忠誠心だ。
神から与えられたものを、他の人(神)を喜ばせるために使うか、保身のために何もせずにいるか。1タレントの下人は自分のことしか考えようとしなかったから、結局何もかも失うことになってしまった。そういう話らしい。
たとえ小さくとも与えられているなら、それを最大限に生かすことが、天国に入る方法なのだ。
だけれど、私たちは自分がすでに大きなものを与えられていることを忘れて、他人を僻んだり羨んだりしてしまう。世の中の基準で美しくなくとも、物を見る目や感じる体があり、話す言葉があり、飢えずに暮らして行けているのに、同じものでもより良いもの、今この社会でより価値の高いタレント(才能)に恵まれている人を目にすると、落ち込まずにはいられない。
かと思えば、美しくて、歌が上手くて、多くのタレントを持っているはずの人が、唐突に命を絶ったりしてしまうこともある。一体、なぜだろう。
与えられたタレントが足りなかったのだろうか。
多すぎてつらくなることがあるのだろうか。
ベストセラー『「死」とは何か イェール大学で23年連続の人気講義』の中では、こんな詩が紹介されていた。
神は泥を作った。
神は寂しくなった。
だから神は泥の一部に、「起き上がれ!」と命じた。
「私の作ったもののいっさいを見よ!」と神は言った。「山、海、空、星を」
そして私は、起き上がってあたりを見回した泥の一部だった。
幸運な私、幸運な泥。
泥の私は起き上がり、神がいかに素晴らし働きをしたかを目にした。
いいぞ、神様!
神様、あなた以外の誰にもこんなことはできなかっただろう!私にはどう見ても無理だった。
あなたと比べれば、私など本当につまらないものだという気がする。
ほんの少しばかりでも自分が重要だと感じるには、どれほど多くの泥が起き上がって周りを見渡しさえしなかったかということを考えるしかない。
私はこんなに多くを得たのであり、ほとんどの泥はろくに何も得なかった。
この栄誉をありがとう!
(『「死」とは何か イェール大学で23年連続の人気講義』シェリー・ケーガン)
生きている、という時点で、私たちには平等に与えられているものがある。そして死ねばまた同じように泥に帰るだけ。
わたしたちは結局、自分たちが作り出した不平等に苦しんでるんだろう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
