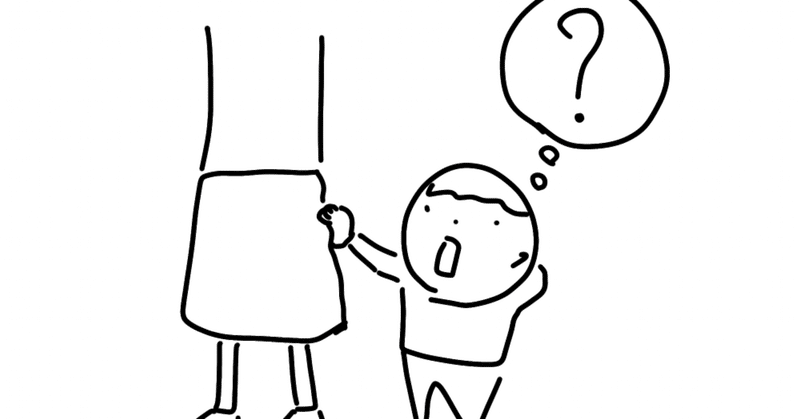
言葉の種を蒔き、水をやり、花を咲かせる
聾学校で働いていると、言葉の尊さを実感する。
耳が聞こえる子供は、耳から言葉を聞いて、特段意識せずに自分の言葉として獲得していく。だが耳が聞こえない子供はそう簡単にはいかない。耳からの情報が少ないことにより、語彙が少なかったり、適切な言葉で自分の考えや気持ちを表現したりすることに課題が見られることもある。
聾学校の教員は耳が聞こえない子供の心の動きに合わせて、その場面に適した言葉を繰り返し音声や手話を用いながら添えていく。一回言っただけでは伝わらないし、一回手話表現しただけでは本当の意味での言葉は定着しない。毎日、言葉の種を蒔き、水をやり、花が咲くのを待つ。
たどたどしい発音であっても子供が自ら言葉を発し、ゆっくりでも手話で言葉が表現された時、私たちは幸せを感じる。
ところが、最近は障害の有無に関わらず、子供の成長、特に言葉の成長を「タイパ」という言葉でいかにも機械的、効率的に考える節があるように感じる。果たしてそれは正しいのだろうか?
子供の成長の早さはまちまちである。特に言葉の成長に関しては、機械的に効率よく言葉に触れるだけでは本当の成長にはならない。その言葉のもつ意味を理解し、使う場面を考え、実際に使ってみてどのように心が動くかといった経験を繰り返し行うことが必要になる。障害の有無に関わらず、言葉の成長には手間と時間がかかるのである。飛ばし見や倍速視聴は通用しない。
子供にとって「やばい」「えぐい」といった言葉はとても便利だと思う。だが、その言葉で会話を終わらせないでほしい。もっと詳しく何を見てどのように感じたのかを自分の言葉をつかって話してほしい。たどたどしくても良い。幼稚でもいい。長くなっても良い。ごまかしの効かない、自分の言葉で語ってほしい。
意識的に言葉の種を撒いて、水をやり、いつ咲くかわからない花を今日か今日かと待ち続ける。「タイパ」は悪いかもしれないが、そんな時間のかかる営みが今を生きる私たちには一層必要になる。
聴覚障害をテーマにしたドラマ「silent」の主題歌の一節に「言葉はまるで雪の結晶」といった表現がある。雪の結晶は様々な種類があり美しい。それぞれに個性がある。だがやがて溶けてしまう。
言葉も同じだ。様々な種類があり美しい。だが使われない言葉はいずれ消えてしまうかもしれない。
未来のために言葉というものを大切に育てたいと強く思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
