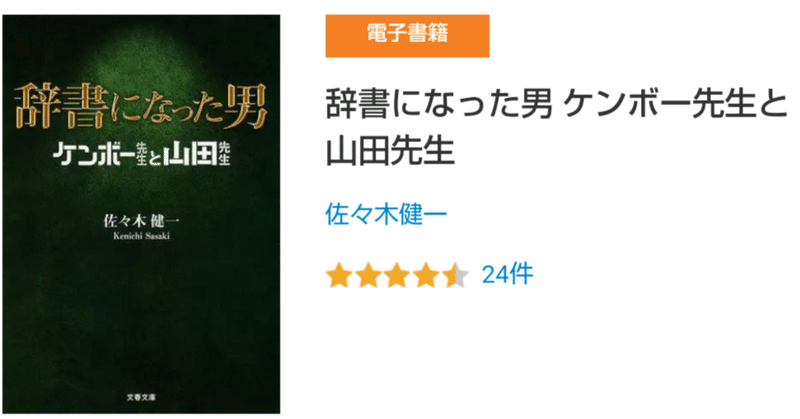
『辞書になった男』、そして辞書と私
『辞書になった男』188頁
以前より気にかけていたこの本を開いたのは日曜日で、その日一日でほぼ半分を読みきってしまった。翌日の通勤電車の中で、会社の昼休みで、やはり読み続けた。
そうしてさしかかった188頁。その中央の段落を切った後の五行の文章。
そのわずか五行の文章を読んだとき、まるで時間が止まったように感じた。時間も空間も凍りついたようで、そこにあるたった数行の文字をただひたすら凝視していた。そこからは次の言葉がまるで紙の上に浮き出し飛び出してくるようだった。
新明解国語辞典
山田
見坊
まさか。
そんなことがあるのだろうか。
天を仰ぎ目を閉じ、その先を思い描こうとしてもとてもかなわなかった。あってほしくない情景が頭の奥底でうごめく。ざわめく。そのような景色を思い描くなど、とうていできない。したくない。
もう一度視線を落としたとき本は開いたままで、その先にもまだまだ文字は並んでいるのだが容易に読み進めることもかなわず、頁がエアコンの風に吹かれ揺れるその姿をただぼんやりと眺めた。
私と辞書
私が辞書に関心を持つようになったのは比較的最近のことで、きっかけは一冊の本だった。
この「国語辞典の遊び方」という本はとても面白い本で、いままで道具にすぎなかった国語辞典というものを一気に読む本へと変えてくれた。
その時にひときわ目をひいたのがこちらに書いた『動物園』の語釈である。
今回読んだ『辞書になった男』のサブタイトルにあるケンボー先生と山田先生とあるのは、見坊豪紀(けんぼうひでのり)氏と山田忠雄(やまだただお)氏のことで、辞書の世界ではつとに有名だ。
今、三省堂から出版されている主な国語辞典に
『三省堂国語辞典』と
『新明解国語辞典』があるが、
『三省堂国語辞典』の主幹が見坊豪紀氏で、
『新明解国語辞典』の主幹が山田忠雄氏である。
だが。
三省堂にはその前にもう一冊の国語辞典があった。
『明解国語辞典』である。『新』はつかない。
そしてそれは、見坊豪紀、山田忠雄、金田一春彦の各氏が編纂した。方々がまだ二十代という若さのことだ。見坊豪紀氏と山田忠雄氏は、かつて同じ辞書編纂に携わっていたということになる。ところが、後に二つの辞書に分かれる。このこと、見坊豪紀氏と山田忠雄氏が袂を分かったということもまた、辞書関係者では有名な話であった。「国語辞典の遊び方」を読んで私もその事を知ることになる。
辞書には何が書かれているだろうか
もちろん、言葉の意味が書かれている。この「言葉の意味」の部分を「語釈」という。品詞が書かれていることも多い。あるいはどのような漢字が使われるのかも書いてあるだろう。そして、多くの辞書に書かれているもう一つのことが「用例」である。過去にその言葉をその意味で使われた文章を例で示す。用例は基本的に辞書編纂者が作成する文章ではない。辞書は勝手に意味を作り出すものではないからだ。実際に使われていたという用例を示すことは、辞書が意味を作り出したわけではないという証拠でもある。
用例の見坊、語釈の山田
両氏はそう評された。そのこだわりというのは常人のそれの遥かに上をいく。
山田忠雄氏の語釈は、先の『動物園』の語釈に見られる通りである。もちろん『動物園』だけに限らない。例えば『恋愛』などはその最たるものと言われる。それまでの辞書にはなかったこれらの語釈は一般人には面白がられたものの、辞書を編纂する諸氏からは批判も多かった。『動物園』や『マンション』などの語釈は、それらに関係する人たちからのクレームもあったという。これらの語釈について、今ここでは書かない。もしよかったら『新明解国語辞典』をひいてみてほしい。辞書で読んだ方が新鮮であるはずだ。『新明解国語辞典』は既に第八版まで版を重ねているが、山田忠雄氏は1996年に他界されているので氏の語釈を読むことが目的であるならば第四版より前の版がいいかと思われる。
一方、見坊豪紀氏は用例こそが辞書の基礎であると考えた。見坊氏曰く、辞書には二つの「かがみ」があると言う。一つは、言葉の模範となって「鑑」たらんとすること。正しい言葉文章意味を提示し人々に示すという立場である。今一つは、その時代の言葉を写す「鏡」であること。優れた言葉、下品な言葉、乱暴な言葉、そのようなものを選りすぐることなく全てを載せる。辞書はわからない言葉を調べるためのものであって、探した時に辞書に載っていないということは望ましくない。そのために必要なことこそが用例収集であった。
国家的規模による辞書の編集は、一方では、国民各自のことばに対する関心が高まり、その結果有志が自発的に、編集上役に立つ、文脈つき・出典つきの用語例を大量に寄付してくれるようになることが必要である。また一方では、編集に従事する人は、ありのように、勤勉で昼夜を分かたず労働することに喜びとほこりを感じる、誠実で責任感のつよい人間でなければならない。
「ありのように」と読んで思わず笑ってしまった。見坊豪紀氏であれば嬉々としてなさったのではなかろうか。文脈つき・出典つきの用語例の寄付を求められたら、わたしもせっせと寄付しそうだ。
この文章に見られる通り、見坊氏の用例収集は想像を遥かに越える。50年にわたって145万の用例を独力で採集した。
袂を分かった理由
見坊豪紀氏と山田忠雄氏が袂を分かった理由はなんだったのか。私は単純に辞書への考え方の相違だろうと考えていた。用例の見坊、語釈の山田と言われたように基本方針のそれが違っていたため、ならばそれぞれの方針に従った二つの辞書を作ったのだろうと。実際に、見坊豪紀氏が編んだ『三省堂国語辞典』は真っ先に新語を入れることで有名である。巷の言葉を含めずしてなんぞ辞書ぞという見坊氏の声が聞こえてきそうである。一方、山田忠雄氏が編んだ『新明解国語辞典』はその語釈で有名になった。従来の辞書にはないその語釈に、一般の人も楽しんだ。
我が家には『新明解国語辞典』が二冊ある。一冊は第四版、そしてもう一冊は第七版である。この第七版には、初版から第七版までの序文が全て収録されている。初版と第二版の序文は同じで、それを読んで少しく違和感を覚えたことは今をもってして忘れられない。全文を引用したいがさすがに憚られるので一部を抜粋引用する。太字は私が成したものであり、それこそが違和感を感じた部分に他ならない。
このたびの脱皮は、執筆陣に新たに柴田を迎えると共に、見坊に事故有り、山田が主幹を代行したことにすべて起因する。言わば、内閣の更迭に伴う諸政の一進一退であるが、真にこれをせしめたものは時運であると言わねばならぬ。
「新たなるものを目指して(初版・第二版 序)」より
『見坊に事故あり』『内閣の更迭』。
見坊氏と別れて別の辞書を編むことは不思議ではない。だが、ただ別れたというだけならば、このような表現は必要だろうか。別れたというよりも、まるで「見坊がダメなので外した」というように読み取れてしまう。仮にそうだとして、わざわざ公に、しかも「新」と銘打った辞書の序文に書かねばならなかったのだろうか。見坊氏自身はどう思ったのだろう。
思えば、辞書界の低迷は、編者の前近代的な体質と方法論の無自覚に在るのではないか。先行書数冊を机上にひろげ、適宜に取捨選択して一書を成すは、いわゆるパッチワークの最たるもの、所詮、芋辞書の域を出ない。その語の指す所のものを実際の用例について、よく知り、よく考え、本義を弁えた上に、広義・狭義にわたって語釈を施す以外に王道は無い。辞書は、引き写しの結果ではなく、用例蒐集と思索の産物でなければならぬ。尊厳な人間が一個の人格として扱われるごとく、須らく、一冊の辞書には編者独特の持ち味が なんらかの意味で滲み出なければならぬと思う。かような主張のもとに本書は成った。今後の国語辞典すべて、本書の創めた形式・体裁と思索の結果を盲目的に踏襲することを、断じて拒否する。辞書発達のためにあらゆる模倣をお断りする。
「新たなるものを目指して(初版・第二版 序)」より
『芋辞書』!
冒頭に『辞書界の低迷』とあるので特定の誰か、特定の辞書を指すものではないと思うが、それにしてもかなり強い表現である。
さらに『用例蒐集』とあるが、そもそも見坊氏の片寄りすぎた用例蒐集を指して事故と言っているのではなかったか。用例蒐集を皆無にすることはできまいが、それにしても先頭にうたわれる言葉になるのだろうか。
『踏襲することを断じて拒否する』
『あらゆる模倣をお断りする』
これは一体、誰の何に対して言っているのだろう。
気にはなったものの、最初に読んだときにはわからなかった。だが、本書『辞書になった男』を読んでそれは氷解した。なるほど、そういう経緯であったか。
以上が、私が新明解初版の序文に抱いた違和感である。
この記事の冒頭に戻ろう
188頁を読んでしばらく佇んだ後、壁の時計を見ると12時55分を過ぎていた。昼休みも、もう終わる。仕事に戻らなければ。それはあるいは救いだったかもしれない。
続きを読んだのは帰りの通勤列車の中でも夕食後でもなく、就寝前だった。
188頁のその五行を読んだときに驚愕したのだったが、もう一度改めて読んでみて何故驚愕したのか我ながら少しく不思議ではある。瞬間的に状況が見えた。どうしてだったろうか。どう考えてもわからない。問題箇所はもう少し先になる。
ちなみに驚愕したのは188頁だけでなく、207頁にもあった。これには絶句した。
見坊豪紀氏と山田忠雄氏が袂を分かったのは何故だったか。
その理由について、この記事では書かない。
出し惜しみしているわけではないが、おそらくは大いなるネタバレになってしまうからだ。ノンフィクションにネタバレかと訝しむ向きもあろうが、実際そうなのだから仕方がない。
もう一つは、このわずかばかりの記事で簡単に書いてしまっていいのかという思いもある。この『辞書になった男』は、あとがきも含めて336頁になる。それだけの量を費やして書ききった内容をわずか数千文字におさめてしまっていいのか。
もし気になる方がおられるのであれば本書を読んでいただくしかない。
ただ。
本書では山田忠雄氏についての記載が少ないかと感じた。『充実した表情』の一言だけのように思える。あの時どう思っておられたのか。その後、どう感じておられたのか。どう考えておられたのか。それがよくわからなかった。
見坊豪紀氏と山田忠雄氏
この本はサブタイトルにもある通り、見坊豪紀氏と山田忠雄氏について語った本である。NHKが取材し番組を制作した過程から得られた情報を元に書籍化した。取材はドキュメンタリーにすることも本にすることも否定される方もおられたようだ。辞書だけを知ってもらえばよくて、その制作秘話などを公にすることはないと。辞書についてはそうかもしれないが、見坊豪紀氏と山田忠雄氏は語らるべき存在ではないかというような気がする。人として、その考え方、成してきたこと、そんなことを語り研究する対象になる方々ではないかと思うのである。近代辞書の先駆けと言われる大槻文彦がいまだ語り継がれるように、きっとお二人に関心を抱き研究する人達が続くのではないか。それだけの魅力を持った人達なのである。
私は、見坊カード(見坊豪紀氏が採集された145万の用例カード)、それに『明解国語辞典 第三版』を見たくてたまらない。これらはいずれ必ずデジタルデータ化していただきたいと切に願う。たとえ私が見ることがかなわなかったとしても。
最後に
国語辞典の最終項目を引いてみたことがあるだろうか。
『新明解国語辞典』からひいてみよう。
んとす [雅][「むとす」の変化]まさにそういう状態にあることを表わす。「われら一同、現代語辞典の規範たらんとする抱負を以て、本書を編したり。乞ふ読者、微衷を汲み取られんことを」
この「われら一同~」のくだりはおそらく作例だろう。だが、辞書を編纂した心意気のようなものを感じられる。どんな仕事でも完璧なるものは難しい。だが、それでも同じように抱負を持って向き合いたい。
あ。
最終項目はすでに「んぼ」にとって変わられていた。
「んぼ」って、なに?(笑)
参考文献
辞書に関する様々な書籍である。
『学校では教えてくれない!国語辞典の遊び方』
私に辞書の面白さを教えてくれた本である。
『新解さんの謎』
『新明解国語辞典』を語ると必ず出てくる一冊である。『新解さん』とは『新明解国語辞典』の愛称であり、タイトル通り『新明解国語辞典』を語り尽くした本である。
『辞書と日本語 国語辞典を解剖する』
見坊豪紀氏の用例収集に対する評価と、ら抜き言葉に関する記載が絶品。著者は『大辞林』(初版)の編集長。
『ことばの海をゆく』
見坊豪紀氏の書籍である。
用例収集に人生を費やした。毎日毎日を、新聞二時間、月刊誌一時間、単行本一時間をかけて読み用例を収集する。一日を休むと二日分がたまるので休めない。そういうことを十数年も繰り返す。ことばは目の前で音もなく変わる。辞書は世間のことばを写すかがみである。柳田國男が「とても寒い」という言い方に驚いたという話は本書で知った。
『辞書をつくる』
本書にある次の言葉が見坊豪紀氏の辞書編纂に思いが集約されているように思う。記事にも書いたが再掲する。
国家的規模による辞書の編集は、一方では、国民各自のことばに対する関心が高まり、その結果有志が自発的に、編集上役に立つ、文脈つき・出典つきの用語例を大量に寄付してくれるようになることが必要である。また一方では、編集に従事する人は、ありのように、勤勉で昼夜を分かたず労働することに喜びとほこりを感じる、誠実で責任感のつよい人間でなければならない。
『私の語誌』
そしてこちらは山田忠雄氏の書籍となる。辞書屋さんの語誌。それはいったいどのようなものだろう。どれだけの語彙が語られるのだろう。開いてみた。そして驚いた。たった三語である。三語! 三語で284頁! しかも用例がひたすら並ぶ。「快挙」と「他山の石」と「風潮」の用例が200頁以上にわたって、文字通りズラリとならんでいるのである。
この本を手に取ったとき、少し違和感も覚えた。山田忠雄氏は用例を評価しないのではなかったか。それについても本書で氷解した。本書は山田忠雄氏の最晩年の書籍である。
『明解物語』
これは未読で、本書で初めて知った。
今一番読んでみたい本である。
『暮しの手帖 1971年2月号』
辞書の話をしているのだろうに、何故『暮しの手帖』が? この「1971年 2月号」には「国語辞典をテストする」という特集があった。この特集については聞いたことがあったのだが、それがどこでだったか。以来、是非読んでみたいと思いつつも果たせないわけで。半世紀以上も前の、しかも雑誌である。リンク先を貼れなかったのもそのためであって、どうやったら読めるのか思案中である。
『ことばのうみのおくがき』
日本語の近代辞書の先駆けと言われる『言海』を作った大槻文彦の文である。この文は『言海』に含まれた。
『大槻文彦『言海』 辞書と日本の近代』
この本の感想はこちらに書いた。
『三省堂国語辞典のひみつ』
こちらも未読。
著者は三省堂国語辞典の編纂者。
他にも辞書に関する本は多々あるがこれくらいにしておこう。まだ読んでないし。
そして。
おまけ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
