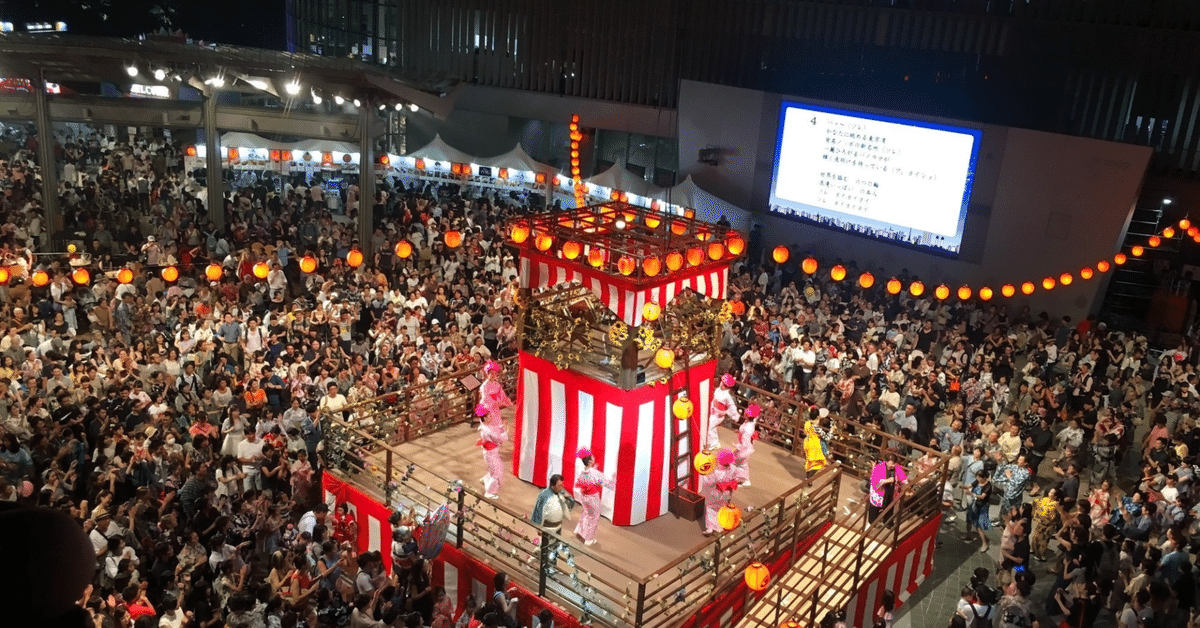
24時間営業を辞めたコンビニ〜2月の販売数値の動向〜「デイリー品」
「商品展示会の復活」
皆さんこんにちわ、あやすけです。
2月も終わりましたね。と同時に、当店の今年の冬も終わったようです。気温はもう春のような季節へと変化し、毎日見ている天気の週間予報から雪のマークが消えました。「日販低下&除雪費等の経費増加」という、毎年やってくる当店経営者にとっての地獄の季節も、何とか無事に通過できそうです。今年の冬の除雪に係る委託費は「ゼロ」でした。
しかしながら、新たな敵は次から次へとやって来るものです。当店にも、新しい敵である「インフルエンザ大流行」が襲来しています。学校に通わせているお子様を持つスタッフが、学年閉鎖や学級閉鎖、そして子や親のインフルエンザ感染という事態に直面し、次々とシフトから脱落しています。
・・・いつものことです。特に大きな変化はありません(笑)
「人手不足」はこれまでも、そして、これからもまだまだしばらくは続くでしょう。既に出来る手は打っていますから、後は生き残るのみです。
そういえば、「商品展示会」を今春から復活するとのお達しが本部からありました。その話で私と親父オーナー&おかん店長との間で喧々諤々の議論があったのですが、想うことはやはり、人によって価値観とは大きく異なるのだなぁと痛感しています。
異なる意見を否定するつもりは毛頭ありませんので、あくまで私の価値観に基づく意見をここで書くことで終わりにしたいと思います。
身内に対するイベントやお祭りに出す金があるのなら、日販にもっと直接影響を及ぼすものに金を出せこのバカタレがぁぁぁぁぁ!!! ※あくまで個人的な見解です
・・・どうしても、お役所さんが「箱物」を量産していた時代の思想と被るのですよねぇ(泣)
また別の記事で詳しく書きたいと思います。
それでは、デイリー品における当店2月の販売数値の動向です。
1.基礎数値
・日販
前年比107%(106%)
コロナ禍初年度比94%(92%)
24時間営業時比84%(84%)
・客数
前年比107%(105%) ※参考 2021年度比96%(105%)
コロナ禍初年度比82%(78%)
24時間営業時比72%(73%)
・客単
前年比100%(102%)
コロナ禍初年度比116%(117%)
24時間営業時比116%(115%)
・買上点数
前年比98%(97%)
コロナ禍初年度比107%(106%)
24時間営業時比108%(103%)
※( )は前月の数値です
2月の数値は1月とそのトレンドにおいて大きく変わらないものとなりました。
併せて、現時点における当店経営陣の今後の数値の見立ても変更ありません。内容は以下のとおりです。
「客数」・・・コロナ禍からの回復度合いは2021年並に留まる
「客単価」・・・上昇度合いの頭打ちから今後ゆっくりと数値が低下
「日販」・・・コロナ禍初年度であった2020年並に留まる→つまりコロナ禍
以前には戻らない
対して2月の状況はというと、客数は予想以上の幅で上ブレ、客単価は上昇の頭打ちが終わったもののそのスピードは予想以上に早く、結果として日販は前年より7%の上ブレ&コロナ禍初年度と比較して7%の下ブレ、となりました。1月と比較してトレンドは全く同じです。今年に入ってからの日販の推移は、予想外の伸び幅で上昇する「客数」の数値に依存する状況にも変化はありません。
現在のところ、10月の経営数値に基づき立てた上記の見立てを変更する要因は無いと視ています。予想以上に大幅な上昇の動きを見せている客数ではありますが、その数値の回復度合いは2021年並に留まるという予測も現時点で変更はありません。問題はそのタイミングがいつ来るかですが、今年に入ってからのこの客数の大幅な上昇、その原因が正直なところ分からないため、タイミングも不明です。
コロナによる行動制限の緩和のインパクトは4年目となる今年にはそれ程無いと考えていましたし、インフレによるコンビニ以外への客数の流出の力が大きいとも考えていました。前月の記事にも書いたとおり、買上点数は連続して下降しており今月も継続中です。
しかし一方で、真に重要な点は、1つ目→現在の日販が原因の分からない「客数の大幅増」に依存していること、つまりそれはいつ終わってもおかしくないということ、2つ目→そうであるならば、タイミングが分からないとしてもいずれ至る結果は変わらないということ、となります。その結果とは、「日販の回復度合いはコロナ禍以前の日販には届かない」ということです。
以上の事から、これまでの経営方針にも変更はありません。その上昇度合いが頭打ちとなった「客単価」を少しでも長い期間下支えすることを基本的な取り組みとしつつ、8月から経営方針を変更した「廃棄額」の適正化による経費のスリム化に軸足を置くウェイトを重くして取り組む、という方針となります。当然のことですが、引き続き撤退戦は継続です。
2.前年比upした分類
◯米飯→前年比111%(111%)
・「おにぎり→大幅up」
・「チルド弁当→down」
・「寿司→大幅up」
・「弁当→up」
・「御飯→大幅up」
・「こだわりおむすび→大幅down」
前月と同様に全体の前年比の数値の状況に変化はありませんが、細かい分類ごとに内容を視てみると、日販の上昇を牽引する力が「客単価」から「客数」へと変化した状況を良く表しているとも言えます。「おにぎり」の上昇幅が大きい点が継続している一方で、「チルド弁当」や「弁当」の数値はその上昇幅を減らしました。
そんな中でも付加価値の高い分類である「寿司」の数値の上昇幅が依然として大きい事は、客単価と付加価値を重視した品揃えを継続して取り組んだ結果とも言えます。販売力の高い新商品の開発も大きいですね。本部さんナイスです。
一方で、廃棄額は予算を超えた状況が未だ続いています。したがって、今後の方針についても特に変化ありません。「付加価値」を重視した品揃えを継続するとともに、販売額に応じた適正な廃棄額をゴールと考え、品揃え全体のスケールを落としていくことを目標とします。
◯フライヤーその他→前年比113%(109%)
・「フライヤー→大幅up」
・「中華まん→down」
・「おでん→取扱い無し」
8月から経営方針を一部変更した「経費のスリム化」に基づき、従前より仕込み数を減らしている分類となりますが、前月に引き続き今月も数値は上向きであり、地区平均と比較しても同水準です。また、今月は廃棄額の数値を予算内に収めることも出来ました。
販売額と廃棄額のバランス&全体のスケールの妥当な水準を昨年12月にある程度決めることが出来ましたので、今後は引き続きその「妥当と見込んだ水準」をコントロールすること、また地区内でもトップレベルの販売額を維持することを目標とします。
◯ペストリー→前年比107%(99%)
・「菓子パン→大幅up」
・「惣菜パン→大幅up」
・「NBパン→大幅down」
・「ドーナツ→大幅down」
現状の品揃えでは付加価値が見込めない分類となりますが、2ヶ月ぶりに数値は上向きました。客数依存の度合いが強い分類であるにも関わらず前月の数値は上向かなかったことから、その原因を販売額と廃棄額のバランスの悪さと結論付けた先月でしたが、今月は数値は上向きました。
一方で、しばらく不調が続いていた「菓子パン」の数値が改善したことは大きな変化でした。もしかすると、現状の品揃えにおいては「惣菜パン」より「菓子パン」の方が客数依存の度合いが強いのかも知れません。
客数が予想外に強い今の状況がいつまで続くかは分かりませんが、これまでの方針である「好調な惣菜パンに資源を集中する」という方針も変更が必要かも知れません。しばらく数値を様子見ですね。
最後に、現在の「撤退戦」という当店の状況においては、付加価値が現状において見込めないこの分類について、「地区平均と同等の販売数値で十分」という方針はこれまでどおり継続です。
◯スイーツ→前年比116%(121%)
・「チルド洋菓子→up」
・「チルド和菓子→大幅up」
・「チルド洋菓子NB→down」
・「ヨーグルト→大幅up」
・「プリン、ゼリー→大幅down」
フライヤーと同様に立地的に弱いこの分類については、「廃棄額をチルド洋菓子で抑えつつ、販売額前年比をチルド和菓子で稼ぐことで、立地的に弱いスイーツを自店の強みとする」という、定石とは真逆の方針に基づき、分類全体を自店の強みにする取り組みを6月から開始しましたが、今月も前年比の数値は上ブレしました。地区平均の数値と比較しても大幅に優位な数値である点も変化無しです。
これで、11月から4ヶ月連続で数値が上ブレとなりました。そろそろ結論を出して良いでしょう。取り組みは半分成功です。自店の強みとするための「方法」は正しかったことが分かりましたので、残る課題はスイーツ全体の販売額を地区内でトップレベルの水準まで押し上げる事となります。
そのためには、「フライヤー」の分類で取り組んだのと同様に、どの程度のスケールを妥当な水準と決めるか、と言うことが必要な課題となります。具体的には、廃棄率を維持したまま毎月少しづつ販売額と廃棄額のスケールを拡大していくこととなります。ここからが難しいですね。
◯調理パン→前年比111%(107%)
・「サンドイッチ→大幅up」
・「ロール→大幅down」
・「ブリトー→大幅up」
前年比の数字が割れている状況が数ヶ月続いていましたが、今年に入ってからは2ヶ月連続して数値は上ブレしました。数値を牽引している分類を視ると付加価値がそれ程高くないと見込んでいる「サンドイッチ」であることから、分類全体の数値が上ブレした要因は、予想外であった「客数の前年比増」であるという予測も、前月と変更ありません。
「予想外の客数の前年比増」という状況が続く限りは、この分類の数値の上ブレは続くでしょう。言い換えればその状況は、「客数依存」の度合いが強いという事です。嫌いな状況ですね。ですがそうは言っても、付加価値の高い「ロール」の分類の数値は、自店・地区平均ともに不調が続いています。
限りある資源を売れている分類に集中するという方針に変更はありません。しかしその集中している分類である「サンドイッチ」には、将来性は無い&伸び代は無いということを頭に入れておくべきでしょう。
3.前年比downした分類
◯デリカテッセン→前年比98%(97%)
・「サラダ→大幅down」
・「惣菜→down」
・「食事サラダ→大幅up」
・「主菜→大幅up」
・「その他→大幅down」
・「副菜→up」
前年比の数値が大幅にupした状況が長らく続いていた分類ですが、12月から3ヶ月連続で数値が下ブレしました。地区平均の数値と比較して同水準であることも変化無しです。客数が上向いている現状&客単価と買上点数が下降している現状を併せて考慮すると、先月の記事で予測した「中食というブームの下火」が現実のものとなってきました。
その原因はやはり、「インフレ」による購買意欲の減となるでしょう。「背に腹は変えられない」という状況ですね。3月も引き続き同様の状況となった際には、「ペストリー」の分類と同様に、「地区平均と同水準の数値が維持できれば十分」という方針に切り替えます。
◯麺類・その他→前年比90%(82%)
・「カップ麺→大幅down」
・「スパパス→down」
・「グラタンドリア→大幅up」
・「うどん焼きそば→up」
地区平均と比較して数値が劣後した先月とは逆に、今月の数値は地区平均と同水準です。これまでも前年比の数値が下降している状況がしばらく続いている分類ですが、客数が上向きに転じた今年に入ってもその状況に変化はありません。廃棄率の数値も適正であることから、つまりその原因は品揃えではないのでしょう。
現状、打つ手はありません。当面は様子見をしつつ、「地区平均と同等の水準」を維持することを目標に耐え忍びます。
それでは今日はこの辺で。
このクソッタレな世界と戦う皆様と明日もともに。
