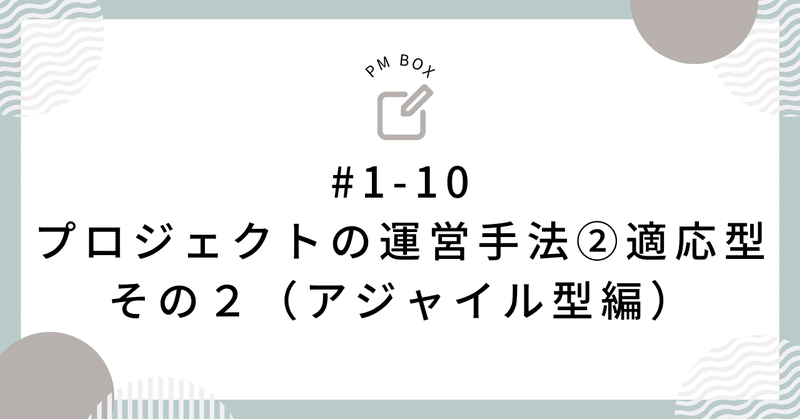
#1-10 プロジェクトの運営手法②適応型その2(アジャイル型編)
このところ前後で関連する記事が続いていますが、今回の記事は特に前回(前日)の記事と繋がっています。
この記事だけ読んでピンとこない場合は、前回の記事から読んでいただけますと幸いですm(__)m
プロジェクトマネジメントには、性質で分けると3つの開発手法があります。
①予測型
②適応型
③ハイブリッド型
今回は適応型の中でも、アジャイル型についての内容です。
「アジャイル」って、どれくらい一般的に浸透している用語なのでしょうかね。「トヨタ生産方式」くらい、ビジネスパーソンの中では知名度あったりするのかなぁ……。
そんなことが気になってしまうくらい、プロジェクトマネジメントの世界で「アジャイル」ってすごく有名な言葉です。
まず、ザックリとアジャイル型の説明です。
「アジャイル」は、「素早い」とか「俊敏な」という意味なのですが、
最初に綿密な計画を立てずに、短い開発工程を何度も何度も繰り返して、都度ユーザーのニーズや新たな要求事項を反映させながら、迅速・段階的に完成度を高めていく方法です。
素早く、というのはだいたい2~4週間であることが多いです。
変化するユーザーのニーズに対応出来たり、最初から見通しの立っていない要件があっても開発を進められたりするメリットがあります。
デメリットとしては、進捗管理が非常に難しいです。
全体のスケジュールが立てにくいうえに、柔軟に変化するぶん開発の方向性がブレやすいので、進捗管理が適切にできない場合、失敗するリスクが高いです。
小規模なシステム開発に向いていると言われています。
個人的な意見ですが、アジャイル開発の理論は、プロジェクトのメンバーが善人で思考することに長けていて、コミュニケーション能力を標準的に備えた人間しかいない場合でないと実践が難しい気がします。
(理論上はそんなことないのですが……)
また、会社の上層部からの裁量の委譲が大前提ですが、日本の企業でそこまで大々的にアジャイル開発のサポートをしているところは、そんなになさそうな印象です。
(資格取得のセミナーやイベントなのでそういう話を聞くだけで、実態の統計を取っているわけでないです。あくまでも個人的な印象です)
アジャイル開発の原型は1990年代から登場していたのですが、2001年に「アジャイルソフトウェア開発宣言」というものが公開されました。

© 2001, 上記の著者たち(この宣言は、この注意書きも含めた形で全文を含めることを条件に 自由にコピーしてよい。)
アジャイル型の中でも、さらに特徴によっていくつかの開発手法のに分かれます。
勘違いされがちなのですが、「アジャイル型」という一つの開発手法があるわけではなく、
「短い開発工程を何度も繰り返して、要件を変更しながら素早く開発を進める開発手法」
の総称がアジャイル型(もしくは、アジャイル開発)です。
具体的には、主に下記の手法があります。
・スクラム
・XP(eXtreme Programming) エクストリームプログラミング
・FDD (Feature-Driven Development) ユーザー機能駆動開発
・DSDM(Dynamic System Development Method) 動的システム開発手法
・ASD(Adaptive Software Development)適応型ソフトウェア開発
・LSD(Lean Software Development )リーンソフトウェア開発
アジャイルと言えば、汎用性の高いスクラムが一番有名だと思います。
スクラムは、ラグビーのセットプレーの「スクラム(scrum)」が語源です。
スクラムを組むように、開発メンバーが一体となってコミュニケーションを取りながら共通のゴールを目指して開発を進める手法です。
これは余談ですが
私は、
A-CSM®(Advanced Certified ScrumMaster)
CSPO®(Certified Scrum Product Owner)
というプロマネ系の資格を持っているのですが、どちらもスクラムの資格です。
スクラムでは、スクラムマスターという役職を持つ人とプロダクトオーナーという役職を持つ人と開発メンバーで構成されます。
A-CSM®(Advanced Certified ScrumMaster)はアドバンスド認定スクラムマスターという資格、CSPO®(Certified Scrum Product Owner)は認定プロダクトオーナーという資格です。
Scrum AllianceというアメリカのNPO法人があり、そこから認定を受ける形で資格の取得が出来ます。Scrum Alliance以外にもスクラムの資格の認定機関はあるのですが(Scrum.org、Scrum Inc Japan)、Scrum Allianceが一番老舗で大手、という感じです。
Scrum Alliance認定トレーナーによる認定講座を受けて資格を取得するのですが、私が受講した講座の認定トレーナーは、コミュニケーション能力とファシリテーション能力が非常に高かったです。
さて。
アジャイル型のデメリットとして、進捗管理が非常に難しいという点を挙げましたが、最低限の知識がなければまず、進捗管理に失敗します。
スクラムはルールはそこまで複雑ではないのですが、習得が非常に難しいです。
それこそ、ラグビーの試合のようなもので、ルールを知ったからといって全員が試合に勝てるわけではありません。
ルールを知ることの先に、勝つための個別の活動が必要になります。
何度か述べていますが、私はプロジェクトマネージャーの世界で一番重要なのは資格ではなく、実践経験だと思っています。
なので、資格は「スクラムのルールを知っています」の証明程度です。
資格を取得したからといって、いきなりそれまで出来なかった規模のプロジェクトマネジメントが出来るようになるかというと、そういうものではないです。
私はプロジェクトマネージャーも監督やコーチ同じようなものだと思っていまして。
例えば、ラグビーチームの監督やコーチをするとして、競技のルールを知らないことは、まずないですよね。
ルールを理解した上で、チームにあった戦略を練っていくのが監督やコーチだと思います。
同じように、プロジェクトマネジメントでも、最低限のルールを知ったうえでメンバーを導いてあげた方が、より良いチーム運営と戦略を練ることができると思っています。
資格を取得する必要はないですが、コーチや監督して最低限必要な知識を身につけよう、という気持ちが大事なのかな、と思ったりしています。
今回の記事ではざっくりとしか触れていませんが「スクラム」というテーマだけで本が一冊掛けるほど、情報量がとても多いです。
一通りプロジェクトマネジメントの基本のキホンの紹介が終わったら、そういうコッテリした個別のトピックスの話もしたいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
