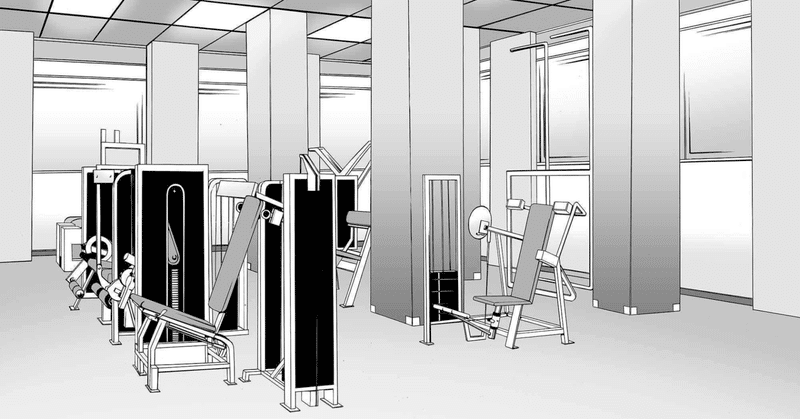
【書評】羽田圭介「スクラップ・アンド・ビルド」
【スクラップ・アンド・ビルド:羽田圭介:2015:第153回芥川賞受賞作】
筋肉をつけると性格が変わるという話をどこかで聞いたことがある。ホルモンの影響で明るくなるとか何とか。そう言われてみればボディビルダーのような体格なのに性格は後ろ向き、などという人間はちょっと想像しにくい。ムキムキの太宰治など想像してみようにも像を結ばず、肉体ゴリゴリの男が「恥の多い生涯を送ってきました」などと呟いたところで真実味がない。恥の多い生涯のなかでいかにしてその見事な身体を作り込んだのかと問いたくなる。
というのも、筋肉をつけようと思うことそのものがある程度明るい証拠ではないかとも思えるわけで、どちらが先かわからない。否応なく筋肉を付けざるをえないような状況に置かれれば皆明るく前向きになるのかもしれず、例えば渡辺京二「逝きし世の面影」には開国以前の日本の肉体労働者は皆幸せそうだったと書かれている。労働がなんでもかんでも機械やプログラムに置き換えられる現代社会というのは、だから人類から「生きる気力」を奪う方向にあるのかもしれない。例えば星新一「ゆきとどいた生活」などはこの進歩の行き尽く先を簡潔に抉り出している。
筋トレと介護の話である。
数年続けたカーディーラーの仕事を退職し実家暮らしの主人公、健斗が、祖父の介護の合間、筋トレ・資格試験勉強・就活に励む。――というのが話の大筋で、そこに健斗の、祖父に対する正も負も併せ持つ想念が語られてゆく。
事あるごとに「死にたい」と漏らす祖父の願いを叶えるべく、健斗は身の回りの世話を徹底して行う。「過剰な介護」によって祖父の筋力や思考力を弱らせることで、最終的に死に至らしめようというわけである。
それだけの筋であれば、単に祖父を弱らせるだけの話に終始するだろうが、そこに「筋トレ」が加わることによって本作は含み多いものとなっている。「目標に向かって前向きに取り組む」といういかにも筋肉質な思想のもと、祖父の「死にたい」を叶えるべく尽力する一方で、認知機能の低下および肉体の衰弱によって卑屈な獣的存在となり果てた祖父に対する容赦のない批判を繰り広げたりなどする。少々長いが、象徴的な一節を抜き出す。
祖父がさする箇所の半分以上は、関節等ではなく筋肉の部分だ。健斗もここのところ、全身のあらゆるところに筋肉痛がある。現役世代の健斗にとって痛みとは炎症や危険を知らせる信号であり、筋肉の痛みに関していえば超回復をともなったさらなる成長の約束そのものである。つまり、後遺症や後々の不具合がないとわかれば苦なく我慢できる。しかし祖父にとっては違う。痛みを痛みとして、それ自体としてしかとらえることができない。不断に痛みの信号を受け続けてしまえば、人間的思考が欠如し、裏を読むこともできなくなるのか。だからこそ痛みを誤魔化すための薬を山のように読み、薬という毒で本質的に身体を蝕むことも厭わない。心身の健康を保つために必要な運動も、疲労という表面的苦しさのみで忌避してしまう。運動で筋肉をつけ血流をよくすることで神経痛の改善をはかったりはしない。その即物的かつ短絡的な判断の仕方が獣のようで、健斗にとっては不気味だった。
以上を読めばわかるように、介護と筋トレという一見すると奇妙な取り合わせは、「若くて健康的で未来のある自分」と「目先の安らぎにすがることしかできない祖父」との対比のために用いられる。考えてみると合理的な道具立てだ。
「肉体的壮健/肉体的衰弱」
「未来志向/現在志向」
「前向き/後ろ向き」
「若さ/老い」
といったように、健斗と祖父との間には対比が効いている。
この明確な対比のもと、少なくとも自分は祖父のように劣った存在ではないと安心したい健斗の心情や、「自死念慮を叶えるのは祖父のためと言いつつ実は厄介払いしたいだけではないか」といった葛藤などが描かれる。
全的に親切とも言い切れない、それでいて思いやりがないわけでもないという、血のつながった(それも祖父という距離感の)家族に抱かれる割り切れない想念が、割り切らないまま描かれているところに本作のリアリティがある。
面白く読んだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
