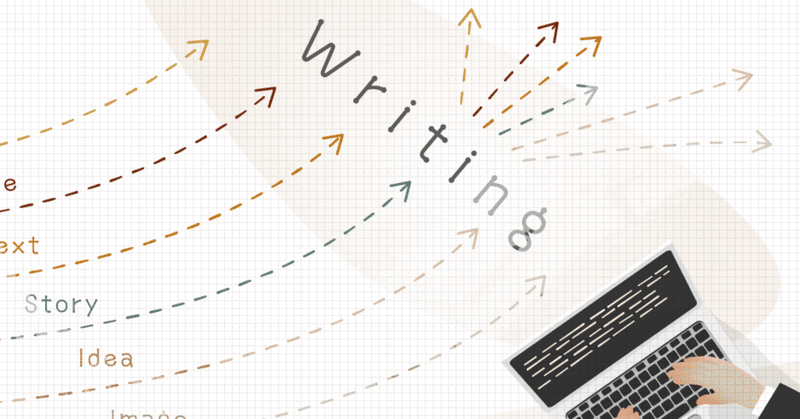
【自分用まとめ】リサーチ関係備忘録(手法・ツール・アウトプット)
はじめに
大学時代、レポートを書く講義が本当に苦手でした。
文献を調べたり読んだりするのは好きでしたが、
それをまとめて自分の考察を加える、という作業は
未だに苦手です。
手当たり次第にリサーチするのではなく、
自分なりの方法を系統立ててまとめておきたいなと
思ってこの記事を書きました。
この記事の流れ
大きく分けて、4つの章に分けています。
リサーチの基本的な流れ
リサーチ手法
リサーチツール
リサーチのアウトプット
基本的なフレームは
アクセンチュア 消費財・サービス業界グループ 著
『外資系コンサルのリサーチ技法(第2版)』
を基にしておりますので、詳細はこちらをご参照ください。
リサーチの基本的な流れ
この章では、リサーチの基本的な流れをまとめていきます。
目的の確認
答えるべき問い
調べるべきことの内容を決定
企画のステージ
調べるべきことの範囲を決定
成果のレベルとまとめるイメージ
スピード・精度・網羅性
リサーチプランの設計
どんなソースに当たるか
いつどの順番で当たるか(優先度)
リサーチの実行
情報に付加価値を付ける
複数ソースから得た情報の合わせ技
通常以外の情報収集ルートで得た希少性の高い情報
アウトプット化
リサーチ結果の整理
リサーチ手法
このテーマでは、リサーチの基本的な手法をまとめていきます。
主に、調べる範囲が広い→狭い順で有用な手法を記載します。
NDCトラバース
調べたいテーマ×NDC(日本十進分類法)を掛け合わせて
横断検索(トラバース)する手法
①取り上げるテーマやトピックを一つ決める
②テーマ・トピックに対して、日本十進分類法の各項目を掛け合わせて、検索を行う
カルテ・クセジュ
既知のものと未知のものを選り分け、
気になる・大事そうなものを優先的に調べていく。
関連を意識することで手当たり次第に調べることがなくなり、
継続しやすい。
①取り組もうとしている分野や課題について、何でも思いつく限り順不同で書き出す
②書き尽くしたら、読み返しながら、まずは知っていることを四角で囲む
③四角で囲んだものの中から気になる/大事そうなものを選んで調べる。調べたものはさらに四角で囲む(四角い二重囲みになる)
④いくつか調べた後で、再び全体を読み返しながら、項目同士で関係がありそうなものを線で結んでいく
⑤調査と結びつけ(③、④の作業)を繰り返し、項目を結びつけたカルテの変化と成長が落ち着いたら、今度はもっと知りたいと思うものを、いくつか○で囲んでいく
⑥カルテを見返しながら、◯をつけた項目の中から、最も知りたいものを一つ選びもう一重、○で囲む。(◎の囲みになる)。
これがあなたの学習/研究のテーマに、少なくともそのコアになる
⑦カルテ・クセジュを学習/研究が進む度に改訂していく
おむすびキーワード
元々はSEO対策用のサイトだけど
関連してよく検索されているキーワードが出てきて便利!
アイデア出しの補足に使えそう。
ラミのトポス
5W2Hが具体的な事象を扱うのに対して、
こちらは抽象的な事象を扱うのに適している。
ソクラテス式の問答法を一人でやっているイメージ?
①自分がわからないこと、または知りたいことについて、次の問いをぶつけて、自問自答する
類(○○は何の一種か?)
種差(○○は、同じグループの中で他とどこが違うのか?
部分(○○を構成する部分を列挙すると?)
定義(○○とは何か?)
語源(○○の語源は?)
相反(○○の反対は?)
原因・由来(○○を生じさせる(た)ものは?)
結果・派生(○○から生じる(た)ものは?)
②自分だけで答えられる問いには答え、調べる必要があるものは後で調べておく
文献たぐりよせ
今持っている本から関連本を発見するのに適した手法。
研究はほとんどが繋がっているので、被引用の数が多いと
中心部分にたどり着きやすくなる。(+批判も多かったりする)
①起点となる文献(参考文献付き)を決める
②起点となる文献の参考文献を手がかりに次の文献を見つける
引用文献たぐりよせ
被引用文献たぐりよせ
著者名たぐりよせ
③②を繰り返して、さらに文献をたぐりよせていく
リサーチツール
Web検索
検索エンジンによる検索
調べているうちに関連情報に行き当たることもあるので、
脇道情報を逃さないこと!
(情報発信元の信頼性や情報の鮮度に気をつけること)
調べ方
代替ワード
そのものズバリのワードで出てこない時は、
より一般的なワードで調べてみるキーワードの組み合わせ
画像検索
ザッピングして情報の場所にアタリを付ける
調べる媒体
公的機関のHP
民間企業のHP
新聞社・ニュースサイト
個人ブログ・サイト
note
Twitter(X)
メモ:ニッチすぎる話題はTwitter(X)でキーワード検索すると
手がかりが見つかることがある(情報の間違いや古さに気をつけること)
文献検索
国内
国立国会図書館 オンライン(https://ndlonline.ndl.go.jp/)
カーリル(https://calil.jp/)
新書マップ(https://shinshomap.info/)
国外
WorldCat(https://www.worldcat.org/ja)
KVK(Karlsruher Virtueller Katalog)
(https://kvk.bibliothek.kit.edu/?digitalOnly=0&embedFulltitle=0&newTab=0)Googleブックス(https://books.google.co.jp/?hl=ja)
記事検索
Web Cat Plus(http://webcatplus.nii.ac.jp/)
Google scholar(https://scholar.google.co.jp/schhp?hl=ja)
JSOR(https://www.jstor.org/)
公的調査・統計
総務省統計局(https://www.stat.go.jp/)
ハブとして使う
民間調査レポート
リサーチのアウトプット
引用・参考文献の内容整理
リサーチログ
①知りたいこと(テーマ)を表の左端の欄に書く
②テーマについて次の3つの質問について自問自答して表を埋める
<既知>既に知っていることは何か?
<欲知>自分が知りたいこと/見つけたいものは何か?
<調査法>どのように知ろうとしているか(どこを探すつもりか? 何を調べるつもりか?)
②調査で分かったことを表に記入する
<得知>調査・学習して知ったこと・分かったこと
<未知>調査・学習したがわからなかったこと
<調査法>実際に用いた調査法(どこを探したか? 何を調べたか?)と反省
<活用>調査・学習したことは何に役立ちそうか
マトリクス(目次・引用・要素別)
目次マトリクス
①独学のテーマごとに、マトリクス(表)を作る
②文献のタイトル、著者などを表の左端のマスへ入力する
③目次から「見出し」を拾い出し、マスへ入力する
④必要な各章の概略を追記する
⑤同じ/似た内容をマーキングしたり、囲んでつないだりする
⑥文献を横断読みしながら気付いたことを抽出し、整理する
引用マトリクス
①集めた文献のタイトル等を表の上端に記入する
②表の左端に参考文献リストを転記する
③左端の文献が出てくる箇所を拾い出して記入する
④言及が多い順に被引用文献をソートする
⑤引用している側の文献をソートする
⑥引用マトリクスを読み解く
要素マトリクス
①文献を集めて年代順に並べる
②マトリクスへ抽出する要素を決める
③選んだ要素を文献から拾い出しマトリクスを埋めていく
④完成した要素マトリクスを読み解き、気付いたことを文章化する
【補足】
文字だけだと分かりにくいので、読書猿さんの
レビュー・マトリクスの記事がオススメです。
文章構成ツール
マインドマップ
Xmind(https://jp.xmind.net/)
Coggle(https://coggle.it/)
MindMeister(https://mindmeister.jp/)
アウトライナー
リサーチの公表媒体(個人)
個人サイト
note
SNS
参考文献
アクセンチュア 消費財・サービス業界グループ (2023)『外資系コンサルのリサーチ技法(第2版)』東洋経済新報社
読書猿(2020)『独学大全』ダイヤモンド社
WordPressサイトではドイツ語学習関係の情報を発信しています! 良ければこちらもどうぞ! 無知の知晴れ https://awonohata.com/
