
HACCPを上手く使うために㉒ ~原則2 CCPの決定 シンプルに考えて!~
こんにちは! あたたけ です。
今回はHACCPの『原則2(手順7) CCPの決定』です。
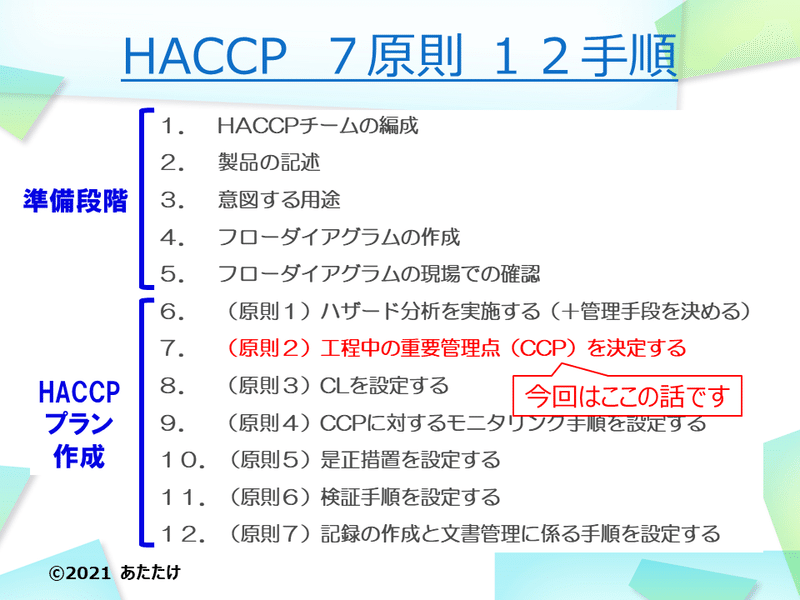
前回までの『ハザード分析ワークシート』の欄6です。
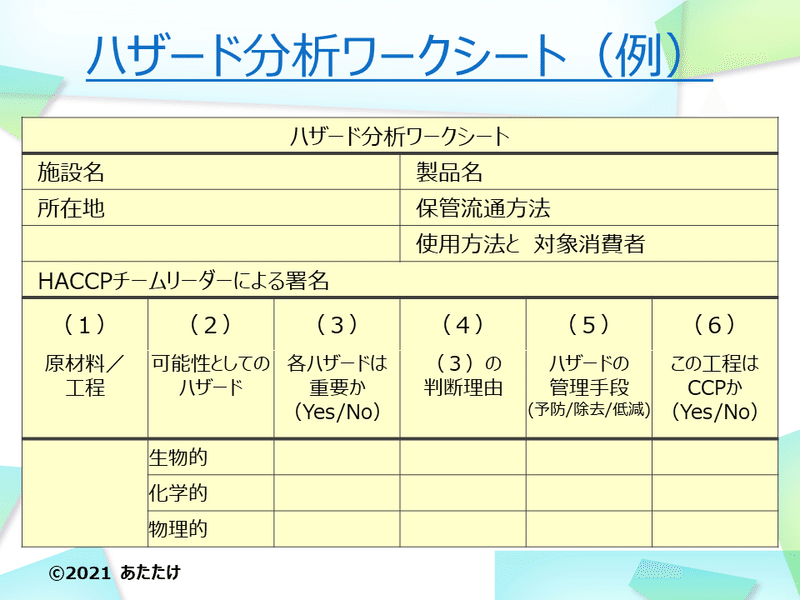

欄3でハザードを評価し『重要』となったものについて、
欄5で管理手段を設定しました。
ここでは、その管理手段をCCPとするのか決めます。
コーデックス委員会の判断樹(Decision Tree)を
使って決めることが多いでしょうか。

が、別に必ずしも判断樹に従う必要はありません。
例えば、食中毒予防3原則との関連から考えても良いと思います。

大切なことは『確実に・効率よく』食品の安全性を確保することです。
考えるべきは、判断の『方法』ではなく『根拠』です。
極端な話、『ここが大事!』と決めてみて
本当に大切か(第三者に説明できるか)、
モニタリングが連続的に・速やかにできるか、などなどで
見直ししていけば良いでしょう。
ちなみに、あたたけ的『CCPを決める時のポイント』を紹介しておきます。
(判断樹をざっくりまとめただけですが)
①原料または工程由来で、ほっといたら事故に繋がるハザードを
②どこで取り除く(もしくは、OKなレベルまで下げる)の?
③その工程前後での交差汚染は予防できてる?
(+その工程後の菌の増殖防止はできてる?)
まぁ、②までで充分だとは思いますが、、、、、
例えば、動線が入り組んでいる&加熱を複数回するような場合には、
CCP前後での交差汚染の可能性を考え、
『最後の加熱をCCPにする』のか『最初の加熱をCCPにする』のか、
どっちが楽か考えた方が良いのかなと思います。
(冷却をCCPにするのかは、、、好みの問題?レベルだと思います。)

※以下、余談です。
HARPCという考え方もあるように、
食品の安全性を確保するために大事なのは、
『CCPを決める、適切に管理する』ことではなく、
『ハザード分析(ハザードの列挙・評価)を行い、
リスクの大きさに応じて、適切に管理する』ということだと思います。
あたたけの感覚では、少なくとも日本の食品工場では、
管理が不足していることよりも、過剰であることの方が多いです。
(その分、どこが本当に大切かわからない、品管の自己満足になっている、
といった状況になっていることもありますが)
ですので、HACCPを通して考えて欲しいのは、
『今の管理レベルは妥当か、過剰になっていないか』ということです。
なので、CCPの決定に関しては、
あまり考えこまず、形にこだわらず、進めてしまった方が良いと思います。
『考える労力は他のところで使ったら?』というのが本音ですね。
それでは、今回はこの辺りで!
次回は『原則3(手順8)CLの決定』です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
