
HACCP! その前に⇒食中毒予防3原則②
こんにちは! あたたけ です。
前回の記事に引き続き、食中毒予防3原則のお話です。
0.食中毒予防3原則の対象は?
個人的に、食中毒予防3原則という考え方はとても素晴らしいと思います。
最初に言い始めた方ってスゴイなぁとも。
ただ、あまりにもシンプルな表現になっているため、
人によって捉え方に違いがあるのが問題だという気もします。
ということで、質問です。
①食中毒予防3原則は何をキレイにするためのものですか?
②そのために、何をつけない、ふやさない、やっつけるのが狙いですか?
①の答えは、食中毒予防が目的ですから、『そのまま食べる食品』ですね。
②は、菌(細菌やウイルス)の特徴から3原則が成り立っていますので、
『菌』をつけない、ふやさない、やっつけるのが狙いとなります。
食中毒予防3原則を理解するため(活用するため)には、
何を対象としているのか忘れないことが大切です。

1.つけない
つけないためには、『どこからつくのか』理解すれば大丈夫です。
菌は、『食材(なまもの)』と『人/従業員(いきもの)』にいますので、
まずは、その2つが汚染源ですね。
また、汚染源の『従業員』『食材』と守る対象の『そのまま食べる食品』の
両方と接触する『器具』も汚染経路として要注意です。
この3つの汚染源(経路)、『食材』『人』『器具』から
菌をつけないようにしようと考えれば、やることは見えてくるはずです。


2.ふやさない
ふやさないためには、『菌はどうすれば増えるのか』理解しましょう。
細菌は、適切な『温度』『栄養』『水分』がそろうと増えます。
また、少しくらい条件が悪くても、『時間』があれば増えます。
ただし、一般的に、食品には栄養・水分はいっぱいありますので、
『温度』と『時間』を管理することが、ふやさないために大切です。


3.やっつける
やっつけるためには、『菌はどうすれば死滅するのか』を知りましょう。
菌を死滅させる手段は、『加熱』と『薬剤』が一般的です。
また、死滅は難しいですが、『洗浄』で数を減らすことも出来ます。

さて、ここで質問です。前回の最後に触れましたが、
器具の消毒は、3原則のどれになるでしょう?
この辺りが、人によって捉え方が異なる一番のポイントです。
『器具の菌をやっつける』のだから、『やっつける』という方もいますが、
私としては、『食品に菌をつけないために器具の菌をやっつける』なので
『つけない』と考える方が良いのかなぁと考えています。
最終的に何が目的なのかブレてしまわないように。

さて、食材の菌をやっつけるためにすることは、
加熱するものはしっかり加熱、
加熱しないものは洗浄(+薬剤消毒)、そのままですね。
ただし、菌は見えないので、キチンとやっつけられたかの判断が難しい。
ですから、『こうすれば大丈夫』という調理(確認)方法を
事前に決めておくことが大切です。


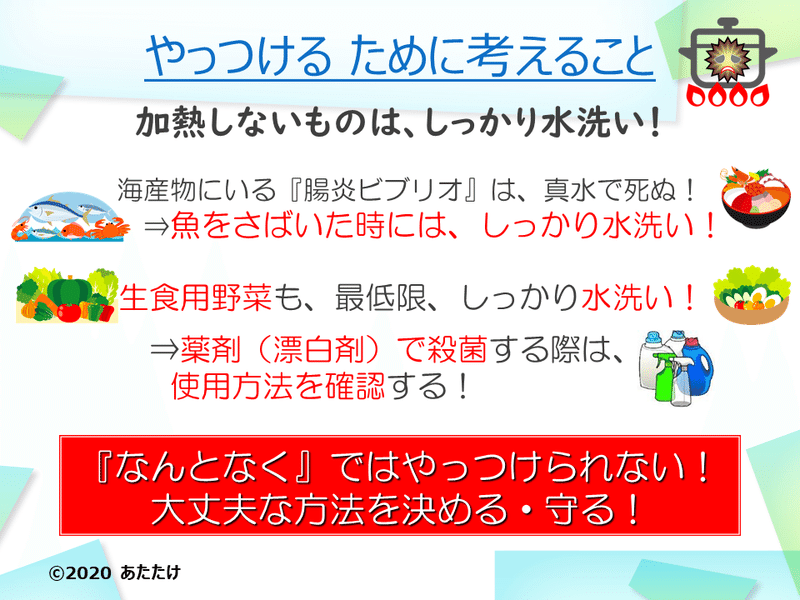
それでは、今回はこの辺りまで。
食中毒3原則をキチンと理解しておけば、
HACCP義務化の対応が、確実にスムーズに進みます!

次回は食中毒予防3原則の補足です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
