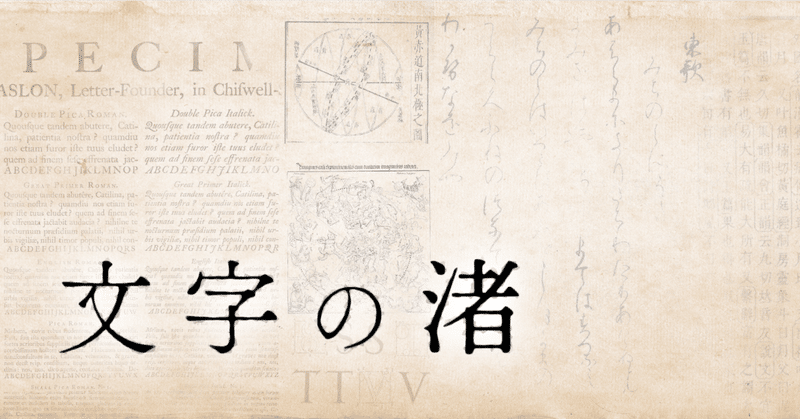
新連載「文字の渚」(岩切正一郎)によせて——担当編集者より
フランス文学者・詩人・戯曲翻訳家であり、わたしの母校・国際基督教大学(ICU)の学長である岩切正一郎先生による連載「文字の渚」が春秋社のウェブマガジン「web春秋 はるとあき」で始まりました。わたしが編集を担当しています。
* * *
まずはどうしてこの企画に至ったのかを書いてみます。
わたしはあまり本を読む子どもではありませんでした。本格的に読書をするようになったのは、中学生の頃、それも受験に忙しくなったころだと記憶しています。進路とか世間とか人生とかいうものを考えるようになるにつれ、手持ちの言葉では言い表すことのできない閉塞感や不安、世の中に対する不満、そして底知れない孤独を感じるようになったのです。そんなときに手が伸びるのは、俗世間の価値やしがらみを離れた文学の世界でした。
いまわたしがしている編集という仕事も、その延長にあるように思います。ずっと言葉を探していた。その根底には孤独と生きづらさがあったように思います。誰とも分かり合えない、誰も分かってくれない。そんな孤独、哀しみ、寂しさを覚えたときに手が伸びるのは文学の世界でした。ここではないどこかへと誘い、俗世の価値を超えたなにかを見せ、自分の人生を生きているだけでは見つけることのできない光を与えてくれたように思います。
いま、たとえば国語教育が文学国語と論理国語に分けられるとか、たびたび浮上する古典文学不要論とか、本が売れないとか……、文学が蔑ろにされているとまでは言わなくとも、顧みられなくなっている、時代に忘れ去られている、そんな気がするのです。というか、本が読まれていた短い100年くらいの時代が、終わろうとしているのかもしれませんね。
たしかに文学に即効性はないし、お金が入ってくるわけでも会社の売り上げに貢献するわけでもない。新聞の人生相談みたいにお悩みの答えを出してくれるわけでもありません。カラマーゾフの兄弟を読破したところで、正しいことが言えるようになるわけでもない。むしろ正しさとか答えとかいうのがない領域だからこそ、思考を自由に働かせて、考えて、行き詰まって、諦めて、寝かせて、また考え始めることができる。それ自体が価値だし、生きているうえですぐには答えの出ない問いや、誰もぶつかったことのない壁に出会った時に力になる、それが文学であり、演劇や映画であり、芸術なのだと思います。
いま芸術は、高尚なもの、立派なもの、ありがたいもの、だけど役には立たない、有閑なインテリの趣味、程度に思われているふしがあります。でもそれは本当は、生きること、なかんずく生きることの苦しさに直結した営みであると、わたしは思うのです。
文学の言葉が失われている一方で、いま膨大な量の言葉が日夜生み出され、忘れ去られています。手を伸ばせばすぐに役立つ言葉が探し出せるし、遠く離れた国や地域のことも、すぐに分かった気になれます。でもそんな簡単ものなんでしょうか。接する言葉の量は増えたけど、質はどうなんでしょうか。なにか簡単に分かったつもりになって、人を評価してはいないでしょうか。人間ってそんなに単純な存在なんでしょうか。
わたしたちは分かり合えない、だから言葉が必要だと思うのです。分かり合えないから、いくら言葉にしても足りないくらいの言葉が溢れ出てくるのだと。分からないものと向き合い、地道な苦労と工夫を重ねて地べたを這うようにして積み重ねられてきた文学には、人が人と友に生きるための叡知が匿されている、と思います。
「文学は無力なのでしょうか」
去年の11月、紅葉の美しい母校のキャンパスに、そんな疑問を携えて訪れ、上に書いたような話を学長室でしました。
このテーマで書いてもらうのには、岩切先生が適任であるように思ったのです。わたしの出身大学の先生であるんだけど、わたしは先生の授業を(正規に)取ったことはなかった。ただ授業や講演を聞きにいくことはあって、文学や戯曲の作品のもつ魅力を、先生自身が魅了されていることを素直に認めながら、でも客観的で的確な言葉で批評している姿を通して、わたしも作品に魅せられていったのです。
わたしが卒業してから岩切先生が母校・国際基督教大学の学長になられました。学長としての姿は、後輩とのやりとりを通してしかうかがい知ることはなかったけれど、ただ形だけのトップではなくて、学長として岩切先生がいることが大学として意味を持つような、そんな学長であるように思えました。その一番の理由は、学生に対して語りかける言葉を持っていたこと、対話する姿勢を持っていたことだと思います。コロナ禍という、先の見えない不安と混乱のなかにあっても。たとえばネット上で話題になった記事には、こんなnoteがありました。
学長室でお話をしてから年が明けて、岩切先生から送られてきた原稿は美しく濃密な言葉が詰まっていました。そしてこれこそが、わたしが求めていた言葉だ、と思いました。
この連載では、言葉の変形(transform)を手がかりにして、文学や詩、演劇、映画などを読み解きながら、改めて芸術が持つ意味を考えます。
* * *
第1回は「錬金術」。岩切先生の若かりし頃の読書経験から始まります。わたしの生まれる前のことですから当時の空気や風潮というのはよく分かりませんが、国書刊行会の「世界幻想文学大系」が刊行されていた頃ですかね。いまわたしのデスクに常備してある『世界神秘学辞典』もその時代を象徴する1冊でしょう。憧れの時代です。科学や合理性の裏側にある、神秘的な思考の系譜に関心が集まっていた頃。錬金術や悪魔崇拝や神秘学の本を読み耽ったという経験から、言葉の持つ作用を考えていきます。幻想文学や神秘主義がお好きな方なら、きっと心に響くものがあるはずです。
引用して紹介したい言葉はたくさんあるのですが、ひとつだけ。
正統な思想史の裏に異端の系譜があり、そこには生きることの苦しみを価値へ変換するための秘法が記されている。そう私には思われた。私は賢者の石の発見に努めなくてはならず、黒の過程の試練をくぐらなくてはならなかった。
俗世の理不尽やしがらみに生きづらさを感じたとき、この世ならざるものや、目に見える世界の向こう側にある神秘の世界に惹かれた。幻想文学を読み耽り、美の世界に心を浸し、超常的な存在を求める。それによってわたしが生きるこの世の外にあるもうひとつの世界になにがしかの光を——それが世では闇と言われるものであったとしても——感じることができた。
そういえば国書刊行会50周年記念冊子『私が選ぶ国書刊行会の3冊』に、谷崎由依さんがこんなことを書かれていました。
幻想文学へ向かう理由はひとそれぞれだろうけど、わたしの場合それは孤独だったと思う。冬の日、ひとひらの雪のように手のなかへ舞い降りた碧い本は、長いこと、誰とも分かち得ない、わたしだけの希望だった。
人は苦しみを抱えて生きることしかできない。だけど、いやだからこそ、言葉によってもたらされる灯りは自分だけの、誰にも分かることのない価値を与えてくれるのではないでしょうか。生きることは苦しい。でも読むべき本があれば、人生は生きるに値する。文学を求めることは、人生を価値のあるものにする言葉を見つける長い旅路を歩き続けることのように、わたしには思えるのです。
* * *
岩切先生による連載「文字の渚」は隔月(偶数月初旬)の更新です。12回の連載ののち、書き下ろしを加えて書籍化する予定です。どうぞお楽しみに。
それからご感想など、ぜひTwitterなどでお寄せ下さい。多くの声が寄せられれば執筆や編集の励みにもなりますし、多くの人に読まれてほしいと思います。
※ちょっと変な箇所があったので修正して、ついでに少しだけ加筆しました(2023.5.12)。
※そういえばこのトップ画像は、没になった連載用バナー画像の試案です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
