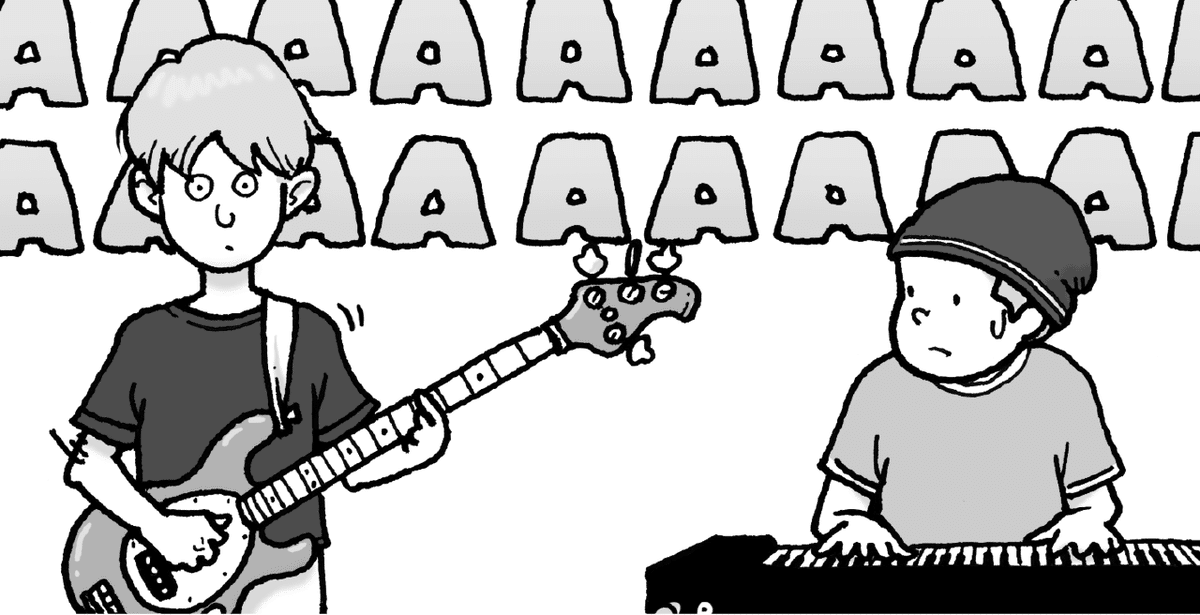
【短編小説】DJシンジロー その3
イジメについての放送があった数日後、シンジローはライブの打ち合わせでシリウスの相棒であるユウイチと都内のレコーディングスタジオで久しぶりに会っていた。いまシリウスは一時期ほどの爆発的な人気はないものの、年に数回ライブを開催し、かなりの観客数を動員していた。
「DJの評判いいらしいな」
とユウイチが声をかける。
「まあな」
とシンジローは少し不満そうに苦笑いを浮かべた。
「どうした。何かあったのか」
「そうだな」
とシンジローは目を見ないで返事をする。
「何でも言ってくれよ」
とユウイチはなんとなくシンジローが気になった。
「若いリスナーたちが俺を信頼してくれるのはありがたいんだけどな」
とシンジローはぼそりと話し出す。
「俺なんか、大した人間じゃない。お前ならわかるだろ」
とシンジローがつぶやく。
「まあ、ただの音楽好きな男だよな」
「そうだろう。それなのに偉そうに人生相談みたいなことをしていいのか。リスナーに俺の本当の姿をハッキリ伝えたほうがいいと思うんだ。ディレクターはこのままでいいというし。リスナーを騙してる、噓をついてる、そんな感覚しかないんだ」
とシンジローが打ち明ける。
「それはタレントやミュージシャンが一番悩むところだよな。一般の人はテレビやネットの情報でいいところしか見てない。画面を通じて明るく爽やかでカッコいいイメージでしか見ていないんだよな」
とユウイチはシンジローの気持ちを代弁する。
「でも、俺たちだって普通の人間だ。聖人君子じゃない。悩みは山ほどある。メシも食えばトイレも行く。酔っ払ってその辺に吐いたり寝転んだりもする。ケンカもするしバカ騒ぎもする。だからラジオでもっともっとおまえの本音を話せばいいじゃないか。そのほうがリスナーの心に響く言葉になると思うけどな」
とユウイチは思いを伝えた。
「でも今の俺のそんな話をリスナーたちは受け入れてくれるだろうか」
とシンジローはため息まじりに訴える。
ユウイチは少し考えて小声で話した。
「じゃあ、いいアイデアがあるぜ」
その翌週。土曜の夜、番組が始まる。
「では、リスナーのメールを紹介します。名古屋のケンジ君、十九才からです。オレの家はじいちゃんの代から食堂をやってます。この前、親父から店を継いで欲しいと言われました。俺はシンジローさんみたいにミュージシャンになりたいから店はやらないと断ったら大喧嘩になってしまいました。だから思い切って家を飛び出して街角でギターを弾きながら歌っています。シンジローさん、これから俺はどうしたらいいと思いますか、というメールです。」
シンジローはうつむいて少し間をおいて話し始めた。
「今日は特別ゲストにきてもらっています。シリウスのユウイチです」
「こんばんは、ユウイチです。元気ですかー」
ユウイチがスタジオの空気を変えるような元気な声で登場した。
「今日の相談、ユウイチはどう思う?」
「そうだね。みんながぶち当たる問題だよね。大きく分けて二つポイントがあるんじゃないかな。まず一つ目。ミュージシャンの件ね。この世界はとても厳しいです。ライバルも山ほどいます。若手が次から次へとデビューしてきます。それでも生き残らないといけない。まずそこがすごく大変ですね。だから、練習、練習です。そして常に新しいものを生み出す努力かな。そうしないといずれ消えていきます」
シンジローもうなずく。
「次に二つ目のポイント。後継ぎの話。ミュージシャンになるにしても親父さんとキチンと話し合いをもったほうがいいですよ。絶対に。急ぐことはない。しっかり相談して決めてください」
とユウイチはリスナーに語りかける。
「そもそも、おまえがそうだったよな」
とユウイチがシンジローに話を向けた。
「実は俺にも似たようなことがありました」
シンジローはデビューするまでのことをゆっくりとした口調で語りはじめた。
シンジローは子供の頃から歌うことが大好きだった。いつもテレビを見ながら歌っていた。どうしても歌手になりたくてギターを手に入れ猛練習をした。そして高校生の頃には将来の職業をシンガーソングライターと決め本格的に準備を始めていた。
ある時、シンジローは父親と将来のことで話し合いをした。
「売れるかどうかわからんことをいつまでもやり続けるのか」と父と口論になった。延々と話をしてもお互い平行線のまま。結論は出なかった。
そしてついに
「もういい」
と言い放ってシンジローは雨の降る真夜中にバイクに乗って家を飛び出していた。
悔しくてずっとバイクを走らせた。
すると目の前に東京タワーが見えてきた。
「絶対プロのミュージシャンになってやる」
と雨に濡れながら心の中で叫んでいた。
それからは父を見返すために一人で曲を作り、歌っていた。
その後、ユウイチと出会い「シリウス」を結成する。
二人で武道館ライブをやるという目標を立てた。
その目標のために、毎日路上ライブをすることにした。
来る日も来る日も、ひたすら歌い続けた。
きっと誰かにわかってもらえる日がくることを信じていた。
ところが、
世間の風は冷たかった。
歌を聞いてくれる人は誰もいなかった。
足を止めてくれる人もいなかった。
それでもめげずに、
路上ライブを続けた。
暑い日も、
寒い日も、
雨の日も、
風の日も
二人は歌い続けた。
通りがかりの酔っ払いから「うるさい」と怒鳴られた。
警官からも白い目で見られることもあった。
それでも
二人で歌い続けた。
するとある時、
パチパチと拍手をしてくれる一人の若い女性があらわれた。
初めてのお客さんだった。
シリウスの二人には涙が出るほどうれしかった。
しばらく観客はその女性一人だけ。
それがシリウス二人の心の支えだった。
その後、一人、また一人と聞いてくれる人が集まるようになった。
指折り数えるほどの人数だったが、当時のシリウスには大観衆に思えた。
観客の手拍子にあわせて歌えるということは夢のような時間だった。
♬
ぼくは歌う
おれも歌う
このバラードを
このバラードを
きみのため
みんなのため
歌は
みんなをつなぐ
しあわせをつなぐよ
みんな強くなれる
この路上ライブで歌っていた「ハピネス」という曲は、後にシリウスの代表曲となる。そして徐々に観客は増えていき、彼らを取り囲むように人の輪ができていった。
いっしょに歌ってくれる人がいる喜びを二人はしみじみと噛み締めていた。
数年後、「シリウス」の路上ライブは駅前の名物となっていた。
二人が登場するだけで拍手が沸き起こるようになった。
路上ライブを見るために遠方から電車に乗って来てくれる人もいた。
やがてシリウスは音楽プロダクションから声がかかり、メジャーデビューが決まった。
二人で飛び上がって喜んだ。
いままでの苦労がやっと報われたと感じた。
早速、シンジローは十年ぶりに実家へ電話をかけた。
久しぶりに聞く母の声。素直に母は喜んでくれた。
シンジローの活躍のことは知人から聞いて知っていたという。
だが、すぐに母の声が暗くなった。
先日病院で父が検査を受け、末期の肺ガンということがわかり入院しているという。
詳しく聞くと父は余命半年だと母が涙声で話してくれた。
シンジローは、携帯電話を握り締めたまま動けなかった。
早く直接会って父にデビューの件を伝えたかった。
後日、シンジローは完成したCDを持って父のいる病院へと走った。
父は、シンジローの顔を見てやっとわかるかどうかという状態だった。
それでも父は声をかけると笑顔を浮かべて喜んでくれた。
握手をし、CDを手渡した。二人に言葉はなかった。
ただ、お互いの目を見てうなずきあった。
十年という時間を一気に飛び越えるように。
久しぶりに見る父の手はかなりやせ細っていたものの温かった。
父は嬉しそうにいつまでもいつまでもCDを眺めていた。
そのCDは病室に飾られていた。
しかし、父の容態が悪化しシンジローとの面会から一週間後、逝ってしまう。
シンジローは、デビューの報告はできたものの
「本当にこれでよかったのだろうか」
という何かが心の片隅に残った。
「と、こんな感じで音楽をやってきました」
シンジローの目は赤くなっていた。最後に声を振り絞って語った。
「音楽は素晴らしいです。ただ、それでも自分にとって大切な人のことも、しっかり考えてあげてください」
ユウイチのおかげで、初めて本当の自分の姿をラジオで伝えることができた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
