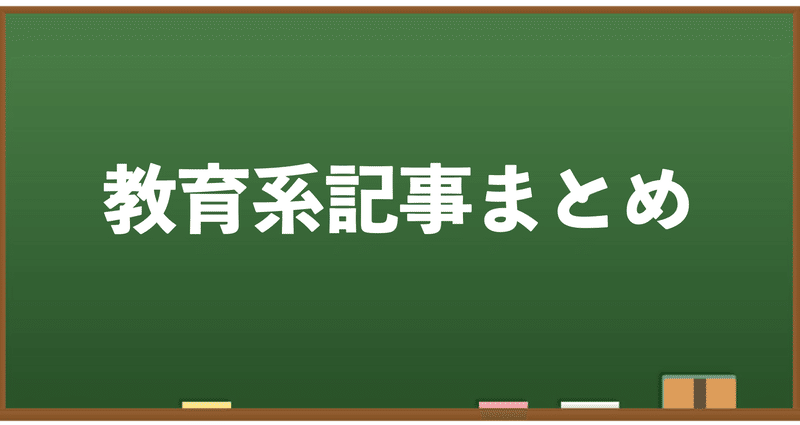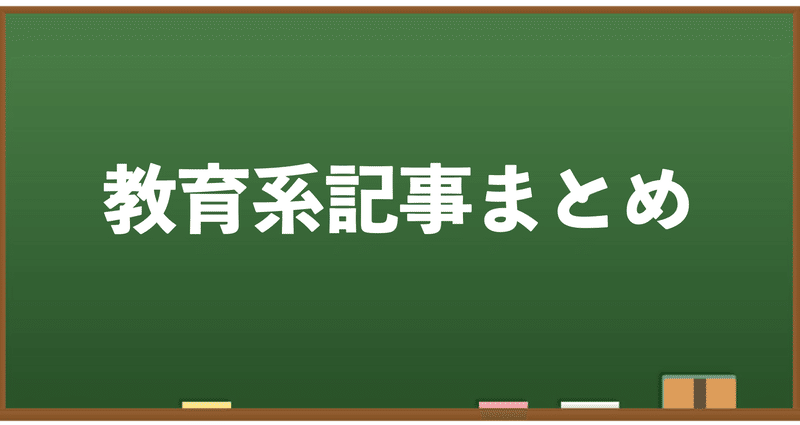学級でタブレットを自由に活用するために指導した4つのこと
タブレット活用にあたって大事なことタブレットを活用する目的を考える時間を設定する
この活動が、最も重要なことです。教師だけではなく児童生徒に”なんのためにタブレットで学習するのか”という目的を考えることで、今後のタブレットの使用方法について学級の中で合意形成を図りながら、議論することができます。タブレットをどのように使用するかは、教師と児童生徒の間でそれぞれの希望があります。教師は授業の中だけで活用したいけれど、児童生徒は休み時間にも使いたいといったように。そういったギャッ